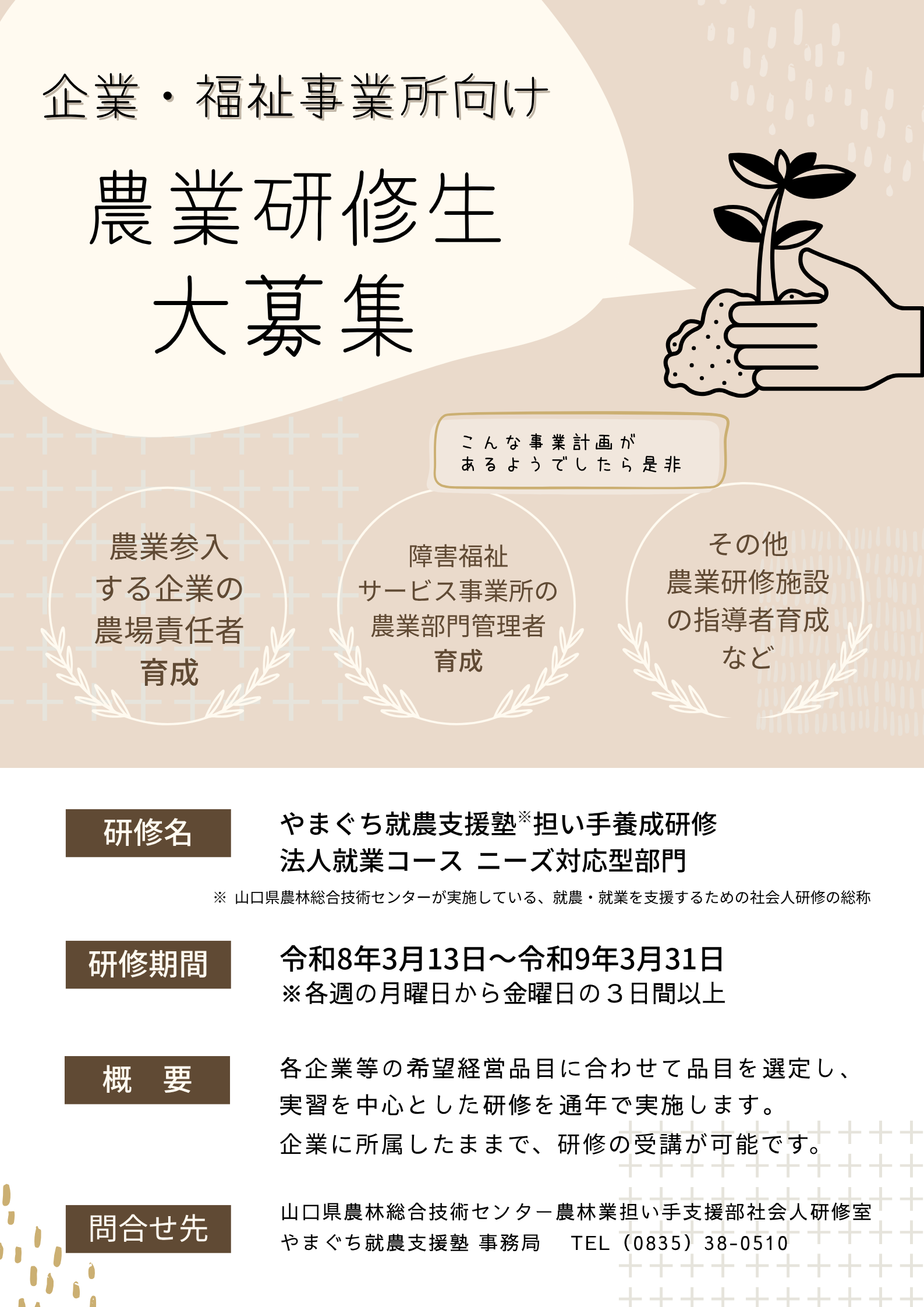メロンの鉢上げを行いました! 6.8.1
8月1日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生2名と1年生2名で、メロンの鉢上げを行いました。7月26日に播いた種が発芽したものです。
トレイの中で育った苗を、あらかじめ土を入れて散水したポットに移します。種の向きをそろえて丁寧に播種したかいがあり、均一な苗に育てることができました。
今後、8月中旬頃ハウス内のベンチに定植した後、誘引などの管理を経て、11月3日の拠点祭を中心に出荷します。品種は、青肉系の「ミラノ夏Ⅰ」、赤肉系の「妃」となっております。お楽しみに!




キャベツとブロッコリーを播種しました! 6.7.29
7月29日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3名と社会人研修生2名が、キャベツとブロッコリーを播種しました。
爪の先ほどの小さな種をつまみ上げ、セルトレイの中に1つずつ置いていく、気の遠くなるような作業です。今回は、128穴のセルトレイ28枚分、約3,600粒を播きました。徐々にスピードを上げ、2時間で終わることができました。
ブロッコリーは発芽するために光を要しますが、キャベツは不要なので、播種後は別々に管理する必要があります。3日ほどで発芽した後、本葉が3~4枚になった時点で畑に定植します。
ブロッコリーは早い品種で11月上旬頃、キャベツは10月下旬頃収穫予定です。拠点祭にも出品しますのでお楽しみに!




経営プロジェクトの調査を行いました! 6.7.26
7月26日(金)、園芸学科花き経営コースでは、経営プロジェクト「オープンハウスと葉面散布がLAユリの花の脱落軽減に与える影響」の調査を行いました。この課題は、7月23日に園芸学科全学生・研修生・職員の前で発表したものです。
今回は、草丈や葉の枚数、落花の数などを調べました。オープンハウスのほうが最高気温は低く推移したものの、乾燥しやすかったということです。このような環境因子が花の品質にどう影響するか、非常に興味深いところです。
気温の推移、乾燥の時期や程度、落花数の推移などから、何が落花に最も影響を及ぼすのかを突き止め、より高品質なLAユリの栽培に役立てます。


経営プロジェクト中間発表会(第5回目)を行いました! 6.7.23
7月23日(火)、園芸学科では、今年第5回目の経営プロジェクト中間発表会を行いました。
今回は、「オープンハウスと葉面散布がLAユリの花の脱落軽減に与える影響」について、担当の2年生が発表しました。
LAユリは、夏季に収穫する作型では、高温、乾燥、栄養不足などにより、花が蕾の段階で落下することがあります。そこで、通常のビニルハウスとは異なり、天井までビニルを開放できるオープンハウスに作り替えて、通常のハウス栽培と比較、調査することにしました。また、栄養不足を補う観点から、葉面散布を行う調査区を設定しました。
担当した2年生は、現時点までの生育の違いなどを説明し、学生からの質問にしっかりと答えていました。
次回は、8月22日(木)に2課題行う予定です。


拠点祭に向けて!メロンの播種をしました!! 6.7.26
7月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの播種を行いました。
今回播種した品種は、「ミラノ夏Ⅰ」と「妃」です。「ミラノ夏Ⅰ」は、黄白色の果肉で高糖度、「妃」は赤肉で肉質が緻密で高糖度の品種です。
1年生2人が、前年度担当した2年生や職員から土の水分、1つのトレイに播種する数、種を置く向きや深さなどを教えてもらいながら、460粒を約1時間でまきおえました。時々職員から、「なぜ向きをそろえてまかないといけないの?」などと聞かれていましたが、しっかりと答えていました。
このメロンは、11月3日(日)の「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」で販売します。お楽しみに!



蒸気消毒を行いました! 6.7.26
7月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、蒸気消毒を行いました。
蒸気消毒とは、高温の蒸気を土に通して土壌に潜む病害虫や雑草を防除する方法です。農薬を使わないため環境にやさしく、生産者にとっては消毒後温度が下がればすぐに定植できるというメリットがあります。
今回は、11月3日の「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」で販売するメロンを定植するためのベンチ内の土を消毒しました。
担当の1年生は、今回初めてに蒸気消毒でしたが、職員から丁寧に教えてもらい、落ち着いた様子で取り組んでいました。
8月上旬ごろには、メロン「ミラノ夏Ⅰ」と「妃」を定植予定です。11月3日をお楽しみに!
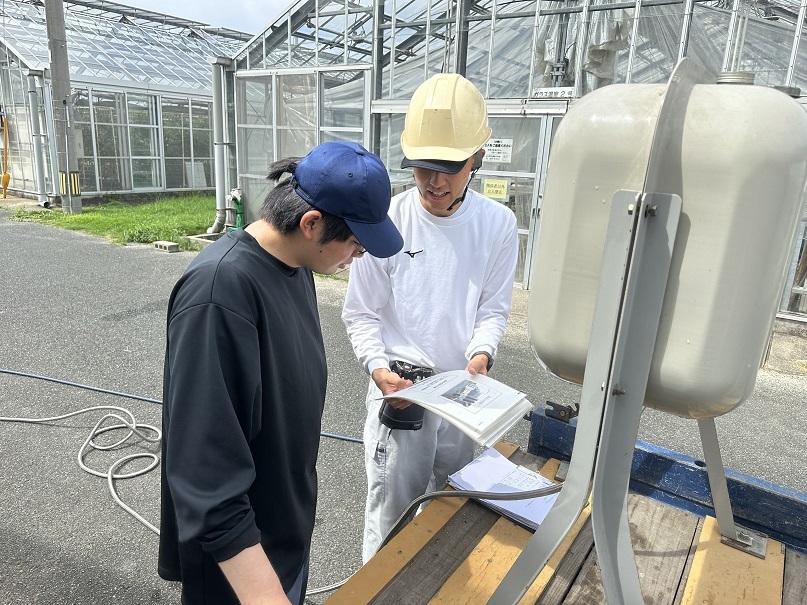


使った田植機は自分たちで整備 6.7.26
土地利用学科では7月3日~5日に、大道干拓で田植え実習を行いましたが、ただ植えるだけでは土地利用学科らしくありません。田植機の基本的な整備方法を学んでこそ土地利用学科の実習です。
ということで、7月24日(水)、(株)中四国クボタの指導のもと、自分たちが使った田植機の整備を行いました。内容は、エンジンオイルやミッションオイルの点検・交換、冷却水の点検、各センサーの点検、植付爪の点検・調整・グリスアップなどなど。説明を聞くだけでなく、実際に自分たちで整備をすると、より理解が深まりますね。学生達は和気あいあいと、口も手も動かしながら、整備に取り組んでいました。
最後は洗車。車体に肥料が付着しているとそこから錆びるので、肥料が残らないように洗車が必要です。学生達は、肥料が残りやすい場所、高圧洗浄機の高圧水を掛けてはいけない場所などを教えてもらいながら、丁寧に洗車していました。
今回学んだことを、次は農大の田植機で実践し、より理解を深めましょう。




大豆の畝立て狭畦栽培に挑戦 6.7.26
土地利用学科2年生の一人が、大豆の畝立て狭畦栽培(きょうけいさいばい:播種の間隔を通常より狭くし、大豆の葉で早期に畝を覆い、雑草の発生を抑える栽培方法)をテーマにした経営プロジャクト学修(卒業論文)に取り組むこととしています。この栽培方法では大豆が過繁茂になる(葉が繁りすぎる)ため、通常の栽培よりも遅い7月22日(月)から23日(火)に、播種を行いました。
最初こそロータリー傾きや播種機の深さ設定に少し時間がかかりましたが、設定が済めばあとは速やかに、計画どおりに播種することができました。この日の為に、播種の間隔を試験場に学び、播種機の調整を入念に行ってきた成果でしょう。
試験のテーマは狭畦(1畝3条)ですが、今回は比較の為に通常の間隔(1畝2条)での播種も行いました。大豆の狭畦栽培は農大では初めての取組、どのような生育になるか楽しみです。




フレールモアで草刈り! 6.7.24
7月24日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、フレールモアを使って草刈りを行いました。
フレールモアとは、草刈りの道具の一つです。本校のフレールモアはトラクターに接続して使用するタイプのため、広い平坦地であればとても楽に草を刈ることができます。
この日は、2年生1名が職員に注意点を教わったのち、慎重にトラクターを操作して草を刈りました。農機メーカーへの就職を希望しているだけあって、一度操作したあとは、慣れた様子で刈り進み、30分ほどで1,500m2ほどのほ場を刈り終えました。
今後、このほ場では キャベツ、ハクサイやブロッコリーなどを栽培します。



農大1年生が阿武萩地域の農業現場を見学! 6.7.23
7月23日(火)、本校の1年生が阿武萩地域の農業現場を見学しました。
最初に、農事組合法人うもれ木の郷を訪れ、法人経営の具体的取組について代表や卒業生からお話を聞きました。
次に、山口あぶトマト選果場を見学し、東京から移住就農された高橋さんからほ場にて自身のトマト栽培方法を聞きました。
続いて、千石台でのダイコン等の露地野菜の栽培の説明を受け、黒ボク土を初めて目にする学生も多く興味深々の様子でした。
最後に、水谷牧場では、約130頭の乳牛を前に酪農経営の実態を聞きました。
学生からは、農業現場の最前線を目にし、「また行きたい」、「また話を聞きたい」という声が多く聞かれました。
農大では今後も関係者の協力のもと、学生が県農業への理解を深める取組を行っていきます。




経営プロジェクト中間発表会(第4回目)を行いました!
6.7.18
7月18日(木)、園芸学科では、第4回目の中間発表を行いました。今回は、『ミニトマト栽培における台木の違いや高接ぎ木法が青枯病の発生や生育、収量に及ぼす影響について』と題して、担当した2年生が説明しました。
トマト、ミニトマト、ナスなどは、青枯病と呼ばれる細菌が原因の土壌病害により、大きな被害を受けます。
この課題では、青枯病を予防する目的で、2種類の接ぎ木法と2種類の台木を組み合わせ、4つの調査区を作りました。なお、接ぎ木法のうち、高接ぎ木法は、山口県農林総合技術センターで開発した技術です。
担当した学生は、事前に一生懸命調べて、職員からの質問にもしっかり答えていました。担当している職員からも、わかりやすい補足があり、充実した内容になりました。
次回は、7月23日(火)に開催予定です。



野菜経営コースでリスク評価を行いました! 6.7.17
7月17日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、リスク評価を行いました。
リスク評価とは、栽培や出荷調製に際して、どのようなリスクがあるか、そのリスクはどの程度の重大性と頻度で発生しうるか、どんな対策をしたらよいかを話し合うものです。
野菜経営コースでは2018年から取り組んでおり、今年で10回目になります。JGAP認証を受けているトマト・ミニトマトについて、約150項目のリスクについて、毎年点検しています。
この日は、1年生3人、2年生2人、社会人研修生1人が、点検項目の内、約80項目について評価を行いました。2年生は経験を積んだだけあって、「これはできている」「これは検討中」などと的確に分類していました。
今後、残りの約70項目について点検します。
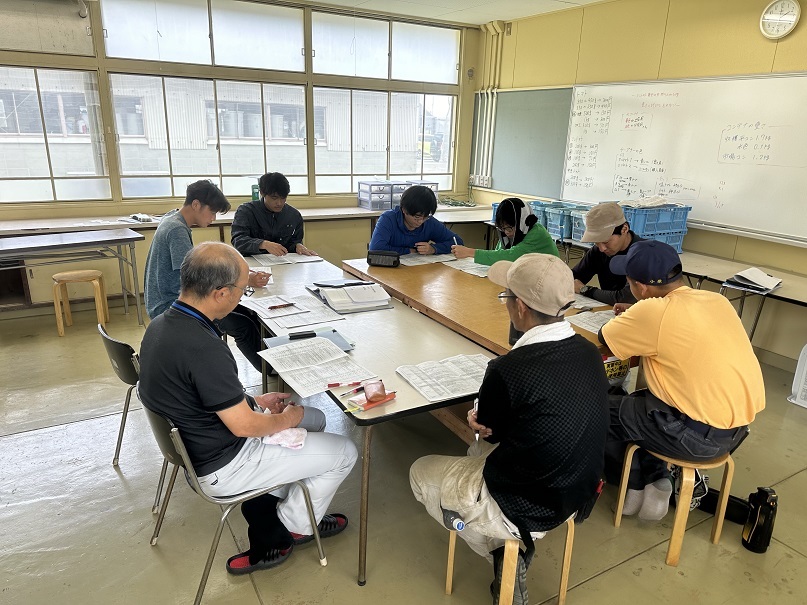
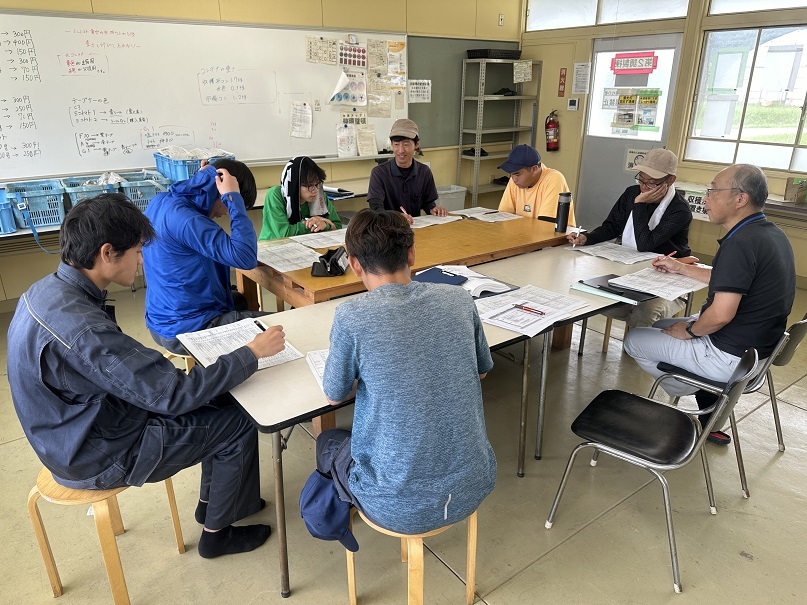
ドローンの操作も上手くなりました! 6.7.19
土地利用学科の1年生と研修生が5月7日からドローンの操作練習を始めて、はや2か月。最後の講習が7月17日(水)に行われました。最後の課題は、「円形飛行」と「八ノ字飛行」。地面に置かれた印の上をなぞって、きれいに円形を描くようにドローンを飛ばさなければなりません。コントローラーの操作も、前進、横移動、旋回の3要素が必要となります。
この円形飛行、毎年学生が苦労する難題ですが、今年はどうでしょうか・・・ ドローンの動きがカク、カクとなったり、勢い余って指定の円から大きくはみ出てしまったり。学生達は、講師から操作のポイントを教えてもらいながら、真剣(楽しそう)な表情で、コントローラーのスティックを慎重に、慎重に、操作していました。
さて、2年生になれば、ドローンの現場活用に向けた講習が待っています。それまで、自主練習しながら操作技術を維持しておきましょう。


トヨタ生産方式で標準作業要領書の作成を学ぶ 6.7.17
7月17日(水)、土地利用学科2年生は、2回目のトヨタ生産方式の講義がありました。今回のテーマは、「標準作業要領書の作成」です。
農業大学校では、様々な実習を行います。いろいろな機械も使います。一方で、学生は2年で卒業し、職員も数年で異動します。作業や操作の標準的な手順を、詳しく、わかりやすく記載した「標準作業要領書」は、まさに農大の継続的な学習に必要不可欠なものと言えるでしょう。
学生達は、「何の」標準作業要領書を作成するかテーマを出し合い、次に優先順位をつけ、18テーマ(3班×6テーマ)の標準作業要領書を作成することにしました。講義の後半では早速作成に着手。これから年末にかけて、どんどん作成していく予定です。
さて、講義の最後は、全員で紙飛行機を折りました。次回の「紙飛行機演習」に向けた準備とのこと。・・・紙飛行機演習? 果たしてどのような演習なのか、乞うご期待。

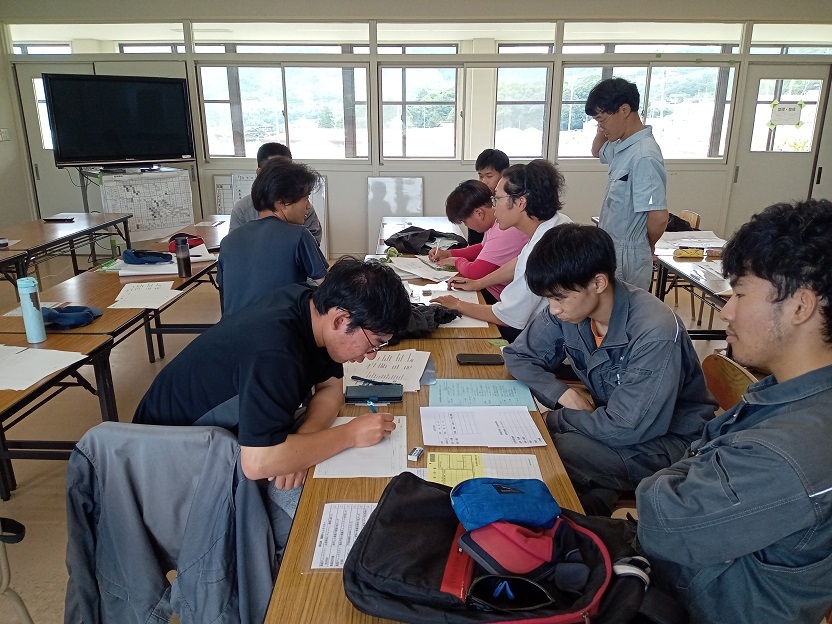

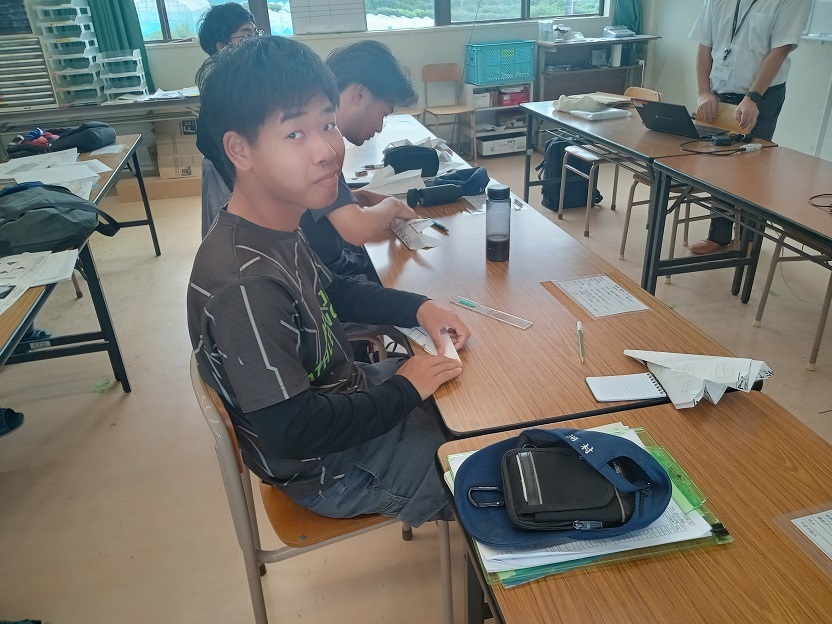
トルコギキョウの花もち調査を行いました! 6.7.16
7月16日(火曜日)、園芸学科花き経営コースでは、経営プロジェクト「トルコギキョウの仕立て方の違いが収支に与える影響」の一環で、花もち調査を行いました。
このプロジェクトでは、1本の茎から多数の花をつける従来の育て方と、1本の茎に1つだけ花をつける育て方を試し、花市場での単価や品質を調査・比較します。
この日は、職員の指導の下、担当の2年生が花の開き具合や花弁の変色の程度などを調査しました。
新しい方法がどのように評価されるのか、今からとても楽しみです。
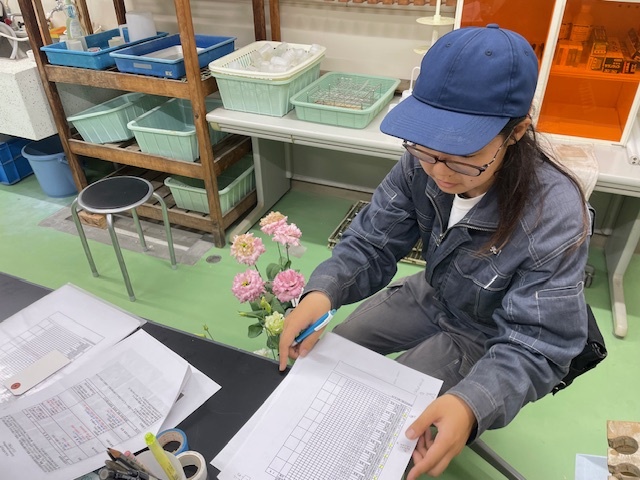


うんしゅうみかんのマルチを移設しました! 6.7.17
7月17日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、うんしゅうみかんのマルチを移設しました。
果樹経営コースでは、うんしゅうみかんの樹別交互結実栽培に取り組んでいます。昨年着果させた樹は、今年は着果させずに休ませます。逆に、昨年休ませた樹は、今年1.5~2倍量を着果させます。このため、昨年着果させた樹の下に敷いたマルチを、今年着果させる樹の下に移設する必要があります。
この日は、1年生1人、2年生1人、社会人研修生2人と職員で、今年マルチを敷く樹の下の雑草除去、昨年敷いたマルチの除去、移設を行いました。皆一生懸命取り組み、夕方までに何とか終わりました。
このマルチを被覆したうんしゅうみかんは、1月中旬ごろから市内外の3か所の直売所等に出荷されます。もう少しお待ちください。


全国トップレベルの技術を勉強しました! 6.7.17
7月17日(水)、全国トップレベルの技術に触れて、本校での学修を一層高めるため、畜産学科1年生5名が、全国大会で数々の受賞歴がある株式会社福嶋牧場を訪問しました。
会長や社長から、肥育牛のつくり方や牛に対する敬意や経営の在り方、技術に対する考え方に加え、畜産経営者としての心構え等について幅広く御指導いただきました。
また、牛舎では、出荷が近い肥育牛を見るだけでなく、肉の張り方が分かるよう直に触らせていただきました。
学生達は、全国トップレベルの肥育牛に直接触れ、目標の姿を具体的にイメージできた様子でした。今後、本校での日々の肥育や子牛生産に生かされることを期待します!


令和6年度第2回短期入門研修を開催しました! 6.7.12
やまぐち就農支援塾では、新たに農業を始めようとする方(就農)や農業法人への就業に興味のある方を対象とした研修会を7月9日から11日にかけて実施しました。
受講者は、暑い中、農作業実習に精力的に取り組むとともに、就農・就業に向けた担い手養成研修生からの助言を熱心に聞いておられました。また、「今後、他の研修を受講してみたい」との声も聞かれ、今後に向けて有意義な時間となったようです。




土地利用学科、リモートセンシングに挑戦してみた 6.7.12
土地利用学科2年生のドローン講義、7月8日(月)のテーマは「リモートセンシング(離れた場所からの診断)」です。使うドローンも、特殊なカメラ(レンズが6つ)付き。
まずは、カメラの仕組みやリモートセンシングの概要についての講義。なかなか難しい講義でしたが、少しは理解できたでしょうか?
講義の次は、ドローンの自動航行(人が操作せずに自動で飛行させる)の準備。飛ばす範囲、ルート、高度などを、タブレット端末を使ってプログラムしました。こういうのは結構楽しそうですね。残念ながら今回は風が強く、ドローンは飛ばせませんでした。
そして最後は画像解析。事前に講師が撮影したセンシング画像を見ながら圃場を巡回し、実際の生育を見ながら、センシング画像の色が意味するところを全員で考えました。
今後も定期的に撮影し、各圃場の生育の違いや過去との比較なども行ってみる予定です。


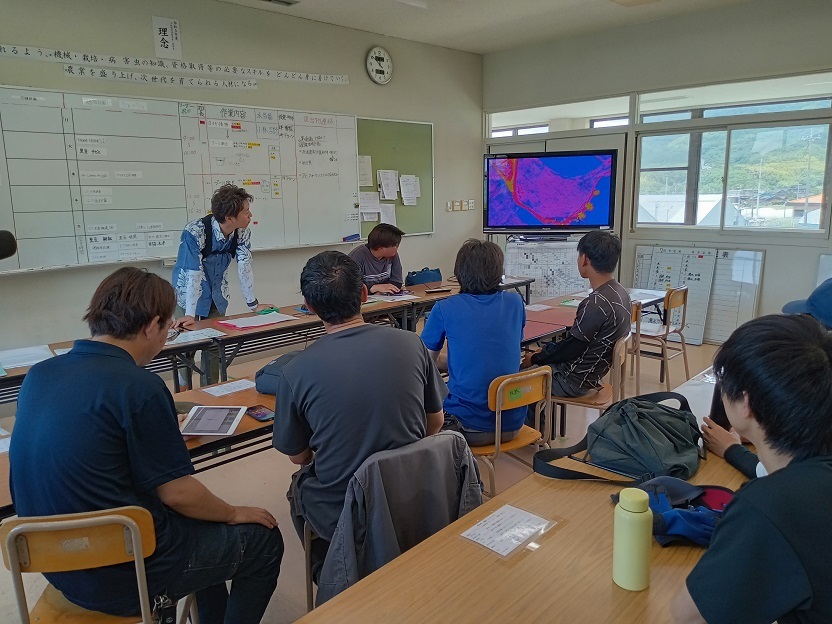
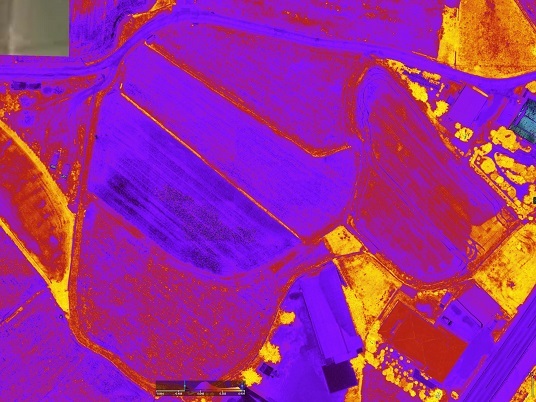
1haの田んぼで田植えに挑戦だ! 6.7.12
土地利用学科の1年生が、7月3日から5日にかけて、防府市内の農業法人(株)ファーム大道の指導のもと、大道干拓の1.1ha圃場(4圃場・合計4.5ha)で田植え実習をさせてもらいました。1.1haって、想像できますか? 野球場のフェアグラウンドと同じ広さです! 土地利用学科がいつも実習している圃場の平均面積が12aなので、その10倍ですね!
これまで連日雨だったのが、田植え日になった途端に良い天気。学生や研修生達は、日差しと水面の照り返しで顔を真っ赤にしながら、ひたすら田植えを行いました。最初こそ苗や機械のトラブルで苦戦しましたが、2日目からは順調に作業も進み、計画どおり3日間で4.5haを植え切りました。今年の1年生もよく頑張りました!




ナス出荷中!!! 6.7.11
園芸学科野菜経営コースでは現在、ナスの収穫・調製・出荷にいそしんでいます。学生と社会人研修生は、朝早くに起きて収穫・調製しています。
学生たちのきめ細やかな管理で、今年も大ぶりでツヤのある外観の立派なナスを作ることができました。お味噌汁、麻婆茄子、煮びたしや揚げびたし、漬物、夏野菜のカレーの具材、鶏肉と一緒に照り焼きにするなどなど、様々な調理ができる野菜です。
農業大学校のナスは、防府市内や近辺の直売所で販売しています。ぜひご賞味ください!

ナスの経営プロジェクトで調査しています! 6.7.11
園芸学科野菜経営コースでは「露地ナス栽培における土着天敵の活用」と題して、経営プロジェクトを実施しています。ナスを加害するアザミウマ類の天敵であるタバコカスミカメやヒメハナカメムシを増やすため、ゴマやブルーサルビアをナスの近くに植えました。現在、ほ場での調査では、これらの天敵が定着し始めています。
この日は、担当の2年生が1年生と一緒に加害程度や奇形の有無などを調査しました。
今後、1月には発表し、3月には報告書として取りまとめることになっています。良い結果になることを期待しています!


カーネーションの摘心をしました! 6.7.11
7月11日、園芸学科花き経営コースでは、カーネーションの摘心をしました。カーネーションは、芽の先端を摘み取る(摘心)ことで、わき芽が増え、1株から何本も収穫することができます。
この日、担当の1年生が約2,000本のカーネーションを、職員と一緒に摘心していきました。ずっと同じ姿勢で同じ作業をしなければならず、集中力と持続力が必要な作業ですが、一生懸命取り組んでいました。
このカーネーションは、早い品種は10月中旬ごろから来年の母の日前にかけて出荷する予定です。



花き推進大会に参加しました! 6.7.5
7月5日、園芸学科花き経営コースは、令和6年度山口県花き推進大会に参加しました。
大会では、各種表彰のあと、日本一の花きの取引量・取引額を誇る株式会社大田花きから講師を招き、今後の展望と山口県の花き生産者への提言がありました。また、株式会社山口県中央花市場に就職した本校OGがデモンストレーションを行いました。
学生たちは、一生懸命メモを取り、事後のレポートはびっしりと字で埋め尽くされていました。
園芸学科では今後も、こうした大会等にも積極的に参加していきます。



「長州黒かしわ」PRイベントに参加しました! 6.7.12
7月12日(金)、山口市内のホテルで開催された山口県産オリジナル地鶏「長州黒かしわ」のGI登録※を契機としたPRイベントに、畜産学科1年生5名が出席しました。
イベントでは、GI登録の経緯や「長州黒かしわ」の説明があった後、ホテルの料理長が考案した「長州黒かしわ」を使った料理を試食しました。
畜産学科では、生乳や牛肉の生産に関する学修を行っていますが、同じ畜産物を生産する立場として、安心・安全な畜産物の生産だけでなく、ブランド保護や消費者へのPRも大切であることを学びました。
今後、参加した学生が消費者を意識した家畜の飼養管理や畜産物の生産に一層磨きをかけていくことを期待します!
※GI登録
その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、国が地域の知的財産として保護する制度(地理的表示保護制度)



長門白オクラを出荷します! 6.7.11
7月11日、園芸学科野菜経営コースでは、長門白オクラの収穫・調製・出荷を行いました。
長門白オクラは、山口県長門地域で古くから栽培されてきた山口県の伝統野菜です。今年は、発芽率の向上のため、金属製のやすりで種皮を削り浸水して播種するなど、1年生を中心に様々な工夫をして栽培してきました。ようやく収穫・出荷とあって、喜びもひとしおです。
この日、担当の1年生は、2年生と一緒に夕方収穫し、大きさをそろえて袋詰めしました。
防府市内及び近隣の直売所で販売していますので、是非ご賞味ください。





販売実践演習の打ち合わせをしました! 6.7.11
7月11日(木)、2年生・1年生各4名の合計8名で、17日(水)に防府市まちの駅うめてらすで行う販売実践演習の打ち合わせを行いました。
今回、主な出荷物はナスということで、ナスを使った料理をそれぞれが考えてお客様に提案することになりました。
7月17日(水)午後2時から3時30分ごろまで、防府市まちの駅うめてらすで販売実践演習を開催しますので、お誘いあわせの上、ご来店ください!



道の駅ソレーネ周南で販売実践演習を実施しました! 6.7.10
7月10日(水)、道の駅ソレーネ周南で販売実践演習を実施しました。
この日は、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、タマネギ、ピーマンなどを販売しました。前回と比べて、お客様の数はやや少なかったものの、学生が一生懸命売り込み、ナス、トマト、ピーマンは完売しました。
次は7月17日(水)、防府市まちの駅うめてらすで行います。皆さん、お誘いあわせの上、ご来店ください!



メロンの袋掛けを行いました! 6.7.10
7月10日、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの袋掛けを行いました。メロンは、直射日光を遮ることで日焼けを防ぎ、上品な色白の果実に仕上げることができます。このため、日射が強まる前に袋を掛ける必要があります。袋は、寮で学生たちが読み終わった新聞紙を再利用します。
この日は、1年生4人で、約300個のメロンに袋をかけていきました。
このメロンは果肉が黄緑色の「ミラノ夏Ⅰ」という品種で、8月上旬頃収穫・出荷予定です。防府市内及び近辺の直売所で販売しますので、お楽しみに!



白ネギを定植しました! 6.7.5
7月5日、園芸学科野菜経営コースでは、白ネギを定植しました。白ネギは畑を20cmほど掘り、その底面にネギの苗を植え付けて育てます。栽培の途中で土をかぶせること(土寄せ)で、日光が当たらない白い部分を作ります。
この日は、ネギが大好きでネギを作りたい1年生が、ネギを植えられるとあって大喜びしながら一人で定植から潅水まで作業しました。
今後、土寄せや雑草管理などを行い、12月下旬ごろ収穫・出荷予定です。



食肉の流通を学びました! 6.7.9
7月9日(火)、畜産学科2年生が食肉の流通を学ぶため、広島市中央卸売市場食肉市場へ視察研修に行きました。
本校では、肉用牛を肥育して出荷していますが、普段、出荷後の動向を見ることがありません。
今回、出荷後の、食肉になる過程を見ることで、食肉の流通を学ぶとともに、より一層の高品質化に向けた飼養管理の見直しに繋げます。
また、「食肉をいただくことは命をいただく」ということを改めて実感した研修となったことから、畜産学科2年生には、今まで以上に家畜を大切に育てるとともに、食の大切さを広めることを期待します!

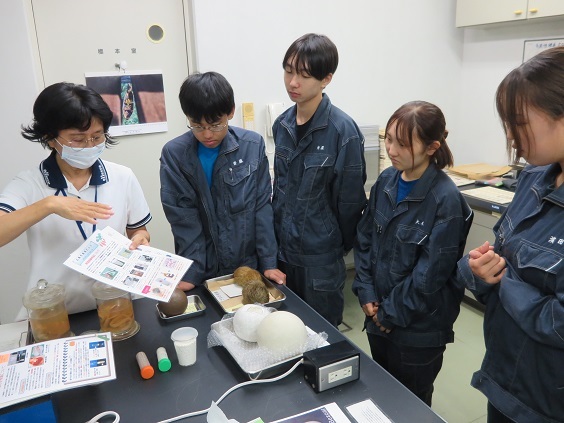
農業高校生が農大を訪問しました! 6.7.8
7月8日(月)、山口農業高等学校西市分校の総合学科1年生23名が農林業への理解を深めるため、本校を訪問しました。
土地利用学科、園芸学科3専攻、畜産学科2専攻のハウスや作業舎、牛舎を回り、学生から各学科や専攻での学修内容について説明を受けた後、学校生活や農大卒業後の進路についても学びました。
高校生からは「牛がかわいかった」「色々な専攻の話を聞けて参考になった」などの感想が聞かれました。
将来、農大を進路の一つとして選択し、農業・畜産に関わる仕事に就いてくれることを期待します!



GAP概論で実践的な講義を行いました! 6.7.1
7月1日(月)、全学科の1年生を対象として、GAP概論を行いました。講師は、4月25日に引き続き、「合同会社つちかい」の大神代表社員です。
今回は、演習法式で図を見てどこに問題があるかを発表しました。その後、調製棟や機械を収納している倉庫に行って、実際に調製する様子や運搬車に乗り込む様子を見て、気を付けていることなどを指摘し合いました。
講師からは、「運搬車に乗る前にぐるりと一周回ってタイヤの空気圧などを見る動作があるとよかった」等の指摘を受けました。
今後、リスク評価や審査の受検などを通じて、GAPの考え方を修得していきます。


カーネーションを定植しました! 6.6.28
6月26日(水)から28日(金)にかけ、園芸学科花き経営コースでは、学生と職員でカーネーションを定植しました。
カーネーションは、定植から収穫まで約1年を要します。今回定植した株は、10月から来年の母の日の前にかけて収穫します。定植に際して、前作の株を除去し、土づくりのため有機物を施用して耕うん、蒸気消毒、フラワーネットを整えて設置しなければなりません。
カーネーションをプレゼントされて喜んでいるお母さんの姿を思い浮かべて、約2,000株を一生懸命定植しました!
来年の母の日前まで、摘心やわき芽とりなど、丁寧に管理を続けます。


イヨカンの摘果をしています! 6.6.27
現在、園芸学科果樹経営コースでは、イヨカンの粗摘果(あらてきか)を行っています。
粗摘果は、樹の下の方に着いている裾なり果、内側に着いている内なり果、小玉果、病害虫被害果などを除去する作業です。粗摘果では、50~60枚の葉につき1果実が残るように摘果し、残した果実の肥大を促します。
担当の2年生は、一つ一つ確認しながら、丁寧かつ手早く、一生懸命取り組んでいました。
今後、80~100枚の葉につき1果実とする仕上げ摘果を行い、12月には収穫、2月下旬~3月にかけて出荷開始予定です。


うめてらすで実践販売演習を行いました! 6.6.26
6月26日(水)、2年生7名、1年生2名の合計9名で、「街の駅うめてらす」にて、実践販売演習を行いました。
全員が手早く準備し、14時から開店しました。開店前には多数のお客様で列ができました。あっという間にレモンが、次いでタマネギやジャガイモが売り切れました。
その後、学生たちはメガホンなどを使ってアピールし、お客様を呼び寄せていました。その成果で、野菜と果樹類は完売しました。
次は7月10日(水)、「道の駅ソレーネ周南」で行います。お誘いあわせの上ご来店くださいませ!!



ナシ「王秋」の大袋掛けをしました! 6.6.27
6月27日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、ナシ「王秋」の大袋掛けを行いました。
大袋掛けは、果面の保護と病害虫防除を目的として行います。
今回は、経営プロジェクト「「王秋」のコルク状果肉障害軽減を目指した着果管理対策の検討」の作業の一つとして、時間を計りながら掛けました。最終的な着果管理(数や不良果の確認)をしながらですが、90分で200枚、1枚あたり27秒で掛けているとのことでした。
「王秋」は、10月下旬~11月上旬にかけて収穫・出荷する予定です。


ナスの誘引をしました! 6.6.25
6月25日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、野菜栽培各論の一環として、1年生8人と社会人研修生4人でナスの誘引をしました。
職員がナスの生理生態、仕立て方や目的などを説明したのち、作業に取り掛かりました。
最初は、どの枝を誘引するか迷っていたものの、徐々に慣れて枝を見分けられるようになり、手早く誘引できるようになりました。
今後は、枝の伸長に伴い、誘引紐を巻き付けて切り返しや追肥を行います。
なお、このほ場のナスは今週から出荷を開始しております。各直売所および販売実習等で販売していますので、お誘いあわせの上、ご来店、お買い上げください!お味噌汁、揚げびたしなど、多様な食べ方があります!




タマネギの選果をしました! 6.6.26
6月26日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、タマネギの選果をしました。
このタマネギは、6月5日に収穫、乾燥貯蔵していたタマネギ(品種は「ターザン」)です。
主担当の2年生1人と1年生2人は、職員の指導のあと、コンベアへのタマネギの送り込み、コンテナの入れ替えなどを自主的に役割分担して作業を進めました。
本日の販売実習で出品したところ、あっという間に完売しました。明日以降も、各直売所に出品予定です。親子丼、カレー、スープなど用途の広い野菜です。ぜひご賞味ください!!



経営プロジェクトの病害虫調査をしました! 6.6.24
6月24日(月)、経営プロジェクト「露地ナスにおける土着天敵の活用」について、害虫や土着天敵の発生状況を調査しました。
このプロジェクトでは、ナスの害虫の天敵を増やし、害虫による被害を軽減できないか検証するものです。
害虫はアザミウマ類、その天敵になるのは、カメムシ類です。カメムシ類が増えるブルーサルビアやゴマをナスの近くに植えることで、ナスに寄って来る害虫アザミウマ類を捕食させる、というしくみです。
この日は、担当の2年生が、金属トレイの上でゴマの花を叩いてカメムシの数を、ナスの花を叩いてアザミウマ類の数を確認しました。今後も土着天敵の効果を継続的に調査します!
野菜の経プロ説明会をしました! 6.6.21
6月21日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8名を対象に、卒論につながる経営プロジェクトの説明会をしました。
農林総合技術センターの農業革新支援担当から、山口県の野菜に関する課題の説明を受けました。
学生は、取り組みたい品目や課題を自分で決め、計画を立て、早い学生は本年9月ごろからスタートを切ります。
山口県の農業を盛り上げるために頑張ります!!

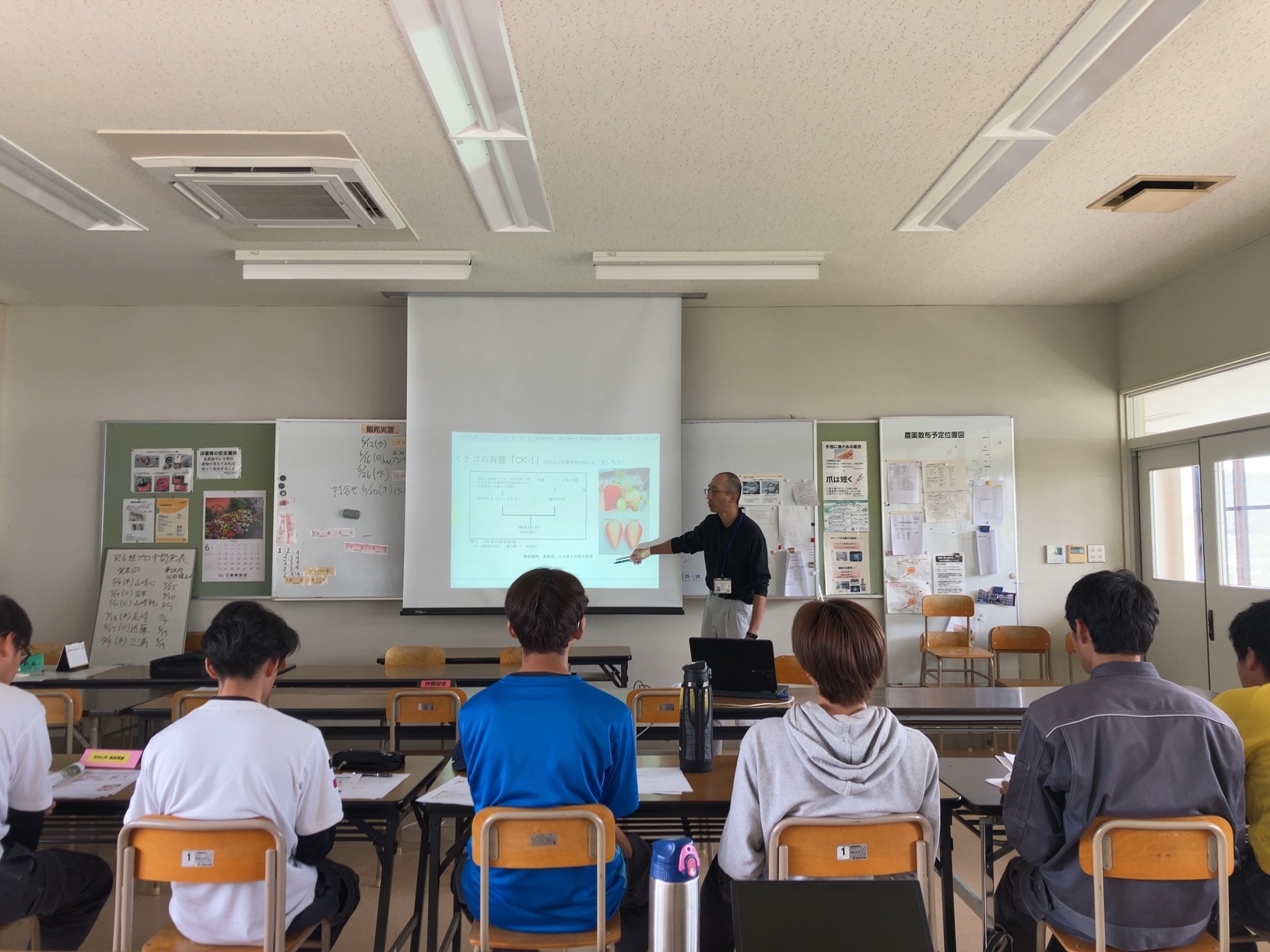
メロンの摘果と球吊りをしました! 6.6.24
6月24日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8人がメロンの摘果と球吊りをしました。
メロンは、1株4花程度人工授粉しますが、そのうち生育や外観の良い果実1個のみを残すようにします。このため、良質な果実を見極めて摘果しなければなりません。
また、果実がそのまま成長すると、重みで枝が折れてしまうことから、球吊りという作業をします。柔らかい茎を強く縛って切ることが無いよう、繊細かつ慎重で迅速な手技が求められます。
1年生は、最初はおっかなびっくりでしたが、徐々に慣れてきて、手際良く作業を進めていました。
今後、8月に収穫し、出荷予定です。お楽しみに!!
うめてらす実践販売演習のお知らせ! 6.6.20
6月20日(木)、実践販売演習(6/26開催)のための打ち合わせを行いました。
2年生7名、1年生2名の合計9名で、まずは今回出荷する生産物に合わせてテーマを決めました。今回は「夏に美味しい冷製スープ」と「華やかな食卓」をテーマに販売することになりました。
どの生産物をどちらのテーマに含めるか、誰がどの役割で、いつどのように行動するかなど、細かく打ち合わせました。
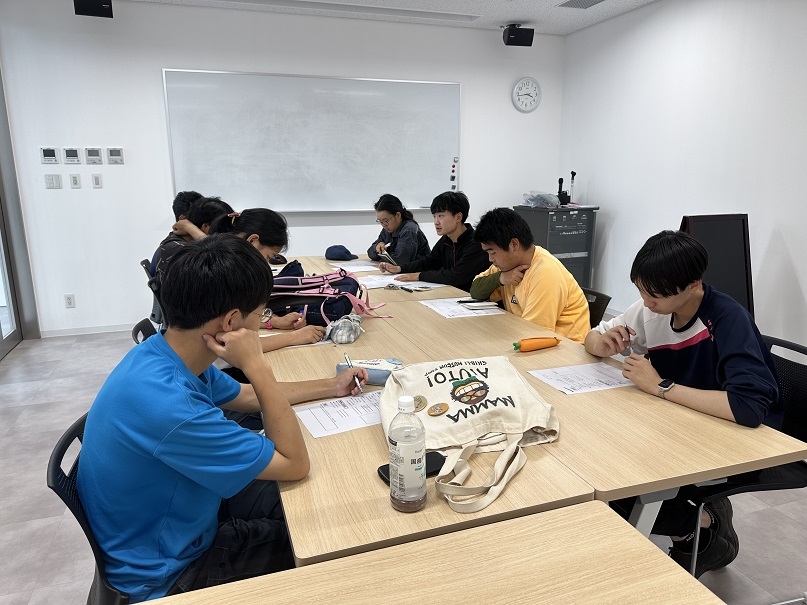

農大生の会社の第一回定時社員総会を開催 6.6.19
本校の学生による「一般社団法人やまぐち農大」の定時社員総会を6月19日(水)に開催しました。
令和5年7月に設立してから初めての総会で、事業報告、本年度事業計画及び役員選出などの議案が承認されました。
本年度は拠点祭等の農産物販売事業、県内企業などと連携した6次産業化商品の開発事業を柱に、SNS を活用した情報発信、会社ロゴの制作などにも取り組む予定です。
会長(代表理事)に選出された山崎心結(園芸学科野菜経営コース2年)は、「会社経営論」などのカリキュラムや販売事業などにより、お互いを助け合いながら共に学び、成長して行きたいと抱負を述べました。



山口農高生が農大でスマート農業を学ぶ! 6.6.21
6月21日(金)に山口県立山口農業高等学校生物生産学科植物生産コースの3年生16名が本校でドローンなどのスマート農業を学びました。
農高生は授業の一環で本校に訪れ、演習「スマート農業機械論」を参観し、ドローン操作体験をしました。
その後、リモコン式草刈機や果樹生産現場で導入の進むロボット草刈機、当技術センターが一般企業と共同開発した果樹用追従型運搬ロボットの説明を職員から受けました。運搬ロボットを体験した農高生は、想像以上に荷物が軽く運べることに驚いていました。
基礎から先端技術までの実践学修を進める本校は、今後も農業高校との連携を深め、農業に携わる人材育成を図っていきます。




ドローンの操作練習もいよいよ佳境! 6.6.21
6月21日(金)、土地利用学科2年生の大型ドローン(農薬散布用)の操作練習も3回目になりました。前回からは、ドローンのタンクに水を入れて飛ばす練習をしています。ドローンが重く、しかもタンク内の水が動くため、練習機よりも操作は難しくなります。学生達は「思ったように動かない」「難しさが半端ない」と言いながら、操作に挑戦していました。
また、水田での農薬散布を模して飛ばすため、補助者(ドローンの位置を合図するナビゲーター)が必要となります。学生達は操縦者と補助者に分かれ、インカムやトランシーバーなどの無線機を使って連絡を取り合いながら、操作練習に取り組みました。みんな、操作も上手になったけど、インカムをつけた姿もカッコよかったよ!




土地利用学科、密苗にも挑戦するぞ! 6.6.20
土地利用学科2年生の一人が、水稲の密苗(みつなえ:苗箱に播く種子量を通常より多くした苗)をテーマにした経営プロジャクト学修(卒業論文)に取り組むこととしています。6月20日(木)、この密苗を植えるために山口市の(株)四辻農機が、専用田植機を貸してくださいました。有難うございます!
最初は、ヤンマーアグリジャパン(株)の職員さんによる、専用田植機の特徴の説明です。種子量が多い苗をどのように少しずつ取って植えるのか、その仕組みを学びました。そしてお待ちかね、密苗の田植えです。今回の専用田植機は農大の田植機よりも一回り大きい機種で操作方法が違うため、(株)四辻農機社長さんの御指導を受けながら植えていきました。
田植えは1時間足らずで終了。「オペの学生さん、運転上手でしたね」、と社長さんからお褒めの言葉をいただきました。これまでの実習の成果です!
さて、農大周辺の田植えはこれで終わりました。あとは7月上旬の大道干拓での田植えを残すのみです。



農業法人で田植えを学ぶ! 6.6.19
土地利用学科の2年生が、6月17日(月)と19日(水)に、農事組合法人 二島西で田植え実習を行いました。といってもいきなり田植機に乗せてもらうのではなく、まずは補助作業から。田植機のオペレーターはみな農大の卒業生。苗や肥料の受け渡し方などを丁寧に教えてくれます。田植機の操作もムダが無く、とても参考になりますね。
さて、ずっと補助作業に従事し田植えも終盤に差し掛かった頃・・・ 田植機を操作させてもらえることになりました。それも、8条植・直進操舵機能付き田植機(GPS機能でハンドル操作しなくても直進してくれる田植機)です。やったね!
この忙しい時期、少しでも早く作業を進めたいところでしょうに、学生達のために貴重な機械を操作するチャンスを与えてくださり、有難い限りです。今回の実習を通じて、機械操作だけでなく、農業法人の田植えの流れや段取りなど、多くのことを学べたのではないでしょうか。




耕作放棄地に牛を放牧しました! 6.6.19
本校では、肉用牛の飼養管理に関する学修の一環として、放牧(山口型放牧※)の実践に取り組んでいます。
6月19日(水)、本校で飼養している妊娠牛2頭を、近隣の耕作放棄地へ移動させ、放牧を開始しました。
牛たちは、青々と茂った野草の中を、嬉しそうに駆け回り、早速、野草を食べ始めました。
今後は、牛や野草の状況から退牧の時期を判断する予定です。
※山口型放牧とは、繁殖用の雌牛を、軽量な電気牧柵で囲んだ耕作放棄地等に放牧することです。肉用牛経営の省力化や遊休地の解消による農地保全などのほか、耕作放棄地がきれいになることで、イノシシなどの獣害が減少することも確認されています。


小学生が酪農を勉強しました! 6.6.19
6月19日(火)、市内の小学2年生 約70名が農林業への理解を深めるため、本校を訪問しました。
畜産学科では、児童が酪農牛舎を見学し、子牛のブラッシングも体験しました。
子牛のブラッシングでは、児童たちよりも大きな子牛に戸惑いながらも、最後には手で触れるようになりました。
将来、農業・畜産や食に関わる仕事に就いてくれることを期待します!



あじさいまつりで販売実習をしました! 6.6.16
6月16日(日)、防府市牟礼の阿弥陀寺で販売実習をしました。
事前に下見をし、当日は朝7時30分から商品を積み込みました。8時過ぎに開店準備が整ったと同時に池田豊防府市長がお客様として来店されました。
9時30分ごろから、お客様が徐々に増え始めたため、お客様の動線にのぼりを持って立ってPRしました。おかげさまで、開店から2時間余りで用意した商品は完売しました。
次回の販売実習は、6月26日(水)防府市まちの駅うめてらすです。お誘いあわせの上、ご来場ください!



ソレーネ周南で今年度最初の販売実習をしました!6.6.12
6月12日(水)、ソレーネ周南で今年度最初の販売実習をしました。事前に打ち合わせたとおり、テーマを「夏野菜」として、トマト、ネギ、ズッキーニなどを中心に販売しました。
今年度最初の販売実習でしたが、開店時刻には大勢のお客様がお越しになり、大賑わいでした。学生たちも、売りがいのある状況に大喜びで一生懸命接客していました。
次回は6月16日(日)、あじさいまつりです。防府市のあじさい寺こと阿弥陀寺で行います。お誘いあわせの上、ご来場ください!



小学生と楽しく田植えをするはずが・・・ 6.6.12
土地利用学科の2年生は、農業法人での実習に取り組んでいます。6月12日(水)は、2名が農事組合法人 二島西(ふたじまにし)で実習に取り組みました。午後からの実習は、二島小学校5年生の田植え体験のお手伝いです。小学生が田植えするのを、そばで手伝ってあげるくらいのイメージで臨みましたが・・・そんな生易しいものではありませんでした! 小学生が植えるところ以外、全て手植えするという超ハードな実習だったのです! ふらっと写真を撮りに行った教官も急遽参加し、どんどん進んでいく田植綱に必死でついていきながら、法人の方々の指導のもと1時間半休む間もなくひたすら手植えをしました。明日は、間違いなく背中が筋肉痛ですね。
といっても、これだけ手植えする機会はなかなかありません。来年は2年生を全員参加させてみてもいいでしょうね。



やまぐちオリジナルユリの球根を掘り上げ、パッキングしました! 6.6.12
6月12日(水)、園芸学科花き経営コースでは、やまぐちオリジナルユリの球根を掘り上げ、パッキングしました。
今回掘り上げた品種は、「プチロゼ」です。5月に一度、切花を収穫し、再度定植するため、約1か月間養成し、球根を大きくしました。
球根は、掘り上げたのち、消毒します。その後、専用のコンテナに厚手のビニル袋を敷き、ピートモスと球根を交互に3~4層重ね、冷蔵庫で9月上旬ごろまで貯蔵します。
花きは、花の数や大きさ、茎の長短や曲がり、葉の一枚に至るまでが商品になります。学生たちはスタートとなる球根の管理に集中して取り組んでいました。
このユリは、9月中旬ごろ定植し、フラワーネットを使ってまっすぐに伸びるよう仕立てるなど管理を徹底し、11月上旬頃収穫する予定です。




今日のよい日のお田植えはじめ♪ 6.6.11
6月10日(月)、土地利用学科の田植えが始まりました。土地利用学科としての田植えは2年目になりますが、今年は新しい田植機での田植えです!! ワクワクの新車、 今から泥だらけにしますよ!!
さて、この日は全体的に少し深水(ふかみず:水田の水量が多い状態)だったので、苗が上手に植えられない場所もあり、田植機の調整に若干手間取りました。初日ですからちょっとしたトラブルはつきもの、予定どおりにはいかないものです。結局、予定時間を過ぎての終了となりましたが、予定していた2圃場はきちんと植えることができました。
6月11日(火)も、2圃場の田植えを行いました。しばらくは代掻きと田植えを同時進行で行うことになりますが、みんなで分担しながら乗り切りましょう。




販売実習の打ち合わせをしました! 6.6.7
6月7日(金)、ソレーネ周南での販売実習に向けた打ち合せを行いました。
販売実習は、農業経営に必要な販売に関する知識・技術を身に付けることを目的に行っています。事前に、販売する品目や品種の特徴を共有する、効果的なPOPづくりに向けた打合せを行います。
5月28日に行った株式会社イズミの山口バイヤーによる講義を受け、今回は、売り場のテーマを設けて販売してみようということになりました。
今回は、「夏野菜」というテーマでトマトなどを販売することとしました。中でも、糖度が高くなるよう栽培した『塩トマト』について、試食して特徴を共有・確認しました。
6月12日、今年最初の販売実習です!頑張ります!



家畜審査競技大会が開催されました! 6.6.12
6月12日(水)、県内農業高校の生徒約60名が来校され、本校で飼養管理する乳用牛・肉用牛を使って、牛の審査競技大会が開催されました。
本大会は、農業高校生の家畜審査技術の向上を目的に、毎年、山口県学校農業クラブ連盟が開催しています。
生徒たちは、7月並みの暑さの中、前後左右から牛を観察するとともに、実際に牛に触って毛の柔らかさや皮膚のゆとりを確認し、熱心に審査されていました。
本日の審査競技(乳用牛の部)で最優秀賞を獲得された生徒は、岩手県で開催される全国大会への出場権を獲得しました。
今後、競技に参加された生徒のみなさんが、高校在学中や農業大学校への進学を含めて牛の審査技術を一層磨かれるとともに、将来、畜産分野でご活躍されることを期待します!




ジャガイモの収穫をしました! 6.6.10
6月10日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、学生3人でジャガイモの収穫をしました。このジャガイモは、3月4日に植え付け、4月22日と5月2日に土寄せして、育てたものです。
先に刈込ばさみで茎を切り、ポテトディガーと呼ばれる機械をトラクターに装着して掘り上げました。職員が畝の高さやふるいの角度を微妙に調節し、どういう意図でどう調節したかを指導しつつ、収穫しました。
掘り上げたジャガイモは、学生が2人でコンテナに入れ、運搬車で運びました。
一週間ほど日陰で乾燥させ、6月中旬ごろ出荷予定です。



野菜経営コースのダンパー試験をしました! 6.6.7
6月7日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生のダンパー(運搬車)試験を行いました。
本校では、動力運搬車など一部の機械を運転する際は、大型特殊免許(農耕車限定)を取得することとなっています。
また、各経営コースのほ場の特徴に応じて運転できるかを確認するため、経営コース内でも改めて試験することとしています。
今回、野菜経営コース内の試験に1年生2人が挑戦し、見事合格しました!これで2人は、運搬車で資材など運ぶことができます。
引き続き、残り6名の試験を順次行います。



トマトを植え付けるための耕うん・畝立てをしました!
6.6.7
6月7日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、トマトを植え付けるための耕うん・畝立てをしました。
ここでは、6月中旬に植え付け、12月まで収穫する『夏秋トマト』と呼ばれる作型で栽培します。今回は、1年生2人で耕うんと畝立てをしました。どうやったらまっすぐに進めるか、職員の指導の下、一生懸命取り組んでいました。
植え付けた後は、かん水、誘引などを行い、7月中旬ごろ収穫開始予定です。


ハウスの屋根の掛け替えをました! 6.6.6
6月6日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、学生、社会人研修生と職員で、ハウスの屋根のかけ替えをしました。
ハウスの屋根は、放置すると、汚れで日光の透過率が低下し、作物の生育に影響を及ぼすようになります。
今回は、長さ30m、幅6mのハウスの屋根をかけ替えました。
入学して2か月足らずですが、1年生は脚立の上の作業も慣れてきた様子でした。2年生は、朝の定例作業が終わって、少し遅れての参加となりましたが、入らなければならない場所を速やかに見つけ、慣れた手つきで一緒にかけ替えをしました。
台風シーズンになる前に全ハウスを点検し、必要があるハウスはすべてかけ替えます。



タマネギを掘り上げて株の分解をしました! 6.6.5
6月5日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、タマネギの掘り上げと株の分解を行いました。
タマネギの掘り上げは、たまねぎ掘り上げ機を使いました。この機械は、タマネギを株ごと引き抜き、不要な部分をカットして畝の上に置くものです。置いたタマネギは、ピッカーと呼ばれる機械で拾い上げます。
掘り上げ終了後、株を切り、どれが「りん葉」でどれが「肥厚葉」かなどを教えられていました。1年生は初めてに近い包丁使いで、見ている方がドキドキするような切り方で、なんとか切っていました。
このタマネギは、少し乾燥させ、6月中旬ごろから出荷します。



ウメの収穫をしました! 6.6.6
6月6日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、学生、社会人研修生と職員でウメ「南高」の収穫をしました。
ウメは、親指、人差し指、中指で持って軽くひねるとぽろっと収穫できます。学生も社会人研修生も、黙々と収穫していました。
このウメは、来週から出荷します!今から暑い季節になります。農大産のウメで作った自家製のウメジュースや梅干しなどでリフレッシュしませんか!


土地利用学科、乾田直播に挑戦するぞ! 6.6.5
土地利用学科2年生の一人が、水稲の乾田直播(かんでんじかまき:畑状態の水田に種をまき、出芽したあとに水を入れる栽培方法)をテーマにした経営プロジャクト学修(卒業論文)に取り組むこととしています。学生は、この日の為に、乾田直播を実践している農業法人で播種機の設定を教えてもらい、試験場から借りた播種機を調整(種や肥料が、目標とする量をまけるように設定すること)し、準備してきました。
そして6月5日(水)、いよいよ播種です。2年生は、自分の経営プロジェクトではあるものの、1年生に経験を積ませるためにサポート役に徹し、トラクタの操作方法等を教えていました。1年生に教える2年生の姿、成長したなぁとつくづく思います(感動)。
さて、今回の播種は無事終わりました。種も肥料も、目標とする量をまくことができたようです。まずは第一段階クリア、次は除草剤の適期散布に臨みます。



小麦の収穫 6.6.3
土地利用学科では、農業法人の基幹作物の一つである小麦の生産にも取り組んでいます。昨年は小麦が倒伏(とうふく:稲や麦が倒れること)して収穫に大変苦労しましたが、今年はなんとか倒伏させずに、成熟期を迎えることができました。
そして6月3日(月)、小麦の収穫を行いました。2年生は講義で不在だったため、コンバインを操縦したのは1年生! 畝立て栽培する小麦の収穫はコンバインが揺れることも多く、操縦が難しかったかもしれません。トラブルが起きてもすぐに対処できるよう、側で職員が見守る中、1年生は頑張って収穫していました。


代かきが始まりました! 6.6.3
6月3日(月)、今年初めての代かき(しろかき:水田に水を入れてかきまぜ、泥状にすること)です。今日のノルマは、水田3枚。農業大学校のトラクタ3台を全て出動させ、学生がそれぞれ割り当てられた水田の代かきを行いました。
土地利用学科の水田は、近隣の生産者の水田を借用して実習を行っているため、形の整った水田(直線の畔が多い)は一つもなく、またいずれの水田にも石垣があって旋回時はぶつけないように気を遣うなど、初心者にとっては難易度が高めです。しかし、そこは1年間経験を積んできた2年生、上手にトラクタを操作して、代かきを行っていました。
土地利用学科では、これから約2週間ほど代かきが続きます。



ナス畑の支柱に針金を張りました!! 6.6.3
6月3日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ナスの誘引用として支柱に針金を張りました。
この支柱は5月20日に約5m間隔に立てたもので、太い支柱の間にはイボ竹を立てています。今回は、この支柱とイボ竹に針金を張りながら巻き付ける作業です。
誘引にはひもを使い片側をこの針金に、もう片側をナスの枝の先端に結び、アルファベットのYの字になるようにします。これにより受光態勢が確保され、風通しがよくなるため、着花促進、病害の予防及び品質の向上が見込まれます。
ふと畑を見渡すと、排水対策として溝が上げられていました。こうしたきめ細やかな努力が、品質の良いナス生産につながります。
今後、誘引や整枝の後、6月下旬ごろから収穫開始予定です。揚げびたし、麻婆茄子、お味噌汁の具やバーベキューの焼き野菜など、多彩な料理が思いつきますね。お楽しみに!!



ピーマンのわき芽とりをしました! 6.6.3
現在、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がピーマンのわき芽とりをしています。ピーマンは枝を4つに分けて育てています。一つ一つの枝をしっかり伸ばすため、4本の枝以外の余計な芽を除去します。最近の暖かさもあって、昨日は見えなかった芽が、今朝は見えるようになった、ということもあり、毎日注意深く株を確認しています。
学生は他の実習の間のわずかな時間もわき芽を取っていました。
こうしたたゆまぬ努力が、収量確保につながります。引き続き頑張ります!!



ピーマンのネット張りをしました! 6.6.3
6月4日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生と職員でピーマンのネット張りをしました。ピーマンは枝を4つに分けて育てています。そのままにしておくと、果実の重さで枝が下垂する、そうすると枝同士の間隔が密になって風通しや受光態勢が悪くなるといった弊害が生じます。生産者は枝吊りで対応しますが、本校では、花き経営コースで使用するフラワーネットで枝と枝の間隔を確保しています。
この日は、2組のフラワーネットを用いて支柱に固定しました。学生は「こんな姿勢でインパクトドライバーを使ったことなんかありません~」などと言いながら、それでも一生懸命取り組んでいました。
今後、伸びた枝の先端をフラワーネットの目に通して育て、6月下旬ごろ収穫予定です。



二十世紀ナシの大袋かけ! 6.6.4
6月4日(火)、園芸学科果樹経営コースでは、2年生が二十世紀ナシの大袋かけを行いました。作業を行うにあたって、「なぜ小袋が必要なの?」「小袋だけではだめなの?」と職員が質問すると、学生は「果実の表面が汚くなるため…ですか?」と答えていました。二十世紀ナシは、黒斑病という病気の予防のため、まだ小さい果実に小袋をかけます。その後、果実が肥大すると小袋は破れます。そのままにしておくと、学生の言うとおり、果実の表面が日焼けして赤くなるなど外観品質が低下すること、また、カメムシなど害虫の被害をうけることから、大袋をかけます。
外観がきれいでおいしいナシに仕上げていきます!


メロンの人工授粉をしました! 6.6.4
6月4日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生2人がメロンの人工授粉をしました。
メロンは果実になる雌花と花粉を供給して枯れる雄花が、一つの株に別々に着生します。雌花はわき芽から出る子づるに、雄花はほとんどが親づるに着くため、物理的に距離が離れており、特にハウスなど虫が飛ばない環境では人工授粉をする必要があります。
今回は、13番目から16番目の子づるについた雌花に順次授粉していきます。1年生は、筆を使って授粉する係と、どの雌花に授粉したかわかるように、テープナーと呼ばれる器具で目印のテープを付ける係とに分かれて、作業を進めました。
今後、摘果、袋掛けなどの後、8月上旬ごろ収穫予定です。


メロンなどの果実の下に敷く麦わらを拾いました! 6.6.3
6月3日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3人と職員3人で、コンバインで刈り取った後の麦わらを拾いました。
メロン、スイカ、カボチャなどは、果実を地面に接した状態で栽培を続けると、腐りや病害虫の原因になります。地面と果実の間に敷く専用のネットが販売されていますが、本校では以前から授業のために栽培し、収穫した後の麦わらを使用しています。
麦わらは硬く、重量のある果菜類の果実の下に敷いても容易に潰れることなく、また、使い終わったら土に混ぜることができます。
一生懸命集めた麦わらを敷いて、SDGsに配慮し、環境にやさしく、おいしい野菜を作ります!



キュウリの定植・誘引をしました!! 6.5.31
5月31日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生2人がキュウリの定植をしました。場所は、5月15日に耕うんし、5月16日に潅水チューブを設置し、マルチを被覆したほ場です。
今回植えた品種は「クラージュ」「兼備2号」「常翔661」の3品種で、どの品種も節なり性という特徴があります。節なり性とは、生育の最初の節から次々と雌花が着く性質で、初期収量を確保できる長所があります。
今後、生育に応じた誘引、摘心及び摘果などの作業の後、6月下旬ごろから収穫を始めます。
みずみずしいキュウリを出荷できるよう、頑張ります!



シミュレーターを活用した研修を実施! 6.5.31
林業即戦力短期育成塾では5月27日(月)から28日(火)、初めての重機操作に向けて、段階的に技術を習得するため、高性能林業機械の「ハーベスタシミュレーター」を体験しました。
併せて林業の作業現場で最も労働災害の発生が多い伐木作業に向け、予め危険な作業を学ぶことができる「林業労働災害VR体験シミュレーター」による研修も行いました。




露地ブドウの摘粒も本格化! 6.6.3
6月3日(月)、園芸学科果樹経営コースでは、露地ブドウの摘粒も始まっています。この日は、赤系ブドウの「安芸クイーン」などを摘粒しました。房ごとに粒の着き方が異なるため、1年生は「難しいです…」と言いながら、何度も見直していました。
引き続き、同じく赤系ブドウの「シナノスマイル」、黒系ブドウ「藤稔」「巨峰」「ピオーネ」「高妻」「ブラックビート」など、どんどん進めて、美味しいブドウを作りますよ!!

リモコン式草刈機を使って草刈りだ! 6.5.31
5月30日(木)、土地利用学科の2年生3人が、農事組合法人
二島東(ふたじまひがし)で草刈り実習を行いました。法人の長大な畔(あぜ)で、リモコン式草刈機を使った草刈りです! わくわく!
学生達は、(農)二島東の方から機械の操作説明を受け、リモコン式草刈機での草刈りにチャレンジしました。おー、これまでドローンの練習をしてきているからか、それともセンスが良いのか、みなスティック操作の上達が早いですね。
学生達の感想は、「楽しい!」「なかなか難しい・・・」「ずっと使っていたい」等など。次回は、農大のリモコン式草刈機も持ってきて草刈りをしてみましょう。
ちなみに、リモコン式草刈機の順番待ち時間には、各自スパイダーモア(斜面用の草刈機)を使って、約100mある畔の草刈りを行いました。これも農大ではできない経験。法人の協力に感謝、感謝です。




令和6年度第1回短期入門研修を開催しました!
6.5.31
5月28日(火)から30日(木)にかけて、新たに農業を始めようとする方(就農)や農業法人への就業に興味のある方を対象とした研修会を実施しました。
受講者は、農作業実習に精力的に取り組むとともに、就農・就業に向けた担い手養成研修生からの助言を熱心に聞いておられました。また、日を追うごとに受講生同士の仲が深まり、仲間づくりという面でも有意義な時間となったようです。




ガラス温室内のブドウ「シャインマスカット」の摘粒をしています! 6.5.31
現在、園芸学科果樹経営コースでは、ガラス温室内の「シャインマスカット」の摘粒作業を進めています。
ブドウは、一つの房になる花穂に数百個の花をつける、円錐花序と呼ばれる花の付き方をするため、開花前に、50個程度まで減らす、花穂整形を行いました。
現在は、大きくなった粒を一房35~40粒になるように整えています(摘粒)。その時、粒と粒の間が詰まりすぎていると、粒が大きくなった時に競り合ってつぶれてしまうため、形の悪い粒や育ち切らない小さい粒も除去します。円筒形の房を作るため、外に飛び出した粒も落とします。
粒が大きくなったらどんな房の形になるか想像しながら除去しなければならず、集中力が必要です。一つとして同じ房がないことから習ったことを応用する力も必要です。腕をあげての作業となるため、肩に負担がかかります。
この日は、学生2人と社会人研修生2人が「この場合はどうしましょうか」と職員に聞きながら一生懸命取り組んでいました。
摘粒後は、房の数を確認して、適正な着房数に調整後、袋掛けを行う予定です。



今年もやります! トヨタ生産方式 6.5.31
令和5年度新設の土地利用学科では、初年度からトヨタ生産方式の学修に取り組んでいます。5月29日(水)、トヨタ自動車(株)から講師を招いて今年度最初の講義を行いました。
今回のテーマは「安全」。危険予知訓練(作業や施設にひそむ危険要因を発見し、解決する能力を高めるための訓練)が中心です。講義は、以下のような段階を踏まえながら進められました。
第1段階:イラストを見て、考えられる危険をどんどん出し合う
第2段階:動画を見て、考えられる危険をどんどん出し合う
第3段階:普段使っている施設に行って、思いつく危険をどんどん出し合う
第4段階:実際の作業を見て、グループで危険箇所を話し合い、対策案を考える
演習中は、講師が次々に、何回も指名して、意見を促します。学生も必死で見て、考えて、答えます。この過程を経ることで、危険を見分けられる、危険予知の目が養われていくのですね。今回も勉強になりました!




JAのタマネギ調製・選別ラインで実習
6.5.29
5月28日(火)、土地利用学科の2年生と研修生の計11名が、JA山口県の大道ライスセンター(防府市)で、タマネギの調製・選別の実習を行いました。県内では、タマネギの調製・選別は手作業で行うところがほとんどですが、今回はJA山口県が新たに導入した機械を使った調製・選別です。
学生達は、コンベア上に流れてくるタマネギをチェックする(根や葉を切る、規格外品を取り除く)班と、タマネギが詰められた段ボール箱をテープで閉じて積む班に分かれて、作業に取り組みました。
今回のタマネギは比較的規格外品が多かったため、タマネギチェック班は大忙し。目(チェック)と手(根葉切りと選別)をしっかり働かせていました。段ボール詰め班は比較的余裕がありましたが、タマネギの詰まった箱をテープできれいに閉じるのはなかなか難しかったようです。
今回は、約4時間の作業で238箱(約2.4トン)の箱詰めを行いました。今後、土地利用学科の恒例行事になると思います。




カーネーションの蒸気消毒をしました!! 6.5.29
5月29日(水)、園芸学科花き経営コースでは、2年生がカーネーションの蒸気消毒をしました。5月23日に耕うんしたベンチに、専用のシートをかぶせ、蒸気が通る太い管をセットします。ベンチの数より管の数が少ないため、途中で管を変える作業をしなければなりません。まるでサウナのような蒸し暑さの中、学生は適度に休みながら、懸命に作業しました。
今後、6月下旬には新しい苗を定植します。来年の母の日を楽しみにしてください!

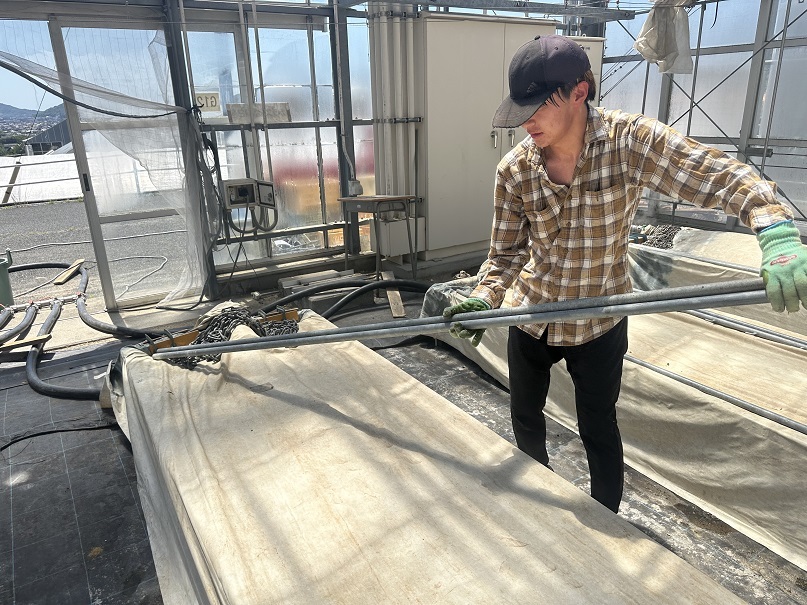
メロンの誘引をしています! 6.5.28
メロンの誘引をしています!
5月28日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、一年生が1人でメロンの誘引をしました。5月14日に15cmほどの高さで最初の誘引をした後、みるみるうちにツルが伸びて、今では80cmほどの高さになりました。こうなると、先端が垂れ下がってくるので、誘引しなおさなければなりません。
最初はツルを折らないようおっかなびっくりで誘引していた学生も、わずか2週間で、淡々と誘引できるようになりました。
今後、交配・着果作業をしながら誘引し続け、最終的には約2.5mほどの高さまで吊り上げ摘心します。



2年生、大型ドローンを飛ばす! 1年生、初めての屋外飛行! 6.5.28
5月21日(火)、土地利用学科は3回目のドローン練習を行いました。
2年生は、農薬散布に使う大型ドローンでの練習です。その大きさは、幅約150㎝、重量約13kg! いつもの練習機(幅約40㎝、重量約1.4kg)とは、存在感が違いますねぇ。2年生は、大型機の操作時や農薬散布時に気を付けることなどについて、講師から説明を受けながら、操縦に挑戦していました。練習機との反応速度の違いなどを実感したようです。
一方、これまで強風で屋内練習しかできなかった1年生、今回が初めての屋外練習です。操縦者と補助者に分かれ、操縦者は補助者にドローンの位置を教えてもらいながら、正確な位置にドローンを飛ばす練習をしました。また、座学も熱心でよく質問する、と講師も感心していました。
土地利用学科のドローン練習、夏休み前まで続きます。




ピッカーでタマネギを収穫しました! 6.5.29
5月29日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生1人と2年生2人が、タマネギの拾い上げ収穫機(ピッカー)でタマネギ「ターザン」を収穫しました。1人が運転操作、他の2人が収穫コンテナの積みおろしと、分担して作業をすすめました。
初めて使う機械で、緊張しながらも職員の指示に従って一生懸命操作していました。
6月5日には、「もみじ3号」を収穫します。


販売実践演習の事前講義を行いました! 6.5.28
農業大学校では、月2回程度、直売所の敷地を借りて、対面販売する講義(販売実践演習)を行っています。5月28日(火)には、販売実践演習を前に、県内外にゆめタウンなどを展開する株式会社イズミから青果物担当のバイヤーを講師として招き、生産物の陳列方法、POPの書き方、接客のマナーについて説明していただきました。
「売りたい商品はしっかり幅を取ってお客様の目につくように並べる」「POPには価格、産地、豆知識などを入れる必要がある。ただし、歩きながら見るので、詳しすぎないよう文言を工夫する」など、すぐに役立つことを教えていただきました。6月7日(金)には、教えていただいたことをもとに、自分たちで陳列やPOPを考えるグループワークに取り組みます。
最初の販売実践演習は、6月12日(水)にソレーネ周南で行います。皆さん、お誘いあわせの上ご来店くださいませ!


白オクラの苗を定植しました!! 6.5.27
5月27日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3人が山口伝統野菜の「白オクラ」を定植しました。「白オクラ」は発芽しにくく、生産者は一昼夜水に浸して発芽促進します。本校では、念には念を入れて、4月22日に金やすりで白オクラの種子の外皮を削り、5月1日に一昼夜水に浸して発芽を促し、翌5月2日に播種しました。努力のかいあって、430個のオクラはかなり発芽が良好で、根鉢もしっかりしていました。
この苗を、50cm間隔の2条千鳥植えで順次植え付けていきました。職員から「オクラはかなり丈が高くなるため、定植の時にしっかり土を押さえてぐらつかないようにする」などの説明を受けながら、430個の苗を植え付けていました。
このオクラは6月下旬ごろから収穫・出荷予定です。



林業の未来を切り拓く!
「やまぐち森林・林業未来維新カレッジ」を開講しました
6.5.17
5月17日(金)、本県林業の未来を切り拓く人材と林業事業体の確保・育成を促進するため、「農林業の知と技の拠点」(農林総合技術センター)を核とした新たな研修体系「やまぐち森林・林業未来維新カレッジ」(6コース49講座)の開講式を研修講座の一つ「林業即戦力短期育成塾」の初日にあわせて行いました。
当日は、受講生6名が、将来の林業担い手への決意を新たにしたところです。
同カレッジの主要な研修となる「林業即戦力短期育成塾」では、10月18日までの55日間、現場で必要な技術習得、資格取得に取り組みます。




カーネーション植え付けのための耕うんをしました!6.5.23
5月23日(木)、園芸学科花き経営コースでは、カーネーションを植え付けるための土づくりと耕うんをしました。
はじめに、赤玉土とバーク堆肥を表面に施用しました。赤玉土は通気性や排水性向上、バーク堆肥は有機質の補給が目的です。次に、専用のベンチ耕うん機を使って耕うんしました。
1年生は、ベンチの両側に足をかけ、耕うん機がベンチの土にもぐりこまないように気を付けながら一生懸命耕うんしていました。耕した後のベンチの土は、蒸気消毒しやすいように2年生が均していました。
6月下旬に苗を定植する予定です。来年の母の日に向けて、もう準備を始めています!


カボチャの誘引とわら敷きをしました! 6.5.23
5月23日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生1人がカボチャの誘引とわら敷きをしました。
わらを敷くのは、雑草対策と着果時に果面を保護するためです。また、カボチャはつるで伸びるため、放置しておくと足の踏み場がなくなります。このため、つるの伸びる方向を定める必要があります。今回は、土地利用学科からもらった麦わらを敷き、細くて丈夫な支柱を使ってつるを固定しました。
今後、追肥、交配、わき芽とりなどの管理を続け、7月下旬ごろ収穫開始予定です。



チーズ製造演習を行いました! 6.5.22
本校では、農畜産物の基本的な特性を理解し、その加工技術を習得するため、農畜産物の加工演習を行っています。
本日5月23日(木)、本校で生産した生乳とレモンを使用して、カッテージチーズを作る演習を行いました。
学生たちは生き生きと演習に臨み、生乳の特性を勉強し、出来上がったカッテージチーズの味や触感を確認していました。
将来、農畜産物の生産に加えて、加工品の製造も行い、山口県を代表する農業経営者として成長することを期待します!



ナシの摘果を行いました! 6.5.22
5月22日(水)、園芸学科果樹経営コースでは、経営プロジェクト『「王秋」のコルク状果肉障害軽減を目指した着果管理対策の検討』の一環として、2年生1人と社会人研修生1人が摘果を行いました。
ナシ「王秋」には、コルク状果肉障害という、果肉に小さなコルクのような乾いた斑点が生じる生理障害が出ることがあります。切ってみないとわからないことから、生産者を悩ませている障害の一つです。
農研機構などの研究により、摘果時期を満開20日後及び60日後にすることで、この障害を減少できることが分かっています。今回は、満開40日後に摘果する調査区(慣行区)の摘果を行いました。
王秋は、10月下旬以降出荷予定です。これで果肉障害が減るかどうか、しっかり見極めます!


ネギを播種しました! 6.5.22
5月22日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3人がネギの播種をしました。
最初に適度な太さの直管で播種のための溝を作り、次に播種します。最後に、覆土して終了です。簡単に見えますが、種は小さく、こぼさないように、一定の密度になるように、集中して続ける必要があります。
今回は、「やまひこ」「ブラックスター」「ブラックサマー」の3品種を、ベンチ内で播種する列の数を変えるなどして生育や品質を調査します。
ネギが大好きで農業大学校に進学した1年生が中心になって、職員に教えられたことを他の2人に指示しながら作業を進めていました(今回はネギが大好きな彼の一人舞台で構成しました)。
今後、間引きや施肥などをして、7月中旬頃から収穫開始予定です。


柳川の清掃をしました! 6.5.22
5月22日(水)、園芸学科、土地利用学科、社会人研修室、農林総合技術センター企画戦略部で柳川の清掃をしました。
柳川は、農業大学校内を流れている水路の一つで、擁壁は2m以上、幅も広いところは4m近くになります。
学生や職員は、水路内に生えている草をスコップ等でそぎ落としてコンテナに入れ、擁壁の上にあげるという作業を繰り返しました。
90分ほどを予定していましたが、全員が一生懸命頑張って、約60分で終わりました。皆さん、お疲れ様でした!



高校生が牛の審査を勉強しました! 6.5.22
5月22日(水)、県内農業高校の生徒約60名が来校され、本校等で飼養管理する乳用牛・肉用牛を使って、牛の審査を勉強されました。
農業高校では、家畜の審査技術向上のため、毎年6月に家畜審査競技(山口県学校農業クラブ連盟主催)が開催されています。今回、本大会に向けて牛の大きさや体型等、審査のポイントを学びました。
生徒たちは、前後左右から観察するとともに、牛を触って毛の柔らかさや皮膚のゆとりを確認するなど、熱心に勉強されていました。
今後、本日学んだことを各学校で復習され、本大会で全力を尽くされるとともに、卒業後は本校に進まれ、畜産・農業に関する知識や技術を深められることを期待します!



ナスの天敵を増やすため、ゴマの定植を行いました! 6.5.21
5月21日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクト「露地ナスにおける土着天敵を活用した防除体系の検証」の一環として、ゴマの定植をしました。
ゴマは、ナスの害虫であるアザミウマ類を好んで食べるタバコカスミカメを増やしてくれます。このゴマは、4月22日に播種したもので、この高さになるまでに約1か月かかりました。今回は、約5mおきに1株のゴマを定植しました。
今後、同じくアザミウマ類の天敵であるヒメハナカメムシを増やすため、ゴマと同じ日に播種した育苗中のサルビアを近くに植える予定です。


経営プロジェクト中間発表会(第3回目)を行いました!
6.5.21
5月21日(火)、園芸学科では、第3回目の中間発表を行いました。今回は、『「ゆめ果菜恵」※における高糖度冬春トマト生産に向けた塩分ストレス下での生産技術の検討』と題して、担当した2年生が、昨年9月から取り組んできた内容を発表しました。
この課題は、高糖度トマトを生産するために塩によるストレスをかけ、生育や果実品質、収量、経営に及ぼす影響を調査するものです。
担当した学生は、事前に一生懸命調べて、職員からの質問にもしっかり答えていました。担当している職員からも、わかりやすい補足があり、充実した内容になりました。
次回は、7月18日(木)に開催予定です。
※(株)サンポリが販売している隔離栽培キットです。


ピーマンの定植を行いました!! 6.5.20
5月20日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ピーマンの定植を行いました。
5月16日に部材をプラモデルのように組み合わせて潅水チューブを設置し、その上にマルチを被覆して準備した畝に、1年生4人が2班に分かれ、植穴の位置を決める人と植穴をあける人に役割分担して植穴を作りました。職員から「ナス科は穂木の自根が出るのを防ぐため、畝の面より2cmほど高めに植え付ける」などと指導を受けた後、学生たちは順次植え付けていきました。
このピーマンは、今後誘引準備や整枝などを行い、6月中旬に収穫・出荷予定です。


ナスの支柱立てを行いました!! 6.5.20
5月20日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ナスの支柱建てを行いました。
トマトやナスは、生育に伴い茎が上方に向かって伸びます。ここに実が着き重くなると、茎が支えきれずに折れる、台風などに伴う強風で倒れる、といったことがあります。
今回は、約5mごとに太い鉄管を専用の道具で打ち込み、鉄管と鉄管の間はイボ竹を差し込んで支柱を作っていきました。
約120本の支柱を、2年生1人と社会人研修生2名で一生懸命打ち込みました。
このナスは、6月中旬に収穫・出荷予定です。



キュウリの潅水チューブ設置とマルチ被覆を行いました!! 6.5.16
5月16日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生3人でキュウリを植え付けるための潅水チューブ設置とマルチ被覆を行いました。
最初は、「潅水チューブってどっちが上?」などと言っていましたが、職員の指示を受けると、自分たちで設置の順番などを工夫しながら、手際よく組み立てました。
次いで、1人がベンチの木枠の上に上がってマルチを展張しながら、残り2人がマルチを埋め込む作業をしました。不安定な足場の上でしたが、熱心に頑張りました。
ここには5月下旬にキュウリを定植します。定植後は整枝・誘引し、6月中旬ごろ、収穫・出荷予定です。



ブドウのジベレリン処理真っ最中! 6.5.16
現在、園芸学科果樹経営コースでは、ブドウのジベレリン処理の真っ最中です。
ジベレリン処理は、無核化(種なしブドウにする)と着粒安定という効果があり、多くの品種では、満開の前後に行います。
この日は、赤系ブドウの「安芸クイーン」などに処理しました。
ジベレリン処理から数日すると着粒が確認でき、直ちに摘粒作業に入ります。
美味しく、種がない食べやすいブドウに育てます。8月上旬から出荷開始予定ですので、ぜひお召し上がりください!


中学生が職場を体験されました! 6.5.16
5月16日(木)、市内の中学生5名が職場体験に来校されました。
畜産学科では、酪農経営コースと肉用牛経営コースそれぞれの施設を見学し、実習内容を確認した後、子牛の哺育と繁殖牛への飼料給与を体験しました。
今回来校した生徒は、みなさん動物が好きで、特に牛が好き人もいました。
将来、畜産や農業に関わる道に進まれることを期待します。




土地利用学科、現地実習の様子(5月第3週) 6.5.15
5月13日(月)と15日(水)、山口市の農事組合法人 二島東で実習を行いました。13日はタマネギの調製作業。タマネギの葉と根を切り取り、黒く変色した薄皮をむき、「秀」「優」「規格外」に分ける作業です(「秀」は「優」より良品)。白い皮が見えるものは「優」にするなど、農大での調製とは違う難しさがありましたが、学生達は黙々と取り組んでいました。15日はタマネギの拾い上げ。畝の上で乾かされたタマネギを、機械でどんどん拾ってコンテナに入れ、コンテナを軽トラックに積む作業です。軽トラックにコンテナを積み込むのは大変な作業ですが、学生としては筋トレになるので良かったとか・・・?
また、5月15日(水)は山口市の農事組合法人二島西でも実習を行いました。作業内容は、大麦収穫の補助、タマネギ収穫用コンテナの運搬です。収穫するコンバインは6条刈120馬力!(少しだけ操縦させてもらえました) 運搬するコンテナ数は3,800個!
農大とは桁違いの規模を、肌で感じ取ることができたのではないでしょうか。




草刈り、草刈り、草刈り! 6.5.15
5月に入ると、草も勢いよく伸び始めます。5月15日(水)、土地利用学科では1年生の練習も兼ねて、一斉に草刈りを行いました。
1年生は担当エリアに分かれて、刈払機、スパイダーモア(斜面の草を刈ることができる機械)、自走式ハンマーナイフモア(平坦地の草を楽に刈ることができる機械)を使い、どんどん草を刈っていきます。特に、スパイダーモアやハンマーナイフモアを使うのは初めてのため、教官や2年生から操作方法を教わりながらの草刈りです。指導していた2年生から「先生、1年前の私より断然上手ですよ!」と驚きの声。それは、あなたの教え方が上手だからですよ。
これから草刈りシーズンに入ります。作業に、暑さに、徐々に体を慣らしていきましょう。




サツマイモを定植しました! 6.5.15
5月15日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、サツマイモの定植をしました。5月2日に、野菜栽培各論の一環としてマルチ被覆した畝に定植しました。品種は、果肉が黄白色の「紅はるか」「なると金時」と紫色の「ふくむらさき」です。
職員から、「土中に3節ほど埋まるように斜めに植え付け、その後、マルチのバタつきを防ぐため苗の周りに盛り土する」と指導を受け、1年生8人は一生懸命植え付けました。
植付に際しては、マルチに穴をあける人、苗を配置する人、植え付ける人に手早く役割分担し、400本の苗を定植しました。
このサツマイモは、11月の拠点祭を中心に販売していきます。甘いサツマイモになるよう一生懸命育てるので、ぜひ買いに来てください!!




ピーマンを植え付けるための畝を立てました!
6.5.15
5月15日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生が職員指導の下、ピーマン等を植え付けるための畝立てをしました。
最初に、畝のセンターを取りやすくするため足跡で印をつけました。次に、高畝にするため管理機で土を寄せました。さらに、畝立て成型機で畝を作りました。合計4本、1人で一生懸命作業しました。
この畝には、4月下旬に鉢上げして現在育苗しているピーマンとパプリカを定植します。
今後、潅水チューブを設置し、マルチ被覆をしたのち、5月下旬に定植する予定です。


カーネーションの撤収! 6.5.15
5月15日(水)、園芸学科花き経営コースでは、カーネーションを撤収しました。
花き類の栽培は、植え付け前に土壌消毒、播種やフラワーネットの準備が必要です。同時に、播種または苗の購入をします。定植、潅水や施肥など一連の栽培管理、収穫・調製・出荷、と次々に作業が押し寄せます。このため、綿密に計画を立て、無駄の無いように作付けしなければなりません。
この日は、大きな需要のある母の日を過ぎたため、撤収と自作に向けた準備を行いました。2年生と職員で刈込ばさみで株を切り、マルチをできるだけ破らないように慎重に引き抜き、まとめて廃棄用バケツに入れて持ち出していました。
多くの花き類は、播種や定植~収穫までが3~6か月ですが、カーネーションは約1年と、長期間にわたり栽培します。6月には、来年の母の日に向けて、再びカーネーションを植え付けます。



第一回就農前集合研修を開催しました(社会人研修室)
6.5.15
5月15日(水)就農を控えた研修生を対象とした研修会を実施しました。参加者は、就農・就業に向けた心得や就農計画の作成方法等について熱心に聞いていました。


オクラを植え付けるための畝立てを行いました!
6.5.15
5月15日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がオクラを植え付けるための畝立てを行いました。
専用の畝立て成型機を使い、あらかじめ目印を付けて中心をずらさないよう集中して、4畝をまっすぐ立てました。さらに、一番外側に、防風目的のためのソルゴーを植え付ける畝も立てました。
4月25日に皮を削り、5月2日に播種したオクラは、学生が管理し、現在、本葉が展葉して、生育は順調です。
収穫は7月上旬頃に開始予定です。


キュウリを植え付けるためのベンチ耕うんを行いました! 6.5.15
5月15日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がキュウリを受け付けるためのベンチ耕うんを行いました。
学生は職員と一緒に、専用のベンチ耕うん機をベンチの中に上げ、ベンチの板に足を掛けた不安定な姿勢でも、機械がしっかり耕うんできるように重心を調整するなど、慎重に操作していました。
今後、潅水チューブを設置し、マルチを被覆し、5月下旬に定植します。



経営プロジェクト中間発表会(第2回目)を開催しました! 6.5.14
5月14日(火)、園芸学科では第2回目の中間発表会を開催しました。今回は、『イチゴ「CK1号」の特性把握と導入効果の検討』と題して、担当した2年生が、昨年7月から取り組んできた内容を発表しました。
この課題は、「CK1号」の育成に携わった農林総合技術センターと連携して取り組んでいるものです。2年生は、職員や学生からの質問に熱心に答えていました。
参加した学生や研修生・職員は、発表が終わった後、栽培しているハウスの中で「CK1号」に実際に触って、果実の硬さを確かめるなどしていました。
次回は、5月21日(火)に開催予定です。


メロンの誘引を行いました! 6.5.14
5月14日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8人と社会人研修生4人で、メロンの誘引を行いました。
あらかじめ2年生と1年生が協力して作って結束していた約300本の誘引ヒモと専用の器具を使って、メロンのつるを誘引します。
学生たちは、職員から教えられたとおり、わき芽や雄花を除去しながら誘引していました。
収穫は8月上旬を予定しています。美味しいメロンになるよう頑張ります!



ナスの定植を行いました! 6.5.13
5月13日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8人と社会人研修生4人で、ナスの定植を行いました。
研修生が運搬車で約700本の苗を運び、その間に学生は運ばれた苗を畝の手前まで移動する係、マルチに穴をあける係などに役割分担して準備しました。
その後、全員で定植しました。前日の大雨で土がぬかるむ中、皆、一生懸命作業していました。
今後、整枝・誘引などを行い、6月中旬ごろ、収穫予定です。



トルコギキョウの生育調査をしました! 6.5.9
5月9日(木)、園芸学科花き経営コースでは、経営プロジェクト「トルコギキョウの少量培地耕の検討」の一環として、生育調査を行いました。
トルコギキョウは、少量培地での栽培により、土耕栽培と比べ花もちが良くなる、草姿がコンパクトになるとされています。
しかし、県内のトルコギキョウ栽培では、土耕栽培が中心のため、本プロジェクトで少量培地耕に取り組み、土耕栽培と比較して品質の差が生じるか検証します。
担当の2年生は、メジャーをあてて草丈を測りながら一生懸命記帳していました。
このトルコギキョウは、8月上旬に収穫・出荷予定です。



現地実習の様子(5月第2週 その2) 6.5.13
土地利用学科2年生の2名が、5月8日(水)から10日(金)の3日間、山口市の農事組合法人 二島西(ふたじまにし)で現地実習として小麦の農薬散布の補助を行いました。(農)二島西には、農大の卒業生が3名就職しています。その先輩達に連れられて、ドローンのバッテリー交換や農薬の調整などをさせてもらいました。学生は、初めて見る自動航行・自動散布ドローン(送信機での操作が不要)での農薬散布に、とても感動したようです。
また、5月9日(木)の農事組合法人 二島東(ふたじまひがし)では、耕耘とタマネギ掘り取りの補助を行いました。圃場の条件が悪かったためタマネギ掘取機の操作はさせてもらえませんでしたが、学生達は畝の上に掘り出されたタマネギの葉を切ったり、タマネギを畝の中央に寄せる作業に黙々と取り組んでいました。しゃがんだり、中腰になったりしながらの作業は結構辛かったと思いますが、よく頑張りました! 土地利用学科でもこれから中生タマネギを収穫する予定ですが、作業を具体的にイメージできたことと思います。


現地実習の様子(5月第2週 その1) 6.5.13
5月8日(水)、土地利用学科2年生3名が、防府市の農事組合法人 上り熊(あがりくま)で現地実習を行い、タマネギを掘り取りました。法人の構成員20名と一緒に、約30アールのタマネギを手で抜いてきれいに並べていきます(刈払機で葉を一斉に切っていくため)。さて、土地利用学科でも4月1日に早生タマネギの抜き取りをしましたが、その時と比べてどうでしたか? 学生からは「雑草がない」「タマネギが浅植えで抜きやすい」「葉を刈っていないので抜きやすい」との声。ただ作業をするだけでなく、次作での改善点も学んだようです。なお、5月10日(金)にも(農)上り熊にうかがい、抜き取ったタマネギを全てコンテナに入れて運び出しました。
5月10日(金)は2年生2名が、(株)ファーム大道(だいどう)でもタマネギの拾い上げを行いました。こちらではピッカー(タマネギを拾い上げてコンテナに入れる機械)を使い、少人数でタマネギを拾い上げて運び出す機械体系を学びました。土地利用学科の中生タマネギでもピッカーを使う予定ですが、今回の実習で操作のポイントをつかむなど、良い予行練習になったようです。



今年度最初の中間発表を行いました! 6.5.9
農業大学校では、経営プロジェクトの一環として、中間発表を行うこととしています。この日は、野菜経営コースの学生が「複合環境技術制御装置を用いた匠の技の実践とイチゴの生育・収量に及ぼす影響への評価」と題して説明し、質問に答えました。
大勢の前で発表する経験は少なく、緊張している様子がよく伝わってきましたが、しっかり丁寧に説明していました。
次の中間発表は、5月14日に行います。


ナシの小袋掛け真っ最中です! 6.5.9
5月9日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、今日からナシの小袋掛けに取りかかりました。
見た目が緑色の「二十世紀」や「なつしずく」は、袋をかけずに育てると果皮が汚くなるため外観品質が低下します。また、梨の花が満開後一定の時期までに袋掛けしないと、病原菌に感染するリスクが高まります。このため、満開後1か月を目安に小袋と呼ばれる袋を掛けます。
この日は、「ゴールド二十世紀」に小袋を掛けていきました。
普段は学生や社会人研修生が3~4名で行っていますが、この日は2年生1名が肩より上に手を上げる負荷の強い姿勢で、時に逆光で顔をしかめながら一生懸命取り組んでいました。この先、大袋掛けや夏の枝管理が待っています。
きれいでおいしいナシになるよう、まだまだ頑張ります!


キュウリの呼び接ぎをしました! 6.5.9
5月9日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、野菜栽培各論の一環として、1年生8人と社会人研修生4名でキュウリの呼び接ぎをしました。
このキュウリは、4月30日に学生が種をまいて育てたものです。
最初に、職員から「接ぎ木について」説明し、穂木や台木などの用語を、実物を見ながら学習しました。
次に、経験者の1年生が、カミソリの刃を持ちながら、「まず、台木の生長点を取る。次に、台木は上から下に、穂木は下から上に斜めに切り込みを入れて、器具で固定する。」と実際にやって見せました。
中には切り込みを入れすぎて切り落とす学生もいましたが、何とか頑張って接いでいました。
接ぎ木に成功したキュウリは、5月下旬ごろ、ほ場に定植予定です。




メロンを定植しました! 6.5.8
5月8日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生1名と1年生8人でメロンの定植を行いました。担当している2年生は、集まった8人を、苗を配る係と植え付ける係に手早く役割分担し、植え付け方法を説明した後、速やかに作業を進めました。1年生は2年生に教えられたとおり、黙々と植え付けていました。
2年生は、「去年は害虫が多発したので、今年は頑張って良いものを作ります!」と意気込んでいました。
今回植え付けた品種は「ミラノ夏Ⅰ」で、各種病害に強く、高糖度が期待できる品種です。
この後、同じ長さの誘引ヒモを作り、つるを切らないように丁寧に吊り上げていきます。さらに、交配、摘果などの作業を経て、収穫は8月上旬ごろに行う予定です。


セット動噴洗浄研修会を開催しました! 6.5.8
5月8日(水)、園芸学科野菜経営コースが中心となって、セット動噴洗浄研修会を開催しました。セット動噴は、農薬散布などに使用します。丁寧に洗浄しないと、薬液を入れるバケツ、噴霧器、ポンプ、ホース、ノズルのどれにも農薬の液(薬液)が残るリスクがあります。このため、2年前から毎年研修会を行っています。今回は、約20名が参加しました。
2年生が「まずバケツを洗って、次に吸水ホースとフィルター、余水ホースを洗います。」など手順を丁寧に説明しました。
聴講していた学生や研修生からは、「巻いているホースは洗わないのですか」「バケツの外側に付いている薬液はどうしますか」などの質問があり、「マニュアルには書いてありませんが、ホースやバケツの外側も洗っています。」などと答えていました。学生は、職員とともに「書いていないがやっていることを記入するなど、マニュアルをどんどん改訂していかないといけないですね。」と話していました。
説明した学生にも、聞いていた学生、社会人研修生、職員にも、実りある研修会となりました。


農業法人での実習が始まりました 6.5.8
土地利用学科の2年生は、定期的に農業法人で実習を行い、農業法人の運営や生産の流れを学ぶこととしています。
5月2日(木)、防府市の(株)ファーム大道(だいどう)と、山口市の農事組合法人 二島東(ふたじまひがし)で実習を行いました。
(株)ファーム大道での実習は、タマネギの農薬散布でした。使用する機械は、キャビン(ガラス張りの操縦席)付きの乗用管理機で、一度に散布できる幅は15m、散布量は車速に合わせて自動調整されるという、高性能なものです。学生もさぞワクワクしながら実習できたことでしょう。
(農)二島東での実習は、耕耘と除草剤散布でした。乗用機械の安全な乗り降り、操作パネルの説明、タイヤ跡を残さない耕耘方法など、丁寧に教えてもらったとのこと。農業法人の方々の人材育成に視点をおいた指導に、只々感謝です。
これからタマネギの収穫、田植え等の農繁期を迎えます。積極的に実習に行き、知識・技術の向上に励みましょう!



今年もドローンの操作練習を始めました 6.5.8
土地利用学科では、トラクタやコンバイン同様、ドローンも重要な農業機械の一つと位置づけ、1年次では基本的な操作方法、2年次では農業現場での活用等について学修することとしています。
5月7日(火)、1回目の講義・操作練習を行いました。講師は、昨年度に引き続き腕利きのドローンパイロット集団「やまぐちドローン操友会」の方々です。
午前は2年生の練習。昨年度の復習として、平面飛行、立体飛行(平面飛行+上昇下降)、円形飛行を行いました。2年生の大半は半年間ドローンを触っていないとのことでしたが、なかなかどうして腕は衰えていませんでしたね。
午後は1年生が初練習。ドローンを使用する際に必ず覚えておかなければならないことなど、ドローンの基本的な操作方法を学びました。当面の目標は、秋のオープンキャンパスで高校生に操作方法を教えることですね。
今年度は、夏休みまでに計6回練習を行う予定です。




母の日の前に大急ぎでカーネーションを調製しています! 6.5.8
現在、園芸学科花き経営コースでは、母の日を前にカーネーションやダリア、やまぐちオリジナルユリの出荷調製に大忙しです。
この日は、1年生と職員の合計3名で山ほどあるやまぐちオリジナルユリを一生懸命調製していました。
まず、台の上に敷いた布に書かれた線に茎の末端をそろえて、長さを測ります。次に、虫や病気の被害を受けている蕾などを落とします。最後に、末端の葉をしごいて落とします。
「その容器の中のを全部調製するの?」と尋ねると、学生は「まだ冷蔵庫に大量にあります」と言いながら、手を止めずに調製を続けていました。
5月12日は母の日ですね。日頃言えない感謝の言葉を、花束に込めて送ってみてはいかがでしょうか。



子牛が産まれました! 6.5.8
5月8日(水)9時30分頃、畜産学科肉用牛経営コースで飼養管理する肉用牛(黒毛和種)の繁殖牛が雄子牛を出産しました。
分娩房(出産用の部屋)に設置したカメラの映像をタブレットで確認することで、分娩の様子を見守り、出生後は学生や職員が畜舎に行き、タオルや乾いた草で子牛の体を拭きました。
本校では学修にIoT技術を取り入れており、今回は牛に取り付けたセンサーから分娩通知をメールで受信し、カメラで分娩の様子を教室から確認することで、何度も畜舎へ確認に行く手間を省力化しています。
今後は、生まれた子牛が大きく元気に育つよう、学生・職員が丹精込めて飼養管理していきます!




サツマイモを植えるためのマルチ被覆をしました!6.5.2
5月7日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8名と社会人研修生4名でサツマイモを植えるための畝にマルチを被覆しました。
事前に職員から「黒色マルチに期待される効果は?」などと聞かれ、学生たちは「草抑え」「地温上昇」などとしっかり答えていました。
職員と社会人研修生でお手本を見せた後、学生たちも、マルチを展張する人、両横でマルチに土をかぶせる人の3人一組になって作業に取り組みました。
前日の雨で足元がぬかるむ中、土を練るようにマルチにかぶせたことから、30mのマルチを被覆し終わると、学生たちは一様に腰が重くなったようなしぐさをしながらも、次の畝に向かって頑張って取り組んでいました。
この畝には、5月15日にサツマイモの苗を植え付けます。




キュウリの台木を播種しました! 6.5.2
5月2日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がキュウリの台木となるカボチャの種をまきました。
キュウリはウリ科の作物で、草勢の調節や病害回避のため、同じくウリ科のカボチャを台木として接ぎ木します。
4月30日に播種したキュウリの台木として、今回はカボチャ「ときわパワーZ2」を播種しました。
1年生は、キュウリの時と同じように、指で溝を作って種の向きをそろえながら、「種が大きいからキュウリよりは楽かも」と言いながらまいていました。
このキュウリは、来週行われる栽培各論の講義にて、接ぎ木予定です。



カボチャを定植しました! 6.5.2
5月2日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生と1年生でカボチャ「くりまさる」の苗を定植しました。
70cm間隔でマルチに穴をあけ、ポットで育てた苗を植え付けていきます。
職員が「ポットからいったん出して、水の中に3秒ほどつけて吸水させ、植穴を少し掘って植える。ポットの土の表面と畝の表面が平らになるくらいまで掘る。」と説明した後、学生たちで水に漬ける係と植え付ける係で役割分担して植え付けました。
今後、7月下旬ごろ収穫予定です。



ミニトマトを定植しました! 6.5.2
5月2日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、2年生と1年生でミニトマトの定植をしました。このミニトマトは、経営プロジェクト「ミニトマト栽培における台木の違いや高接ぎ木法が青枯病の発生や生育、収量に及ぼす影響について」の一環として栽培するもので、一見同じ苗に見えますが、①2種類の台木、②台木と穂木を接ぐ位置を通常より高い場所で接いだ高接ぎ木苗、③通常の高さで接いだ苗、④台木と接ぎ木せずに育てている自根苗で、合計5種類あります。この5種類の苗を一つの畝に順番に植えていきます。
効率的かつ順番どおりに定植するため、入念に打ち合わせをした後、植穴をあけ、苗を置きました。次いで、職員から「浅植えにして、しっかり周りの土となじませる」などの注意点を聞きながら定植していました。
このミニトマトは、6月上旬から収穫予定です。




オクラを播種しました! 6.5.2
5月2日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がオクラの種をセルトレイにまきました。
この種は、4月25日に鉄やすりで種皮の一部を削ったものです。根気よく削った種は、なんと430個ありました。
昨日から吸水させたところ、種が一回り大きくなり、中にはすでに発芽しそうなものも見られました。
職員から、セルトレイに土を充填する方法、あける穴の深さなどを聞いた後、自分でも実際に取り組みました。
今後、5月下旬に定植し、6月下旬に収穫予定です。



ナスの施肥・耕うん・畝立てをしました! 6.5.1
5月1日、園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクト「露地ナスにおける土着天敵を活用した防除体系の検証」の一環として、ナスを植え付けるための施肥、耕うん、畝立てを行いました。
肥料を施用した後、トラクターに乗って耕うんし、目印として足跡を付けました。その後、足跡にトラクターのセンターマーカーを合わせて、曲がらないように注意しながらトラクターに付けた畝立成型機で畝を立てました。
今後、畝にマルチを被覆し、5月中旬にナスを定植し、土着天敵の種類や量、害虫による被害の程度などを調査します。




ブドウの花穂整形が始まりました! 6.5.2
5月2日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、学生と社会人研修生が、ガラス温室内のシャインマスカットの花穂整形を始めました。
ブドウは、1本の枝に1~3房、1つの房には数百の花が着生します。まず、1枝1房として、その房の先端3~4cmを残して他の花蕾を除去します。
先端の細い専用のハサミを使って、集中力を切らすことの無いよう、一生懸命取り組んでいます!
美味しいブドウになるよう、心を込め、集中して頑張っています!




コンバインの清掃は、ボルトを折らないよう注意!
6.4.30
4月30日(火)、土地利用学科ではコンバインの清掃を行いました。水稲の収穫後に一度清掃していますが、麦の収穫前に再度徹底的に清掃するため、そして1年生にコンバインの清掃を教えるために実施しました。
実は、農大のコンバイン清掃では、毎年ボルトをねじ切る(締め過ぎ又は逆回しで折ってしまう)トラブルが起きています。1年生は、みな今年度第1号にならないように注意しながら、慎重に作業していました。結果、今回はボルト折損ゼロ。手が届きにくい場所のボルトを、コンバインの下に潜り込んで外した1年生もいました。なかなか積極的でいいですね!
さて、部品を外してみると、コンバインの中には意外なほど籾やワラ屑が残っています。学生達は、部品を洗ったり、圧縮空気(コンプレッサー)で籾等を吹き飛ばしたり、回転部分に詰まったワラ屑を手で取り除いたりと、地道に清掃していました。きれいになって、オイルもさしたことですし、麦の収穫が順調にいくことを期待しています。




キュウリを播種しました! 6.4.30
4月30日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、キュウリを播種しました。
最初に、職員が「このトレイは約50cmだから、5cmおきに9列、1列6粒で54粒になる」「第一関節の深さまで掘りながら筋をつける」「種の向きを合わせてまく」などと教えながらやってみせました。学生は、教えられたことを自分なりに解釈しながら、取り組んでいました。
今回は、「兼備2号」「クラージュ」「常翔661」の3品種を植え付けました。この後、呼び接ぎをしたあと移植し、6月中旬ごろ収穫予定です。



カボチャを植えるための耕うんと畝立てをしました!
6.4.30
4月30日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、カボチャを植え付けるための施肥、耕うん、畝立てを行いました。
肥料を施用した後、トラクターに乗って耕うんし、目印として足跡を付けました。その後、畝立成型機で畝を立てました。
畝立成型機はいくつもレバーがあり、学生は職員に教えてもらいながら、まっすぐな畝を立てるため、集中して作業していました。
明後日には育苗中の苗を定植し、7月下旬ごろ収穫予定です。



サツマイモを植えるための耕うんと畝立てをしました!
6.4.26
4月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、サツマイモを植えるための耕うんと畝立てをしました。
まず、2年生がトラクターに乗って耕うんした後、目印として足跡を付けました。次に、足跡に沿って、溝上機で畝の中心となる場所に土を寄せました。最後に、畝立成型機で畝立てました。2年生は溝上機や畝立整形機の使い方も丁寧に教えてくれました。
今後、5月中旬に苗を定植する予定です。




出生牛に初乳を給与しました! 6.4.30
4月26日(金)未明、畜産学科酪農経営コースで飼養管理する乳用牛(ジャージー種)が雌子牛を出産し、学生が初乳を給与しました。
生まれたばかりの子牛は病気に対する抗体を持たないため、初乳(分娩直後の母乳)から抗体を得る必要があります。
入学して間もない1年生が、母牛から搾った初乳をバケツに入れて、慣れない手つきで給与しました。
始め、子牛も哺乳には慣れていませんでしたが、バケツの乳首が口に含まれると、上手にごくごくと飲み始めました。
将来、母牛のように丈夫な子牛が産めるよう、学生・職員一同、大切に育てていきます!


メロンの糖度調査をしました! 6.4.26
4月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの糖度調査をしました。
昨年11月上旬に播種し、約半年間丁寧に育てました。このたび、収穫期をむかえるにあたり、糖度検査を行いました。
これまでは春と夏に播種してベンチに定植し、それぞれ夏と秋に収穫する栽培でした。今回は、晩秋に播種して畝に定植し、春に収穫する栽培に挑戦しました。
品種は「早春のマリアージュ」で、糖度は13.8度となり、目標としていた13度を超え、美味しい味に仕上がっていました。
今後、3か所の直売所に出荷予定です。


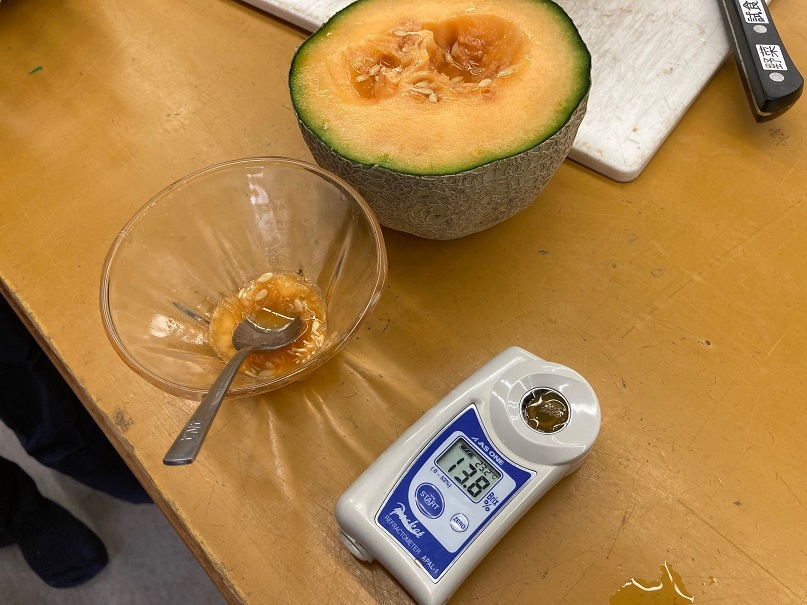

GAP概論始まりました! 6.4.25
4月25日(木)、1年生の共通科目「GAP概論」が始まりました。
今回は、ASIAGAP指導員及びJGAP審査員補の資格を持つ、合同会社つちかい代表社員の大神健治さんを講師に迎え、『GAPを始めてみませんか』と題しての講義でした。今回は、補助として卒業生も参加してくれました。
大神さんは、「あなたにとって安心・安全な農産物とは何ですか」などと学生に問いかけながら、スライドで丁寧に説明されました。
今後、ヒヤリハットやトレーステストなどを通じて、GAPの理解を深めます。

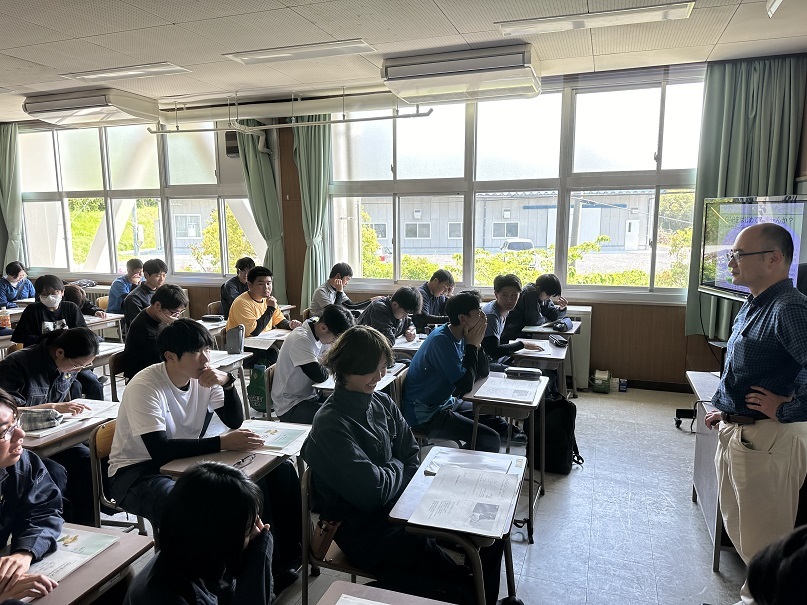


オクラの種の皮を削りました! 6.4.25
4月25日(木)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、白オクラの種子の皮むきをしました。
白オクラは、山口県長門地域で栽培されている伝統野菜です。
一般的にオクラの種子は硬い種皮でおおわれており、そのままは種しても発芽しにくい、あるいは発芽ぞろいが良くないことが課題です。
そこで、このたび、オクラの種皮を鉄やすりで一部削り、胚乳を出す作業に取り組みました。
5月1日に、削った種を一昼夜水に漬け、翌日(5月2日)には種する予定です。芽が出るか楽しみです!
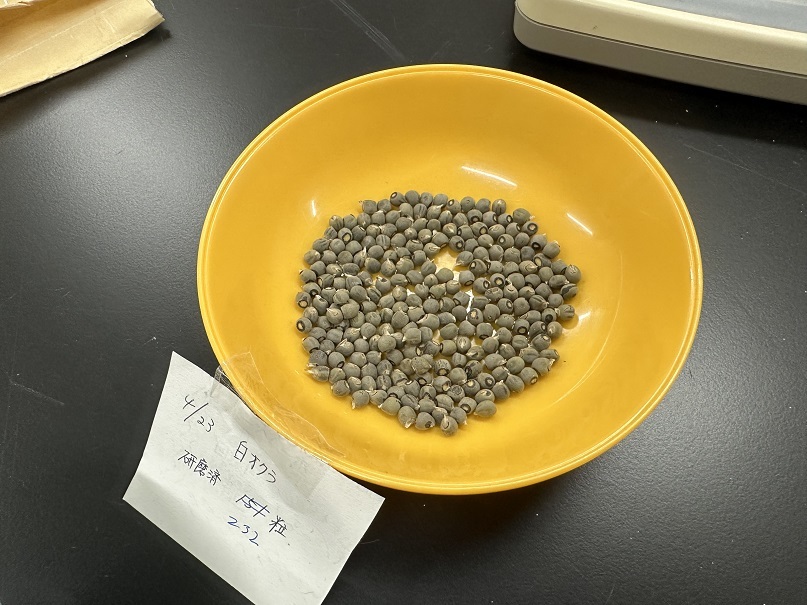
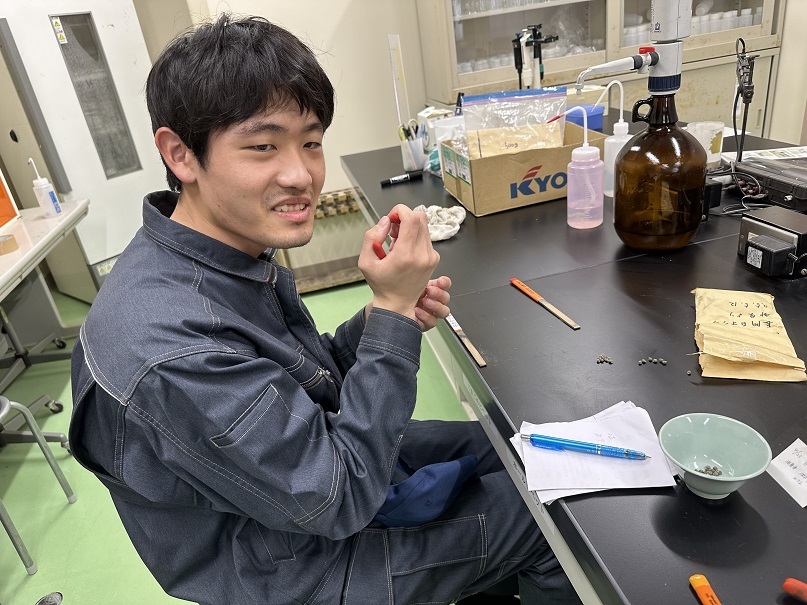
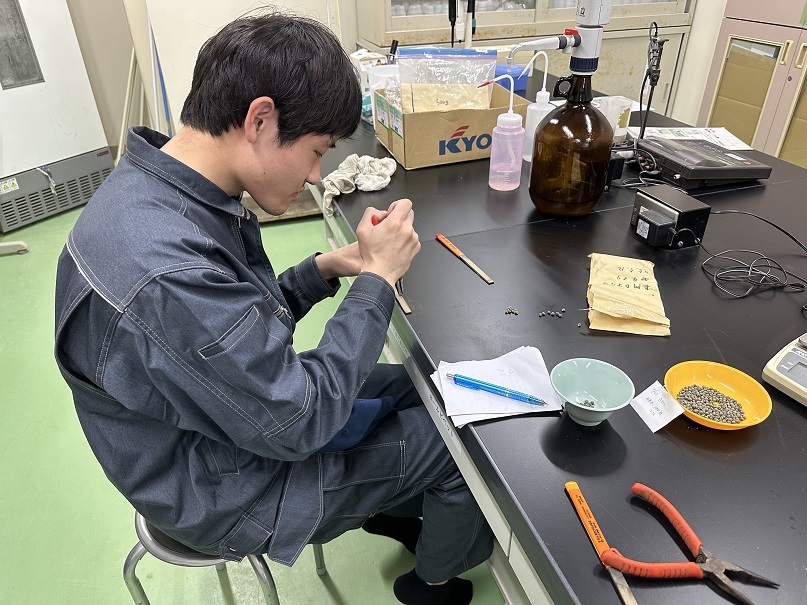
ライスセンターで乾燥機の清掃実習を行いました! 6.4.24
4月24日(水)、土地利用学科の2年生と研修生の計11名が、JA山口県の大道ライスセンターで乾燥機の清掃実習を行いました。乾燥機の中や周りに残っている籾(もみ)やゴミを取り除き、麦(6月頃収穫し、大道ライスセンターで乾燥調製)の中に籾等が混ざらないようにするための大事な清掃です。
ライスセンターには、見上げるばかりの大きな乾燥機が15台。この乾燥機の中に入って清掃するのか!(イイ写真が撮れるぞ!)とドキドキしましたが、乾燥機の中は既に清掃が終わっていました。学生達は、乾燥機のカバーを外してコンプレッサー(圧縮空気)で噴いたり、網目に詰まっている籾・ワラ・草の実などを道具や手で取り除いたり、ほこりまみれになりながらも一つ一つきれいにしていきました。みんな黙々と、真面目に取り組んでいました。
さて、麦の収穫前に乾燥機の清掃があるということは、水稲の収穫前にも同じように乾燥機の清掃があります。・・・次は暑い時期になりますね。・・・頑張りましょう。


ナスの接ぎ木をしました! 6.4.24
4月24日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクト「露地ナスにおける土着天敵を活用した防除体系の検証」及び野菜栽培各論の一環として、ナスの接ぎ木を行いました。
台木は各種病害に強い「トナシム」、穂木は果皮が柔らかく食べやすい「PC筑陽」を選びました。台木も穂木も2月中旬に播種し、丁寧に育て上げました。
台木に切れ込みを入れ、くさび状に切った穂木を差し込みクリップで固定する『割接ぎ』を行いました。
今後、1週間程度遮光し、湿度を保ったトンネル内で穂木と台木がつながるよう養生します。定植は5月中旬を予定しています。




ビワの袋掛けをしました! 6.4.25
4月24日(水)、園芸学科果樹経営コースでは、学生と社会人研修生でビワの袋掛けを行いました。
少しずつ大きくなってきたビワに、カメムシの飛来が認められるようになってきたことから、急いで袋を掛けることにしました。
2年生は、1年生に対して「カメムシがいないか確認して袋を掛けるように」と教えていました。社会人研修生は、傷ついて商品性が低下した果実を除去しつつ、手早く袋を掛けていました。
このビワは、6月中旬に収穫予定です。


ピーマンとパプリカの鉢上げを行いました! 6.4.23
4月23日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生8人がピーマンとパプリカの鉢上げをしました。
2月19日に2年生がプラグトレイに台木の種をまき、3月28日に接ぎ木した苗を、1年生が鉢上げしました。
1年生は、ピーマン組とパプリカ組に分かれ、ポットの培土に穴をあける人、あけた穴にプラグトレイから苗を取り出して移植する人、移植した苗の周りの土を均してコンテナに移す人、と役割分担して、丁寧に作業していました。
3週間ほどポットで育て、5月下旬にハウス内に定植します。


シクラメンの溶脱水調査を行いました! 6.4.23
4月23日(火)、園芸学科花き経営コースでは、シクラメンの溶脱水調査を行いました。
溶脱水調査とは、シクラメンのポットに水を加え、ポット内の土を通ってポットの外に出てきた水(溶脱水)を採取し、pH、EC、窒素、リン酸、カリウム、カルシウムを分析するものです。
初めて調査するという2年生は、わからないことを職員に聞きながら調査していました。ときどき、職員から理解度を確認する質問を受けて懸命に考えて答えていました。「小さなポットなので、養分がなくなったらあっという間に生育に影響を及ぼすので、葉がどれくらいのペースで何枚でていているか、葉色の濃さは、といった日々の観察も大切です」と指導を受け、しっかり理解できた様子でした。
今後、2週間に一度の頻度で調査していきます。


ジャガイモの土寄せをしました! 6.4.22
4月22日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ジャガイモの土寄せをしました。
最初に、ジャガイモの周りに肥料を施用し、その後管理機で畝の間の土を耕したのち、ロータリーを変えて耕した土を畝に跳ね上げていました。
「土寄せにはどんな意味があるの?」と聞いたところ、1年生と2年生は「土が増えるため収量が増えます。また、株が倒れにくくなります。」と的確に答えていました。
このジャガイモは、もう一度土寄せした後、6月上旬に収穫予定です。




ナシの摘果を始めました! 6.4.22
4月22日(月)、園芸学科果樹経営コースでは、ナシの摘果を始めました。
開花期に人工授粉して2週間ほど経過し、結実を確認できるようになりました。職員から「今回は粗摘果なので、1果そうに1個とする。3~5番果で果形が良いものをしっかり見極めて残す。満開20日後までに終えたいので、今月末までに終わるのが目標。」などの説明を受け、早速2年生、1年生と社会人研修生で始めました。
最初はどれが何番果かわからない様子でしたが、職員にたずねながら、少しずつ進めていました。
次は、満開1か月後(5月上旬)を目安に仕上げ摘果を始める予定です。



幼稚園児が子牛とふれあいました! 6.4.22
4月22日(月)、市内の双葉幼稚園の園児17名が本校へ社会見学に来ていただき、畜産学科が飼養する子牛とふれあいました。
園児たちは職員や2年生の説明を受けながら、子牛のブラッシングと、心音や腸音を聴診器で聴く体験を行いました。
最初は、園児たちよりも大きな子牛に戸惑いながらも、次第に慣れて、最後には手で触れるようになりました。
将来、畜産や食に関わる仕事に就いてくれることを期待します!


GAP演習のグループ分け! 6.4.19
4月19日(金)、園芸学科2年生は、講義「GAP演習」の中で、来る審査に向けた役割分担のグループ分けを行いました。
審査は10月下旬ですが、それまでに「JGAP農場用 管理点と適合基準」に沿って、管理点ごとに様々な資料を準備しなければなりません。農業大学校では、園芸学科の2年生を共通項目と農産専門項目に二分し、さらに管理点ごとに担当者を決めます。担当者は、必要な資料を準備し、審査員からの質問に答えます。
審査に向けてしっかり準備していきます!

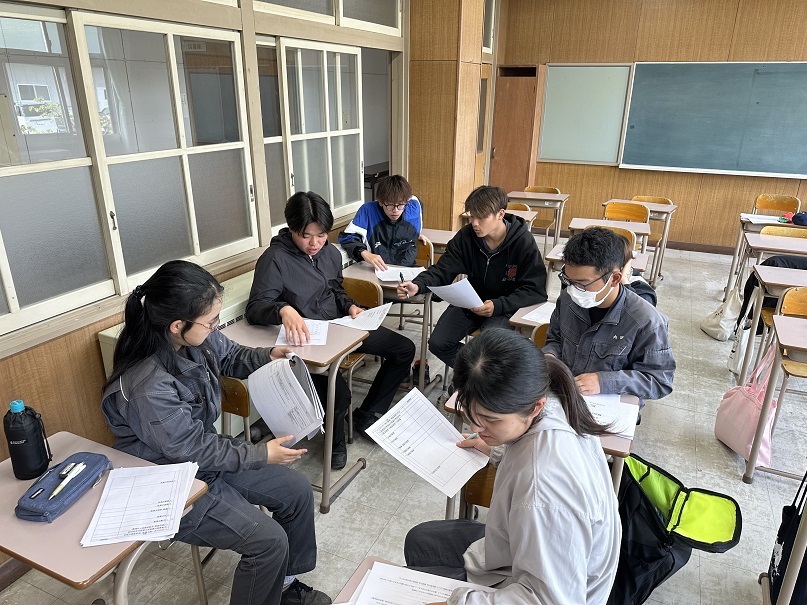
少しずつ2S(整理・整頓)3定(定品・定位・定量)を進めています! 6.4.19
土地利用学科ではトヨタ式カイゼンの学習・実践に取り組んでいます。
現場改善を進めていくには、まずは「2S・3定」が大事ですよ!ということで、少しずつ2S・3定を進めています。どんなことを行っているかというと・・・
①(左上)機械のキャスタースタンドを片づけるラックを自作しました。これまでは、格納庫内の適当な場所に置いていましたが、これからは置き場所が一目でわかります。しかもなんかカッコイイ!
②(右上)複数ある道具に番号を付け、箱に総数を書きました。これまでは、何個あるかすらわかりませんでしたが、これからは個数管理ができます。
③(左下)鋸の収納箱を自作しました。これまでは鋸が箱の中に散乱していましたが、これからはより安全に収納でき、個数管理もできます。見た目も美しいね!
土地利用学科では、これからも少しずつ、現場の「なんか使いにくい・・・」「なんかやりにくい・・・」などの、ちょっとした課題のカイゼンに取組んでいきます。




「花き」栽培各論が始まりました! 6.4.18
4月18日(木)、園芸学科では、経営コース(専攻)に関する講義(各論)が始まりました。花き経営コースでは、職員が実際にほ場を回りながら、「これは何という花でしょうか?」「切り前って何かわかる?切る前、つまり収穫適期のことを指します」など、栽培している花の種類や専門用語を丁寧に説明しました。
学生は、メモを取りながら熱心に説明を聞いていました。
各論は通年で30コマ(1コマ100分)、行っています。


「野菜」栽培各論が始まりました! 6.4.18
4月18日(木)、園芸学科では、経営コース(専攻)に関する講義(各論)が始まりました。野菜経営コースでは、農薬の計算に不可欠な面積や濃度の計算について、問題を解きながら理解を深めました。
学生たちは、メモを取りながら説明を聞き、時には学生同士でも教え合いながら、必死に計算問題を解いていました。
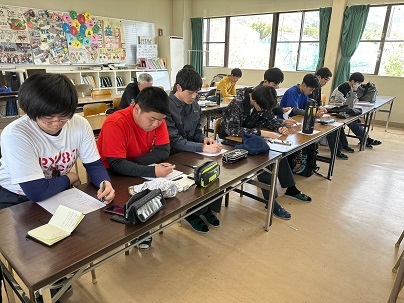

「果樹」栽培各論が始まりました! 6.4.18
4月18日(木)、園芸学科では、経営コース(専攻)に関する講義(各論)が始まりました。果樹経営コースでは、果樹栽培で用いるハサミの種類や研ぎ方、ノコギリの目立てなどについて説明しました。「同じノコギリでも長さや刃の目の大きさがあり、樹種に合わせて選ぶよい」という説明を聞き、学生や研修生は興味を持って聞いていました。
その後、ほ場に出て、果樹栽培で頻繁に使う『男結び』を練習しました。
学生たちは、「もう少し末端が短い方が良い」などと指導を受けながら、一生懸命練習していました。
各論は通年で30コマ(1コマ100分)、行っています。



防府天満宮大石段花回廊を飾り付けました! 6.4.17
4月17日(水)、園芸学科花き経営コースの2年生、1年生、農林総合技術センター職員、防府商工会議所会員など約30名で、防府天満宮大石段花回廊に「幸せます」の文字になるよう、ビオラ、ベゴニア、バーベナなどの鉢花を飾り付けました。
農業大学校では、鉢花の生産を通じてイベントに参画しています。
前日に枯れた花弁などを除去した鉢花を、バケツリレーで温室からトラックの荷台に運び出しました。
学生たちは、次から次に送られてくる鉢花を周囲の方々に負けないスピードで、必死で運んでいました。
花回廊は4月19日(金)から5月6日(月)(6日は午前)まで展示され、夜間はライトアップも行われます。皆さんお誘いあわせの上、農大生が丹精込めて栽培した鉢花と大きな「幸せます」を見て、大きな大きな『幸せ』を感じてください!




畜産学科の心構えを学びました! 6.4.12
4月12日(金)、学校全体のオリエンテーションを終えた新入生は、それぞれの学科に分かれました。
畜産学科では、学科のオリエンテーションで畜産を学ぶ意義や心構えを学びました。
その後、専攻に分かれ、酪農経営コースでは早速、2年生が酪農牛舎での飼養管理の説明を、肉用牛経営コースでは職員が専攻のオリエンテーションを行いました。
なお、各教室のホワイトボードには、新入生を歓迎する2年生からのお祝いメッセージが記されていました。


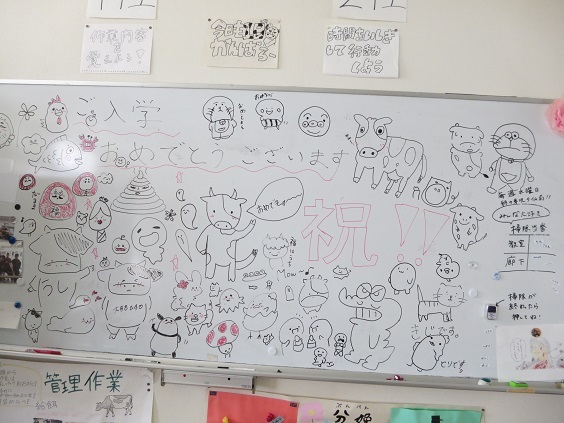
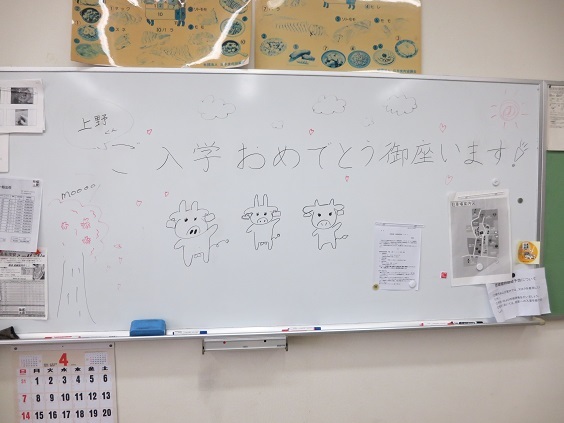
畑ワサビを堀り上げました! 6.4.17
4月17日(水)、園芸学科野菜経営コースの1年生8名と社会人研修生4名で、畑ワサビを掘り上げました。
事前に、指導農業士の梅川仁樹さんから「今から掘り上げるのは、チューブワサビの原料になるワサビです。静かに手を動かして頑張ろう」と激励されました。
1年生は、職員の「2人一組となって畝の両側から掘り上げる。茎を傷つけないよう、てこの原理で掘り上げて畝に置く」と指導を受け、不慣れな道具を一生懸命扱いながら集中して作業していました。
掘り上げたワサビは、葉を落とすなど調製し、翌日、加工事業者のもとに運搬予定です。





わさびを調製しました! 6.4.17
4月17日(水)、園芸学科野菜経営コース2年生、1年生、研修生が、わさびの調製をしました。
今回は茎を出荷するため、事前に葉を除去し、わき芽をかぎ取り、細根を落として茎と主根を残します。
学生たちは、「先生、これは落としすぎですか?」などとたずねながら調製していました。最初はわき芽がどれかわからなかった学生も、数回調製して慣れてくると、理解できた様子で、一生懸命取り組んでいました。
調製後のわさびは、4月18日、島根県の加工事業者まで運搬しました。




指導農業士 梅川仁樹さんの白熱講義を聴講しました! 6.4.17
4月17日(水)、園芸学科野菜経営コースの1年生8名と社会人研修生2名が、指導農業士 梅川仁樹さんの講義を聴講しました。
最初は「わさびの産地はどこと思う?」「本わさびと西洋わさび、どっちの単価が高いと思う?」といった問いかけから始まり、「去年、パウダーを作ってジェラートとして楽しんだ」「中国が一大産地だったが、国内需要確保のため、輸出されなくなった。今、価格が高騰している」など、梅川さんの豊富な経験を惜しみなく披露してくださいました。また、本わさびと西洋わさびの実物を見せて、わさびの生理生態や栽培方法等について説明してくださいました。
学生たちは、メモを取りながら熱心に聞いていました。

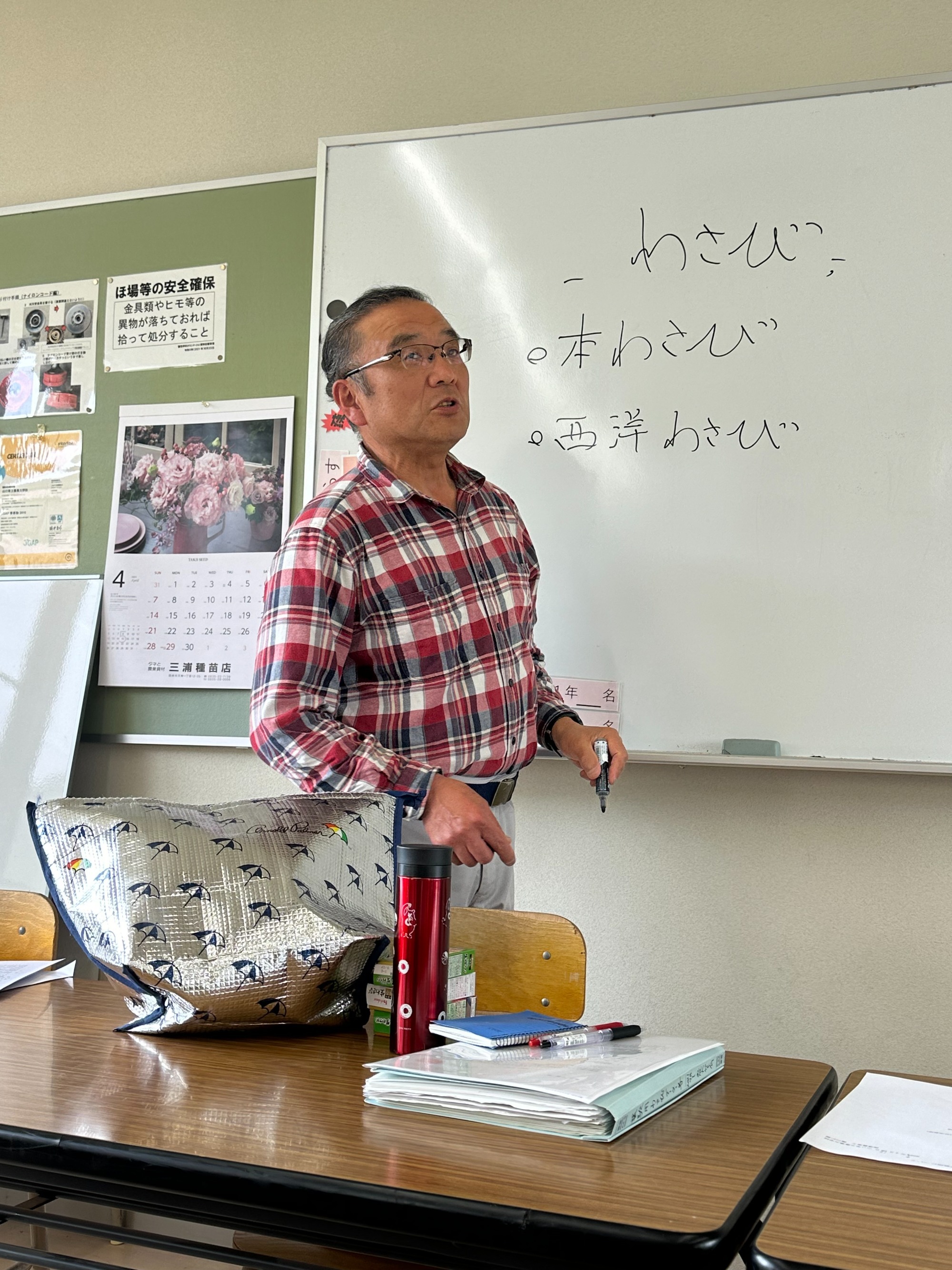

ブドウの芽かきをしました! 6.4.16
4月16日(火)、園芸学科果樹経営コースの2年生、1年生、社会人研修生で、ブドウの芽かきをしました。
ブドウは、1つの芽から2つ以上の枝が発生することがあります。花房がいくつついているか、枝の強弱または伸長の程度を見て残す枝を決めます。
2年生は1年生に対し「この芽は、1つの芽から2つ枝が出ているよね。花房はどちらも2つで、大きさもあまり変わらない。この場合、しっかり伸びているこっちの枝を残して、こちらを取る」と教えながら手本を見せていました。
1年生も要領をつかんだのか、どんどん先に進めていました。
これらのブドウは、8月中旬から収穫・出荷予定です。


メロンの袋掛けをしました! 6.4.16
4月16日(火)、園芸学科野菜経営コースの2・1年生が、メロンの袋掛けをしました。袋掛けは、メロンの果皮が日焼けするのを防ぐために行います。
あらかじめ、切り込みを入れた新聞紙を準備しておきます。
次に、メロンの軸に切り込みを入れた新聞紙を差し込み、ステープラーで止めます。
2年生は、1年生の前でやり方を説明し、実際にやって見せ、1年生からの質問にもしっかりと答えていました。
1年生は入学後初めての管理作業となり、緊張しながら取り組んでいましたが、一つできると安心したのか、「メガネをとったほうがイケメンです」と言いながらポーズに応じてくれました。
このメロンは、5月上旬ごろから収穫・出荷します。




専攻オリエンテーションを開催しました! 6.4.15
4月15日(月)、園芸学科の各経営コース(専攻)では、新入生を中心に、専攻内の実習内容や注意点などを説明する「専攻オリエンテーション」を開催しました。
出荷調製中の服装や実習内容や機械の使用簿の記帳などといった実習に関することを中心に、幅広く説明しました。
新入生、2年生、社会人研修生は、資料を見ながら、自分たちが守らなければならないルールをしっかりと聞いていました。


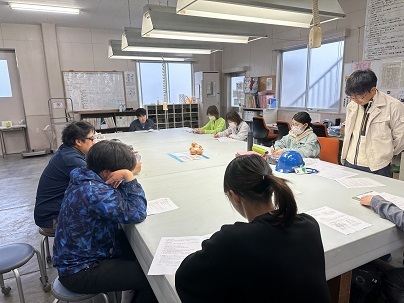
ミニトマトを植え付けるためのマルチ被覆をしました! 6.4.15
4月15日(金)、園芸学科野菜経営コースの2年生が、ミニトマトを植え付けるため、先週ほ場づくりしたハウス内の畝にマルチ被覆をしました。
1人は後ろにさがりながらマルチを畝の上に展開していき、二人がマルチの端に重石として土を乗せました。
途中でマルチを展開している2年生が「内ももが痛くなってきた」と言うと、他の二人から「内ももにシップ貼ってる姿を想像してきたら笑えてきた」と、足腰に負担のかかる作業ながらも、楽しく進めていました。
今後、5月上旬に定植を行い、出荷は6月中旬から予定しています。



「不知火」「せとみ」をせん定しました! 6.4.15
4月15日(月)、園芸学科果樹経営コース2年生と担い手養成研修生の計5名で、「不知火」・「せとみ」の縮伐とせん定を実施しました。
実施に際しては、職員があらかじめせん定方法を教え、2年生と研修生が切った後に再度確認して、どう修正したらよいかを指導していました。
「不知火」「せとみ」ともに、現在開花中です。今後、摘果や潅水をしっかり行い、美味しい果実を作っていきます。




トルコギキョウを定植しました! 6.4.15
4月15日(月)、園芸学科花き経営コース2年生が、経営プロジェクトの一環として、トルコギキョウを定植しました。
4月8日に調製した土を入れた少量培地に穴を掘り、購入したトルコギキョウの苗をピンセットで取り上げ、慎重に定植しました。
担当の2年生は、「点滴チューブはありますが、定植直後は土が沈むので、手潅水なんです」など、今後の管理方法についてもしっかり理解していました。
引き続き丁寧に管理し、通常の栽培方法(ベンチ栽培)と比較して、生育や品質に違いが出るか、労働時間や収益性の違いはどうかを調査し、取りまとめます。



高く売れるとやる気もでます! 6.4.12
土地利用学科では4月初旬に早生タマネギを収穫し、それ以降、ひたすらタマネギの調製(生産物を出荷できる状態にすること)を行い、市場に出荷しています。
1回目の調製は、4月3日(水)。タマネギの根と葉を取り除く者、サイズ分けする者、袋詰めする者に分かれて、作業を進めました。そして4月4日(木)に初出荷したのですが、これが予想以上の高値に!! これなら、たとえ単調な作業でも、たとえ体がタマネギ臭くなっても、ちょっとやる気が出るってもの。
また、市場からのリクエストもあり、袋に「農大マーク」を貼ることにしました。少しは農大の商品らしくなったでしょうか?
4月12日(金)、学生達は今日もタマネギの調製に励んでいます。まだまだ初心者マークの土地利用学科ですが、農大ブランドの一角を担えるよう、今年度も頑張っていきましょう!




出産に向けて準備を行いました! 6.4.12
4月12日(金)、畜産学科肉用牛経営コースの2年生が、2週間後の出産(分娩)に向けて、分娩房の清掃や牛の移動を行いました。
牛の妊娠期間は人間と同じで約285日です。本校では、出産予定日の1~2週間前になると、牛を分娩房に移動させ、出産の準備を行います。
元気で大きな子牛が無事に生まれるよう、学生・職員一同見守っています!



入学式に向け、装花しました! 6.4.10
4月11日(木)の入学式に向け、園芸学科花き経営コース2年生が10日(水)に会場などを装花しました。
農業大学校で栽培したカーネーションやダリアなど10種類以上の花を「どこに、どの高さで、どの色のどの花をどのように配置したら美しく見えるか」と懸命に考えながら飾り付けました。給水用のスポンジ(オアシス)は、一度挿すと穴が開いて元に戻らず、他の花を挿し直しても吸水できないため、一本一本が真剣勝負です。
途中、「この部分が空いているのでスターチスで飾りたいが、花が多すぎるのでどうしたらいいか悩んでいます」という学生の質問に、職員は「スターチスを長めに切っておいて、不要な花を間引いていったら、良い密度にできるのでやってみて。」とアドバイスしていました。事前の準備を含め、10時間以上かけて完成しました。
在学生並びに職員一同、新入生の入学を心よりお祝いいたします。また、新1年生と一緒に学修する日を楽しみにしています。
ようこそ、山口県立農業大学校へ!!





ナシの人工授粉真っ最中!! 6.4.10
園芸学科果樹経営コースでは、現在、ナシの人工授粉を進めています。
多くのナシの品種は、自家不和合性(同じ品種では受精せず、果実ができない)なので、別の品種の花粉を採取し、人の手で授粉しなければなりません。当コースでは、花粉樹から花や花粉を採種する方法などを丁寧に学んでいます。
本年は、例年よりやや遅く4月2日からの開始となりました。最近の高温で、一斉に開花し、学生、研修生、職員が総出で一生懸命人工授粉しています。
今回は、「ゴールド二十世紀」や「王秋」などのめしべに、「長十郎」と「豊水」の花粉を授粉しました。「ゴールド二十世紀」は、8月下旬から収穫予定です。




話題の野菜『ロマネスコ』植え付けに向けてほ場つくりをしました! 6.4.9
4月8日、園芸学科野菜経営コース2年生2名が、ロマネスコとキャベツを植え付けるため、施肥・耕うん・畝立てを行いました。
ロマネスクは、最近栽培され始めた野菜で、カリフラワーの仲間です。カリフラワーは曲線的な外観ですが、ロマネスコは円錐を集めたような形をしています。
最初に高度化成肥料、ようりん、苦土石灰を施用し、トラクターで耕うんした後、畝立てしました。
満開の桜の下、2年生が一生懸命作業している姿を、通りかかった方がにこやかに見守っていました。
ロマネスコ・キャベツとも今週中に植え付け、6月中旬に収穫予定です。



トルコギキョウの少量培地耕用の土づくりをしました! 6.4.8
4月8日、園芸学科花き経営コース2年生が、経営プロジェクトの一環として、トルコギキョウを栽培するための土づくりを行いました。経営プロジェクトでは、トルコギキョウの少量培地耕について取り組む予定です。
ピートモス:パーライト:培土=20L:10L:90Lの割合で混ぜました。ピートモスは塊になっているものを、鉄網を通しながら大きさをそろえました。その後、パーライトと培土と一緒にミキサーで混ぜて作りました。
今週末~来週初めに、トルコギキョウの苗を移植し、草丈、一級品比率などを土耕栽培と比較して調査します。



花き経営コースの出荷研修を行いました! 6.4.9
4月9日、園芸学科花き経営コースの2年生を対象として、花の収穫方法、品質維持方法や出荷時の等級区分の見方を共有するための研修会を開催しました。
担当職員が、「収穫は朝夕の涼しい時間帯に行う」「よく切れる刃物で収穫する」「収穫後はできるだけ早く水あげする」「直売と市場で出荷に適する開き具合が異なる」など収穫・出荷の注意点を指導すると同時に、学生に対し「なぜ花が老化するのか」など、植物生理に基づいたディスカッションを行いました。
学生からは、「ナデシコは長さが何cmあればいいですか」「オリジナルリンドウの段数や長さはどれくらいあればいいですか」などと言った質問が出ていました。
花き経営コースでは、今回の研修内容を2年生から新1年生にしっかり伝え、一層の品質向上に努めていきます。




メロンを植え付けるための蒸気消毒を行いました! 6.4.9
4月9日、園芸学科野菜経営コース2年生が、メロンを植え付けるため、土壌の蒸気消毒を行いました。
蒸気消毒は、メロン黒点根腐病を予防するために行います。
前日のうちに、専用のチューブを土壌に埋設し、約90℃の蒸気を2時間通すことで病原菌を殺菌する効果があります。今回は、ベンチを2列ずつ、計6列消毒しました。
大きな機械ですが、職員指導の下、学生がてきぱきと実施しました。
メロンの植え付けは4月下旬頃、収穫は7月下旬頃を予定しています。



ミニトマトの高接ぎ木と鉢上げを行いました! 6.4.5
4月5日(金)、園芸学科野菜経営コースの2年生が、経営プロジェクトの一環としてミニトマトの高接ぎ木と種から育てた苗(自根苗)の鉢上げをしました。
高接ぎ木とは、通常の接ぎ木よりも高い位置で穂木を接ぐことで台木部を長くし、台木の持つ細菌の移動・増殖抑制効果を高め、青枯病の発生を抑制する技術です。担当の1年生はこれまで接ぎ木をしっかりと練習していたため、練習の成果を存分に発揮しました。
今後、高接ぎ木と台木の種類の違いがミニトマトの重要病害である青枯病の発生程度、生育、収量にどのように影響を及ぼすか調査します。




2年目の土地利用学科、サトイモ生産に挑戦します!6.4.3
初年目の土地利用学科では、水稲、麦類、大豆、キャベツ、ブロッコリー、タマネギ、ジャガイモ、サツマイモ、ポップコーンの生産に取り組みました。令和6年度は、新たにサトイモ、カボチャ、黒大豆等の生産に取り組む計画としています。
4月2日(火)、さっそく新品目第1弾であるサトイモの定植を行いました。このところの雨で圃場が充分乾いていませんでしたが、翌日(4月3日)が大雨予報だったので決行です。
使う機械は、土地利用学科お馴染みの「ポテトプランタ(ジャガイモを定植する機械)」。今回は、このポテトプランタに「マルチャー(畝にマルチを張る機械)」を付け、どんどん植えていく計画でしたが・・・ やはり土が湿り過ぎていて、種イモの上に十分土が掛かりません。残念ですが鍬で土を掛け、マルチも手作業で張ることにしました。とはいえ、これも鍬の使い方を学ぶ良い機会。便利な機械の使い方だけでなく、鍬等の手作業も修得していきましょう。




新年度最初の実習は、早生タマネギの収穫! 6.4.3
新年度初日の4月1日(月)、土地利用学科は早生タマネギの収穫を行いました。黒マルチで被覆栽培したので、手で収穫することにしました。
最初にタマネギの茎葉部を刈払機で切除していくのですが・・・さすがタマネギ、刈れば刈るほど目に染みる・・・ そして、タマネギの香りが充満する圃場で、ひたすらタマネギを抜いてコンテナに詰めていきました。
黒マルチの穴(タマネギを植えた穴)から雑草が発生し、多発した場所では雑草をかき分けながらタマネギを引き抜くなど手間取りましたが、なんとか2アール分のタマネギを収穫することができました。
この日収穫したタマネギは、雨で外作業ができない日などに調製(茎や根の切除、サイズ分け等)し、出荷していく予定です。




ミニトマトの接ぎ木! 6.3.25
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、トマトの重要な病害である青枯病の防除対策として本県で考案された「高接ぎ木法」をミニトマトで調査することとしています。
3月25日(月)には、調査に供するミニトマト苗として、台木品種の「キングバリア」や「Bバリア」に穂木品種の「TY千果」を「合わせ接ぎ」という方法で、接ぎ木しました。
今回は、台木品種が4葉期に達したため、通常の接ぎ木位置(台木の子葉の上)で接ぎ木を行い、担当の一年生は、288本の接ぎ木苗を作成しました。
週末には、台木品種が5から6葉期に達すると見込まれ、生育状況確認後、「高接ぎ木法」による接ぎ木を行う予定です。




キュウリの生育調査! 6.3.25
園芸学科野菜経営コースは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。
本調査では、月に2回生育調査を行うこととしており、定植から6日目の3月25日(月)には、葉数、第6節の葉幅、6節目の茎径について調査を行いました。
この経営プロジェクトでは、定植した苗が活着してから、積算日射量に応じた潅水を行うハウスと慣行の潅水を行うハウスで、潅水方法を変えることとしており、生育調査などを通じて、それぞれのハウスでの生育や収量に関するデータ収集を継続的に行います。
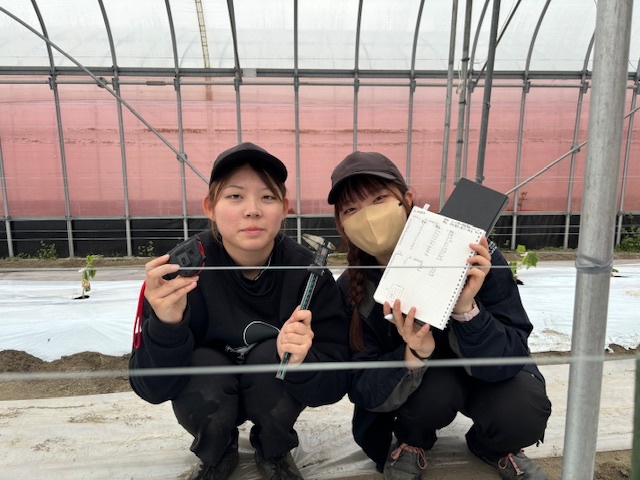



防府天満宮「大石段花回廊」展示用の鉢花の搬出! 6.3.21
防府天満宮では、毎年4月中旬から5月上旬に、「花回廊」として大石段を花鉢で飾るイベントが行われており、農業大学校も花鉢の準備で関わっています。
3月22日(金)には、園芸学科花き経営コースで育ててきたビオラの花鉢のうち260鉢が、防府市内の5つの中学校等に搬出されました。
残りのビオラやオダマキ、ベゴニア、マリーゴールドの花鉢は、引き続き校内で管理を続け、4月17日に防府天満宮に搬出する予定です。




トマトの果実品質調査を行いました! 6.3.21
園芸学科野菜経営コースでは、高糖度トマト生産を目指し、塩分ストレス栽培に関する経営プロジェクトを進めています。
本プロジェクトでは、週に一度、生育や果実品質に係る調査を行っています。
調査日に当たる3月21日(木)、生育調査として茎径や伸長量の測定を、果実品質調査として果実重や糖度、食味を調査しました。
今回の果実品質調査では、塩分ストレス栽培のトマトは、慣行栽培に比べて、果実重はやや劣るものの、糖度は高く、味も濃く、両区に差が見られました。
このプロジェクトは、6月下旬まで行う予定であり、今後は食味アンケートなど数値以外の観点からも調査することを検討しています。継続した調査を通じて、どのような結果が得られるか、とても楽しみです。


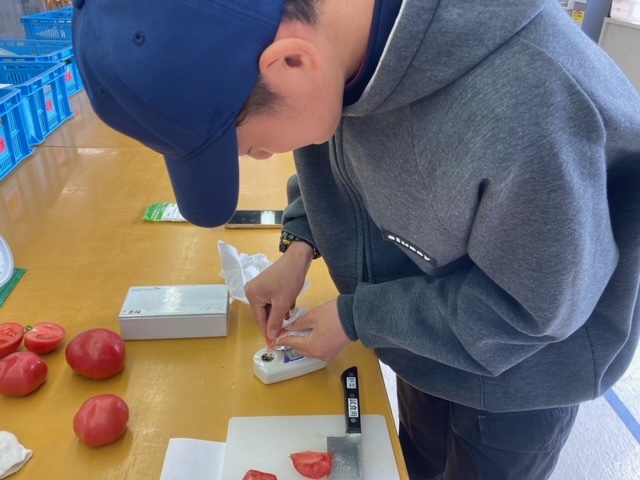

柑橘「南津海(なつみ)」の収穫! 6.3.21
園芸学科果樹経営コースでは、ガラス温室で「南津海」を栽培しています。
「南津海」は、本県の周防大島町で、カラマンダリンと吉浦ポンカンを交配して生まれた柑橘の品種で、収穫は4月前後で、樹上で完熟させるため、酸味が落ち着き、高糖度に仕上がるのが特徴です。
3月21日(木)には、春のオープンキャンパスに参加された高校生とともに「南津海」の収穫を行いました。
果実の糖度は15度を超え、十分な甘みを確保できているため、4月上旬から直売所に出荷する予定です。




ナシへの基肥施用! 6.3.19
園芸学科果樹経営コースでは、3月19日(火)にナシに肥料を施しました。
今回使用した肥料は、有機入りの配合肥料で、今年のナシの生育を長期にわたって支えていく基肥として施すものです。
施肥作業に携わった学生と研修生は、樹ごとに肥料の量を量り、株元周辺に丁寧に肥料をまいていました。




ナシへの花粉採取準備! 6.3.19
当校では、例年4月上旬にナシが開花期を迎えます。
当校で栽培するナシの品種の多くは、自家不和合性のため、確実に結実させるためには、他の品種の花粉で受粉させる必要があります。
このため、この時期、園芸学科果樹経営コースでは、人工受粉用の花粉採取を行います。
3月19日(火)には、受粉樹の切り枝の開花を促進するための保温施設を、ガラス温室内に設けました。
3月下旬頃には、切り枝を保温施設に移し、1週間程度で開花させ、花粉の採取を行う予定です。




シクラメンの鉢上げ準備! 6.3.19
園芸学科花き経営コースでは、来月、主力品目であるシクラメンの鉢上げを行います。
現在、ガラス温室内で、大輪の「ドリームスケープ」を栽培していますが、これらを3.5号ポットに植え替えることにより、株を大きくするものです。
3月19日(火)には、一年生が、培養土づくりや培養土のポット詰めを行いました。
一年生は、この1年間、何度も培養土づくりを経験したため、手際よく作業を進めていました。




キュウリの定植! 6.3.19
園芸学科野菜経営コースは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。
3月19日(火)には、供試するパイプハウス2棟に、キュウリの苗を定植しました。
今回定植した苗は、穂木品種が「常翔661」、台木品種が「ときわパワーZ2」で、担当する一年生たちが、ハウスあたり100本定植しました。
本経営プロジェクトでは、定植した苗が活着して以降、それぞれのハウスで潅水方法を変えることとしており、日射比例潅水を行うハウスでは、日中の積算日射量に応じた潅水を行います。




イチゴ親株への施肥! 6.3.19
3月も半ばを過ぎ、少しずつ暖かさを感じる中、育苗温室で管理しているイチゴの親株も根や芽が動き始めています。
これから、親株からランナーが伸び、このランナーをポットで受けて、子株を増殖し、秋に本ぽへ定植することとなります。
このため、親株の充実とランナーの旺盛な伸びを促すよう、3月19日(火)、園芸学科野菜経営コースのイチゴ担当の一年生が、親株に肥料を施しました。
今後、良質子株生産に向けて、施肥だけでなく、潅水や防除にも気をかける必要があります。
自身の経営プロジェクトとともに、来年度に向けた準備を両立できるよう頑張っていきます!




令和5年度卒業式! 6.3.18
3月14日(木)、令和5年度卒業式を挙行しました。
好天にも恵まれ、25名の卒業生の門出を祝う佳き日となりました。
4月から、新たな地での活躍を祈念します。




果樹園周辺の草刈り! 6.3.18
3月も半ばを過ぎ、圃場内外の草が勢いよく伸びつつあります。
このため、園芸学科果樹経営コースでは、3月18日(月)に、果樹園周辺の草刈りを行いました。
この日は、一年生や研修生が、ナシ園や柑橘を栽培しているパイプハウスの周辺を、ナイロンコードを使って、丁寧に草を刈っていました。
今後は、圃場内も含めて、随時草刈りを行っていきます。




バラへの追肥! 6.3.18
園芸学科の花き経営コースでは、バラの土耕栽培をしています。
パイプハウスで栽培しているバラは、1月中旬から下旬にかけて、地上から60cmのところでまで切り戻しました。
3月に入り、新芽が動き出したことが確認できたことから、今後の生育を促すため、3月18日(月)に追肥を行いました。
今後は、毎月1度、追肥を行っていく予定です。




ズッキーニの鉢上げ! 6.3.18
園芸学科の野菜経営コースでは、3月18日(月)、ズッキーニ苗の鉢上げを行いました。
この苗は、3月7日にセルトレイに播種したもので、品種は「ダークヤングマン」と「イエローヤングマン」です。
発芽後に子葉が展開したため、今回、ポットに移植しました。
担当の一年生は、根を傷めないよう慎重に苗を扱い、ポットに移植し、合計180ポットの鉢上げを行いました。




キュウリの定植準備(誘引線設置)! 6.3.15
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす営業を調査します。
3月15日(金)には、定植準備として、畝に設置された支柱へキュウリの主茎を誘引するための誘引線を張りました。
担当の一年生は、同級生の力を借りながら、調査で使用する2棟のパイプハウスそれぞれに、誘引線を設置しました。
3月19日には、定植を行う予定です。


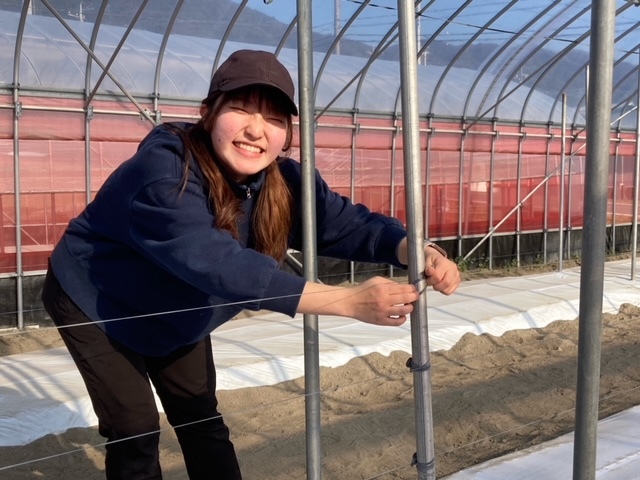

刈刃を研いでみよう! 6.3.15
土地利用学科の草刈りでは、状況に応じてチップソーとナイロンコードカッターを使い分けています。チップソーは使っていると刃が丸くなって切れ味が悪くなりますが、学生達はまだ刃を研いだことがありませんでした。そこで、雨で圃場実習ができない3月5日(火)、チップソーを研ぐ練習をすることにしました。
教官から研磨機のセッティング方法と安全な使い方を教わったら、さっそく練習開始です。簡単そうに見えますが、実際にやってみると意外と難しい。学生達はセッティングに悩みながら、きちんと研げているか何度も確認しながら、頑張って研いでいました。
さて、良く研げましたか? あとは仕上げを御覧じろ? 今度の草刈りが楽しみですね。

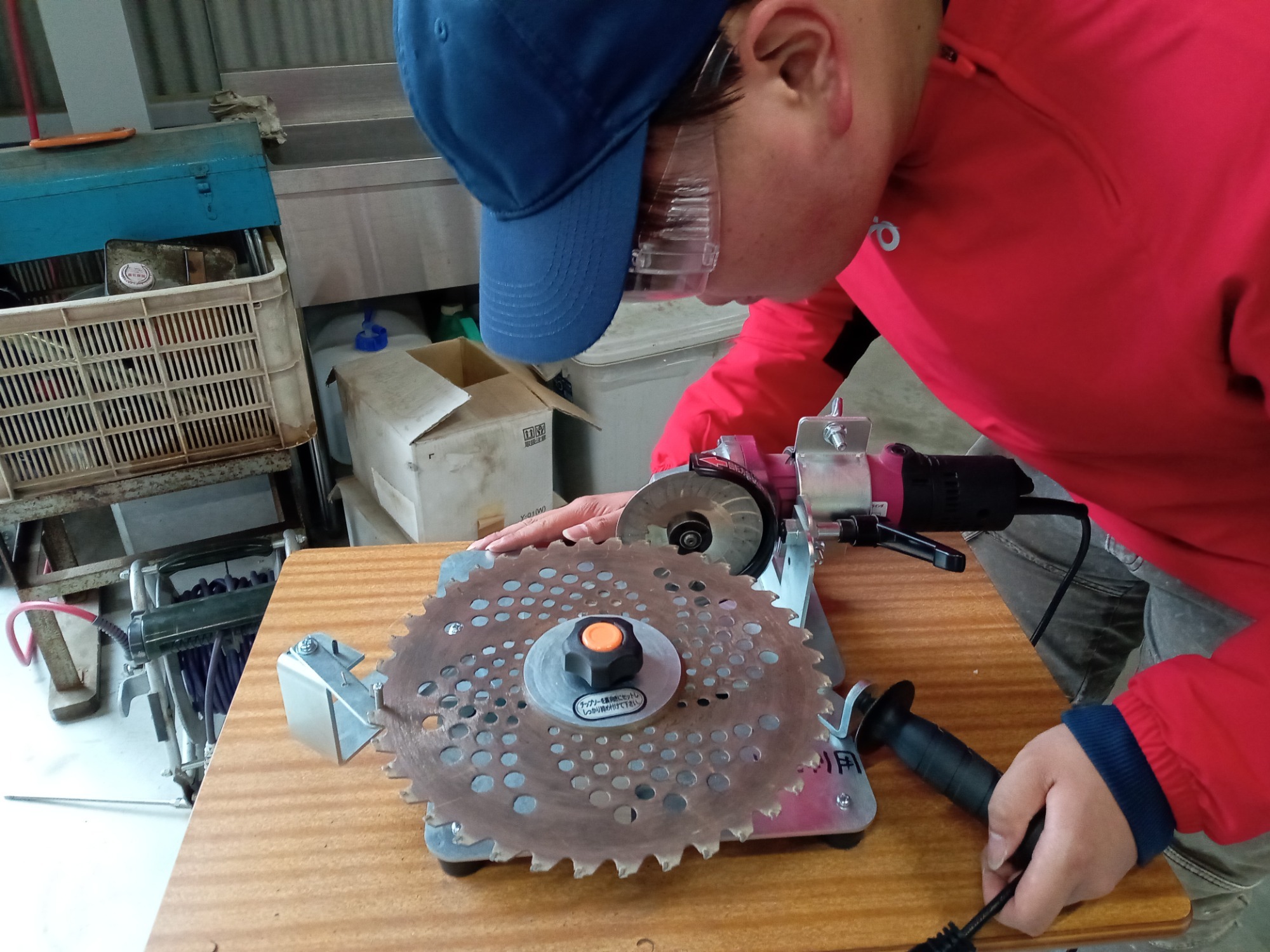


今年度最後のトヨタ生産方式の講義! 6.3.15
土地利用学科では、トヨタ生産方式について学んでいます。3月12日(火)、今年度最後の講義がありました。
まずは、前回の宿題の発表です。「トヨタの問題解決手法を使い、学科の問題の解決策を検討する」という宿題を、学生達は2班に分かれ、年末年始に取り組んできました。検討状況と自分たちが考えた解決策を各班の代表が発表し、講師から山ほどの助言をもらいながら、検討内容や解決策の見直しをみっちり行いました。
午後からは、問題としている事の現場・現状を、動画を撮りながら全員で確認。その後教室に戻って、動画を再生しながら意見交換を行いました。いつもどおりの作業でも、改めて動画で見てみるとヒヤリハットがとても良く見えるんですね。いつも使っている機械でも、実は操作方法が曖昧だったことも分かりました(これには教官も反省)。
トヨタ生産方式の講義は、2年生になってからも続きます。内容を少しレベルアップさせながら、学科の問題を解決する小集団活動に取り組んでいく予定です。




道の駅ソレーネ周南で8名の学生が販売実習を実施!6.3.6
3月6日(水)、「道の駅 ソレーネ周南」で、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の一年生6名、畜産学科の一年生1名、計8名の学生が、販売実習に臨みました。
風が強く肌寒い気候のためかお客様の出足は鈍く、販売開始時にもかかわらず、呼び込みをしなくてはならないほどの客数でスタートとなりました。
ソレーネ周南さんの放送設備を使わせていただいて店舗内外へ興味を引くような放送をしたり、車から降りてこられるお客様に近寄って案内をしたりと、とてもがんばってアピールをしていました。
ブースに来てくださったお客様に対しても、笑顔で雑談を交えながら商品説明を行うことにより、心配していたよりもたくさんの売上げをあげることができました。
今年度はこれで実習は終わりですが、来年度の実習では新一年生へアドバイスする姿が期待できそうです。
是非、来年度も学生の成長と農業大学校の農産物を楽しみにお越しください。




「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備!6.3.1
3月6日(水)の午後2時より「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習を行います。
この準備のため、3月1日(金)に、当日対応する学生たちが打ち合せや資機材の確認を行いました。
参加者は、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の一年生6名、畜産学科の一年生1名の計8名で、協力して打合せを進めました。
今年度最後の販売実習となり、要領も分かってきたものの、中にはソレーネの販売実習が初めての学生もいたため、過去の反省を思い出しながら情報交換を行いました。
また、今は販売品目が少ないですが、柑橘類は種類が多いため試食を行い、味の違いをどう説明すればお客様に伝わるのか、苦労していました。“甘くておいしい”以外の表現は難しいようです。
新鮮な商品と学生の笑顔で素晴らしいおもてなしを提供できることと思いますので、「道の駅 ソレーネ周南」へ足をお運びください。

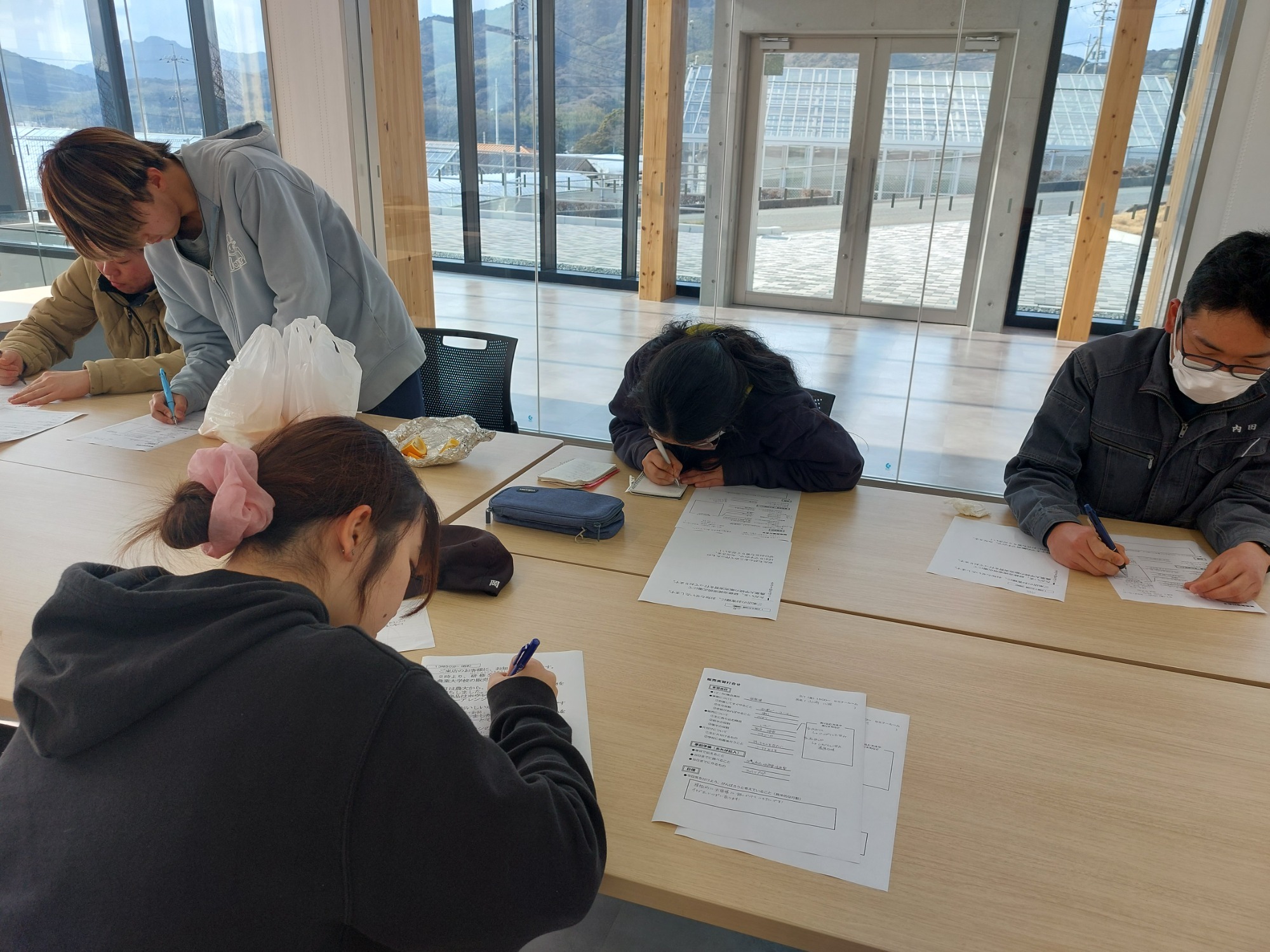

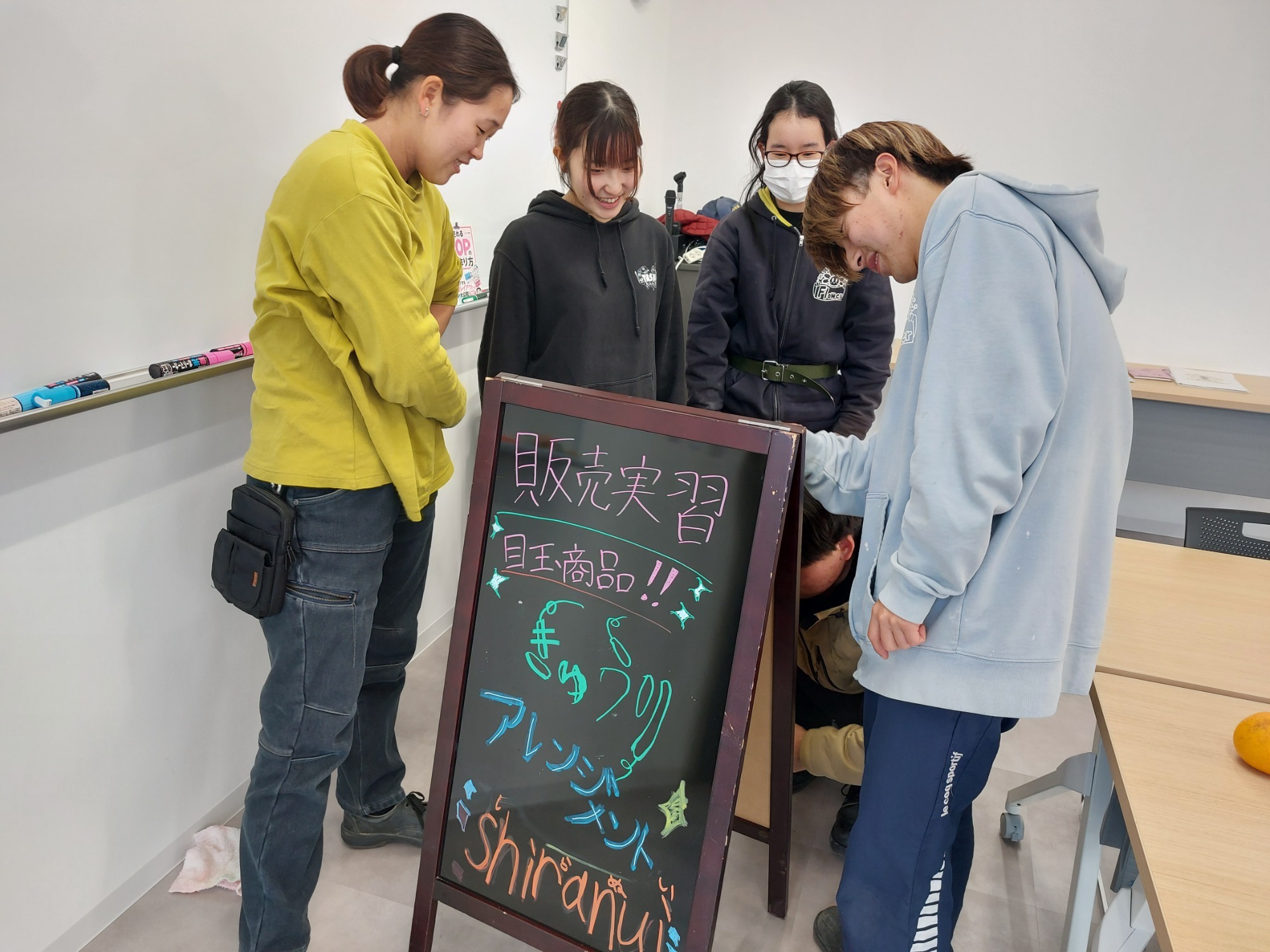
卒業式会場への壺花活け込み! 6.3.13
「令和5年度卒業式」に向けて、3月13日(水)に花き経営コース等の職員が、卒業式会場に飾る壺花の活け込みを行いました。
当校で栽培した花もふんだんに使用して、みごとな出来栄えに仕上がりました。




卒業式会場の装花(その2)! 6.3.13
「令和5年度卒業式」に向けて、3月13日(水)園芸学科花き経営コースの一年生と職員が、農大教育棟各階に装花を施しました。
1階から2階に上がる階段には、3月12日に作成したフラワーアレンジメントが飾られました。
2階の踊り場から3階にかけてのホールには、様々な色で染色したカスミソウで作成したフラワーガーランドを吊り下げられました。
これにより、会場は一層華やかに彩られました。




卒業式会場の装花! 6.3.13
「令和5年度卒業式」に向けて、3月13日(水)園芸学科花き経営コースの一年生と職員が、農大教育棟の2階廊下に設置したパラレルスタンドの活け込みを行いました。
一年生は、職員のアドバイスを受けながら、見事な出来栄えに仕上げました。




卒業式に向けたフラワーアレンジメントの制作! 6.3.12
「令和5年度卒業式」は、3月14日に挙行されます。
園芸学科花き経営コースでは、卒業式の会場等を彩るためのフラワーアレンジメントを制作しました。
一年生たちは、お世話になった二年生への感謝の気持ちを込めて作成していました。




メロンの脇芽取り! 6.3.12
園芸学科の野菜経営コースでは、パイプハウスでメロン栽培に挑戦しています。
冬季における栽培ということもあり、当初の予想より生育が遅れていましたが、寒さが和らぐにつれ、つるの伸びに勢いがみられるようになりました。
果実も順調に肥大しており、2月19日に交配した果実は、摘果作業を経たのちに、大きいもので果高が11cm、果径が8cmとなっています。
3月12日(火)には、担当の一年生が、メロンの脇芽取りを行いました。
これは、養分の消耗を最小限に抑え、果実が大きくなるように不要な脇芽を除去するものです。
先輩から引き継いだメロンを今後も収穫までこまめに管理していきます!
順調に進めば、5月上旬頃に収穫が行える予定です。




キュウリの定植準備(支柱立て)! 6.3.12
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。
3月12日(火)には、調査で使用する2棟のパイプハウスで、定植の準備として、キュウリを誘引するための支柱立てを行いました。
まず、マルチへ支柱を立てる位置に印をつけました。その後、一年生が二人一組となって、一畝に17本の支柱を立てていきました。
来週には定植を行う予定です。




やまぐちオリジナルリンドウに追肥を行いました! 6.3.11
園芸学科花き経営コースでは、やまぐちオリジナルリンドウである「西京の初夏」、「西京の涼風」、「西京の夏空」、「西京の白露」、「西京の瑞雲」の栽培に取り組んでいます。
大半の品種が定植3年目を迎えることから、本年度は、これまで以上に良質な花が収穫されることが期待されます。
3月11日(月)には、リンドウの萌芽が確認されたため、追肥を行いました。
担当の一年生は、マルチの穴からリンドウの株の周りを目掛けて、化成肥料を丁寧に施していました。
これらのリンドウのうち、6月上旬には「西京の初夏」が収穫を迎える予定です。




ブドウ棚のトンネルメッシュ被覆を行いました! 6.3.11
園芸学科果樹経営コースでは、3月に入って、ブドウ棚に付属しているトンネルメッシュをビニルで被覆する作業を進めています。
3月11日(月)には、露地ブドウ2号園のトンネルメッシュの被覆を行いました。
当日は、若干、風が吹いていましたが、作業に参加した一年生や研修生、専攻職員が協力して、ビニルを張ったり、バンドでビニルを固定したりしました。
この作業は、3月下旬までには終える予定です。




トマトの果実品質調査を行いました! 6.3.11
園芸学科野菜経営コースでは、高糖度トマト生産を目指し、塩分ストレス栽培に関する経営プロジェクトを進めています。
このプロジェクトに供試しているトマトの第1段果房の果実が収穫期を迎えたため、3月11日(月)に、果実品質調査を行いました。
今回、塩分ストレス栽培と慣行栽培を行っているトマトそれぞれについて、一果重や糖度を計測するとともに食味調査を行いました。
糖度に関しては両区で大きな差はみられませんでしたが、食味はいずれも美味しく仕上がっていました。
この果実品質調査は毎週行うこととしており、担当の一年生は、今後、栽培方法によって果実品質に差がでることを大いに期待していました。
また、3月13日から、防府市内の直売所等へトマトの出荷を行う予定です。



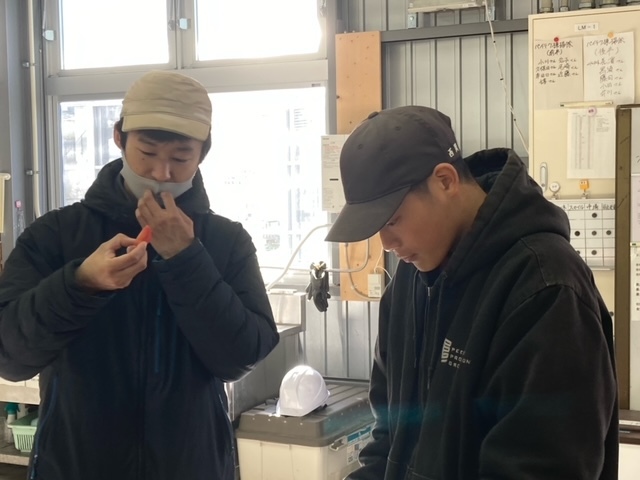
防府市まちの駅「うめてらす」で8名の学生が販売実習を実施! 6.2.28
2月28日(水)、防府市まちの駅「うめてらす」で、土地利用学科の一年生2名、園芸学科の一年生4名、畜産学科の一年生2名の計8名の学生が、販売実習に臨みました。
気持ちの良い好天のおかげで天満宮参拝の方や、梅園に散歩される方も多く見受けられ、お客様との交流が楽しめました。
端境期のため残念ながら商品の種類は少な目ではありましたが、元気な売り場に見えるようにレイアウトや飾りつけを工夫していました。
販売実習後の反省会では、来年度に向けての意気込みも聞かれましたので、楽しみですね。
次回の販売実習は、令和6年3月6日(水)に、「道の駅ソレーネ周南」で行う予定です。




土地利用学科、福岡に行ってきました(その2)! 6.3.1
土地利用学科では、トヨタ生産方式について学んでいます。少しずつ2S(整理整頓)に取り組んでいますが、このたび特別に福岡県宮若市のトヨタ自動車九州宮田工場を見学させてもらえることになりました。
部品や工具等は必要な物しか置いていない、運搬車や人が通行する箇所ははっきりと色分けされている、机・椅子・書類等様々なものに番号を付けて収納箇所が一目でわかるなど、5S6定(整理・整頓・清掃・清潔・躾、定置・定品・定量・定路・定色・定名)のお手本を見せてもらうことができました。
学生達からは、「職場環境の改善や作業性の向上、効率化をするために作業者が話し合い、必要なものがあれば作っていることが印象に残った。」「5S6定の完成形を見た。すごく気持ちの良い職場だと感じた。」「整理整頓を習慣化したいと思った。」「レクサスがめっちゃかっこよかった。」などの感想が聞かれました。
少しは2Sのイメージが出来たでしょうか? これからも2Sや小集団活動に励み、少しずつ学科をカイゼンしていきましょうー!
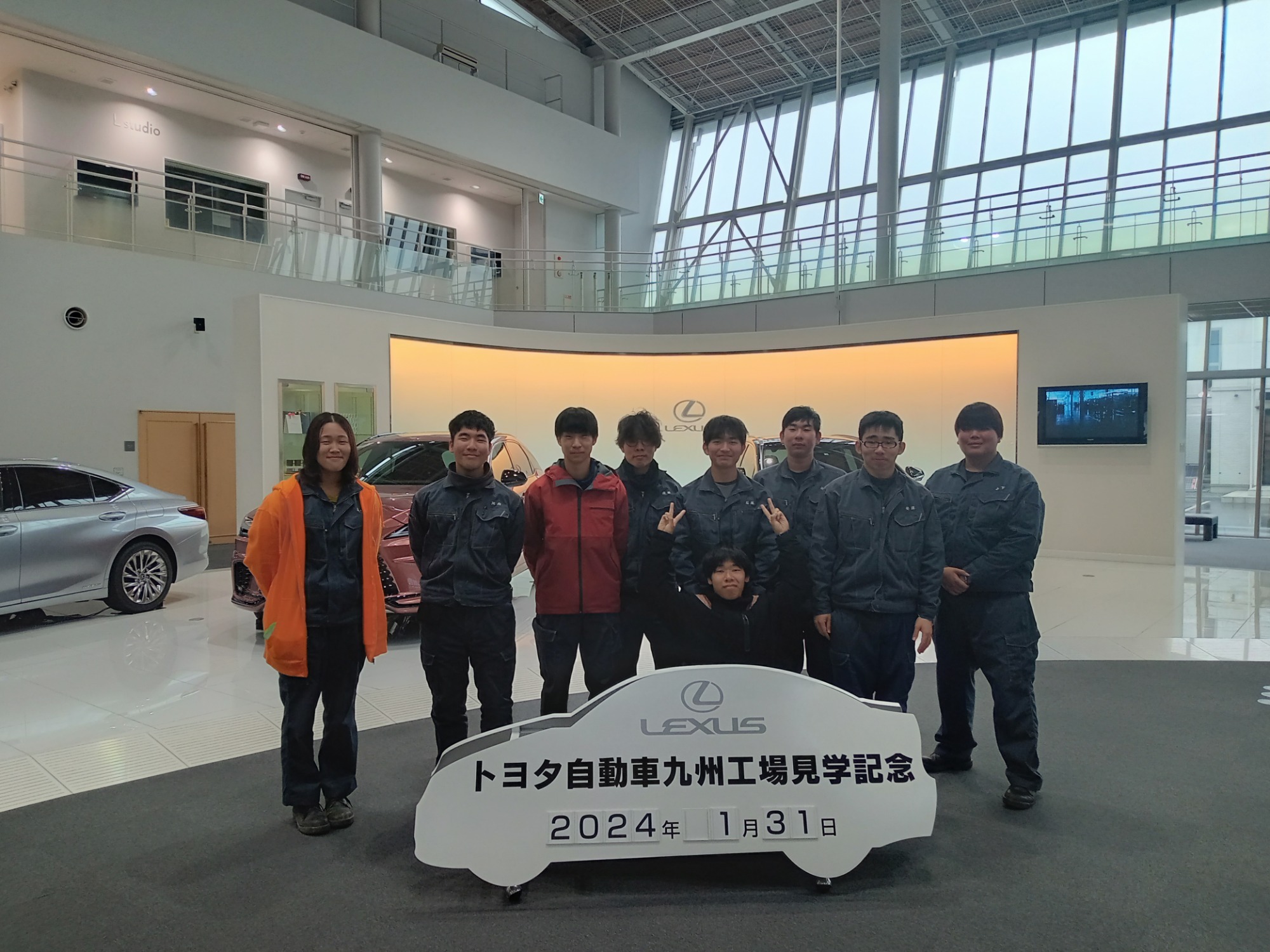
土地利用学科、福岡に行ってきました(その1)! 6.3.1
土地利用学科学生の大半は、農業法人への就職を希望して日々の実習に励んでいます。折を見ては県内の農業法人のところへ研修に行っていますが、たまには他県の農業法人のことも知りたいですよね。
そこで、1月31日(水)に福岡県鞍手町の(株)遠藤農産に視察に行ってきました。水稲を中心に麦、大豆及び露地野菜を約60ヘクタール生産し、農機メーカーや県等関係機関と連携してスマート農業にも積極的に取組まれている、地域の旗振り役的な先進農業法人です。
視察では、遠藤社長から、主にスマート農業の取組状況やスマート農機に対する考え方、法人として求める人材などについてお話をしてもらい、学生達は熱心に聞き取っていました。
最後に遠藤社長から「農大卒業後、即法人就業では勿体ないなぁ。20代前半は(親のすねをかじりながら)いろいろ経験してみるのがオススメ。」という話が出ると、学生達は口々に「休学しよー」「休学しよー」とつぶやいていました。みんな、冗談だよね?



君は畝を真っすぐ立てられるか! R6.2.29
2月28日(水)、土地利用学科は、ジャガイモの定植を行いました。
ジャガイモ・・・昨年9月の定植では、機械の事前調整不良により全て手で種芋を植える羽目になった、あのジャガイモです(令和5年9月11日の農大ニュース参照)。
今回は、機械も順調に動き、全て機械で定植することができました。ヨカッタ、ヨカッタ。
さて、この蒲鉾状の畝を作りながら種イモを植えていく機械(ポテトプランタ)、トラクタの操作技能(真っすぐ走らせられるかどうか)が如実に表れる機械です。今回トラクタを操縦した学生は、以前はよく蛇行していましたが、今回の作業では真っすぐ走らせているじゃないですか! 冬休みの特訓の成果ですね。まさに「男子三日会わざれば刮目して見よ」。
あ、褒めたら急に畝が曲がり始めました。まだまだ練習が必要なようで・・・


少しでも機械の操作経験を積んでいこう! R6.2.29
2月28日(水)、土地利用学科では、タマネギのべと病防除を目的とした農薬散布を行いました。もちろん乗用管理機のブームスプレーヤを使います。この日は、天気は良好、風も弱く、タマネギにしっかりと薬剤をかけることができたと思います。あ、ブームスプレーヤから出る薬液の霧に虹が・・・
タマネギの畝の長さは約80mもあり、手作業で防除すると大変です。乗用管理機で防除するメリットを実感できますね。
さて、今日の防除はこれだけではありません。次は、午前中にジャガイモを植えた圃場で除草剤を散布します。乗用管理機を一旦帰らせて、念入りに洗浄し、薬液を調整したら、再度防除に出発!
ジャガイモ圃場の面積はわずか4アール(400㎡)。こちらは手作業で除草剤散布できる面積ではありますが、土地利用学科では少しでも機械の操作経験を積ませるために、乗用機械を使うようにしています。学生は、「車高が高くて怖いです」と言いながらも、教官から操作を教わり、丁寧に防除を行っていました。




動画完成。イイ出来だね! R6.2.29
講義時間だけでなく、空いた時間を使いながら取り組んできた動画作成も、いよいよ最終盤。2月15日(木)に、最後の講義が行われました。今回も、皆で話し合いながらどんどん作り込みます。
ある程度完成したところで、いよいよ試写会です。この段階で、なかなか良い出来になっていましたが、講師や他班のメンバーから意見・アドバイスをもらい、より良いものを目指して編集作業を進めます。結局、講義時間内には完成しなかったので、翌週末までに完成させることで講義は終わりました。
そして、2月22日(木)、ついに「トラクタの始業点検」と「トラクタの作業機の脱着」の2本の動画が完成! 早速講師に送ったところ、「素晴らしい出来栄え」「構成・組立てがしっかりしており、全体的に理解しやすい」「テロップが今風でセンスが良く、エンド部の閉めも素晴らしい」などお褒めの言葉を頂きました。「しっかり関わった学生は、駆け出しのYoutuber程度の動画製作能力は身に付いたと思います」とも言われました。
この動画ですが、土地利用学科だけでなく、農業機械の講義等でも活用されることでしょう。また、土地利用学科としては更に動画の本数を増やし、学修の効率化と理解促進に努めていく予定です。

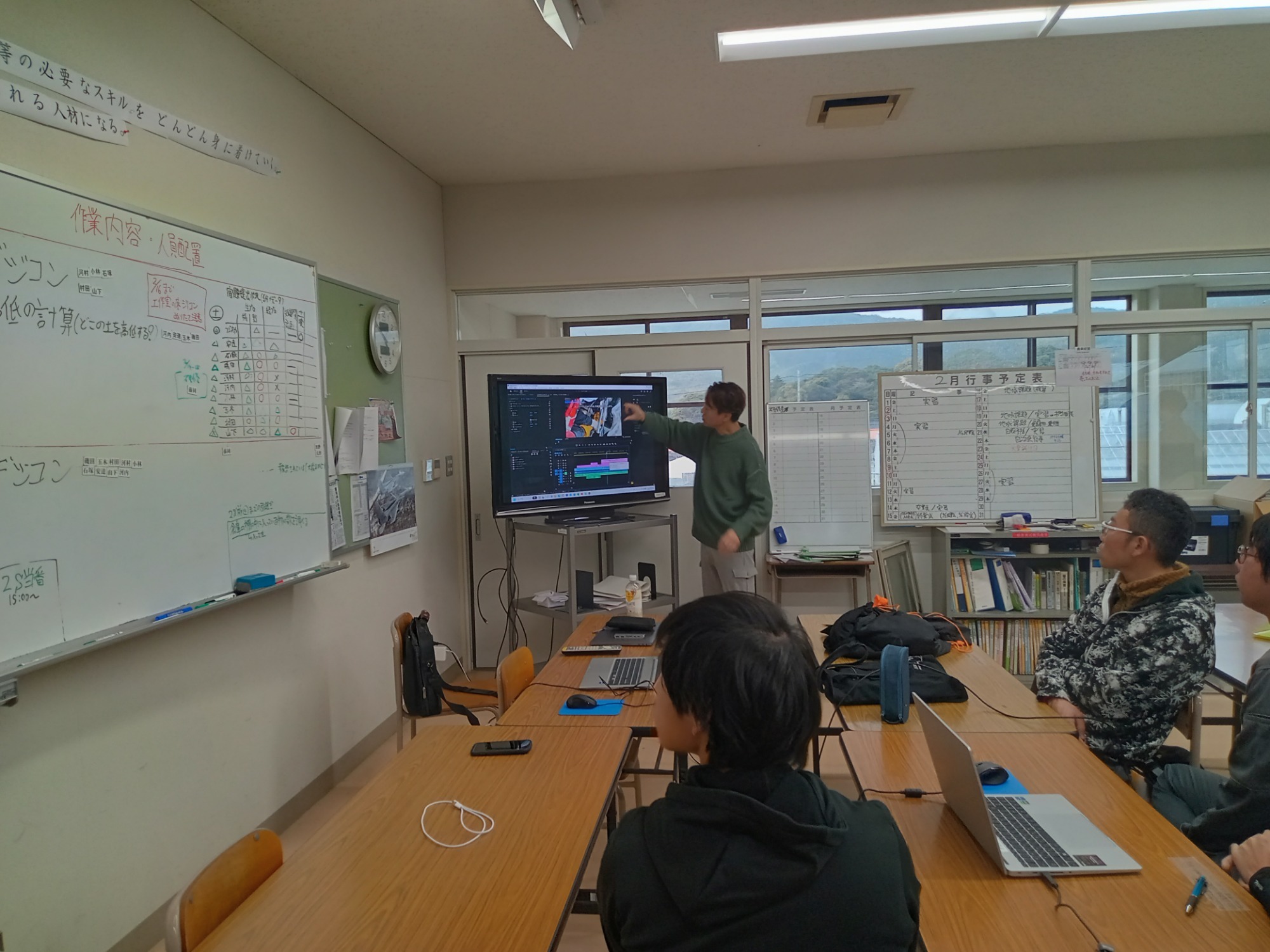
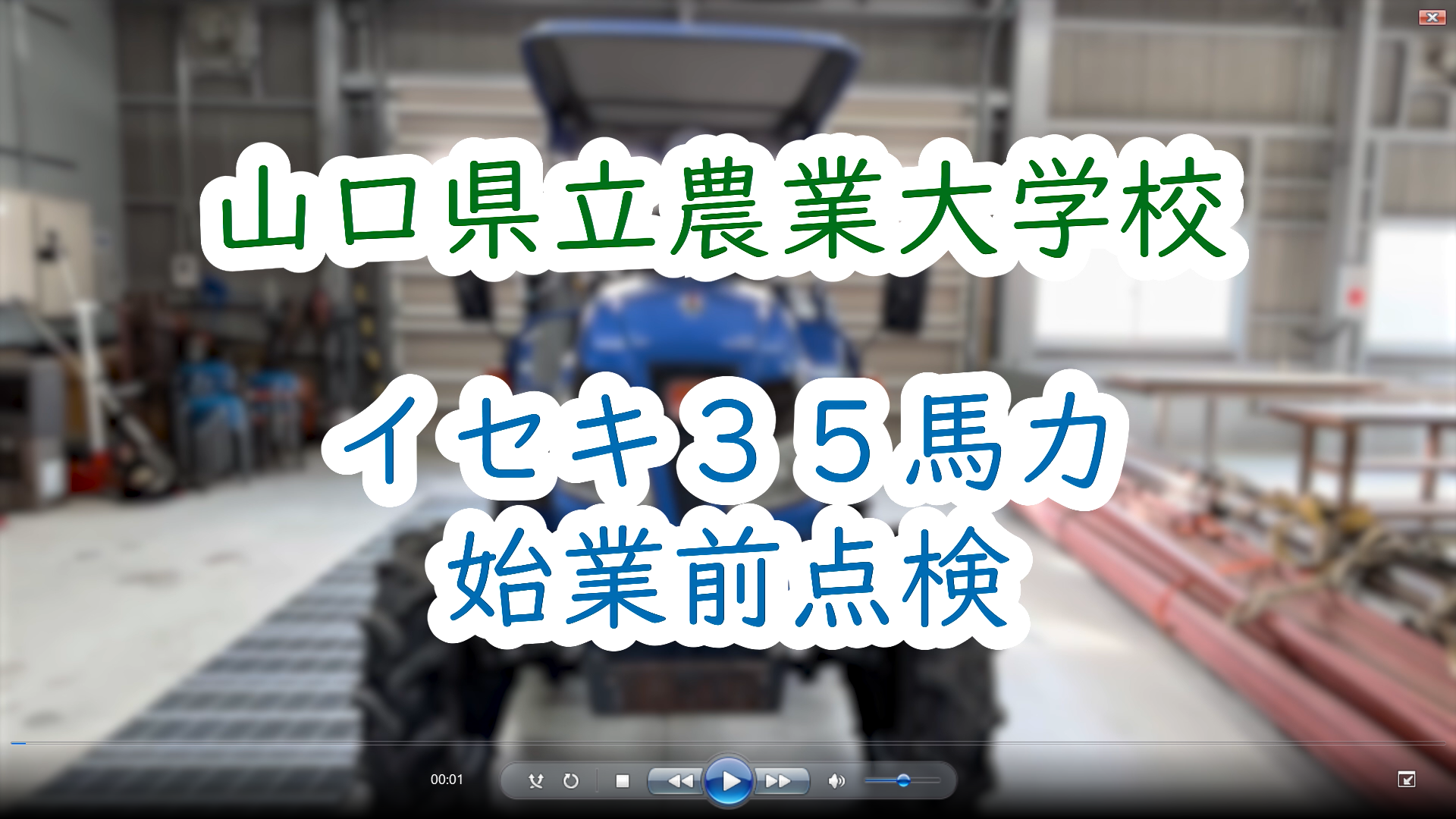

キュウリ苗の呼び接ぎ! R6.2.26
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。
本調査で使用するキュウリの苗として、2月13日に穂木品種の「常翔661」を、2月15日に台木品種の「ときわパワーZ2」を播種したところですが、播種後曇雨天の日が続いたため、苗が徒長してしまいました。しかし、穂木品種は第1本葉が径3cm前後に発育し、台木品種は双葉が展開し、第1本葉が出始めていることから、2月26日(月)、穂木品種と台木品種を「呼び接ぎ」という方法で、接ぎ木を行いました。
具体的には、穂木品種は第1本葉の直下へ斜め上に切り込みを入れるとともに、 台木品種は双葉の直下へ斜め下に切れ込みを入れ、直ちに切り込み部をかみ合わせて、接木クリップで固定を行いました。
徒長してはいましたが、担当の一年生は、穂木と台木の植える深さや位置などを工夫することで、320株の接ぎ木苗を作成し、無事にポットに植付けました。
一週間後には穂木品種の軸切りを行い、3月中旬には定植を行う予定です。




キュウリの定植準備(畝立て)! R6.2.21
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。
その一環として、2月21日(水)、調査で使用する2棟のパイプハウスで、畝立てを行いました。
最初に畝の位置や幅を決めるとともに、畝をまっすぐ立てるための目印をつけました。
次に、管理機を使って溝を切るとともに、畝の設置場所に泥を寄せました。
最後に、畝立成型機を使って畝を立てました。
担当の一年生は、教官の指導を受けながら的確に作業を行い、まっすぐで均平な畝を立てていました。
今後、潅水チューブの設置や白黒マルチの被覆、支柱の設置などを行い、3月中旬には定植を行う予定です。




花き経営コース生産プロジェクト発表会! R6.2.21
園芸学科花き経営コースでは、2月21日(木)、園芸・バイテク実習棟花き教室にて、生産プロジェクトの発表会を行いました。
当校では、プロジェクト学習として、学生自らが課題を設定し、課題解決のための計画を立て、これに基づき課題解決活動を行う学修方法を実施しており、一年時には「生産プロジェクト」として、基本的な生産技術等の習得を図ることとしています。
今回、同コースの一年生4名が、それぞれが行ったトルコギキョウ、カーネーション、スプレーギク、ビオラに関するプロジェクトの成績を発表しました。
学生たちは、課題の背景や目的、調査方法や結果、考察を丁寧に説明するとともに、教官や同級生からの質問に慎重に回答していました。

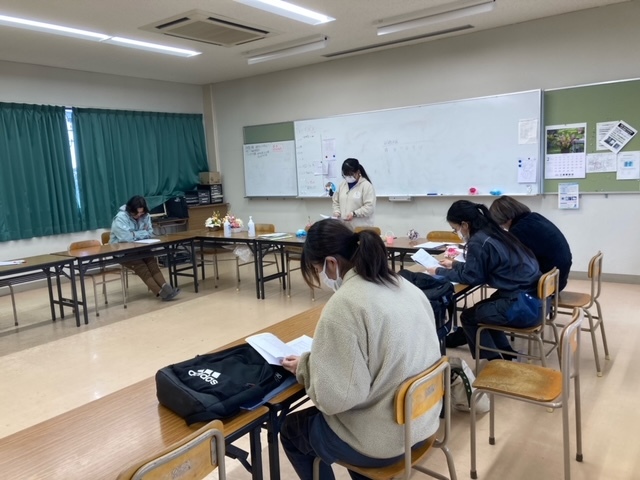
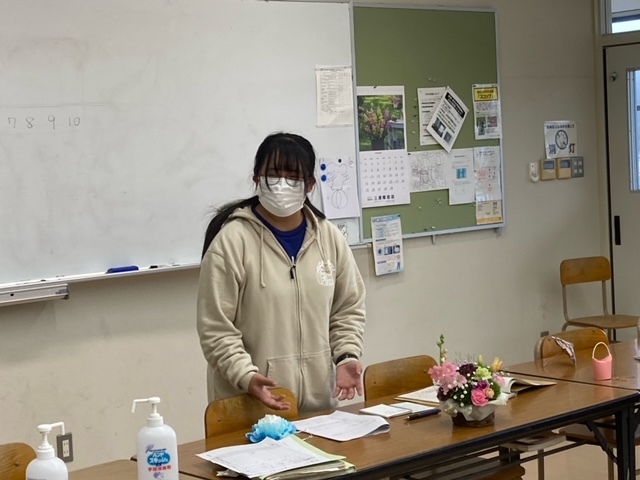
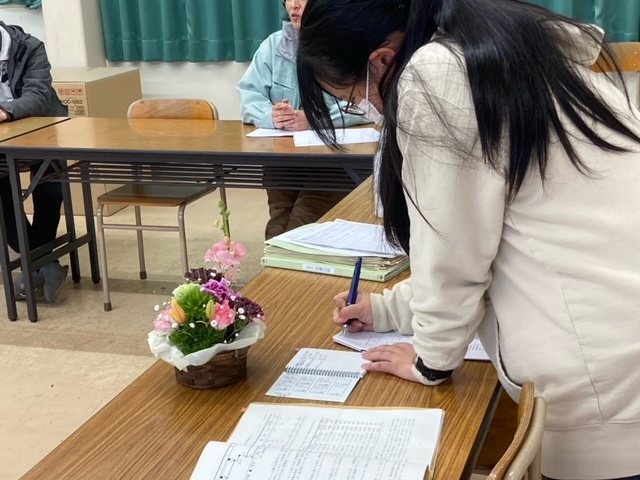
防府市まちの駅「うめてらす」での販売実習に向けた準備! R6.2.21
2月28日(水)の午後2時から防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行います。
このため、2月21日(木)に、当日参加する学生たちが打合せを行いました。
1年間経験したおかげで話し合いはスムーズに進みました。
役割分担や流れの確認に時間を割くことが少なかったため、商品の詳細を担当専攻に確認したり、個々の目標を考えてみたりと充実した打合せになりました。
来年度に向けて試してみたいことの提案もあったので、終わったあとの感想が楽しみです。
当日は新鮮な商品と学生の笑顔でおもてなしをさせていただきますので、ぜひ、2月28日に防府市まちの駅「うめてらす」へ足をお運びください。




出荷調製棟シャッター前の防鳥ネットの設置改善! R6.2.20
当校では、GAP(農業生産工程管理)をカリキュラムに取り入れるとともに、園芸学科では、平成31年1月にJGAP認証を取得し、GAPの実践を行っています。
この一環で、「野菜・花き出荷調製棟」の2つのシャッターには、鳥などの有害生物が施設内に入らないよう、防鳥ネットを設置しています。
しかし、防鳥ネット設置個所の隙間から鳥が入った事例や出荷時の出入り時にネットが邪魔になるといった問題点もありました。
そこで、GAP担当の二年生が、防鳥ネットの設置改善に取り組みました。
防鳥ネットの設置個所の隙間は磁石を使って塞ぎ、ネット開口部は塩ビパイプをネットに抱かせ、開閉を楽にするとともに、開口部が大きく取れるようにしました。
おかげで、有害生物の侵入防止効果や作業性の向上が期待できます。




ナシ「新高」の伐採! R6.2.20
2月20日(火)、園芸学科果樹経営コースのナシ班では、ナシの晩生品種である「新高(にいたか)」の伐採を行いました。
この「新高」は、定植から40年を経過しており、近年は樹勢の低下が顕著で、枝の伸びや果実品質も思わしくないことから伐採することに決定しました。
ナシ班の二年生は、教官の指導の下でチェーンソーを使って太い枝を次々と切り進めました。
今後は、他の「新高」や同じく植裁から約40年経過した晩生品種の「愛宕(あたご)」を伐採し、花粉樹を定植する予定です。




「せとみ」のMA包装! R6.2.19
2月19日(月)、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、1月23日に収穫した「せとみ」をMA包装しました。
MA包装とは、青果物をプラスチックフィルムで包み、青果物の呼吸によってフィルム内のガス組成を低酸素、高二酸化炭素状態にして呼吸を抑制して鮮度を保持するもので、当校では、フィルム面に小さな穴の開いた「微細孔フィルム」を利用しています。
学生たちは、果実一つ一つを丁寧にこの微細孔フィルムで包装していました。
MA包装の後は、冷蔵庫で保管し、4月頃から出荷を開始する予定です。




キュウリの定植準備(施肥・耕うん)! R6.2.19
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。
その一環として、2月19日(月)には、調査で使用する2棟のパイプハウスで、定植の準備を行いました。
まず、基肥となる化成肥料を手で撒き、その後トラクターを使って耕うんしました。
今後、畝立てや畝へ潅水チューブの設置、白黒マルチの被覆、支柱の設置などを行い、3月中旬には定植を行う予定です。




ピーマン・パプリカの播種! R6.2.19
園芸学科野菜経営コースでは、パイプハウスでピーマンとパプリカの栽培に取り組みます。
その一環として、2月19日(月)には、担当の一年生が、セルトレイに播種しました。
今回使用する品種は、穂木はピーマンが「さらら」、パプリカが「フルーピーレッド EX」と「フルーピーイエロー」、台木が「バギー」です。
学生は、計7枚のセルトレイへ播種し、その後、新聞紙を被せて、軽く潅水を行いました。
これらのセルトレイ苗は、育苗温室で約3週間管理した後、接ぎ木を経て、鉢上げする予定です。




ビオラの仕上げ鉢への植え替え! R6.2.19
防府天満宮の「花回廊」イベントに関連し、当校の園芸学科花き経営コースが、ビオラ、ベゴニア、オダマキ、マリーゴールドの栽培に取り組んでいます。
このうち、ビオラは、昨年12月6日にポリポットへ鉢上げを行いましたが、生育が進んだため、2月19日(月)に仕上げ鉢(ボールプランター)に植え替えを行いました。
学生たちは、ビオラのポリポット苗4鉢分を仕上げ鉢に丁寧に植え替えていました。
このビオラの仕上げ鉢への植え替えは、全部で320鉢行う予定です。
3月中旬には、防府市内の中学校に鉢を配布して、イベント開催まで中学生が管理する予定です。




令和5年度全国農業大学校等プロジェクト発表会に出場! R6.2.16
2月7~9日に東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された全国農業大学校等プロジェクト発表会に本校野菜経営コース2年の岡村美雨さんが中四国ブロックの代表として出場し、優良賞に当たる全国農業大学校協議会長賞を受賞しました。
大会では、それぞれの地域や生産現場での課題解決にむけ、栽培方法の改善や6次産業化など農大生が自ら取り組んだプロジェクトの発表がありました。
また、全国から集まった農大学生等と本校から参加した岡村さん含む6名の学生が意見交換会や交流会等で親睦を深めていました。




キュウリの台木品種の播種を行いました! R6.2.15
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。
2月13日の穂木品種に続き、2月15日(木)には、台木品種の播種を行いました。
今回播種した品種は、「ときわパワーZ2」で、発芽揃いが良く、接ぎ木がしやすく、何れの品種とも親和性がよく、成苗率が高いことが特徴です。
担当の一年生は、同級生と協力して、バット内に充填した培土にスジをつけ、それにそって、3cm間隔で種子をまいていきました。
今後、2月26日に呼び継ぎを行う予定です。




やまぐちオリジナルユリの定植! R6.2.15
園芸学科の花き経営コースでは、やまぐちオリジナルユリについての経営プロジェクトを行います。
その一環として、2月15日(水)には、球根の定植を行いました。
今回、供試する品種は「プチロゼ」で、花色が濃いピンク色であり、通常のユリに比べ、花径が10cmと小ぶりなサイズであることが特徴です。
定植前には、担当の一年生が、無作為に抽出した球根20個について、芽の長さを測定し、腐敗球根数を数えました。
また、定植は、定期試験で対応できない学生の代わりに、二年生や教官が行いました。
今後も一月置きに定植を進めていく予定です。
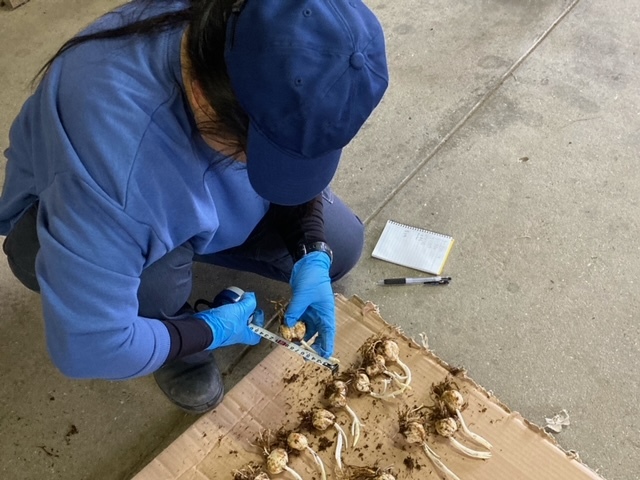



資材庫の片付けが進みました(野菜専攻)! R6.2.15
園芸学科野菜経営コースの二年生は、残りわずかな農大での実習時間を、後輩が少しでも実習しやすくなるようにとの思いから、今できる様々なことに取り組んでいます。
とくに、栽培資材を収納している資材庫の整理、整頓、清掃に力を入れており、不要なものを捨て、使い勝手がよくなるよう位置決めを行い、きれいに掃除を行いました。
2月15日(木)には、資材庫の2階の片付けが終わったので、そのお披露目が行われました。
資材が整然と置かれ、通路も以前に比べ格段に広くなるなど、以前とは見違える状態に、二年生も非常に満足していました。




せとみ園のマルチ被覆! R6.2.15
園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、2月13日より、柑橘園の土壌改良を行っています。
マルチを行っている園では、土壌改良の前にマルチを部分的に剥ぎ、牛糞堆肥やカキ殻石灰を施用した後、マルチを元通りに被覆します。
2月15日(木)には、せとみ園において、マルチの被覆作業が行われました。
二年生は、隙間がないようマルチを被覆し、丁寧にUピン杭で止めていました。
次週には、土壌改良に係る全ての作業が終わる予定です。




「みどり戦略学生チャレンジ」 交流会参加に係る報告! R6.2.15
2月14日に、岡山県で、環境負荷低減を目指す「みどり戦略」の実現に向け、農業系高校や農業大学校の取り組みを共有する 交流会が開催され、中国四国地方からの4県7校の生徒らが参加し、取り組みの発表や意見交換会が行われました。
当校からは、園芸学科果樹経営コースのナシ班の二年生2名が参加しました。
そのうちの1名は、環境にやさしい防除体系の確立に向け、土着天敵を活用した取り組みについて発表しました。
2月15日(木)には、参加した学生が、校長に当日の様子を報告し、いただいた感謝状を披露しました。
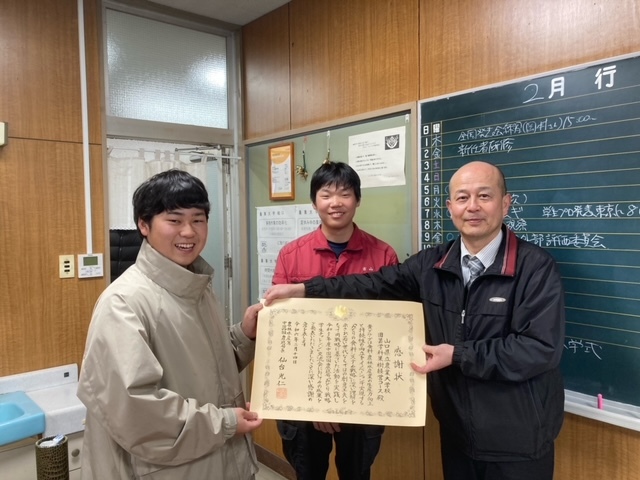
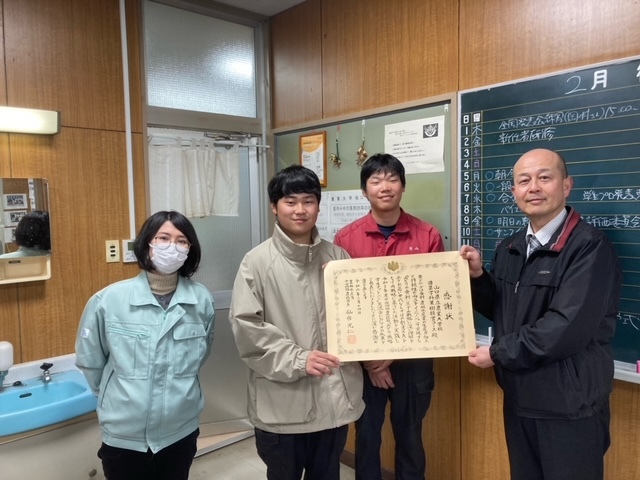
「道の駅 ソレーネ周南」で7名の学生が販売実習を実施! R6.2.14
2月14日(水)、「道の駅
ソレーネ周南」で、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の二年生3名と一年生2名、畜産学科の一年生1名、計7名の学生が、販売実習に臨みました。
2月にしてはとても暖かく穏やかな天候の中、元気よく実習を行いました。
販売品目はやや少なめではありましたが、その分丁寧な説明を心掛け、お客様と長く会話する姿が見られました。
知らない人に声をかけることは恥ずかしく、勇気がいるものですが、大きな声を出して遠くの人にお知らせしたり、近くを通る方に目を合わせて誘導したりできました。
1年間実習を経験し、それぞれ自分なりの反省を踏まえて改善やチャレンジを行ったようです。
次回の販売実習は、2月28日(水)に、まちの駅「うめてらす」で行う予定です。




穂木用ナスの播種を行いました! R6.2.14
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ナスの露地栽培における土着天敵を用いた防除体系の有効性を検証します。
その一環として、2月14日(水)には、担当の一年生が、供試するナスの穂木品種の播種を行いました。
品種は「PC筑陽」で、単為結果性が高く、ホルモン処理や虫媒による受粉をしなくても、安定的に着果・肥大するとともに、果実のヘタや茎葉などにトゲがほとんどなく、果皮に傷を付けにくく、作業がしやすいことが特徴です。
担当の一年生は、二年生の助けを得ながら、128穴のセルトレイ9枚に播種しました。
今回播種したセルトレイは育苗温室で管理し、鉢上げ、接ぎ木を経た後、5月中旬ごろに定植する予定です。



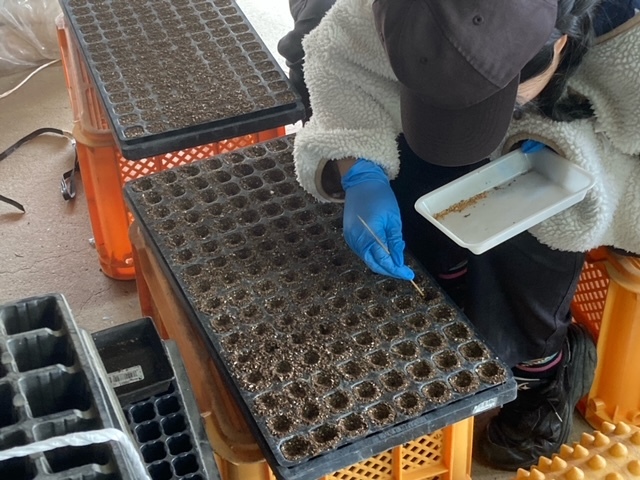
やまぐちオリジナルユリの定植準備(フラワーネット設置)! R6.2.14
園芸学科の花き経営コースでは、やまぐちオリジナルユリ「プチシリーズ」に関する経営プロジェクトに取り組んでいます。
その一環として、2月14日(水)には、プロジェクトを担当する一年生が、二年生の協力を得ながら、ハウス内の4つの畝の端に杭を打ちフラワーネットを設置しました。
翌日には、最初の球根定植を行い、今後も一月置きに定植を進めていく予定です。




キュウリの播種を行いました! R6.2.13
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、キュウリの半促成栽培における日射比例潅水が生育や収量に及ぼす影響を調査します。
2月13日(火)には、担当の一年生が調査に供試するキュウリを播種しました。
品種は「常翔661」(じょうしょう661)で、生育初期から各節に連続して雌花が咲くとともに、果実肥大は早く、果形が安定し、食味が良好であるのが特徴です
学生は、バット内に充填した培土にスジをつけ、それにそって、3cm間隔で種子をまいていきました。
今後、台木品種を播種した後、2月26日に呼び継ぎを行い、3月中旬に定植する予定です。




葉ネギの播種を行いました! R6.2.8
園芸学科の野菜経営コースでは、パイプハウスで、葉ネギの栽培に取り組みます。
2月8日(木)、担当の一年生が、葉ネギの播種を行いました。
今回播種した品種は「冬どり若香2号」で、低温伸長性に優れ、生育が早く、周年栽培ができるとともに、葉は細く長く、葉色は濃いため、荷姿が美しいことが特徴です。
今回、手押式播種機を使って播種作業を行いましたが、最初、担当の一年生は操作に苦戦していましたが、二年生の指導により要領を得て、上手く操作できるようになりました。


葉ネギの定植準備(耕うん)! R6.2.6
園芸学科の野菜経営コースでは、パイプハウスで、葉ネギの栽培に取り組みます。
この準備として、2月6日(火)、担当の一年生が、トラクターを使用して耕うん作業を行いました。
学生は教官の指導を受けながら、慎重に操作を行い、パイプハウス内をきれいに耕うんしました。
耕うん後は畝立ても行い、2月8日には播種作業を予定しています。




柑橘園の土壌改良! R6.2.13
園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、2月13日(火)より、柑橘園の土壌改良を始めました。
この日は、ブドウ班の学生も参加し、「興津早生」など早生の温州みかんが植栽されている園や「ポンカン」などが植裁されている園地に、当校畜産学科で作られた牛ふん堆肥を施用しました。
この時期にしては暖かい日であったこともあり、学生たちは汗をかきながら堆肥をまいていました。
今後は、「青島温州」や「せとみ」などが植裁されている園へ牛ふん堆肥を施用するとともに、続いてカキ殻石灰等も施用する予定です。




メロンの脇芽取り! R6.2.13
園芸学科の野菜経営コースでは、パイプハウスでメロン栽培に挑戦しています。
冬季での栽培ということもあり、当初の予想より生育が遅れ、節間も短くなっていますが、寒さが和らぐにつれ、つるの伸びに勢いが感じられるようになるとともに、雄花の開花も確認されるようになりました。
2月13日(月)には、担当の二年生が、メロンの脇芽取りの作業を行いました。
これは、少しでも養分の消耗を防ぐため、不要な脇芽を除去するもので、学生は一株一株丁寧に脇芽を取り除いていました。
二年生が農業大学校で実習を行える期間は残りわずかですが、少しでもメロン栽培に携わり、学びを得ようと頑張っています。




パイプハウス建設実践技術研修を開催しました!(R6.2.6~9) R6.2.9
2月6日から2月9日にかけて、やまぐち就農支援塾 「パイプハウス建設実践技術研修」を開催しました。
パイプハウスの骨材など栽培施設設備費が高騰する中、中古ハウスの移設や自家施行による経費節減を図ることが重要となっています。そこで、この研修は、新規就農者や資質向上を希望する農業者を対象に、パイプハウス建設に必要な知識・技術を修得することを目的に行いました。
今回は8名の一般受講者と10名の担い手養成研修生が参加し、パイプハウスの建設から、解体まで実習しました。
受講者からは「実際に建設してみないとわからないコツがわかった」「今後の建設する際の手順が理解できた」等の感想が聞かれました。




不知火の収穫を行いました! R6.2.8
園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、2月8日(木)、パイプハウスで栽培している「不知火」の収穫を行いました。
この「不知火」は、「ヤケ果」と呼ばれる果皮障害になりやすい傾向があり、果皮障害を避けるには果実にできるだけ衝撃を与えないようにする必要があります。
このため、収穫作業を行った学生は、果実に衝撃を与えないよう、慎重に収穫や運搬作業を行っていました。
今回収穫した「不知火」は、選果や軽い乾燥処理(予措)を行った後、貯蔵し、2月下旬頃に出荷する予定です。




「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備! R6.2.8
2月14日(水)の午後2時から「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習を行います。
このため、2月8日(木)に、当日対応する学生たちが打合せを行いました。
参加者は、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の一年生2名、二年生3名、畜産学科の一年生1名の計7名で、一年生と二年生が協力して打合せを進めました。
一年生は先輩のアドバイスを受ける最後の実習となります。
回数を重ねてきたことで効率よく話し合いを進めることができていましたが、役割分担では全体のバランスを考えたり、商品の特徴を詳しく説明を受けたり、一年生はまだまだ先輩に助けてもらっていました。
販売当日も、しっかりと先輩の背中を見て、今後に活かしてほしいと思います。
当日は新鮮な商品と学生の笑顔で素晴らしいおもてなしを提供できることと思いますので、ぜひ、2月14日に「道の駅 ソレーネ周南」へ足をお運びください。

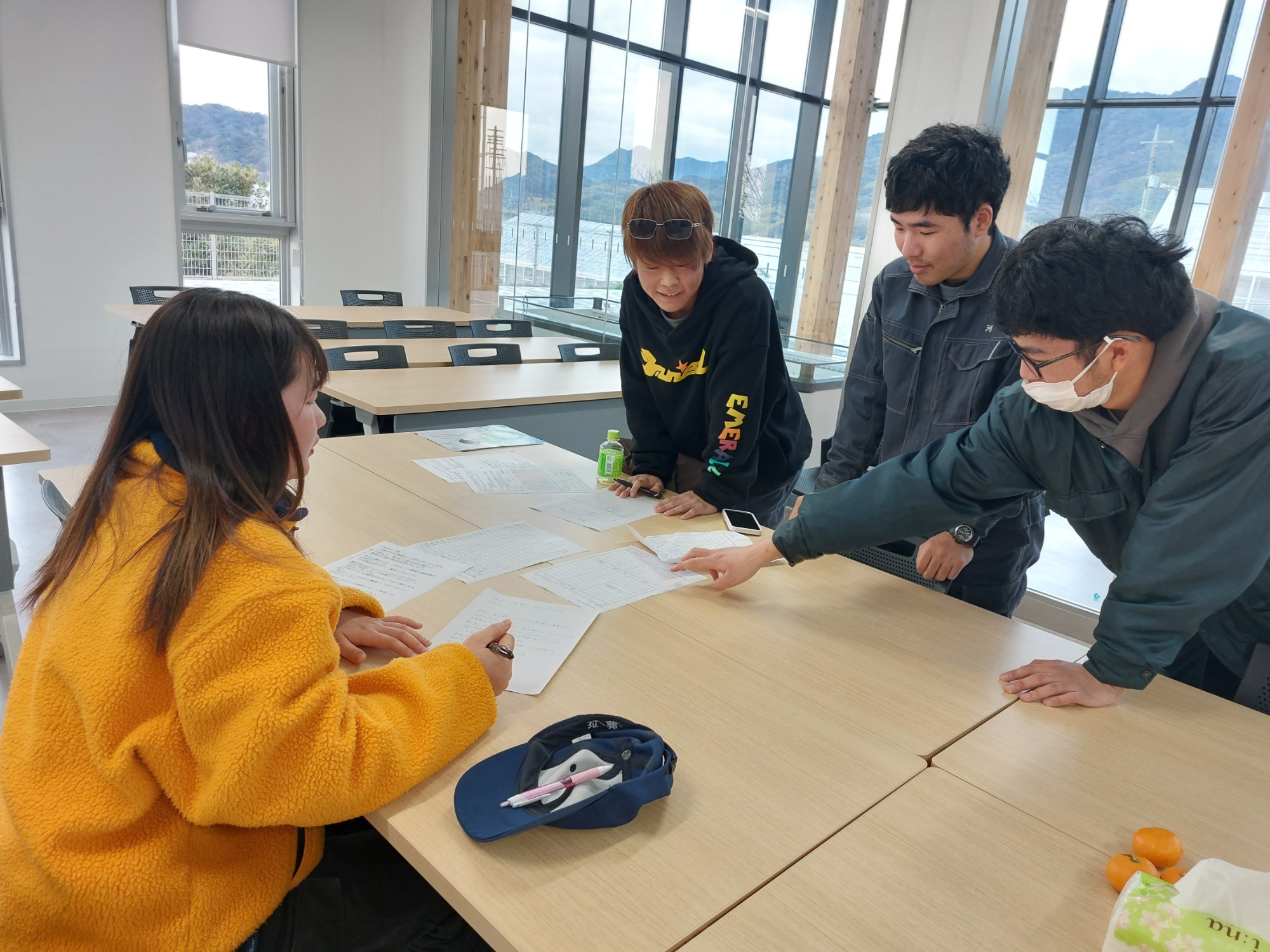


花きパイプハウスの天井ビニル張替(その2)! R6.2.7
園芸学科花き経営コースでは、2月6日に、パイプハウス1棟の天井ビニルの張替を試みましたが、ビニルを取り外した後、風が強まったため、この日は張替を断念しました。
その翌日の2月7日(水)、再び天井ビニルの張替作業を行いました。
昨日よりは風はやや弱まりましたが、それでも風が吹いていたため、パイプハウスをビニルで覆った後も、ビニルが風で飛ばされないよう抑えたり、ビニルの位置のズレを整えたり、スプリングで固定したりといった作業をてこずりながら進めました。
しかし、学生と職員は連携して、無事にビニルの張替を終えました。
今後、このパイプハウスでは、やまぐちオリジナルユリである「プチロゼ」を使った経営プロジェクトを行う予定です。
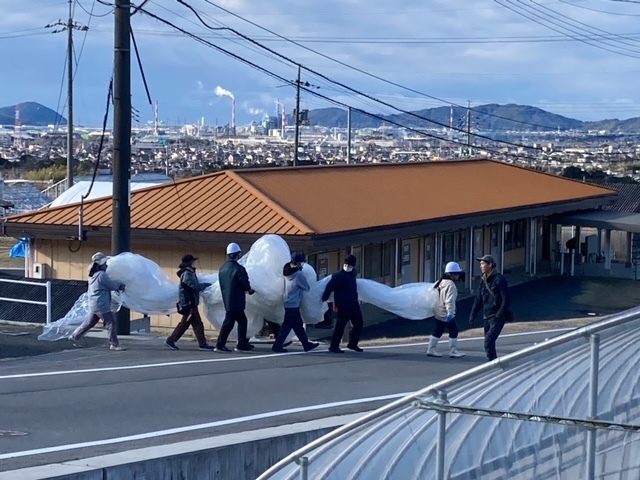



栽培資材の洗浄・片付けを行っています! R6.2.6
2月6日(火)、園芸学科野菜経営コースの二年生達が、自分達が使用した栽培資材の洗浄と片付けを行っています。
プラ船の中にお湯を貯め、潅水チューブなどを丁寧に洗い、使いやすいように丸めたりし、所定の場所に片づけていました。
二年生たちは、残りわずかな農大での実習時間を、後輩たちが少しでも実習しやすくなるようにとの思いから、今できる様々なことに取り組んでいます。




圃場横の溝掃除を行いました! R6.1.31
1月31日(木)、園芸学科野菜経営コースの二年生が、露地圃場横に設けられた溝の掃除を行いました。
溝にたまった泥等を上げる作業はきついですが、二年生は後輩たちのためにと一生懸命作業を行っていました。
二年生が農大で実習を行えるのも残りわずかとなり、現在は、こうした環境整備も積極的に行っています。




全国農業大学校等プロジェクト発表会へ向けて出発! R6.2.7
2月7日(水)の午前5時30分、翌日に東京で開催される全国農業大学校等プロジェクト発表会に参加する学生6名が、引率の職員とともに、当校を出発しました。
このうち、発表者として参加する園芸学科野菜経営コースの二年生は、これまで十分な練習を行ってきたこともあり、練習の成果を発揮したいと意気込んでいました。
出発時は、野菜経営コースの二年生が、朝の作業の合間をぬって、見送りを行いました。
当日は、これまで一緒に頑張ってきた仲間や後輩たちの応援が、実力発揮の力となるでしょう。すばらしい発表が行えることを期待しています。

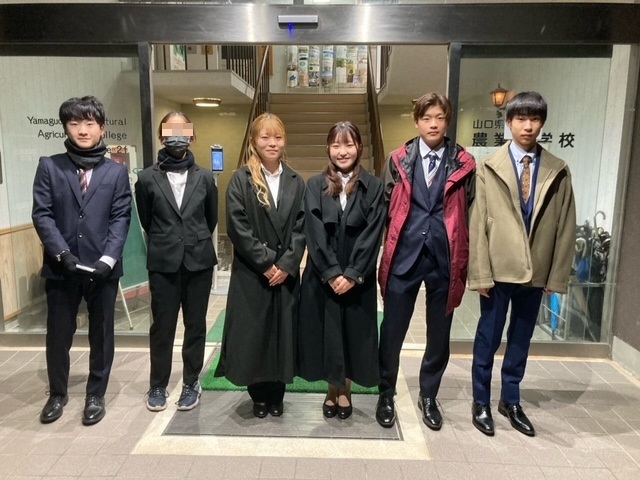


台木用ナスの播種を行いました! R6.2.6
2月6日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、台木用のナスの播種を行いました。
品種は「トナシム」で、青枯病や半身萎凋病、サツマイモネコブ線虫など複数の病気や害虫に耐性を有しており、茎や葉にトゲがないことが特徴です。
担当の一年生は、二年生の助けを得ながら、72穴のセルトレイ14枚に播種しました。
その後、これらのセルトレイは育苗温室に移動させました。
一週間後には、穂木用のナスの播種を行う予定です。




花きパイプハウスの天井ビニル張替(その1)! R6.2.6
園芸学科花き経営コースでは、パイプハウス1棟の天井ビニルの破損が顕著となったため、張り替えることとしました。
2月6日(火)の9時30分より、まず、天井ビニルの除去作業を行いました。
学生と職員は、協力し合いながら、バンドやスプリングの取り外しを行いました。
その作業が終わると、天井ビニルの除去作業に取り掛かりました。
作業中、風が少しず強くなりましたが、なんとか天井ビニルの除去と回収を終えることができました。
しかし、その後、風がさらに強くなったため、この日は新しいビニルの被覆は断念し、翌日に再チャレンジすることとなりました。




第4回短期入門研修を開催しました! R6.2.7
1月29日から2月1日にかけて、やまぐち就農支援塾第4回短期入門研修を開催しました。この研修は、農業未経験の方などを対象に、将来の就農を目指すきっかけとしていただくために、毎年度4回実施しているものです。
今回は12名の受講者が参加され、農業機械・小農具の取り扱いや、野菜・果樹・花き・酪農の作業体験を、農業大学校の職員や学生らから指導を受けながら実施しました。
受講者からは「実際に作物や家畜に触れながらの作業体験ができ参考になった」「学生たちともいろんな情報交換ができ良かった」「今後の就農に向けた検討の材料にしていきたい」等の感想が聞かれました。






全国農業大学校等プロジェクト発表会の練習! R6.2.5
2月8日に東京で開催される全国農業大学校等プロジェクト発表会に、園芸学科野菜経営コースの二年生が参加します。
参加する学生は、現在、発表練習で受けた指摘を元に、発表原稿やスライドを修正し、より理解しやすい発表となるよう励んでいます。
2月5日(月)の発表練習では、全国から集まる農業大学校の学生にも印象深く、理解してもらえるようにと工夫した発表を行い、発表を聞いていた他の学生からは、わかりやすいとの感想が上がりました。
発表会まで残りわずかですが、発表する学生は、「経営プロジェクトの調査や取りまとめは大変だったけど、代表に選ばれたのも、支えてくれた仲間のおかげであり、皆の思いも東京へ持っていき、県代表として頑張りたい」と意気込んでいました。

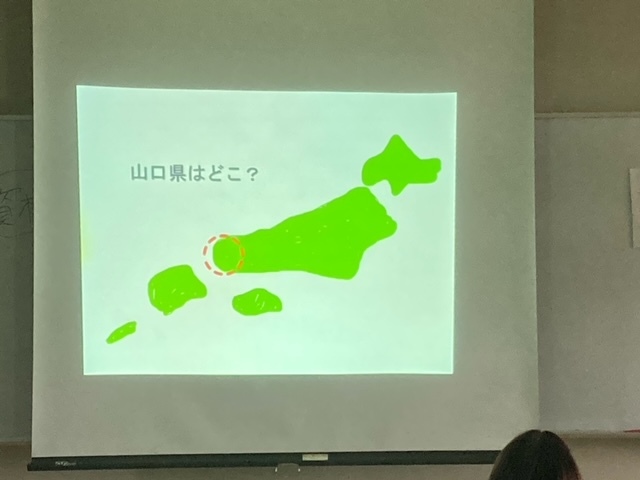
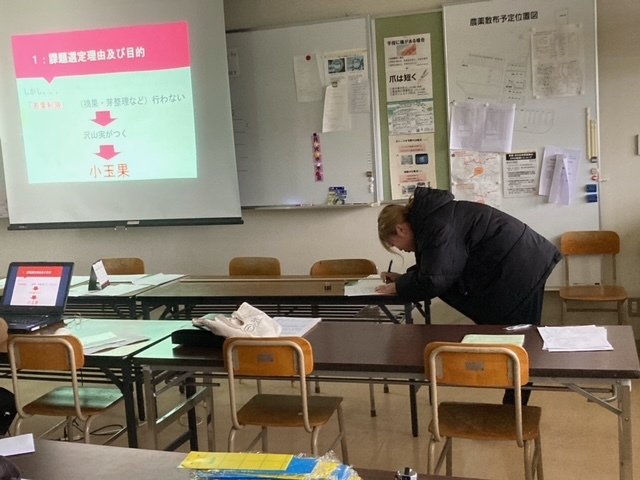
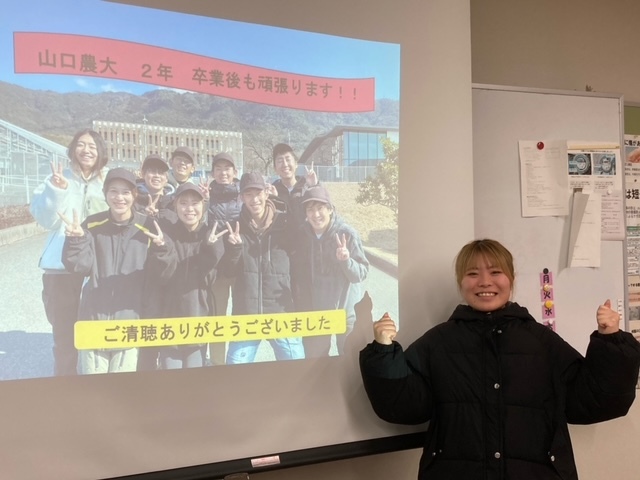
イチジク園の土壌改良! R6.2.5
2月5日(月)、園芸学科の果樹経営コースでは、イチジク園の土壌改良を行いました。
当校では、古くから日本で栽培されている品種の「蓬莱柿」と緑色の果皮に黄色の縞模様が入る個性的な「ゼブラスイート」をパイプハウス内で栽培しています。
今回、これらイチジクに対して、1樹当たり、バーク堆肥を4.5㎏、炭酸苦土石灰を270g施用しました。
作業を担当したカンキツ班の二年生たちは、資材の計量と施用で役割分担し、手際よく作業を行っていました。




防府市まちの駅「うめてらす」で7名の学生が販売実習を実施! R6.1.31
1月31日(水)、防府市まちの駅「うめてらす」で、園芸学科の一年生3名と二年生4名の計7名の学生が、販売実習に臨みました。
当日は、小雨が続き、客足も途絶えがちでしたが、声が周辺の建物に届くように拡声器を活用し、販売実習の開催を宣伝し続けました。
売り場の設営もスムーズで、お客様が少ない中でもモチベーションを保ちながら、雨対策をしつつ、商品説明も行えました。
先輩の的確な指示に答えた一年生たちは、多くのことを学んだようです。
次回の販売実習は、令和6年2月14日(水)に、「道の駅ソレーネ周南」で行う予定です。




「せとみ」の階級分け! R6.1.31
園芸学科果樹経営コースでは、山口県が育成した「せとみ」を施設と露地で栽培しています。
このうち、露地栽培の「せとみ」は、寒波の襲来に備えて1月23日に急遽収穫を行い、現在、調製棟内で貯蔵しています。
1月31日(水)には、同コースのカンキツ班が、この「せとみ」の階級分けを行いました。
カンキツ班の学生は、選果規格板を使用して、果実の大きさ別に仕分けていました。
この「せとみ」は、軽く乾燥させた後、貯蔵庫内で貯蔵し、3月中旬以降に出荷する予定です。


晩柑園の土壌改良(溝堀り)! R6.1.30
1月30日(火)、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、柑橘園の土壌改良作業を始めました。
晩柑園には伊予柑(いよかん)や八朔(はっさく)、約50本が植わっており、バックホウを使用して、土壌改良場所の溝堀りが行われました。
カンキツ班の二年生は、馴れた手つきで、黙々と溝を掘り進めていました。
今後は、掘り上げた土に、当校の畜産学科で生産されている堆肥に加え、カキ殻石灰を施し、土と資材を混和して溝に埋め戻す予定です。




マリーゴールドの仕上げ鉢への植え替え! R6.1.29
防府天満宮の「花回廊」イベントに関連し、当校の園芸学科の花き経営コースが、ビオラ、ベゴニア、オダマキ、マリーゴールドの栽培に取り組んでいます。
このうち、マリーゴールドは、昨年11月8日にポリポットへ鉢上げを行いましたが、生育が進んだため、1月29日(月)に仕上げ鉢(ボールプランター)に植え替えを行いました。
学生たちは、マリーゴールドのポリポット苗3鉢分を仕上げ鉢に丁寧に植え替えていました。
このマリーゴールドの仕上げ鉢への植え替えは、全部で195鉢行う予定です。




全国農業大学校等プロジェクト発表会の練習! R6.1.29
1月18日に岡山県で開催された中国四国ブロック農業大学校等経営プロジェクト発表会の結果、園芸学科野菜経営コースの二年生1名が優れた成績を収め、2月8日に開催される全国農業大学校等プロジェクト発表会の参加者に選ばれました。
その準備の一環として、1月29日(月)には、この学生が発表練習を行いました。
学生は、原稿やスライドを確認しながら、ゆっくり大きな声で発表しました。
発表後は、指導教官から原稿やスライドに関するアドバイスを受け、修正箇所の確認を行いました。
発表会までには、数回発表練習を行い、更なる改善を図っていく予定です。
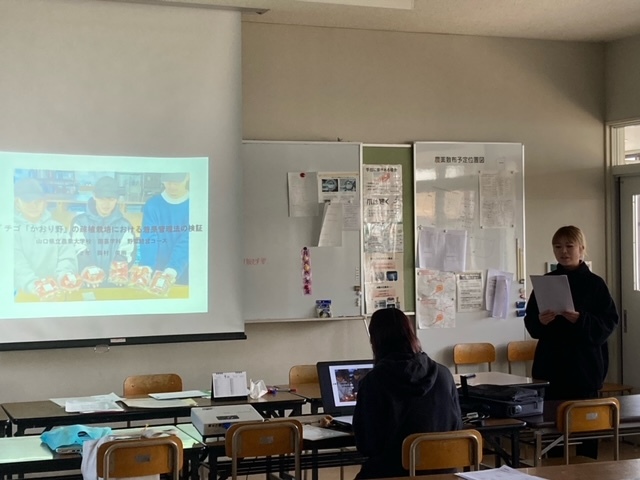
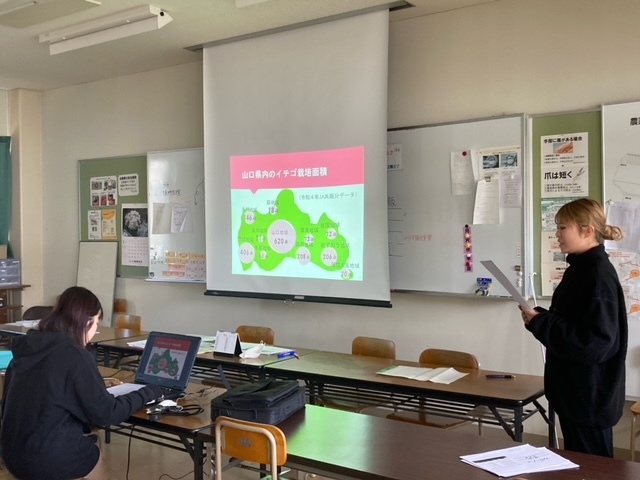
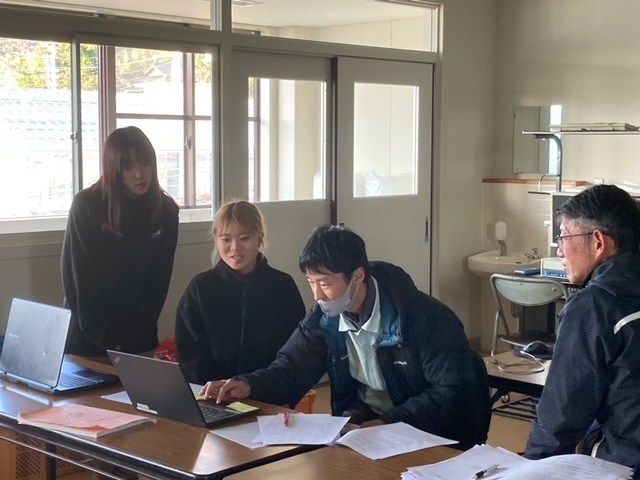
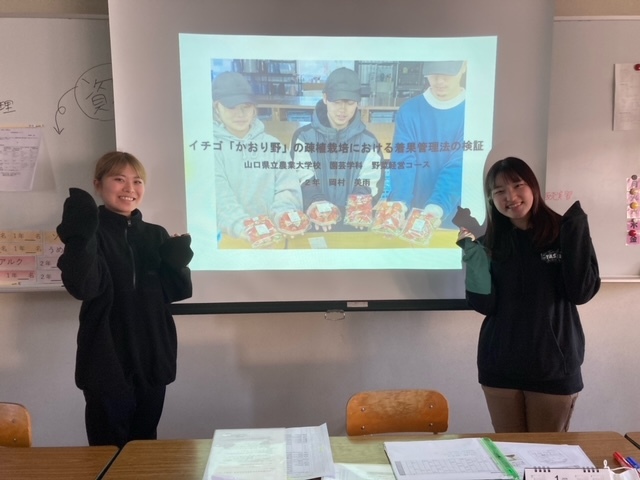
やまぐちオリジナルユリの定植準備(フラワーネット製作)! R6.1.31
園芸学科の花き経営コースでは、やまぐちオリジナルユリ「プチシリーズ」を用いた経営プロジェクトに取り組んでいます。
1月29日から30日にかけて、パイプハウス内の耕うん、畝立てを行ったところですが、1月31日(水)には、施設内で使用するフラワーネットを製作しました。
プロジェクトを担当する一年生は、短期入門研修の受講生や二年生と協力して、垂木を切り出し、畝の長さに合わせて4畝分のフラワーネットを製作しました。
今後、2月中旬には、最初の球根定植を行う予定です。
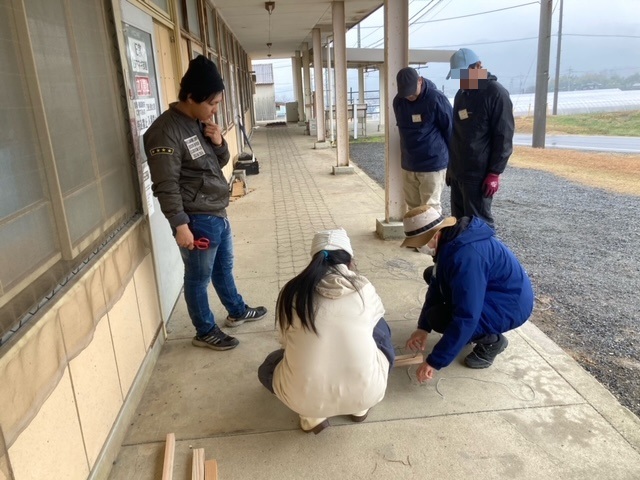

ビオラの鉢間広げ! R6.1.30
防府天満宮の「花回廊」イベントに関連し、当校の園芸学科花き経営コースが、ビオラ、ベゴニア、オダマキ、マリーゴールドの栽培に取り組んでいます。
このうち、ビオラは、昨年の12月6日にポリポットへの鉢上げを行い、ポットトレイに入れて管理していましたが、生育が進み、隣接する株と葉が触れ合い始めたため、1月30日(火)に、鉢間広げを行いました。
担当の一年生は、ポットトレイに入ったビオラのポットを、前後左右が隣合わないように抜き、別のポットトレイに手際よく移し替えていました。
このビオラのポットは、2月中旬頃に仕上げ鉢に植え替える予定です。




やまぐちオリジナルユリの定植準備(畝立て)! R6.1.30
園芸学科の花き経営コースでは、やまぐちオリジナルユリ「プチシリーズ」を用いた経営プロジェクトに取り組むこととしています。
1月30日(火)、プロジェクトを担当する一年生が、前日にトラクターを使って全面耕うんしたパイプハウス内を、畝立成型機を使用して、畝立てを行いました。
学生が慎重かつ丁寧に畝立てを行ったので、立派な畝ができ上りました。
今後、フラワーネットや潅水チューブの設置後、2月から8月にかけて球根の定植を行っていく予定です。




やまぐちオリジナルユリの定植準備(耕うん)! R6.1.29
園芸学科の花き経営コースでは、来年度の経営プロジェクトとして、山口県が育成したやまぐちオリジナルユリ「プチシリーズ」を用いて、球根の貯蔵期間が生育や品質に及ぼす影響について調査することとしています。
1月29日(月)には、オリジナルユリの定植準備として、プロジェクトを担当する一年生が、トラクターを使って、パイプハウス内を耕うんしました。
トラクターで耕うん作業を行うのが3回目の学生は、教官に指導を受けながら、慎重に操作を行い、パイプハウス内の全面をきれいに耕うんしていました。
翌日には、畝立てを行う予定です。


ウメのせん定! R6.1.29
1月26日(月)、園芸学科果樹経営コースのナシ班では、ウメのせん定を始めました。
当校のウメ園には、「南高」、「白加賀」、「前沢小梅」の3品種、11本が植わっていますが、今年は暖冬傾向であり、一部の樹では例年より早く開花が確認されました。
学生たちは、樹形を乱す徒長的に伸びた枝を中心に、ノコギリやハサミを使ってせん除していました。
ウメのせん定は、今週中には終了する予定です。




早生種の温州ミカンの伐根! R6.1.26
園芸学科果樹経営コースでは、現在、「興津早生」など早生種の温州ミカンを栽培している園地で列状間伐を行っています。
1月22日から23日にかけては、間伐する樹の太枝をチェーンソーで切除しました。
1月26日(金)からは、幹だけとなった樹の伐根を始めました。
この作業には、ブドウ班の二年生も参加し、丁寧に根を掘り出し、最終的には根ごと樹を抜いていました。
根気のいる作業ですが、学生たちは黙々と作業に取り組んでいました。




防府市まちの駅「うめてらす」での販売実習に向けた準備!
R6.1.25
1月31日(水)の午後2時より、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行います。
このため、1月25日(木)に、当日参加する学生たちが打合せを行いました。
参加者は、園芸学科の一年生3名と二年生4名、計7名で、皆が協力して進めました。
今回が二年生にとって最後の販売実習となるため、いつも以上に丁寧に話やアドバイスを行い、一年生も熱心に耳を傾けていました。
今回は園芸学科のみの対応であることや販売物が少ないことから、商品について詳細な話ができ、自分の専攻でなくても、お客様への上手なアピールができそうです。
当日は新鮮な商品と学生の笑顔でおもてなしをさせていただきますので、ぜひ、1月31日に防府市まちの駅「うめてらす」へ足をお運びください。
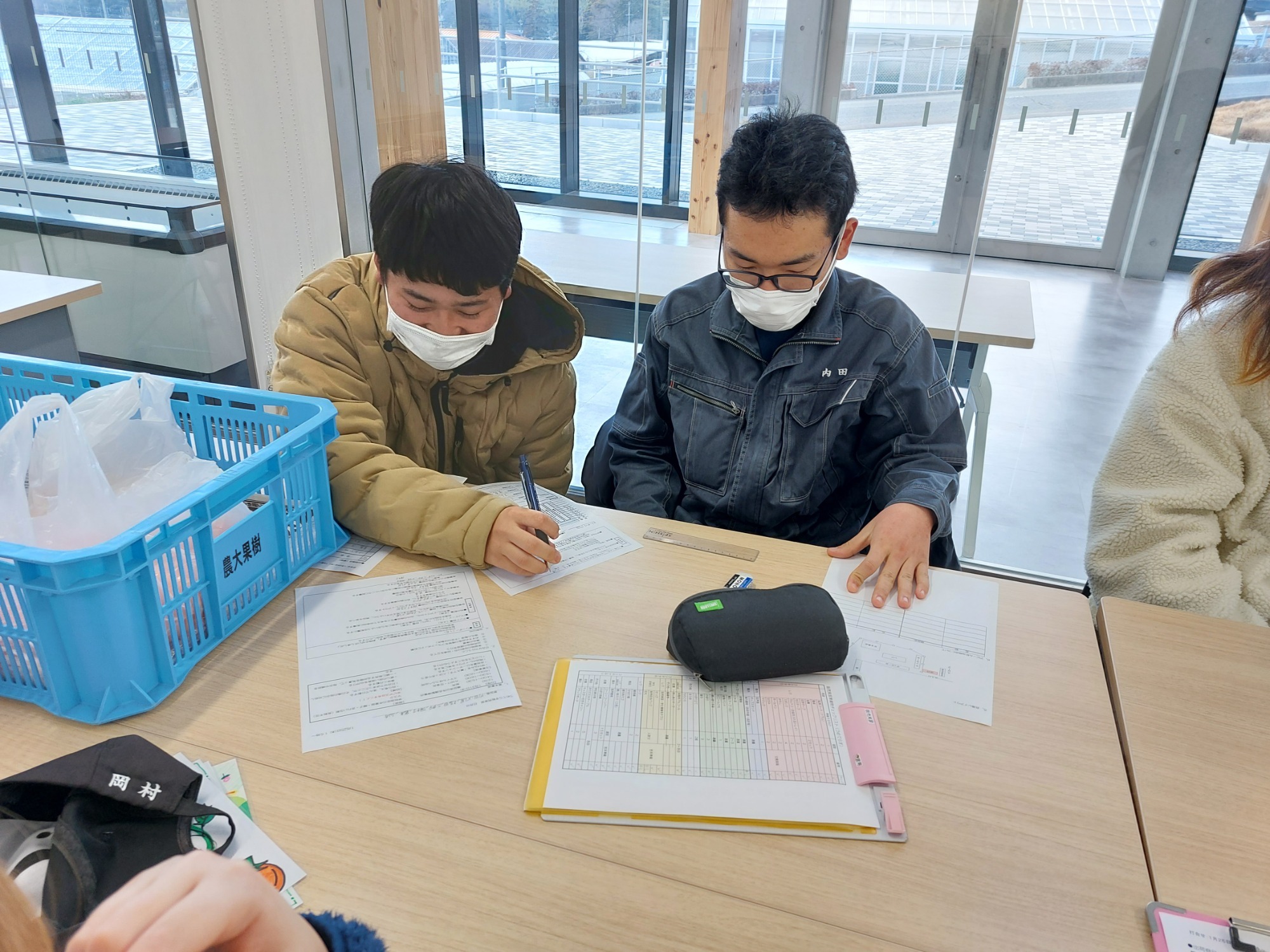

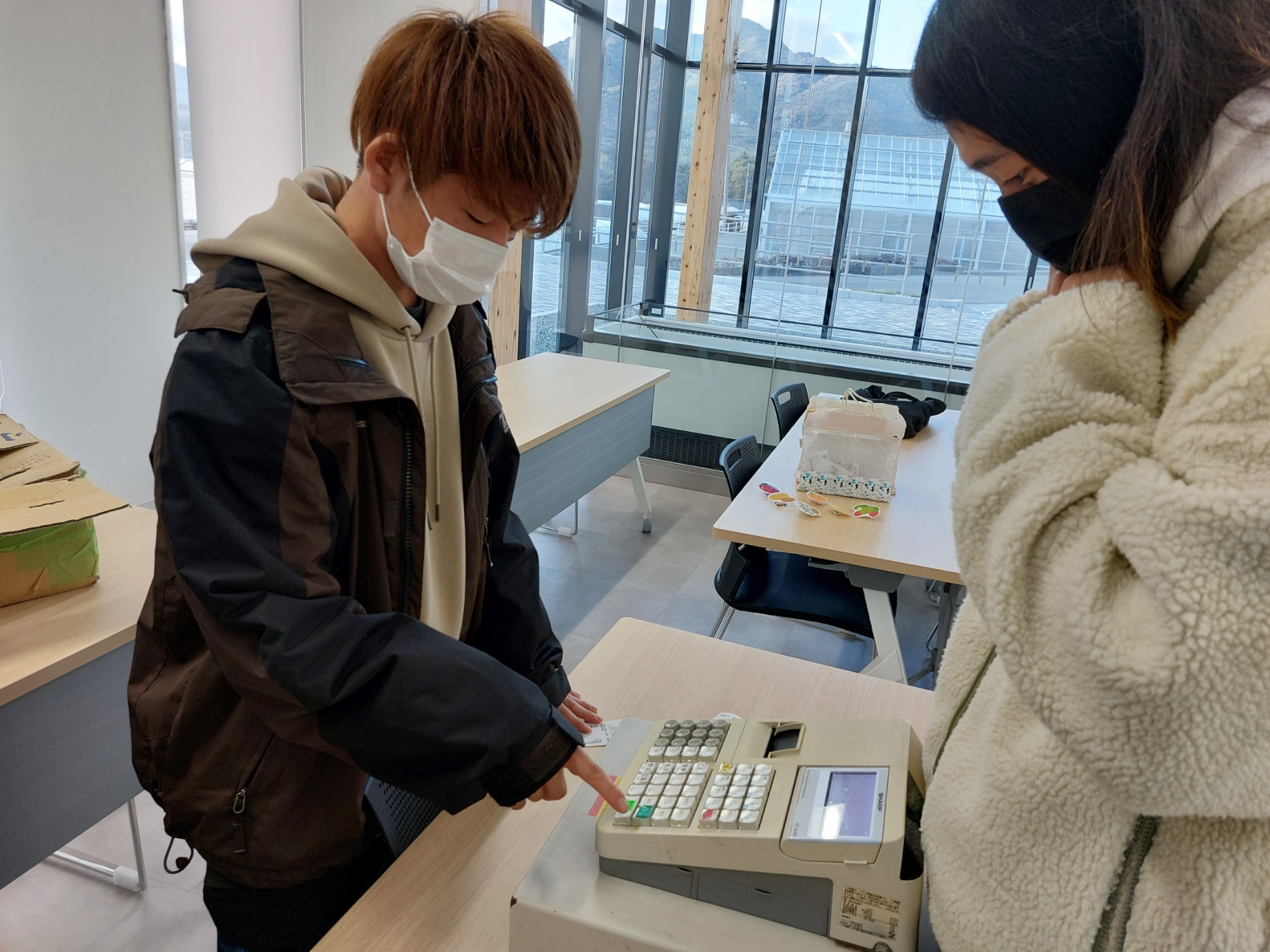

アスパラガスへの培土作業! R6.1.22
1月22日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、アスパラガスへの培土作業を行いました。
アスパラガスの品質が安定するためには、りん芽の深さが5~10cm程度必要です。
しかし、栽培ハウスでは、りん芽の位置が浅かったため、今回、培土を行いました。
担当の1年生や研修生は、溝上機を使用して畝上に土を盛り上げていきました。
培土作業後は、鍬や手を使って、畝の形を整えました。
今後は、潅水を十分行い、ハウスを閉め切って保温します。
2月下旬には春芽の収穫を開始する予定です。




牽引(けんいん)免許取得研修 R6.1.23
土地利用学科の学生は、将来コンバイン搬送用トレーラー等を運転することを想定し、牽引(けんいん)免許を取得することとしています。
1月22日(月)から、試験コースを使っての本格的な練習が始まりました。まずは方向転換(車庫入れ)とS字の練習です。方向転換は冬休みに自主練習を行っていたので、今日は全員合格です!・・・と思いきや、いざコース上での練習となると少し勝手が違ったのか、感覚を忘れてしまったのか、失敗する学生がちらほら。んー、試験は来週だけど大丈夫かなぁ? と少し心配になりましたが、最後には全員方向転換もできるようになり、なんとかコース走行の練習まで行うことができました。
試験日は、2月1日(木)です。万全の態勢で試験に臨めるよう、これから1週間、練習に励みましょう!




早生種の温州ミカンの間伐! R6.1.22
園芸学科果樹経営コースが管理する柑橘園の中で、早生種の温州ミカンが主体となっている園地では、植付けてから10年が経過したため、樹も大きく成長しました。
これにより、隣り合う樹同士が触れ合う状態となり、日当たりや作業性が悪化し、収量や果実品質に影響を及ぼす恐れが生じています。
そこで、現在、一列おきに樹を間伐する列状間伐を行っています。
1月22日(月)には、カンキツ班の学生たちが「興津早生」の間伐を行いました。
学生たちは、将来を見据えた作業の意義を理解して、黙々と作業に取り組んでいました。




温州ミカンの伐採! R6.1.22
1月22日(月)、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、「青島温州」という晩生種の温州ミカンの伐採を行いました。
本品種は、植付けてから25年以上経過していることに加え、昨夏の高温乾燥により樹体が衰弱し、収穫前に枯死した樹も数本見受けられました。
これを受けて、数年かけて園内の樹を伐採し、新たな苗木を植える計画が立てられています。
カンキツ班の学生は、チェーンソーを使って、大きな枝や幹を次々と切り、最終的には、1列に並んだ11本の樹を伐採しました。




いよいよ動画の作成開始です! R6.1.17
土地利用学科の動画制作は一通り講義が終わり、いよいよ動画作成の段階に移りました。今回は、2班に分かれて動画作成に取り組みます。テーマは「トラクタの始業点検と操作方法」、「トラクタの作業機の脱着」の2つ。
最初に各班で5W1H+T(時間)の目安を決めたら、次はロケーションハンティング(ロケハン)。対象となるトラクタを見ながら、動画の内容や画角を探っていきます。なんとなくイメージできたかな?
最後は、絵コンテの作成。これが最も重要な作業ですから、時間をかけて考えます。トラクタに関する知識もまだまだ不足していることもあって絵コンテは完成しませんでしたが、この動画作成の講義は、単に動画の作成方法を学ぶだけではなく、動画作成を通じてトラクタの取扱等を詳しく学ぶことが目的です。次回までにしっかりと調べて、絵コンテを準備しておきましょう。
さて、次回は撮影本番です。



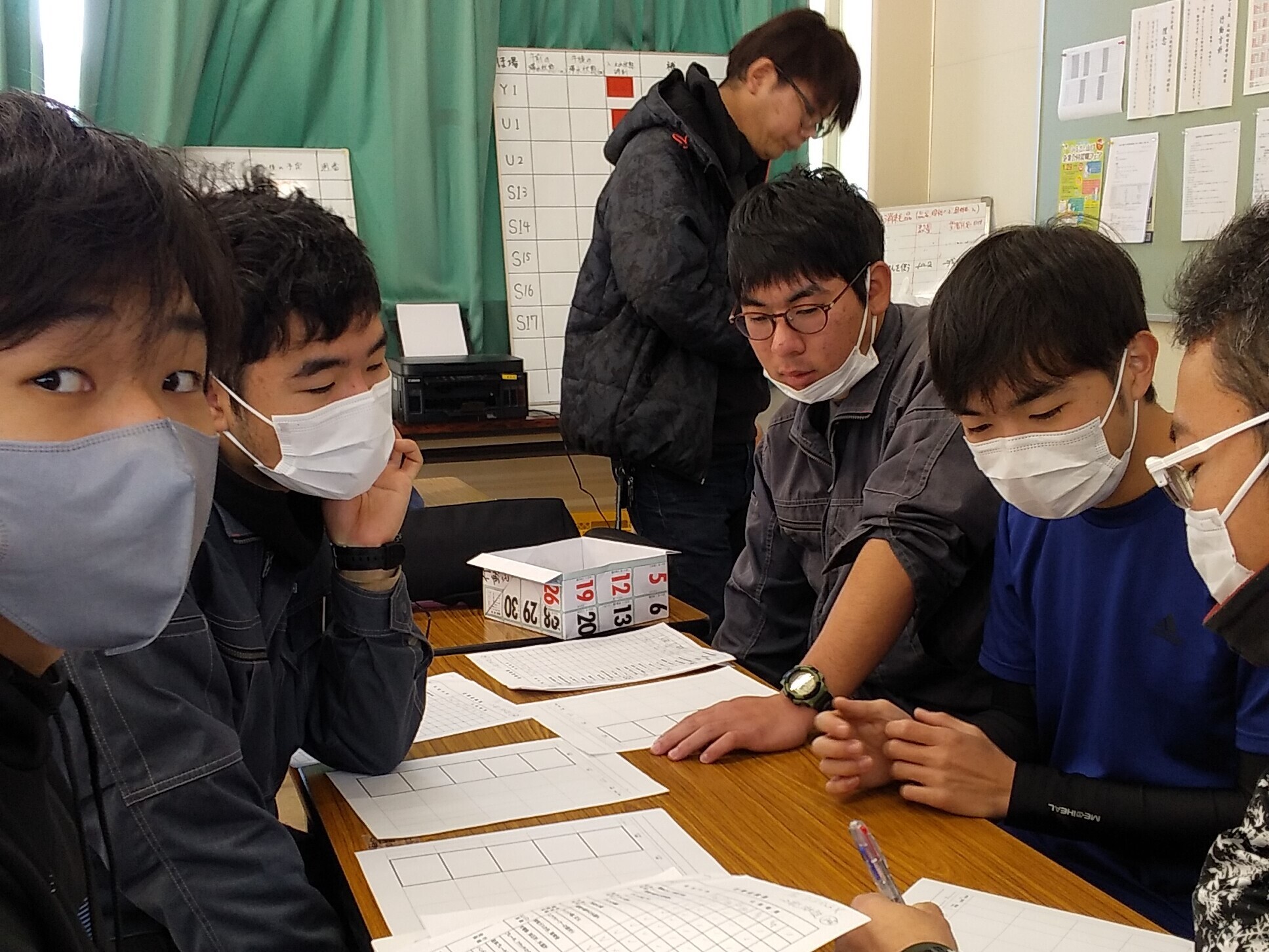
レモンの選果! R6.1.17
園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、1月16日(火)にガラス温室内で栽培しているレモンを全て収穫し、翌17日(水)から収穫したレモンの選果を始めました。
学生たちは、果実一つ一つを丁寧に拭き、電子天秤で重さを量り、重量や規格に基づいてに選別していきました。
本年度の作柄は、昨年度に比べて量は少ないものの、選果完了までには2日程度かかる見込みです。
選果されたレモンは、果実の腐敗や果肉内の水分消耗を防ぎ、長期の貯蔵にも耐えられるよう、果皮を軽く乾燥させた後、貯蔵庫に保管される予定です。
1月下旬からは、直売所などへ計画的に出荷を行いますので、ぜひ、お買い求めください。




白ネギを収穫しました! R6.1.17
1月17日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、白ネギを収穫しました。
品種は「夏扇4号」で、昨年の4月に播種したものです。
生育期間中に5回の土寄せを行ったので、ネギの白い部分は十分な長さが確保できました。
昨年夏の暑さ等により欠株が発生したため、目標とした収量は確保できませんでしたが、今回収穫したネギは、寒さに遭って、甘みが増していますので、今の時期、鍋にぴったりです。
防府市内の直売所などに出荷しますので、ぜひお買い求めください。




「道の駅 ソレーネ周南」で8名の学生が販売実習を実施! R6.1.17
1月17日(水)、「道の駅 ソレーネ周南」で、土地利用学科の一年生2名、園芸学科の二年生1名と一年生3名、畜産学科の一年生2名の計8名の学生が、販売実習に臨みました。
当日は、天候に恵まれたおかげで人の流れがよく、お客様と会話する機会がたくさんありました。
購入していただけたことはもちろん達成感につながりますし、そうでなくてもアピールのチャンスがあることはありがたく、学生たちは生き生きとしていました。
商品の動きもあるため、商品補充やレイアウトの変更等考えることが多く、充実した実習となりました。
次回の販売実習は、1月31日(水)に、まちの駅「うめてらす」で行う予定です。




中国四国ブロック経営プロジェクト発表会の練習! R6.1.17
1月5日に行われた当校の経営プロジェクト発表会の結果、園芸学科野菜経営コースの二年生2名が優れた成績を収め、1月18日に開催される中国四国ブロック農業大学校等経営プロジェクト発表会の参加者に選ばれました。
その準備の一環として、1月17日(水)には、この2名の学生が、最後の発表練習を行いました。
学生たちは、原稿やスライドを確認しながら、ゆっくり大きな声で発表しました。
発表後は、指導教官から原稿やスライドに関するアドバイスを受け、最後の修正に取りかかっていました。
翌18日の発表会では、練習の成果を発揮できることを期待しています。頑張ってください。

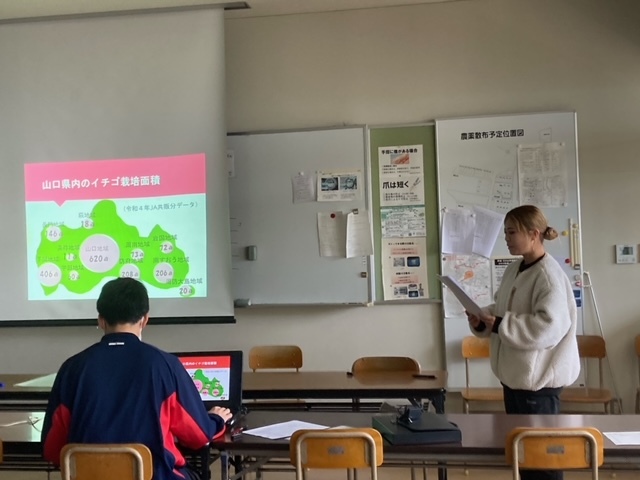
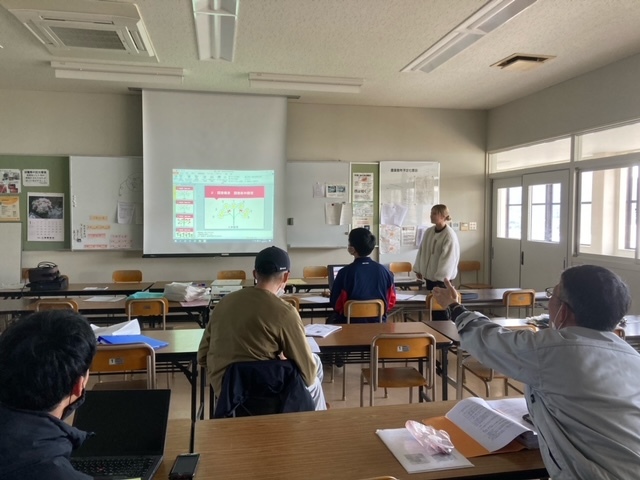
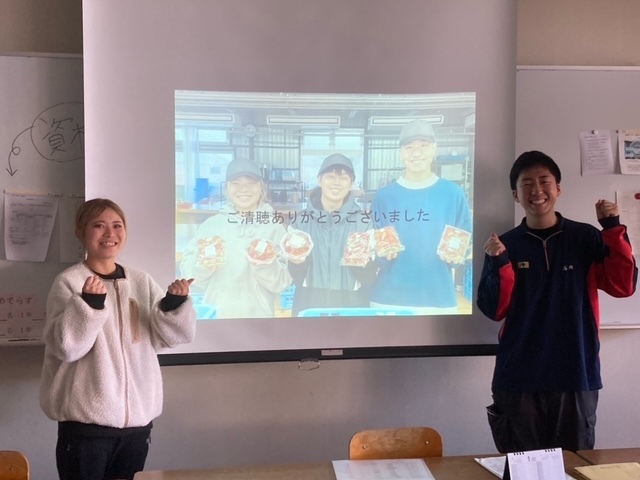
ヒヤリハット報告の表彰を行いました! R6.1.17
園芸学科では、日々の実習で起きたヒヤリとした瞬間やハッとした気づきを共有することを通じて、学生や研修生、職員が事故を未然に防げるよう、こうした「ヒヤリハット」事例を積極的に報告するよう働きかけています。
令和5年4月1日から同年12月31日までのヒヤリハットの報告数は46本で、このうち、花き経営コースの学生や職員からの報告が約7割を占め、同コースの二年生から最多となる11本の報告がありました。
そこで、令和6年1月17日(水)、専攻と個人に対して表彰や商品の授与を行いました。
これからも、より多くのヒヤリハット報告が行われるよう、表彰を継続していくこととしています。


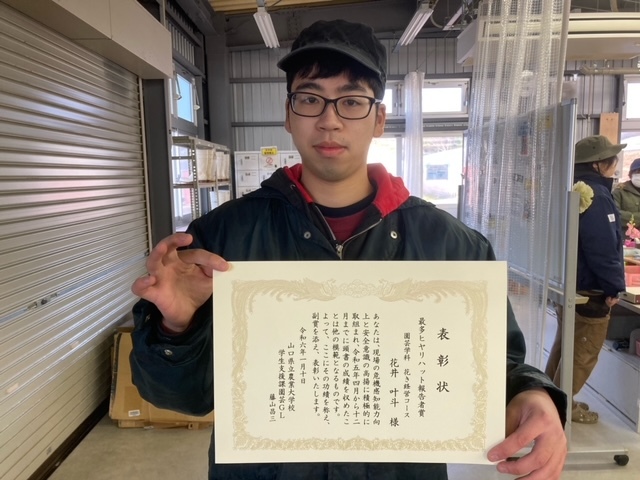

レタスの定植を行いました! R6.1.15
園芸学科の野菜経営コースでは、1月15日(月)、ガラス温室内の隔離ベンチに、結球レタスの「ビックガイ」を定植しました。
冬季のレタス栽培では、低温によって生育が抑制されて小玉になったり、不結球となることがありますが、当品種は、低温結球性に優れ、玉肥大がよいのが特徴で、生産の安定や収量向上が期待されます。
生育が順調に進めば、2月下旬頃に収穫を開始する予定です。




レタスの定植準備! R6.1.11
園芸学科の野菜経営コースでは、ガラス温室を使用して「ビックガイ」という低温結球性に優れ、玉肥大のよい品種のレタス栽培に取り組みます。
12月7日に播種した苗も、順調に成長してきたため、1月11日(木)の午前中には、担当の学生が、定植準備として、ベンチ内の培土に肥料を施し、ベンチ耕うん機を使用して耕うんを行いました。
午後からは、潅水チューブを設置し、その上を黒マルチで覆いました。
翌週には、定植を予定しています。




「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備! R6.1.14
1月17日(水)の午後2時より「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習を行います。
当日のスムーズな運営を確保するため、1月12日(金)に、対応する学生たちが打合せを行いました。
大半が1年生の中、2年生に確認をとりながら役割分担をしていました。
先輩の指示で動くのとは違い、責任をもって話し合いや備品の準備を行うことで積極性が出てきたようです。
当日も自らお客さんとどう関わってくのか楽しみです。
当日は新鮮な商品と学生の笑顔で素晴らしいおもてなしを提供できることと思いますので、ぜひ、1月17日に「道の駅ソレーネ周南」へ足をお運びください。

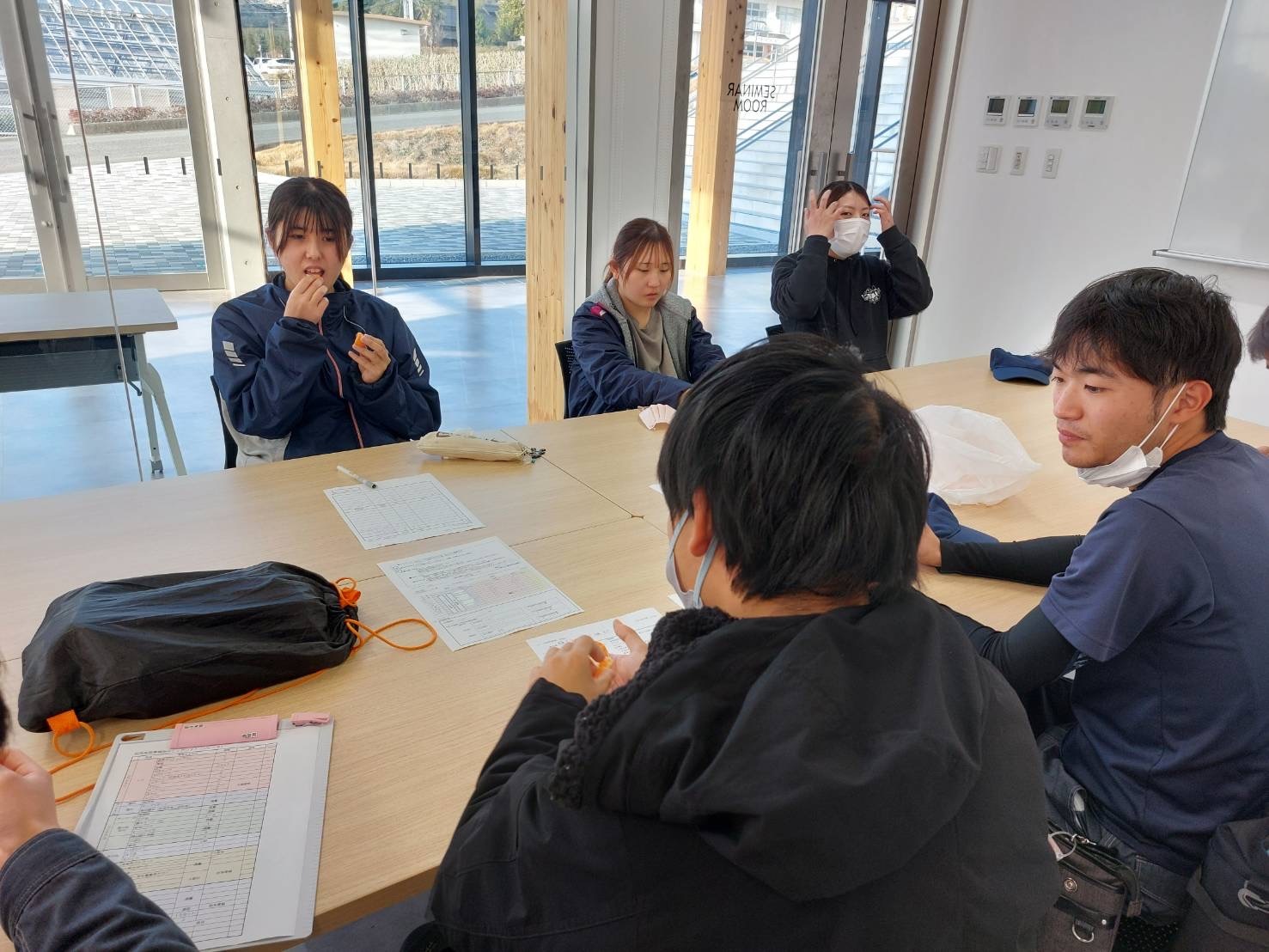
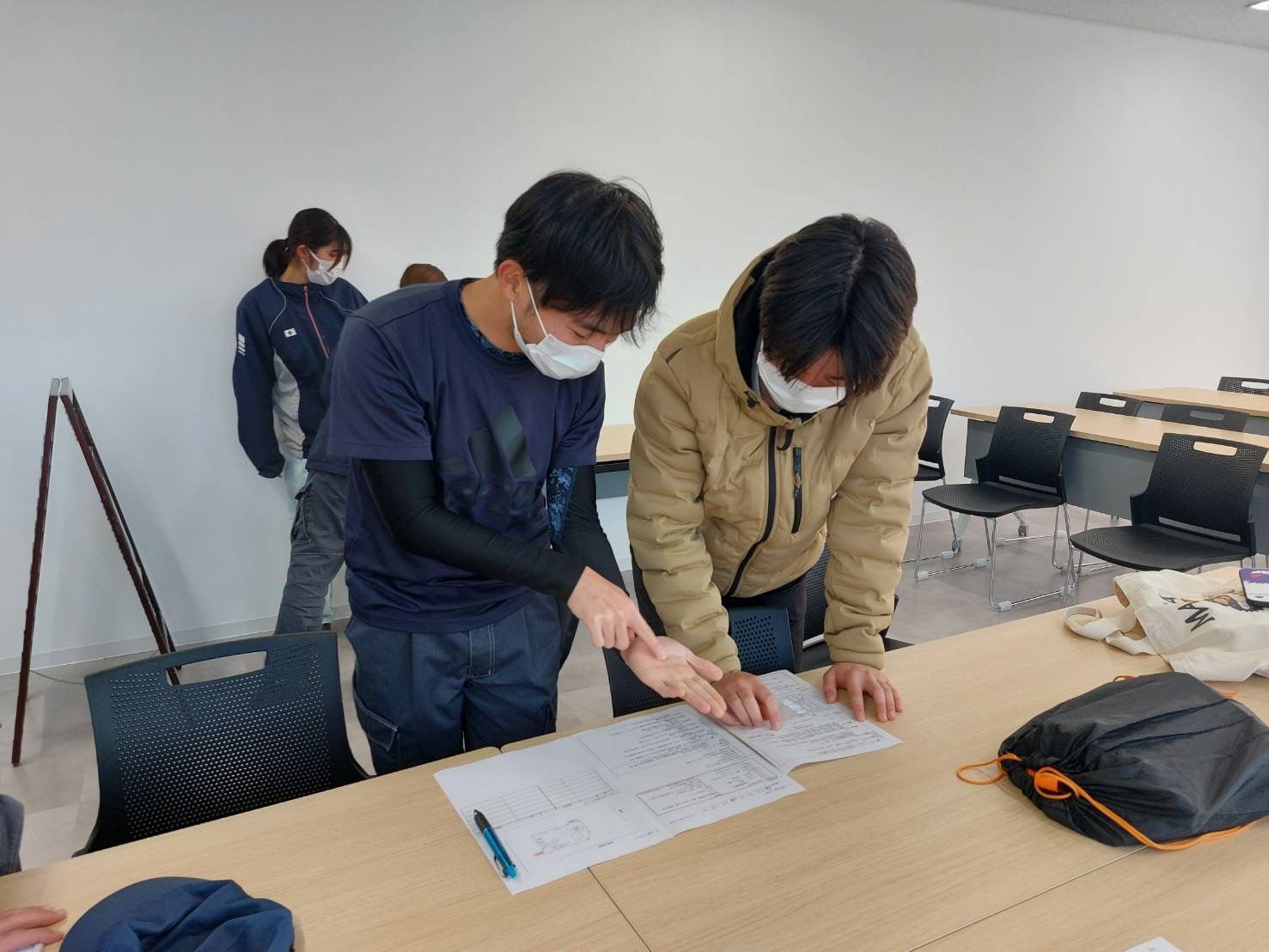

はれひめの収穫を行いました! R6.1.15
園芸学科の果樹経営コースのカンキツ班では、1月15日(月)、中晩柑の「はれひめ」を収穫しました。
「はれひめ」は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が育成した品種で、果皮は手で簡単に向け、じょうのう(果肉を包んでいる薄皮)は薄く、果肉はオレンジ系の爽やかな香りと食べやすさが特徴です。
当校での栽培本数はわずか14本ですが、学生らは丁寧に収穫し、その後選果と規格別の保管を行いました。
この「はれひめ」は、2月中旬より防府市や周南市の直売所に出荷する予定です。
今作は、夏以降の降水不足が果実に良い影響を与え、品質は上々ですので、ぜひお買い求めください。




凍結防止対策の実施【野菜専攻】! R5.12.19
12月に入って暖かい日が続いていましたが、週末にかけて強い寒気が流れ込み、気温が氷点下を下回るとの天気予報を受けて、12月19日(火)、園芸学科の野菜経営コースでは、栽培施設に関係する水道設備の凍結防止対策を行いました。
初めに、二年生が一年生や研修生に対して、凍結防止対策の方法を指導しました。
その後、学生や研修生たちは、担当する施設に係る水道の立ち上げ部分や配管部分に、不織布や肥料袋を巻き付け、テープで固定していきました。
皆が手際よく作業した結果、当日中に凍結防止対策を完了することができました。




令和5年度秋季山口県花き展示品評会の表彰! R5.12.27
山口県花卉園芸組合連合会が主催する秋季山口県花き展示品評会が、11月17日から19日にかけて、下関市の「シーモール下関」で開催され、県内の生産者が出品した切り花や鉢物などが審査や展示されました。
当校の園芸学科花き経営コースでも、本展示品評会にダリア「NAMAHAGEノアール」を出品し、優良賞を受賞しました。
その後、本賞に係る景品が届いたので、12月27日(水)、花き経営コース内で授与式が行われました。
指導教官から、ダリアを担当した二年生に景品が渡されました。
花き経営コースの学生と職員たちは、今後も本展示品評会で高い評価を得るため、品質の高い花の生産に取り組んでいく意気込みを示していました。
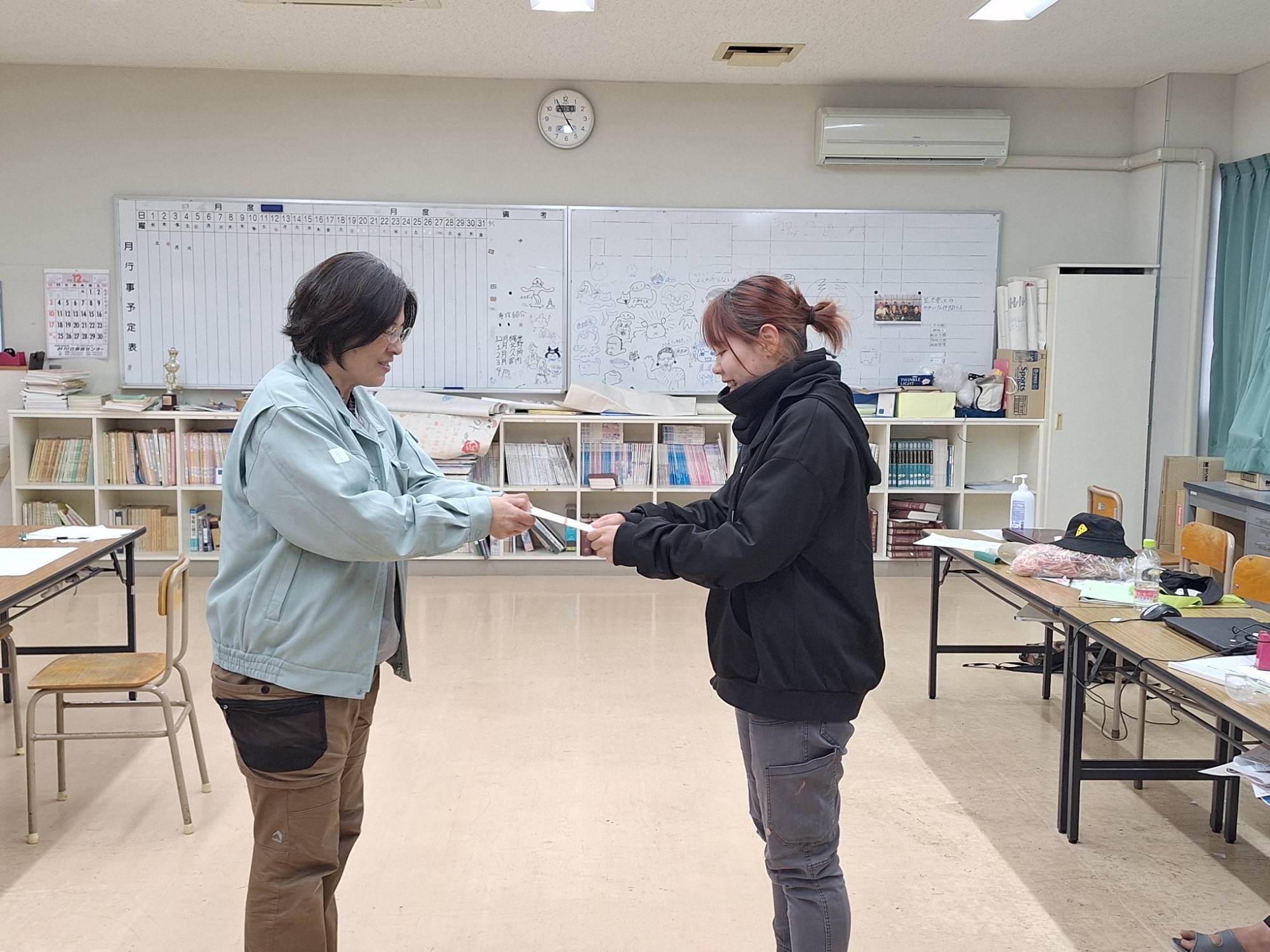

アスパラガスの残茎等の焼却! R6.1.10
園芸学科の野菜経営コースでは、ハウスでアスパラガス栽培に取り組んでいます。
アスパラガスが休眠期に入った昨年末には、病害の発生を抑制するため、伝染源となり得る茎葉の刈取りとハウス外への持出しを行いました。
1月10日(水)には、地表面に残った茎や畝表面に落ちた残さを残茎の焼却を行いました。
焼却は、職員と学生が肩掛け式の火炎バーナーを使用しました。
はじめは、火炎バーナーの取り扱いに苦労しましたが、時間が経つにつれ要領を得て、安定した火炎で焼却作業を行うことができました。
今後は、薬剤を土壌に潅注する予定です。




シクラメンの播種! R5.12.27
園芸学科花き経営コースでは、12月27日(水)、シクラメンの播種を行いました。
シクラメンは、当コースの主力品目で、今年は2,000粒播種する予定で、今回は、種400粒を200穴のセルトレイ2枚にまきました。
担当の学生たちは、種を一粒ずつピンセットで挟んでは、セルトレイに充填した培土に慎重に播種していました。
今回播種した品種は、鮮やかな花色と花弁のフリンジが特徴の「ハリオス カーリー フレームミックス」など2品種です。
播種したセルトレイは、約3カ月育苗ハウスで育苗した後、鉢上げを行う予定です。
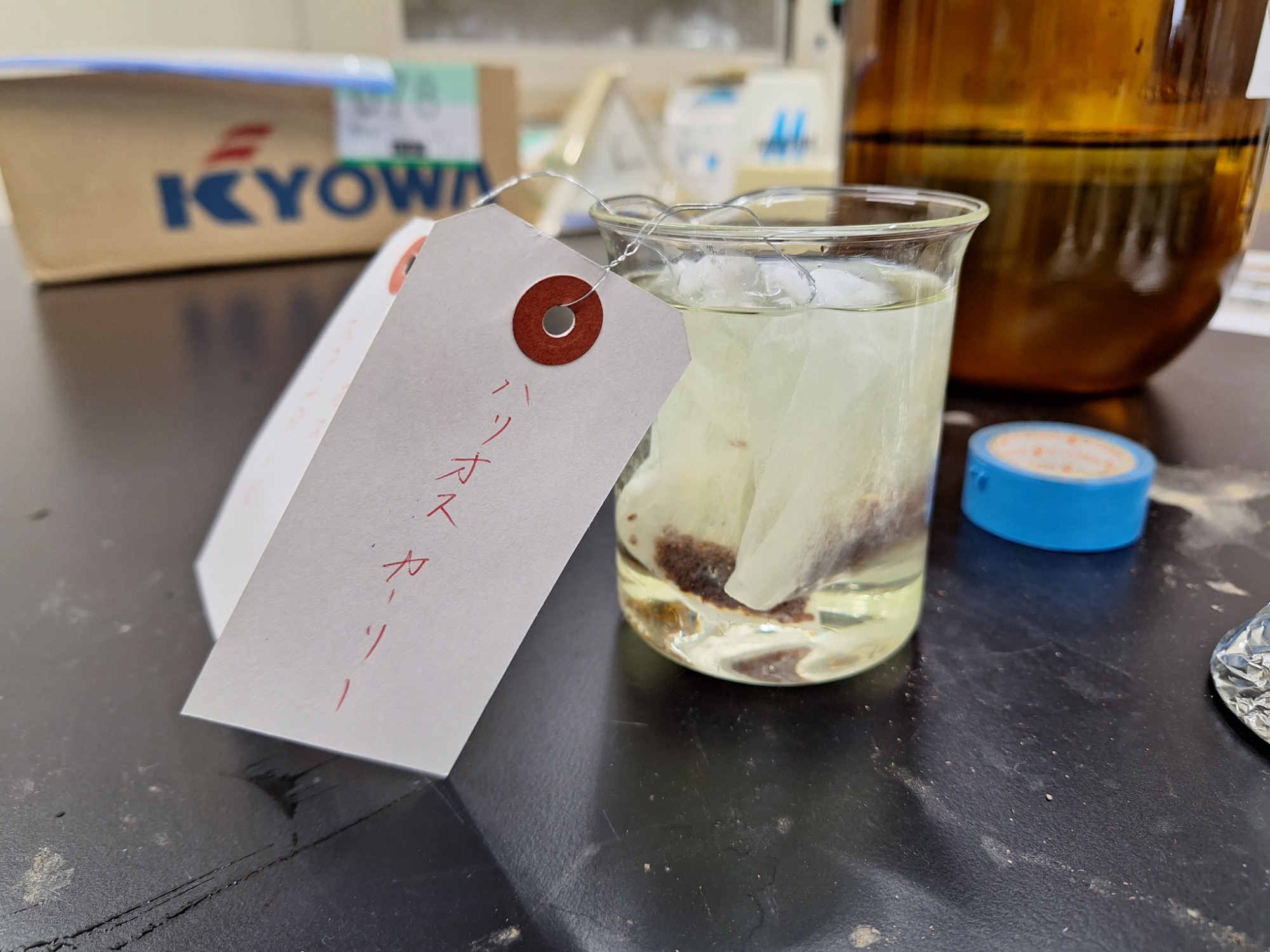
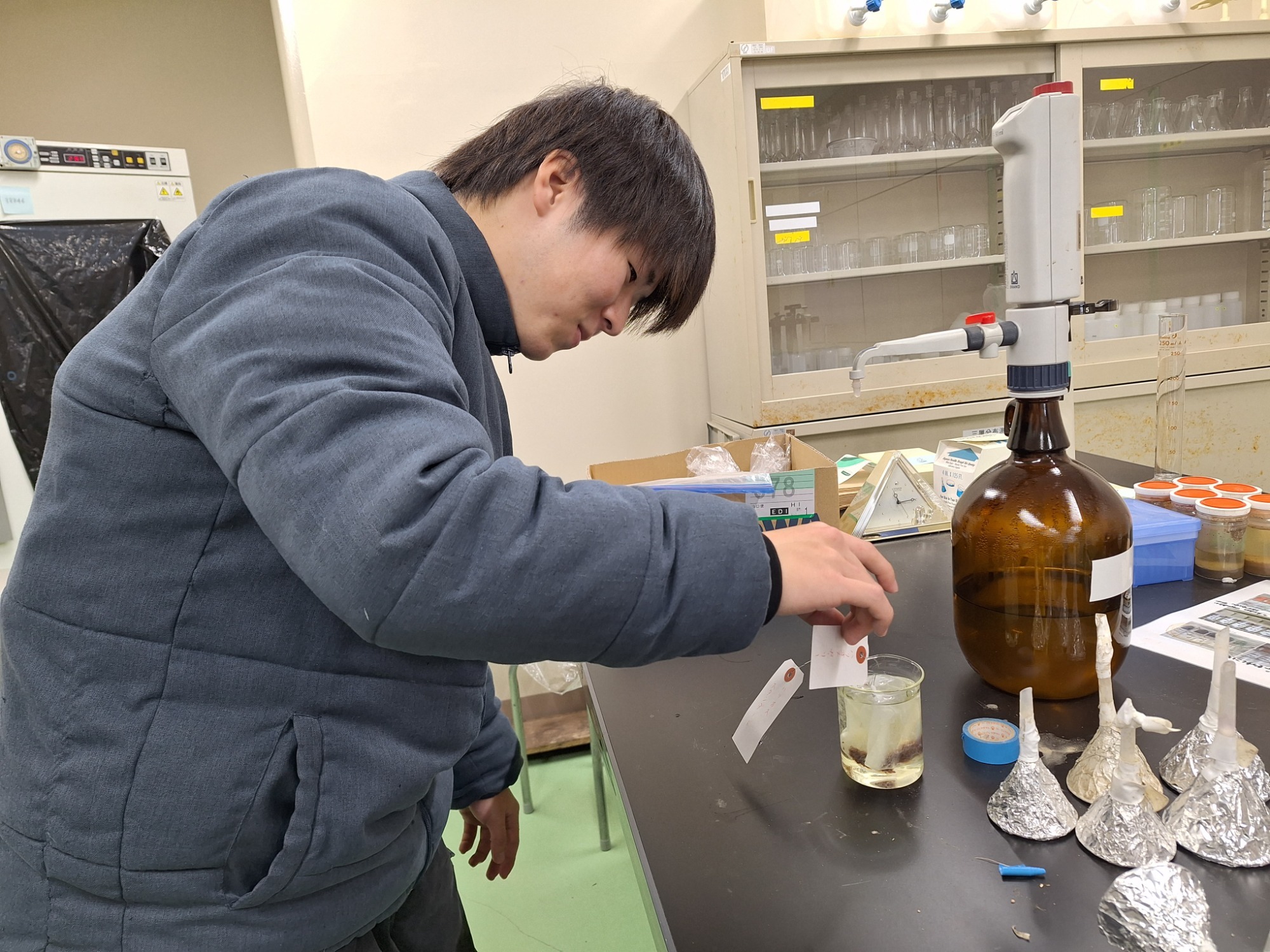


防府市まちの駅「うめてらす」で10名の学生が販売実習を実施! R5.12.25
12月25日(月)、防府市まちの駅「うめてらす」で、土地利用学科の一年生3名、園芸学科の一年生5名、畜産学科の一年生2名の計10名の学生が、販売実習に臨みました。
当日は、やや風が強かったものの穏やかな天候に恵まれ、多くのお客様に来場いただきました。
今年は秋冬の気温が高かった影響か、年末の野菜が少なくて残念な面もありましたが、ミカンやシクラメンなど季節ものに人気が集まり、学生たちも精一杯のアピールをしていました。
また、恒例となった抽選会ではさまざまな農産物が当たって盛り上がりました。
これを機に、日頃の直売所での売り上げにもつながってほしいと思います。
次回の販売実習は、令和6年1月17日(水)に「道の駅ソレーネ周南」で行う予定です。




キュウリの植付けを行いました! R5.12.21
園芸学科の野菜経営コースでは、ガラス温室でキュウリの促成栽培に取り組みます。
12月22日(金)には、担当の二年生と研修生が、「ニーナZ」という品種の苗を植付けました。
この品種は、生育初期から各節に連続して雌花が咲く「節成り」タイプの品種で、分岐性もよいことから、高収量が期待されます。
今回、厳寒期寡日照の条件下で栽培を開始することから、暖房温度を通常より1、2度高めにしたり、ぬるま湯で株元潅水したり、透明マルチで地温を上げる工夫を行い、初期生育の確保に努めています。
生育が順調であれば、1月下旬頃から収穫を開始する予定です。




冬キャベツの収穫終盤! R5.12.21
園芸学科の野菜経営コースでは、8月下旬に定植したキャベツが収穫の終盤を迎えています。
12月21日(木)には、圃場内では9割近くが収穫され、現在は小玉のキャベツを中心に収穫しています。
今年はヨトウムシ等の発生が多く、降雨も少ない厳しい条件でしたが、担当の1年生が適期の防除や畝間潅水、追肥などを実施し、細やかな管理のおかげで、終盤においても良質なキャベツが収穫できています。
収穫量は、目標の5t/10aに到達し、売上も好調です。
担当の1年生は、この結果に手応えを感じているようです。




青島温州の収穫開始! R5.12.20
園芸学科の果樹経営コースでは、12月20日(水)から、温州ミカンの晩生品種である「青島温州」の収穫を開始しました。
「青島温州」の果実は、普通の温州みかんより一回り大きく、扁平で、味が濃く、甘味が強いのが特徴です。
週末にかけて強い寒気が流れ込むことが予報されたことから、「青島温州」の一斉収穫を行うこととなりました。
この収穫作業には、カンキツ班だけでなく、ナシ班やブドウ班の学生たちも総動員し、協力して作業を進めました。
この収穫作業は、12月22日に完了する予定です。




メロンの定植を行いました! R5.12.21
園芸学科の野菜経営コースでは、この冬、パイプハウスでメロン栽培に挑戦します。
12月21日(木)には、担当の二年生が、同級生や一年生の補助を得ながら、メロンの苗150本を定植しました。
二年生は、これまで当校で4作のメロン栽培に携わってきましたが、今回が最後の栽培となります。
厳しい条件下での栽培に加え、経営プロジェクトの発表会や卒業論文の作成といった忙しいスケジュールの中で栽培管理を行いますが、二年生は有終の美を追求しています。これまで行ってきたベンチ栽培ではなく、土耕栽培に初挑戦ということもあり、ドキドキです。
生育が順調であれば、1月下旬に、人工授粉を予定しています。




ダンパーの乗車試験を行いました【花き経営コース】! R5.12.19
園芸学科の花き経営コースでは、12月19日(火)、ダンパー(ダンプ式運搬車)の乗車試験が行われました。
ダンパーは、学生たちが最も頻繁に利用する機械であり、当経営コースでは、安全を期すため、普通免許や大型特殊免許(農耕車に限る)を取得した後、教官が見極めを経て、初めて運転が許可されます。
一名の一年生が試験に挑戦し、慎重な運転と確実な安全確認を行った結果、見事合格しました。
合格した一年生は、引き続き安全運転を実施していくことを誓っていました。




防府市まちの駅「うめてらす」での販売実習に向けた準備! R5.12.19
12月25日(月)の午後2時から、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行います。
このため、12月19日(火)に、当日参加する学生たちが打合せを行いました。
参加者は、土地利用学科の一年生3名、園芸学科の一年生5名、畜産学科の一年生2名の計10名で、皆が協力して打合せを進めました。
今回は一年生のみの参加ですが、これまでの経験と反省をお互い話し合いながら役割分担ができました。
過去に大きな売り上げを上げた経験をした学生は、今回もたくさん売ろうと気合が入っていました。
今回の目玉商品である柑橘「みはや」の試食も行い、お客様へは自信をもってお勧めできそうです。
当日は新鮮な商品と学生の笑顔でおもてなしをさせていただくとともに、毎年恒例の大抽選会を行いますので、ぜひ、12月25日に防府市まちの駅「うめてらす」へ足をお運びください。




凍結防止対策の実施【花き専攻】! R5.12.19
12月に入って暖かい日が続いていましたが、週末にかけて強い寒気が流れ込み、気温が氷点下を下回るとの天気予報を受けて、園芸学科の花き経営コースでは、12月18日より、栽培施設に関係する水道設備の凍結防止対策を行いました。
12月19日(火)には、パイプハウス周辺の水道の立ち上げ部分に、保温を目的とした気泡緩衝材を巻き付け、テープで固定していきました。
一年生は、初めて行う作業でしたが、手際よく行っていました。




年末出荷に向けたキクの収穫最盛期! R5.12.18
園芸学科の花き経営コースでは、ガラス温室において年末出荷用のキクの栽培に取り組んでいます。
需要が多くなる年末に向けて、電照によって開花時期を調節してきましたが、本年は予定通りの時期に咲かせることができました。
このため、12月18日(月)には、採花基準に達したキクが多く、担当の一年生は、収穫と出荷調製に追われていました。
本作では、近隣の直売所を主体に出荷していますので、ぜひお買い求めください。




トヨタ式カイゼンの実践! R5.12.19
土地利用学科では、トヨタ自動車株式会社から講師を招いてトヨタ式カイゼンについて学んでいます。11月10日の講義では、現場の問題解決の8ステップを学びました。そして、「次回(1月10日)までに、この手法を使って学科の問題解決に取り組む」という宿題が出されたわけですが、12月以降、学生達はこの宿題に取り組んできました。
取り上げた課題は、2つ。①準備時間の短縮(今は作業の準備に時間が掛かり過ぎ!)、②安全な実習の実施(ヒヤリハット:重大な事故に直結する一歩手前の出来事 が多い!)です。どちらも土地利用学科にとっては重要な課題。トヨタ式カイゼンの5W1H(「なぜ」を5回繰り返して真因を特定し、確かな解決策を打つ)を念頭に、全員で意見を出し合いながら、ひたすらグループワークです。
初めての取組で苦労したようですが、なんとか12月15日(金)に暫定版が完成しました。よく頑張りました! 次回、講師からの評価やコメントが楽しみです。

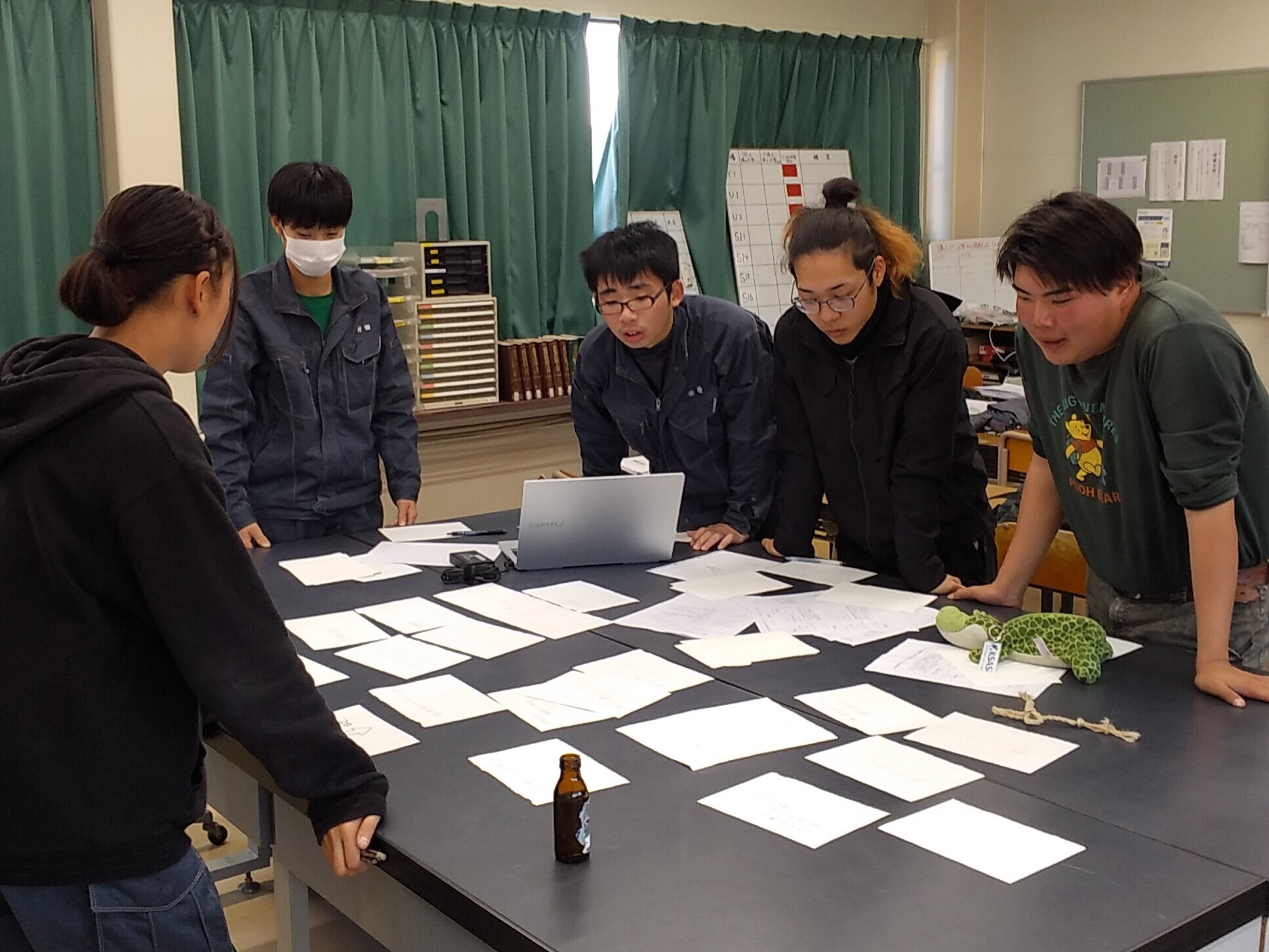
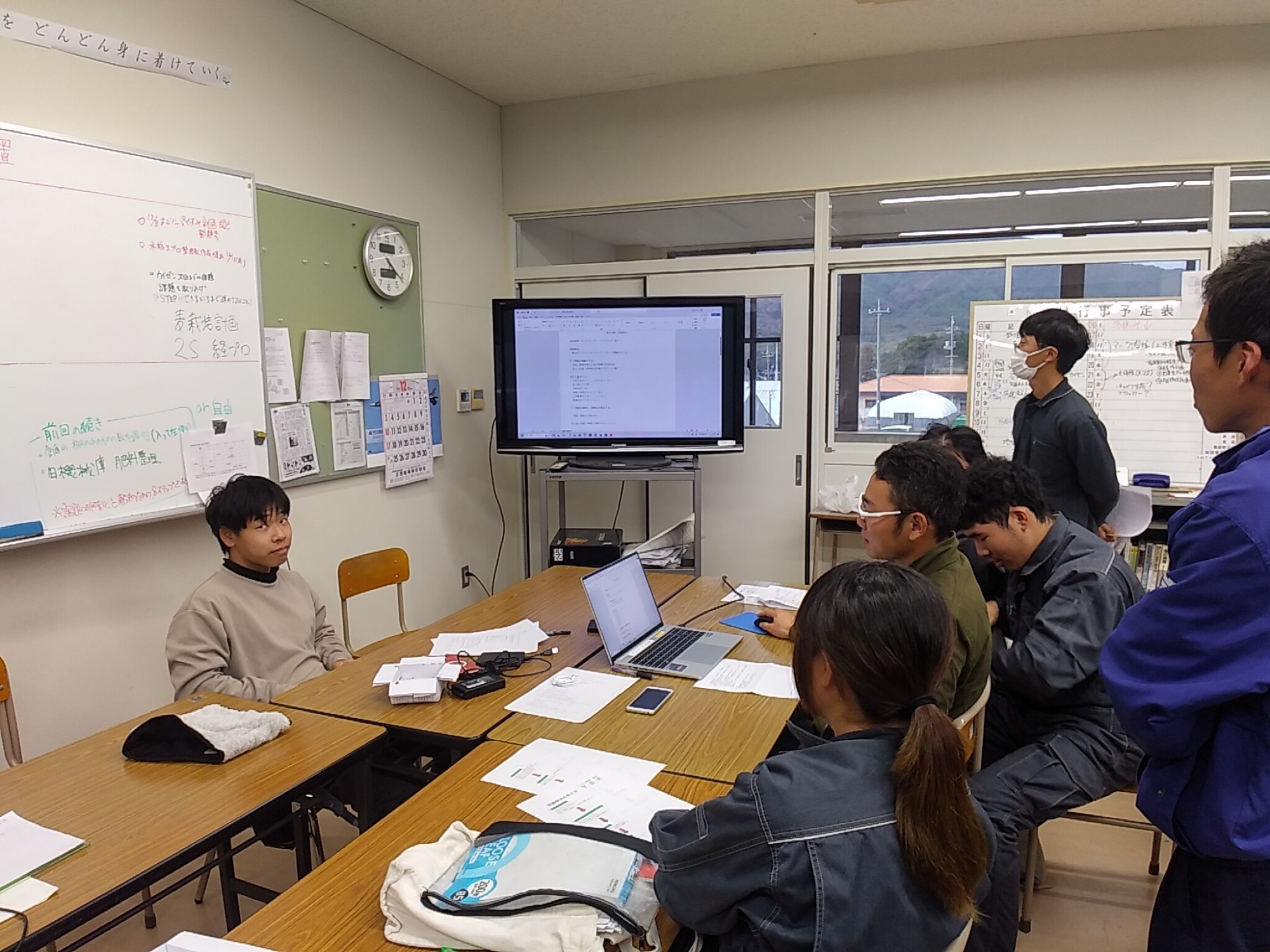
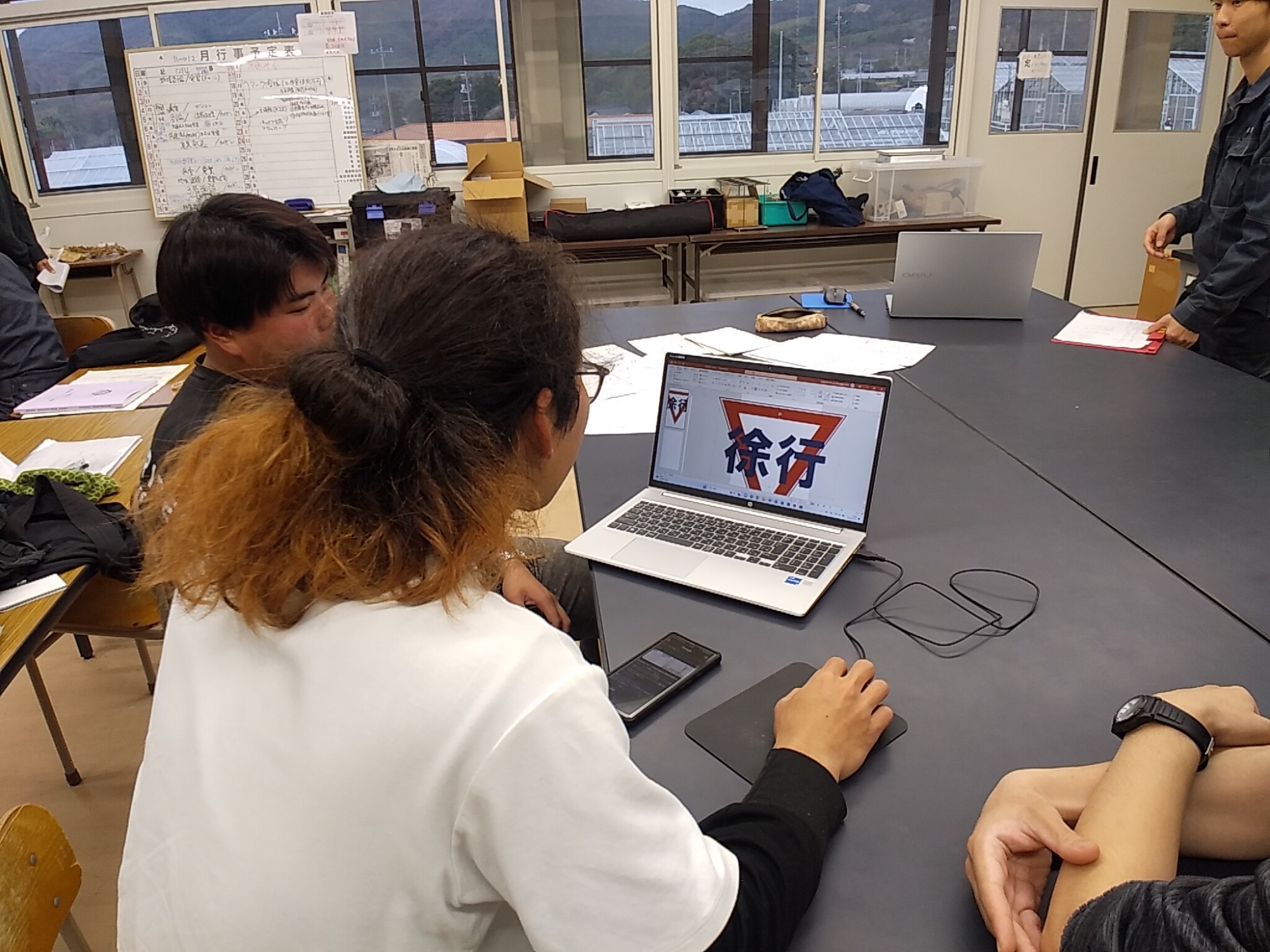
イチジクのせん定を行いました! R5.12.18
当校では、パイプハウス内でイチジクを栽培しており、「蓬莱柿(ほうらいし)」、「桝井ドーフィン」、「ゼブラスイート」の3品種43本を植裁しています。
イチジクが落葉を終え、休眠期にはいったことから、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班が、12月18日(月)、イチジクのせん定を行いました。
当校では、イチジクを「株仕立」で栽培しているので、せん定は、今年伸びた枝の基部から数えた2芽の直上で、枝をせん除します。
同時に、込み合った部分やカミキリムシの被害にあった部分などもせん除し、樹の健全化も図ります。
今後、せん除部分には、ゆ合剤を塗布する予定です。




トマトの生育調査を行いました! R5.12.18
園芸学科の野菜経営コースでは、高糖度トマト生産を目指し、塩分ストレス栽培に関する経営プロジェクトを進めています。
この取り組みの一環として、担当の1年生が、12月18日(月)に、トマトの生育調査を行いました。
今回の調査では、約2週間前に定植した苗の茎径の測定や開花の有無を確認するとともに、伸長量の測定に向けた茎への目印付けなど次回調査に向けた準備を行いました。
これらのデータは、トマトの株の生育推移を把握するために収集し、今後も毎週の生育調査が計画されています。




クボタのKSASキャラバンで事例発表! R5.12.15
土地利用学科では、日々の実習の状況を、クボタのKSAS(ケーサス:インターネットクラウドを利用した営農支援システム)に入力し、データの一元管理を行っています。それを聞きつけた中四国クボタから、KSASキャラバン(KSASの使い方や活用方法の共有、意見交換や個別相談等を行うイベント)への参加を打診され、12月14日(木)のキャラバンに土地利用学科の学生3名が参加してきました。一般参加ではなく、実践事例発表者としての参加です!
事例発表では、学生3名が交代しながら、日々のデータ入力の状況や活用方法、KSASを使うメリット、KSASに追加してほしい機能などを話しました。もちろん緊張したでしょうが、3名とも自分たちの取組事例を交えて具体的に、かつ使用者としての率直な感想を述べており、聴講者には参考になったと思います。しかも最後は「KSASはオススメですよ!」という営業トークで締め括るそつのなさ。出来過ぎです・・・
キャラバンでは、クボタのKSAS開発担当者とも意見交換ができました。果たして学生達の意見が反映されるのか? 楽しみに待ちましょう。
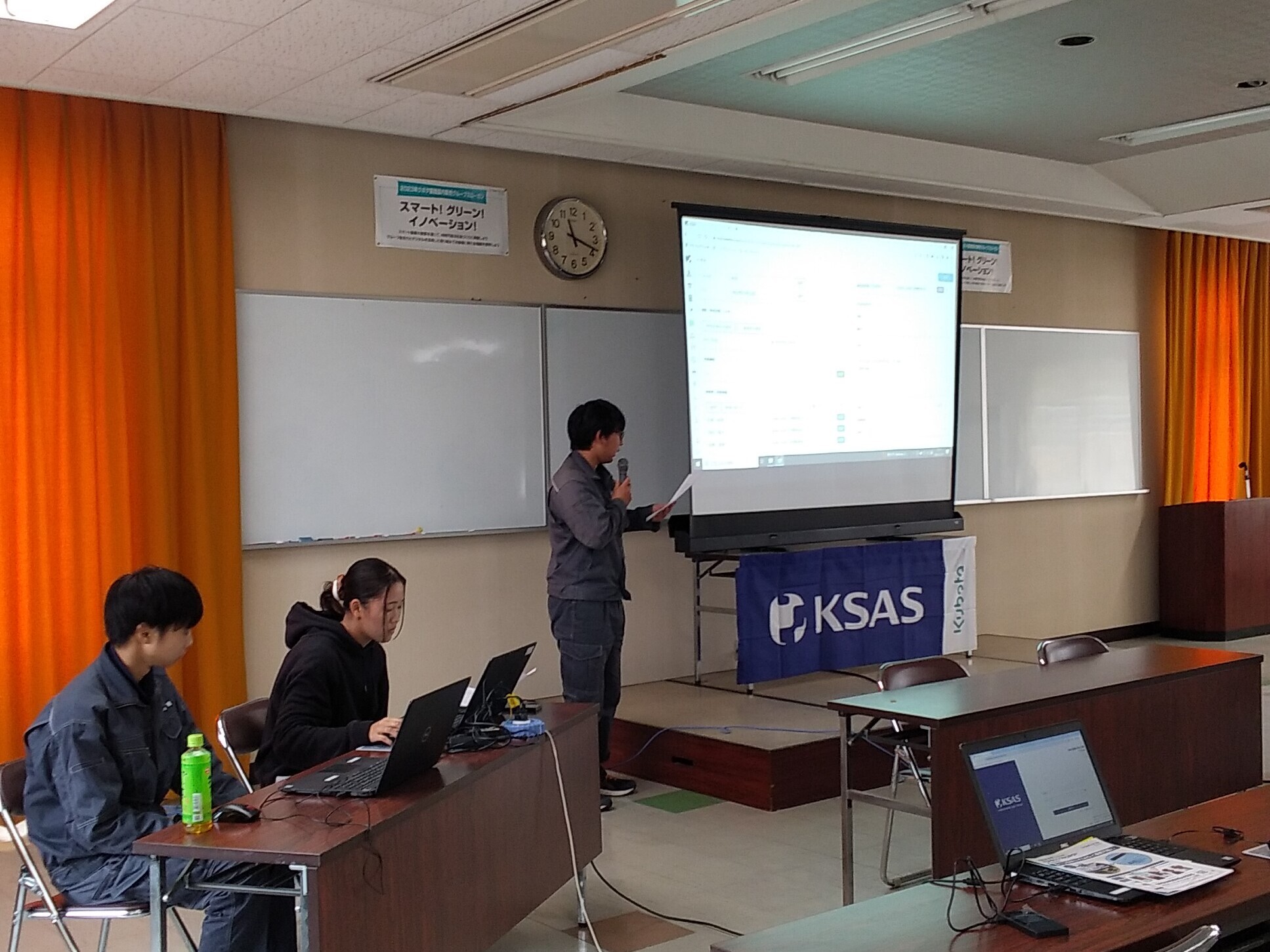

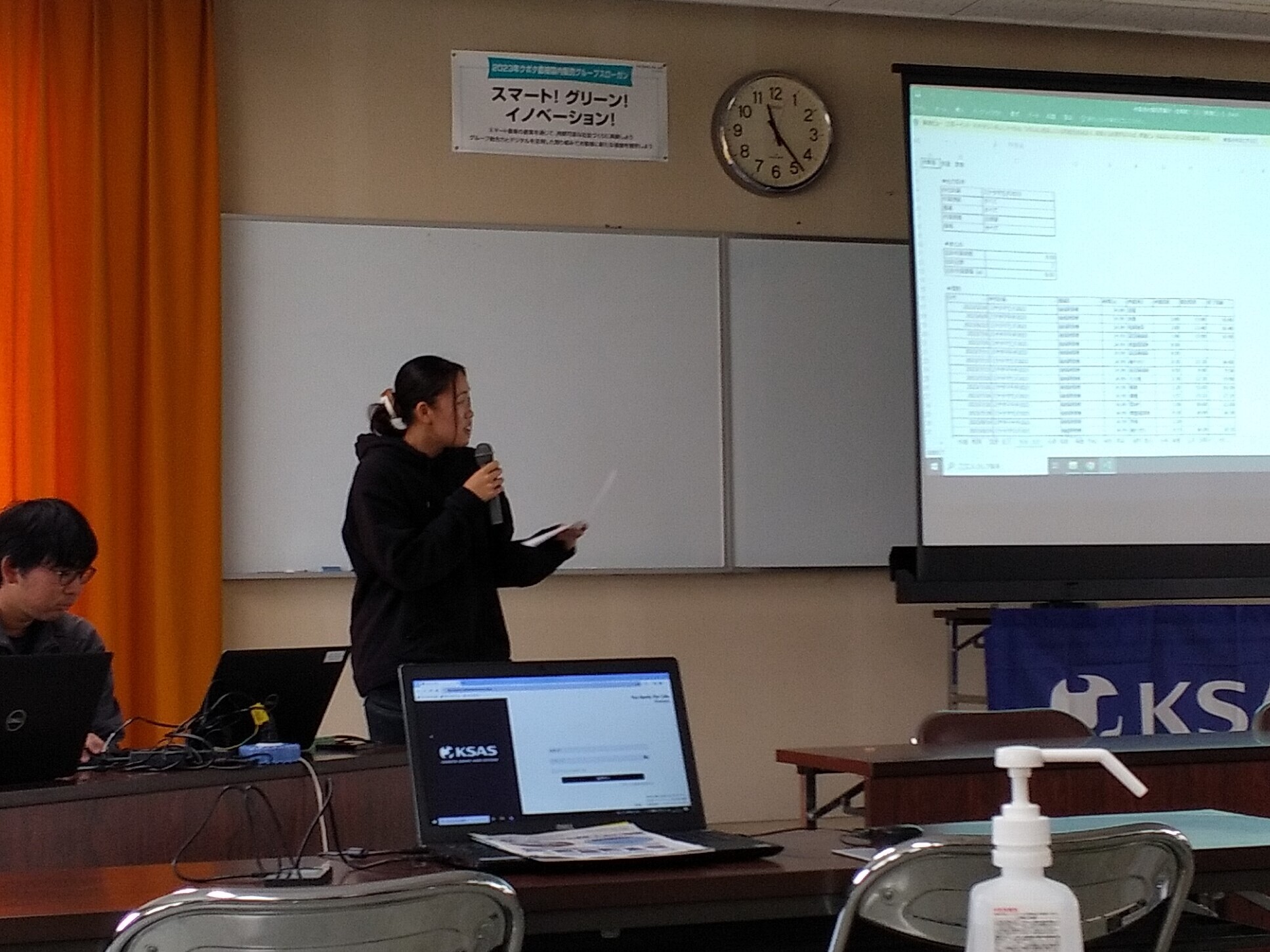
ジャガイモの掘り上げを行いました! R5.12.13
園芸学科の野菜経営コースでは、12月13日(水)、ジャガイモの掘り上げを行いました。
ジャガイモの経営プロジェクトを行っている二年生が、トラクタに取り付けたポテトディガーを使って、次々とジャガイモを掘り上げていきました。
12月11日に行った試し掘りではイモの数は少ないと予想されましたが、実際に掘り上げてみると、イモの数もサイズも上々の結果でした。
土がやや湿っていたため、半日ほど天日で乾燥させた後、担当の2年生と補助に入った一年生の3人でイモの拾い上げを行いました。
今後、収穫調査を行うとともに、出荷に向けた準備を進めていく予定です。




ジャガイモの試し掘り! R5.12.11
園芸学科の野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ジャガイモのマルチ栽培導入に係る経営評価に取り組んでいます。
9月に定植した秋作のジャガイモが収穫期を迎え、12月11日(月)に、担当の二年生が試し掘りを行いました。
株あたりのイモの数は少なかったものの、十分に肥大していることを確認しましたので、12月13日にイモの掘り上げを行うことに決定しました。
今作の出来具合が、楽しみです。




ナシのせん定を始めました! R5.12.11
園芸学科果樹経営コースのナシ班では、12月12日(火)から、ナシのせん定を開始しました。
学生たちは、教官からナシのせん定、枝の誘引、芽整理について説明を受けた後、「ゴールド二十世紀」という青ナシの品種で、実際にせん定作業を行いました。
今回、就職先の関係からブドウ班の2年生も加わり、ナシ班の1年生とともに、ナシ班の2年生に枝の切り方や誘引の仕方などを教わりながら、作業を進めていました。
ナシのせん定は、これから本格的に行われ、終了時期は2月中旬を予定しています。




令和5年度作目基礎研修の閉講式を行いました! R5.12.10
12月10日(日)に、今年度の「作目基礎研修」の閉講式を行いました。
この研修は、日曜日を利用して農業・畜産の基礎的な知識・技術を学ぶもので4月の開講以降、十数回実施し、62名の方が研修を終えられました。
当日は、農産物の流通販売の講義のあと、閉講式及び各コースの担当講師を囲んでの最後の懇談を行い散会しました。
研修を終えた受講生からは、「来年から本格的に栽培に取り組んでいきたい」との意気込みも聞かれました。




「防府市農業まつり」で8名の学生が販売実習を実施! R5.12.11
12月10日(日)、JA山口県防府とくぢ統括本部で、「令和5年防府市農業まつり」が開催されました。
当校も出店し、土地利用学科の一年生4名、園芸学科花き経営コースの一年生4名の計8名の学生が、販売実習に臨みました。
当日は、午前6時前から出荷準備を行い、午前7時には会場へ移動し、学生主体で会場設営や出荷物の展示を行いました。
今回、シクラメンと花束を出品しましたが、穏やかな天候のもと、多くのお客様が来場され、学生たちの積極的な声掛けや丁寧な接客により、出品したシクラメン100鉢は販売開始2時間で完売しました。
その後、シクラメン20鉢を追加しましたが、正午過ぎには全ての出荷物を販売することができ、学生たちは大きな達成感を得ることができたようです。




ベゴニアの鉢上げ準備! R5.12.6
防府天満宮では、毎年4月中旬から5月上旬に「花回廊」として大石段を花鉢で飾るイベントが開催されており、当校も花鉢の準備で協力しています。
園芸学科の花き経営コースでは、来年の「花回廊」に飾る花鉢に使用する花として、 「ビオラ」、「マリーゴールド」、「西洋オダマキ」、「ベゴニア」の4種類を用意します。
このうち、10月20日にセルトレイに播種した「ベゴニア」が、鉢上げが可能な状態となったため、12月7日(木)、担当の1年生が鉢上げの準備を始めました。
今回、「スプリントプラス ホワイト」など3品種、1,800株を鉢上げする予定としており、当日は、ポットに充填する培土の準備を行いました。
ベゴニアの鉢上げは、12月13日頃から行う予定です。




ひたすらタマネギ苗を植える(その2)! R5.12.7
12月6日(水)と7日(木)の2日間、土地利用学科は(株)ファーム大道(下津領)のタマネギ圃場において、機械移植作業の実習を行いました。今回実習した圃場の面積は約1.3ha! 学生達は、畝の上にある稲株を除去する班、移植機を操作する班に分かれて、ひたすらタマネギ苗を植えていきました。
「畝の上にある稲株」というのは、前作の水稲を収穫した跡に残った稲株が、畝を作る時に全て土中に鋤き込めずに畝の上に残った稲株のことです。機械が苗を移植する際の邪魔になるということで、手作業で畝の上から取り除いていかなければなりません。機械に順調に作業してもらうために、場合によってはこのような作業も必要なのですね。
さて、今回の圃場ですが、畝の長さがなんと100m。1畝植えるのに移植機で20分かかります。ぱっと見気が遠くなるようですが、集中して作業していると結構アッという間に時間が過ぎるものです。2日がかりで、32畝植えました。
来年の収穫や調製についても、実習させてもらう予定です。




レタスの播種! R5.12.7
園芸学科の野菜経営コースでは、ガラス温室でレタス栽培に取り組みます。
今回栽培する品種は、低温結球性に優れ、玉肥大のよい「ビックガイ」です。
12月7日(木)には、担当学生が、セルトレイ5枚に種をまきました。
これらセルトレイは育苗用温室内で3週間の育苗を経て、その後定植します。
なお、このレタスの収穫は、来年2月以降に行われる予定です。
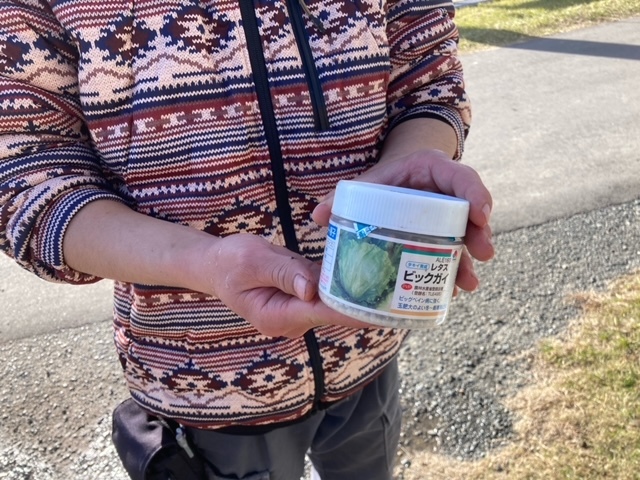

ウメ園の土壌改良! R5.12.7
園芸学科果樹経営コースのナシ班では、ウメ園の土壌改良を始めました。
12月7日(木)には、学生がミニバックホウを使って、深さ40cm前後の溝を掘りました。
その後、スコップを使って、溝中に埋まっていた石を取り除いたり、深さを微調整しました。
今後、12月中旬には、牛ふん堆肥を施用した後、土を埋め戻す予定です。




「道の駅 ソレーネ周南」で7名の学生が販売実習を実施!
R5.12.6
12月6日(水)、「道の駅 ソレーネ周南」で、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の二年生4名と一年生2名の計7名の学生が、販売実習に臨みました。
当日は、穏やかな天候のもと、ハウスで栽培されたスイートコーンや中晩柑の「みはや」のほか、冬野菜など様々な青果や花きが出品され、賑やかな雰囲気でした。
珍しくお客様が少なかったため、学生たちは呼び込みに苦労しました。
しかし、このようなときにこそ、注意すべきことや努力すべきことがわかり、よい勉強となったようです。
特に、お客様お一人お一人とゆっくり会話ができたことが、大きな学びであったようです。
次回の販売実習は、12月25日(月)に、まちの駅「うめてらす」で行う予定です。




第3回短期入門研修を開催しました R5.11.27
11月27日から11月30日にかけて、やまぐち就農支援塾第3回短期入門研修を開催しました。この研修は、農業未経験の方などを対象に、将来の就農を目指すきっかけとしていただくために、毎年度4回程度実施しているものです。
今回は15名の受講者が参加され、農業大学校の職員や学生らから農業機械・小農具の取り扱いや、野菜、果樹、花き、酪農、肉用牛の管理指導を受けながら作業体験を行いました。
受講者からは「実際に作物や家畜に触れながらの作業体験ができ参考になった」「学生たちともいろんな情報交換ができ良かった」「今後の就農に向けた検討の材料にしていきたい」等の感想が聞かれました。





トマトの定植! R5.12.6
園芸学科の野菜経営コースでは、高糖度トマト生産を目指し、塩分ストレス栽培に関する経営プロジェクトに取り組んでいます。
このプロジェクトの一環として、12月6日(水)、ガラス温室内の隔離ベンチにて、トマトの定植が行われました。
今回の定植したのは、「桃太郎ホープ」という早生品種で、低温伸長性に優れており、黄化葉巻病にも耐性があります。
合計330本の苗が定植され、果実の収穫は2月中旬頃を予定しています。




ビオラの鉢上げ! R5.12.6
防府天満宮では、毎年4月中旬から5月上旬に「花回廊」として大石段を花鉢で飾るイベントが開催されており、当校も花鉢の準備を協力しています。
園芸学科の花き経営コースでは、この取り組みの一環として、12月6日(水)に、ビオラの鉢上げを行いました。
作業は、まず、培土の準備から始まり、次にポットに培土を詰め、その後、セルトレイからビオラの苗を取り出し、ポットに植え替えていきました。
今回、花色がクリーム色からラベンダー色に変化する「ピエナ(R)ラベンダーマジック」など4品種、計1600本を鉢上げしました。
これらの苗は、今後、パイプハウス内で管理を行い、来年2月には仕上げ鉢(ボールプランター)に植え替える予定です。




ナシ園の土壌改良! R5.12.6
当校のナシ園では、土壌改良作業も最終段階に入っています。
土壌改良作業11月上旬から行われており、これまでに、土壌改良場所の穴を掘ったり、掘り上げた土にバーク堆肥や苦土石灰、パーライトなどの土壌改良資材を施したり、掘った穴に落ち葉を埋める作業までが完了しています。
今週からは、掘り上げた土と土壌改良資材を混ぜて、穴に埋め戻す作業を進めています。
12月6日(水)には、園芸学科果樹経営コースのナシ班の学生2名が、スコップを使って、土塊を細かく砕き、土と土壌改良資材を混ぜ、穴に埋め戻していました。
この作業は、12月8日までに終了させる予定です。




小麦の播種、経プロの開始 R5.12.5
土地利用学科では、11月29日(水)、パン用小麦「せときらら」の播種を行いました。
この小麦、学生が経営プロジェクト(卒業論文)の調査課題に位置付けて栽培するものでもあります。テーマは、「緑肥作物のヘアリーベッチを小麦と同時に播種すれば、開花期追肥を減らせるのではないか?」。パン用小麦「せときらら」は、パン用に相応しい品質にする(タンパク質含有率を高める)ため、一般的に開花期(4月)に窒素肥料を追肥していますが、この削減を狙ったものです。
播種に使用する機械は、大豆の播種にも使用したトラクタ+ロータリー+施肥播種機のセット。加えて、ヘアリーベッチを播種できる機械を、麦の播種機の横にセットしてみました。そして、学生と教官が、プロジェクトの設計書どおりにきっちり播種・施肥できるよう、入念に機械の設定を調整。この日はトラブルもなく、無事播種を終えることができました。
土地利用学科として初の経営プロジェクト、順調に実施できることを期待しています。




トラブルを乗り越え、タマネギを移植 R5.12.4
9月に播種した土地利用学科のタマネギですが、いよいよ定植時期となりました。施肥、畝立て、苗の準備は事前に行っていましたので、あとは植えるだけ。11月24日(金)、タマネギ移植機を使って定植を行いました。
ところが、いざ植え始めると、苗がうまい具合に植えられないではありませんか! ジャガイモでもこんなことがあったような・・・(既視感) ということで、少しずつ作業を続けながら(そしてどんどん出てくる植付け失敗苗を手で捕植しながら)、機械の様子を観察し、苗の葉の長さや根の量を急遽変更したり(苗準備班が即座に対応)、機械の傾きや植付け口の開き具合を調整したり、学生も教官も原因究明に取り組みました。なんとか作業序盤のうちに不具合を解消し、機械が順調に定植できるようになりましたが、結構な時間をロスしてしまったため、定植が終わったのは11月28日(火)となりました。とはいえ、順調にできなかったからこそ、いろいろ学ぶことの多い実習でした。




強風の中でこそ学べることがある R5.12.4
土地利用学科では、9月からほぼ隔週でドローンの操作練習を行っています。順調に操作技術が向上してきていることから、11月28日(火)、いよいよGPS無しでドローンを操作する練習を行いました。
GPSを切ると、ドローンは風に流されます。しかもこの日の予報は風速8m! これは、GPS無しの練習にはもってこいの状況です。
風が徐々に強くなっていく条件下(最大瞬間風速は10mを超えたようです)、学生達は講師の指導のもと、GPS無しのドローン操作に挑戦していました。特に、風の弱まった瞬間を見極めての安全な着陸は難しかったようです。みんな、いつにも増して肩に力が入った、前のめりの姿勢で操作していました。
風に流されたドローンが転倒したり、ネットに引っかかったり、とアクシデントもありましたが、ドローンに大きな損傷もなく、無事講義を終えることができました。学生達の操作技術も、また一つレベルアップしたことでしょう。




ドウ園の防風垣の刈込み! R5.12.4
園芸学科果樹経営コースのブドウ班では、露地ブドウ園の防風垣の刈込みを行っています。
ブドウは、台風などの強い風に弱いので、安定した収量を確保するために、防風垣が必要です。
そのため、農閑期である冬に、防風垣の手入れを行っています。
12月4日(月)には、学生たちが、夏季の茂り具合を予測しながら、適度な茂り具合となるよう刈込みを行いました。
この防風垣の刈込みは、12月8日までに終える予定です。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.12.3
12月3日(日)、農業大学校において、受講生12名を対象に作目基礎研修の「果樹コース」を実施しました。
当日は、果樹の冬期作業として、樹種別の剪定方法の説明と併せて、校内園地で実際にウメとクリの剪定作業を行いました。
師走らしく、気温は低い日でしたが風は弱く、剪定作業には好都合な日となり、受講生たちは熱心に聴講及び実習に取り組んでいました。


「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備! R5.12.1
12月6日(水)の午後2時より「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習を行います。
当日のスムーズな運営を確保するため、12月1日(金)に、当日対応する学生たちが打合せを行いました。
参加者は、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の一年生2名、二年生4名の計7名で、一年生と二年生が協力して打合せを進めました。
放送原稿やブラックボードの作成では、全員の意見が取り入れらました。
また、今回出品予定の中晩柑の「みはや」の試食も行い、自信をもってお客様にお勧めできそうです。
当日は新鮮な商品と学生の笑顔で素晴らしいおもてなしを提供できることと思いますので、ぜひ、12月6日に「道の駅 ソレーネ周南」へ足をお運びください。

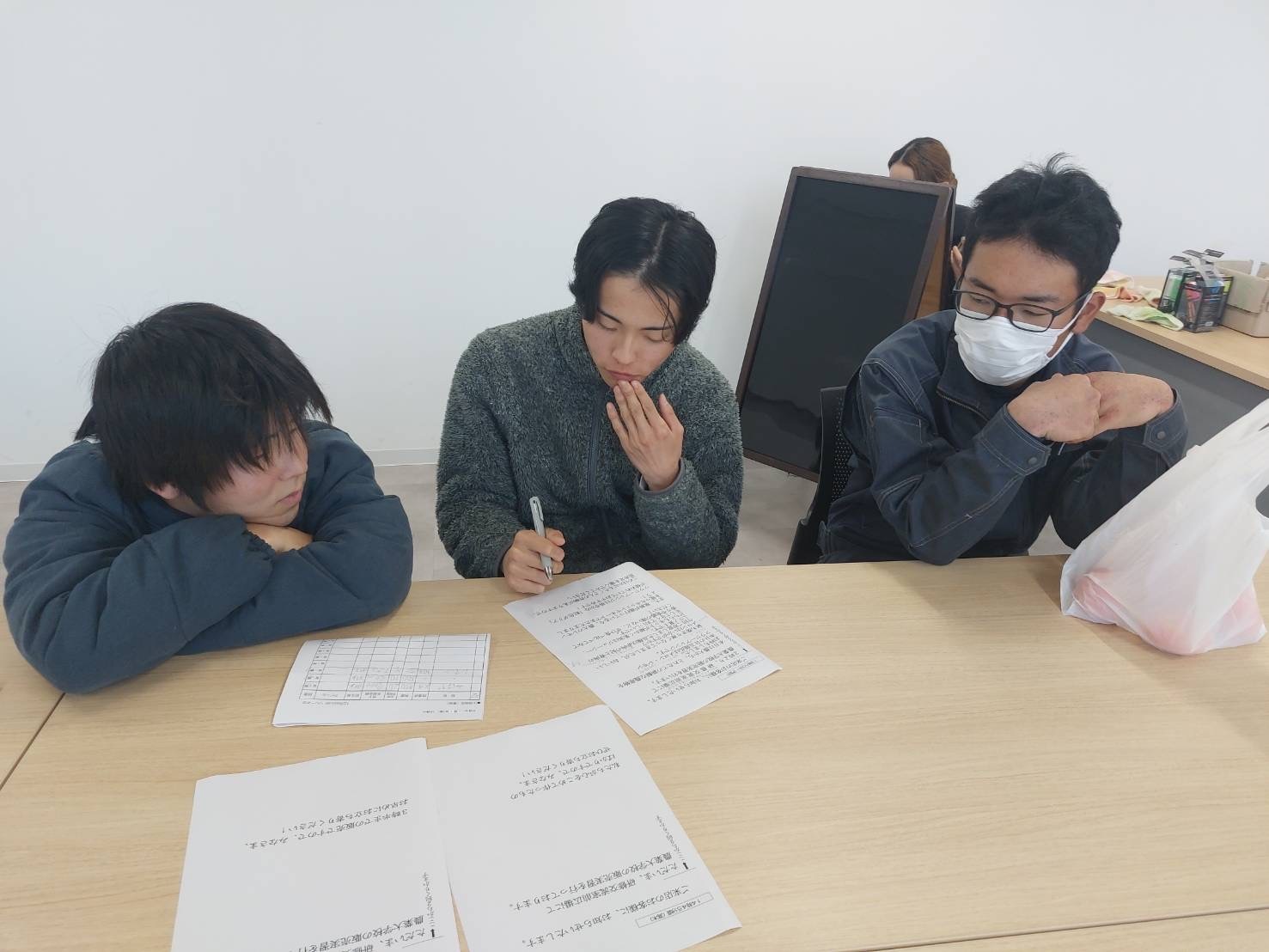


まちの駅「うめてらす」で8名の学生が販売実習を実施!
R5.11.29
11月29日(水)、防府市まちの駅「うめてらす」で、土地利用学科の一年生2名と園芸学科の二年生6名が、販売実習に臨みました。
今回の販売実習では、キャベツ、フラワーアレンジメント、柑橘(「みはや」)、精米(「きぬむすめ」)が目玉商品として出品され、これに加えて多くの商品が販売され、賑わいました。
初めて精米を販売する土地利用学科の学生は意気込み十分でしたが、声掛けに苦労したようです。
また、どの商品についてもお客様からのご質問が多く、対応した学生は多くの学びがあったようです。
次回の販売実習は、12月6日(水)に、「道の駅ソレーネ周南」で行う予定です。




ナシ園の落葉収集! R5.11.30
現在、園芸学科果樹経営コースのナシ園では、気温の低下に伴い、落葉が進行しています。
土壌改良用に掘った穴は落葉でいっぱいになっていますが、穴に入りきらなかった葉もまだまだ残っています。
これらの葉をそのままにしておくと、ナシ黒星病菌などの落ち葉に潜伏する病原菌が残り、翌年の感染源となる恐れがあるため、穴に埋めて処分する必要があります。
そこで、11月30日(木)には、果樹経営コースのナシ班の学生が、園地内の落葉を集めて、土壌改良用の穴に埋める作業を行いました。
気温が低く、風が強い中での作業でしたが、学生たちは黙々と落葉を集めていました。
この落葉の収集作業は、穴の埋め戻しを行う12月中旬まで行う予定です。




せとみの袋掛け! R5.11.29
園芸学科の果樹経営コースでは、11月29日(水)、露地圃場で栽培している「せとみ」の果実に袋掛けを行いました。
せとみの果実への袋掛けは、気温が本格的に下がる前の11月に行われ、果実の着色を促進し、鳥の食害や寒さの被害から果実を保護する目的があります。
手間のかかる作業ですが、学生たちは、果実1個1個に丁寧に袋を掛けていました。
せとみの収穫は1月下旬頃を予定しており、2カ月ほど度熟成させて、糖度を上げ酸味を少なくしてから出荷する予定です。




西洋オダマキの鉢替え R5.11.29
園芸学科の花き経営コースでは、11月29日(水)、西洋オダマキの鉢替えを行いました。
今回の鉢替えは、西洋オダマキのポット苗を、ポットより大きなボールプランターに植え替えるもので、ボールプランターあたり3株のポット苗を寄せ植えしました。
担当の学生や短期研修の研修生たちは、ボールプランターへ増し土する培土づくりから行い、最終的には40鉢の鉢替えを済ませました。
この鉢替えした西洋オダマキは、毎年4月中旬から5月上旬に、防府天満宮の大石段を花鉢で飾る「花回廊」に使用される予定です。




シクラメンの市場出荷準備 R5.11.28
園芸学科の花き経営コースでは、11月28日(火)、シクラメンの市場出荷の準備を行いました。
今回の出荷は、年末の需要期に合わせたもので、シクラメン140鉢を出荷する予定です。
担当の学生は、出荷用の外鉢にシクラメンの鉢を入れ、全体の形を整え、出荷の準備をしていきました。
シクラメンの出荷は12月中旬にかけて続きます。


やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました R5.11.28
11月26日(日)、農業大学校において、受講生6名を対象に作目基礎研修の「農業機械コース」を行いました。
当日は、実物を見ながら、コンバインと田植機のエンジンや操作部の構造・性能の説明を行うとともに、コンバインの体験試乗も行いました。
両機の実物を真近に見たことがない受講生がほとんどであり、非常に興味深げに熱心に聴講していました。



土地利用学科、動画作成に取り組んでいます(その2) R5.11.28
土地利用学科では11月から動画作成に取り組んでいますが、3回目の講義が11月21(火)に行われました。今回のテーマは、ナレーションと音声処理について。特別講師は、テレビやラジオ等でお馴染みのフリーアナウンサー柴田まゆみさん! プロの技を生で見ながら聞きながら、発声やナレーションのポイントについて学びました。どんなテーマに対しても、決められた時間ピッタリに、ポイントを絞って、わかりやすく聞きやすく話す技術(しかも即興で)に、ただただ驚愕です。
さて、後半の実技課題は、「15秒の機械説明動画を作る」こと。普段使っている機械でも、その特徴を15秒にまとめるのは至難の業。ですが、学生達は何度も話し合って、何度も撮り直して、結果なかなか良い動画を作り上げていました。
次回は、SNSを使った情報発信について学ぶ予定です。




ひたすらタマネギ苗を植える R5.11.28
土地利用学科では、農業法人の実態に即した学修を行うため、市内の農業法人(株)ファーム大道と連携した実習に取り組んでいます。
11月16日(水)は、(株)ファーム大道のタマネギ圃場において、機械移植作業の実習を行いました。今回実習した圃場も、7月に田植えをした圃場のように面積は約1haの大区画。使用する機械は、同社保有の全自動タマネギ移植機。学生は交代で機械を操作し、残りのメンバーはうまく移植できなかった苗(ちょっと調子が悪かったようです)の補植を行いました。9時半から16時まで、ひたすらタマネギ苗を植える、植える、植える・・・
学生の感想は、「こういう単純作業は苦になりません」「腰が悲鳴を上げてます」「ネギの匂い、好きです」など。広大な圃場で、農大には無い機械を使い、一つの作業をひたすら続けたこの実習、よい経験になったのではないでしょうか。
タマネギ移植作業の実習は、今回だけでなく、12月上旬にも行う予定です。




飼料用トウモロコシ収穫用コンバイン、ゴジラの足のよう R5.11.28
様々な実演会に参加して見分を広めることにしている土地利用学科ですが、このたび飼料用トウモロコシの収穫実演会があると聞き、さっそく参加してきました。
おー、ヤンマー普通型コンバインYH1150(飼料用トウモロコシ収穫仕様)、さすがにでっかいですね・・・
実演会では、飼料用トウモロコシの取組の概要や飼料用トウモロコシの栽培上のポイント等についても説明を受け、コンバインが実際にバリバリ音を立てながら収穫していく様子も見学することができました(迫力満点)。
あとは、やっぱり、味も知りたいですよね。収穫したて(コンバイン収穫のものではなくて、手収穫のもの)の飼料用トウモロコシ、ちょっと食べてみました。粉っぽくて美味しいものではありませんでしたが、クセになる味と言いながらつまんでいた人が約2名いました。
今後も、様々な実演会等に参加しながら、県内農業法人の取組や機械について学んでいく予定です。




キクの摘蕾(てきらい)! R5.11.21
園芸学科の花き経営コースでは、年末に向けて出荷するキクの摘蕾作業が行われています。
対象となるのは、1本に1輪の花を咲かせるキク(「輪ギク」)の品種です。
輪ギクでは、頂点(生長点)についた蕾を残し、脇についた蕾をすべて取り除く摘蕾が必須であり、この丹念な作業の結果、輪ギクが作られています。
担当の1年生も、頂点の残す蕾を折らないよう、慣れない手つきで、丁寧に不要な蕾を取り除いていました。




西洋オダマキの古葉取り! R5.11.24
毎年4月中旬から5月上旬に、防府天満宮では、「花回廊」として大石段を花鉢で飾る行事が行われており、農業大学校も花鉢の準備に協力しています。
園芸学科花き経営コースでは、毎年、この花鉢に使用する花に、これまで使ったことのない品目を追加しており、今年は、「西洋オダマキ」を採用しました。
西洋オダマキは、キンポウゲ科の宿根草で、春から初夏まで花を楽しむことができます。
現在栽培している品種は、アーリーバードというシリーズで、花色が赤白の「レッドホワイト」と花色が白色の「ホワイト」の2品種です。
11月24日(金)には、この西洋オダマキのポット苗の古葉取りが行われました。
この作業は、古葉につく病気の発生や蔓延防止のために行うもので、担当の学生は、丁寧に古葉を取り除いていました。
今後、西洋オダマキのポット苗は、随時、ボールプランターに植え替える予定です。




シクラメンの葉組(はぐみ)! R5.11.21
園芸学科の花き経営コースでは、現在、シクラメンの葉組作業が進行中です。
葉組とは、株の中心にある葉を外側に引っ張り、外側の葉に引っ掛け、株の中心部にスペースをつくる作業です。
これにより、球根の頭頂部に光が当たり、花芽が育ちやすくなり、花が中央に集まって咲くようになります。
現在、シクラメンは出荷のピークを迎えていますが、担当学生は、良質なシクラメンをお客様に届けるため、日々株管理を行っています。
また、12月10日には、JA山口県防府とくぢ統括本部で開催される「令和5年防府市農業まつり」でも販売しますので、ぜひその機会にお買い求めください。




フラワーアレンジメントのラッピング! R5.11.15
11月15日(水)の午後2時から「道の駅 ソレーネ周南」で販売実習が行われました。
このため、同日の午前中に、園芸学科花き経営コースの学生が、販売実習に出品するフラワーアレンジメントのラッピングを行いました。
2年生は、手慣れた様子で、フラワーアレンジメントを透明なフィルムで覆い、リボンを装飾していきました。
販売実習では、フラワーアレンジメントの他に、ダリアの花束なども販売しました。




イチゴの親株定植! R5.11.22
園芸学科の野菜経営コースでは、次年度のイチゴ栽培に向けた準備が進行中です。
次年度、ガラス温室やパイプハウスで、約600㎡のイチゴの作付けを予定しており、作付用の苗、約3000株の確保を計画しています。
その一環として、11月22日(水)、イチゴ担当の一年生らが、親株125株をラックに定植しました。
これらの親株は、今後、ガラス温室内で管理しますが、学生らは目標とするイチゴの苗数の確保に向けて、細やかな管理を行うと意気込んでいました。
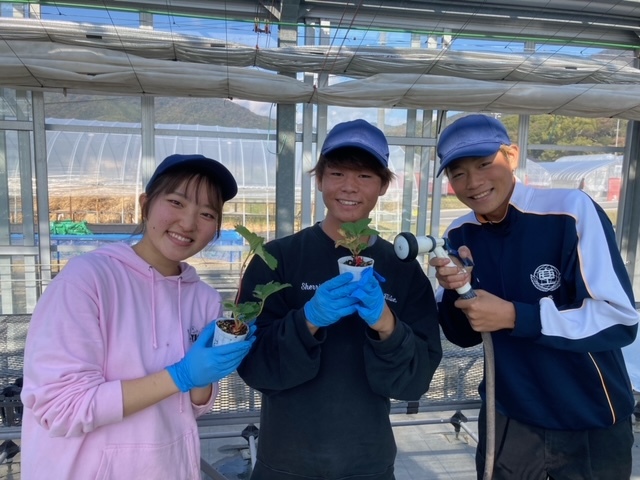



防府市まちの駅「うめてらす」での販売実習に向けた準備!
R5.11.22
防府市まちの駅「うめてらす」での販売実習に向けた準備が進んでいます。
販売実習は、11月29日(水)の午後2時からの開始を予定しており、当日のスムーズな運営を確保するため、11月22日(水)に、当日対応する学生たちが打合せを行いました。
参加者は、土地利用学科の一年生と園芸学科の二年生で、皆が経験者ということで打合せは円滑に進みました。
ブラックボードの作成やレジの動作確認、事務用品のチェックなど、調べ物を交えながら丁寧に進めていました。
今年初出荷の米を販売する予定であり、土地利用学科の学生は意気込み十分です。
当日は新鮮な商品と学生の笑顔で素晴らしいおもてなしを提供できることと思いますので、ぜひ、11月29日に防府市まちの駅「うめてらす」へ足をお運びください。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.11.22
11月12日(日)、農業大学校において、受講生44名を対象に作目基礎研修の
「野菜Ⅰコース(施設野菜)」と「野菜Ⅱコース(露地野菜)」、「果樹コース」及び「水稲コース」を併行して実施しました。
当日は、コース別に、ハウスイチゴの生育状況観察、ハクサイ・キャベツ・サツマイモなどの収穫、ナシ・ブドウの剪定などの講義及び実習を行いました。
初冬のやや肌寒い日でしたが、受講生たちは熱心に聴講するとともに、実習時には汗を流していました。



せとみ・不知火栽培のためのパイプハウスの被覆! R5.11.22
園芸学科の果樹経営コースでは、11月22日(水)、「せとみ」や「不知火」を栽培しているパイプハウスをビニルで被覆しました。
「せとみ」や「不知火」の収穫は2月中旬頃を予定していますが、冬季の低温にさらされて果実が凍結すると、果肉に苦みが発生したり、果汁が消失したりして、果実品質が大幅に低下します。
これを防ぐため、パイプハウスにビニルを被覆し、低温時には加温できるようにしました。
ビニルの被覆には、果樹経営コースの学生、塾生、職員全員が参加しました。
皆が協力して行ったおかげで、仕上がりよくビニルが張れました。




ダリアの脇芽取り! R5.11.21
園芸学科の花き経営コースでは、現在、ダリアの脇芽取りの作業が進行中です。
この作業は、不要な芽を取り除き、必要なつぼみに養分を集中させるために行います。
一番花が出荷のピークに達していますが、来年の5月頃まで、質の高い二番花、三番花を断続的に出荷するためには、この作業が不可欠です。
今年は、「NAMAHAGEノアール」(特徴的なボール咲の赤黒色品種)や「キセキ」(大輪の白色品種)、「マルガリータ」(淡いピンク色品種)、「ガーネット」(鮮やかな赤色品種)など5品種を栽培しています。
これらは、花市場や近隣の直売所に出荷しますので、ぜひお買い求めください。




ダリア一番花の収穫ピーク! R5.11.15
園芸学科の花き経営コースでは、今年はガラス温室でダリアの栽培に取り組んでいます。
今年は、「NAMAHAGEノアール」という特徴的なボール咲きの赤黒色品種や「キセキ」という大輪の白色品種など5品種を栽培しており、現在、一番花の収穫ピークを迎えています。
11月15日(水)の午前中には、当日の午後に行う販売実習用の花束づくりを行いました。
また、前日には「キセキ」の花を、染料を溶いた水に挿し、花弁に色をつけました。
これは、同じく販売実習に出品するフラワーアレンジメントに使用されました。
ダリアの出荷は、市場を主体に行うとともに、直売所への出荷も行っていますので、ぜひお買い求めください。




育苗温室の加温準備! R5.11.15
園芸学科の野菜経営コースでは、11月15日(水)、育苗用のガラス温室の加温準備を行いました。
学生や研修生が協力して、温室内の妻面や側面に内張ビニルを設置したり、先日稼働前の掃除・点検を行った暖房機にはダクトを取り付けました。
現在は、メロンの苗を育苗していますが、今後、トマト等の育苗を行う予定です。


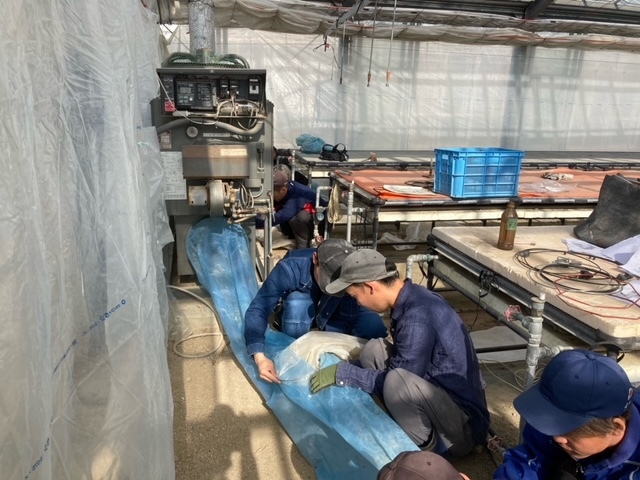

ハウスメロンの作付準備(マルチング)! R5.11.20
園芸学科の野菜経営コースでは、この冬、パイプハウスでメロン栽培に取り組みます。
11月20日(月)には、先日立てた畝に、潅水チューブを設置した後、マルチシートで覆うマルチングを行いました。
今回は寒い時期での栽培ということもあり、通常の黒色のマルチシートで覆う畝と地温上昇効果の高い透明なマルチシートで覆う畝に分け、メロンの生育への影響を調べる予定です。
今後、地温の上昇を待って、12月中旬頃にメロンを定植する予定です。


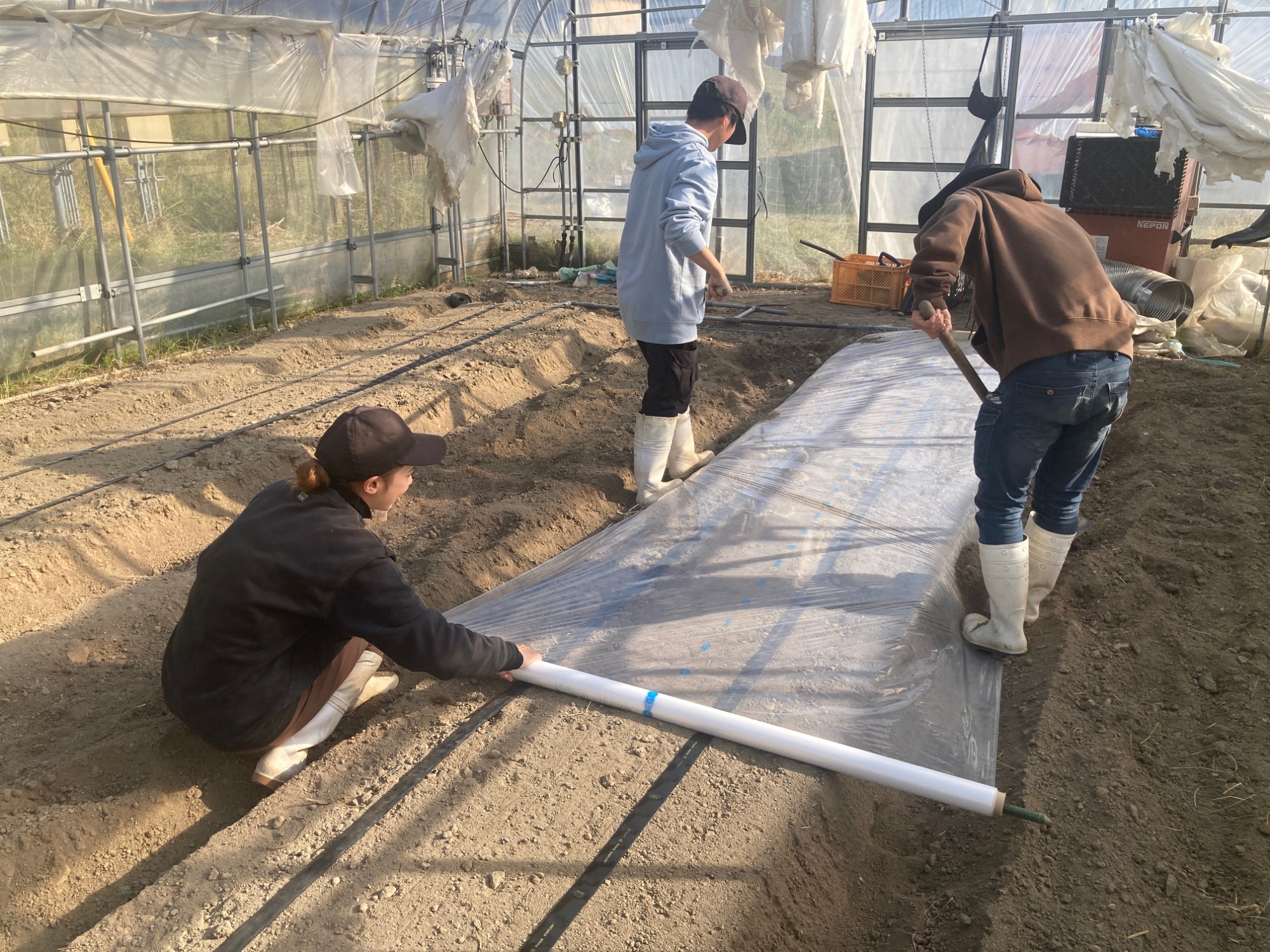

メロン苗の鉢上げ! R5.11.17
園芸学科の野菜経営コースでは、11月17日(金)、メロン苗の鉢上げを行いました。
この苗は、11月6日にセルトレイに播種したもので、品種は赤肉系の「早春のマリ
アージュ」です。発芽後に子葉が展開したため、ポットに移植するものです。
担当の二年生は、根を傷めないよう慎重に苗を扱い、ポットに移植し、合計190ポットの鉢上げを行いました。
これらの苗は、本葉が3~4枚に揃う12月中旬頃に定植予定です。
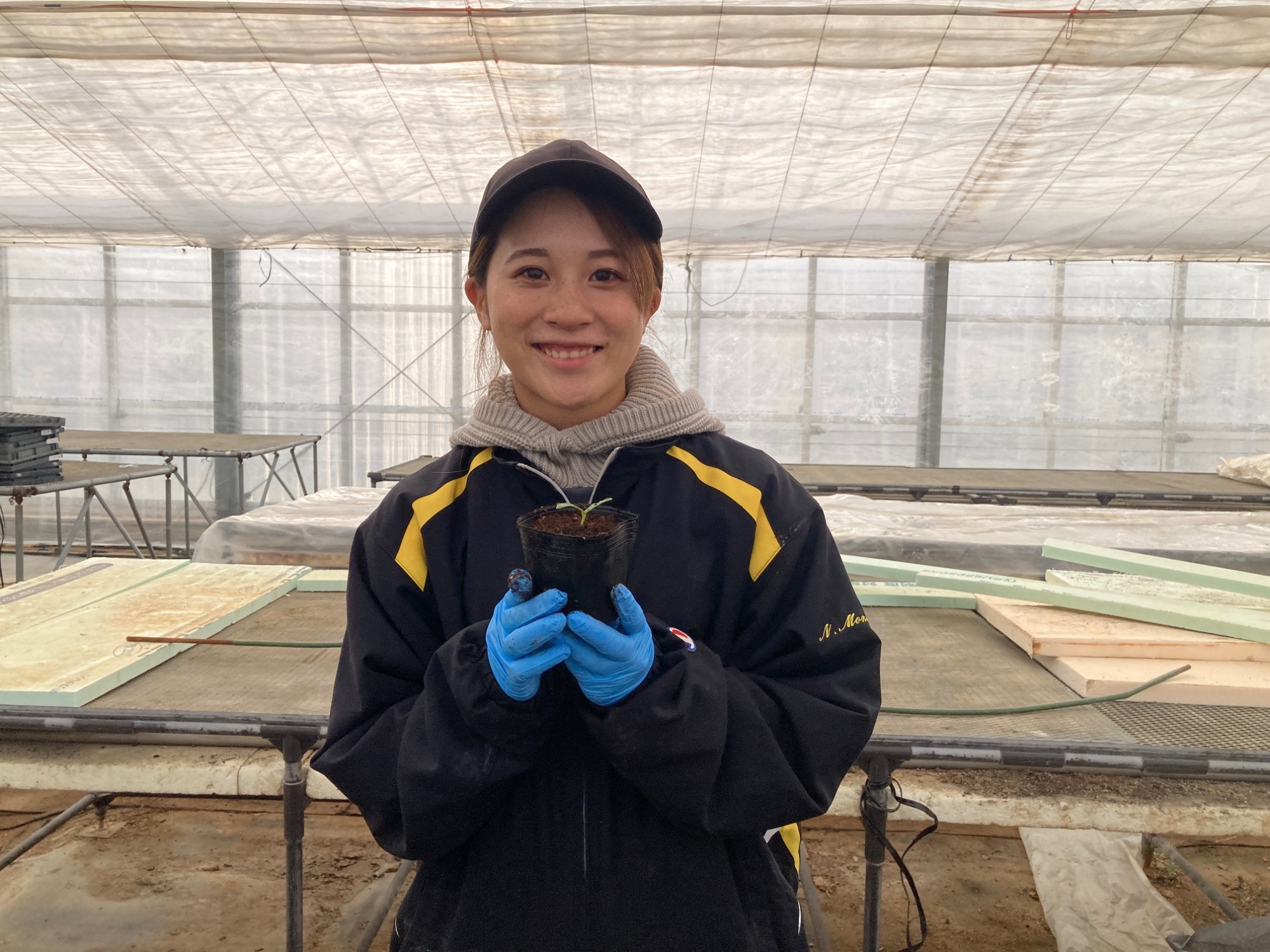



ハウスメロンの作付準備! R5.11.15
園芸学科の野菜経営コースでは、この冬、パイプハウスでメロン栽培に取り組みます。
11月15日(水)には、担当する二年生が、トラクタを使用してハウス内を耕うんするとともに、畝立て成型機を用いて畝を立てました。
今後、潅水チューブの設置やマルチ被覆を行い、12月中旬頃に定植する予定です。




温州ミカン「田口早生」の収穫! R5.11.15
園芸学科の果樹経営コースでは、11月15日(水)に、温州ミカンの早生品種の収穫を行いました。
今回収穫した品種は、「田口早生」で、皮は薄くて剥きやすく、酸が低くて食べやすいのが特徴です。
収穫作業は、かんきつ班の一年生と二年生が行いました。
学生は、果実の着色状況を丁寧に確認するとともに、果実を傷つけないように注意しながら、ハサミを使って収穫を行いました。
収穫したミカンは、翌日に選果を行い、来週以降に防府市や周南市の直売所に出荷する予定です。
今年は、夏以降の降水量が少なかったため、果実品質は上々ですので、ぜひお買い求めください。




「道の駅 ソレーネ周南」で8名の学生が販売実習を実施! R5.11.15
11月15日(水)、「道の駅 ソレーネ周南」で、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の二年生7名の合計8名の学生が、販売実習に臨みました。
当日は、メロン50個のほか、冬野菜など様々な青果や花きが出品され、賑やかな雰囲気でした。
学生たちは、お客様との対話や質問に答えながら、貴重な経験を積みました。
また、館内の放送を使って、販売実習や出品物の紹介を3回行いましたが、そのたびにお客様が集まってくださり、売上に大きく寄与したことから、学生たちは達成感を味わったようです。
次回の販売実習は、11月29日(水)に、まちの駅「うめてらす」で行う予定です。




冬キャベツの収穫ピーク! R5.11.14
園芸学科の野菜経営コースでは、8月下旬に定植したキャベツの早生品種が収穫ピークを迎えています。
現在、主に収穫しているのは、「おきなSP」という品種です。今年はヨトウムシ等の発生が多く、降雨も少なく厳しい条件でしたが、担当の1年生が適期の防除や畝間潅水、追肥等を実施した結果、順調に肥大し、目標とするL~2Lのサイズが多く取れています。
担当の1年生は、収穫後、重量を量って選別するとともに、裂球の有無などしっかり確認していました。
調製したキャベツは、直売所等へ出荷する予定です。


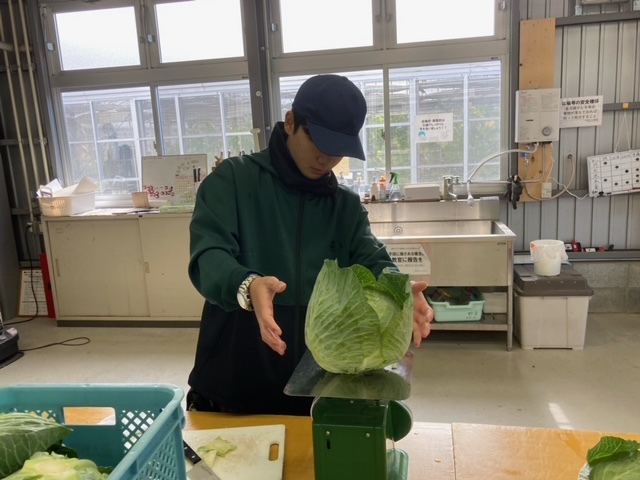

土地利用学科、動画作成に取り組んでいます R5.11.15
土地利用学科では、11月から動画作成の講義が始まりました。「農業大学校なのに、なぜ動画作成の講義を?」と不思議に思われるかもしれません。この取組は、①効率的な実習を行うために機械に関する動画マニュアルを作成すること、②自ら動画作成に取り組むことで情報発信の力を身につけること、③動画マニュアルの作成過程で機械の操作方法やメンテナンスに関する知識・技術を向上させること、を目的として行っています。
2回目となる11月14(火)のテーマは、撮影機材の扱い方です。映像制作会社から講師を招き、ビデオカメラやスマートフォンの特徴、三脚やジンバル(手ブレを抑えて滑らかな動画を撮ることができる機材)の使い方等を学びました。特に、走りながら撮影する場合、ジンバルを使うか使わないかでスピード感や臨場感に大きく違いが出ることを実感しました。
次回はナレーションや音声処理について学ぶ予定です。




大豆コンバイン登場 R5.11.15
土地利用学科が栽培している大豆も、いよいよ収穫時期を迎えました。そこで、11月13日(月)の午後から14日(火)にかけて、大豆の収穫を一気に行いました。
使用する機械は、大豆コンバイン。土地利用学科が使用する機械の中で、最も大きい機械です。構造上、後方はほとんど見えないので、後進時はヒヤヒヤです。また、水稲と違って大豆は畝があるので(しかも中耕培土を頑張ったので、畝がとっても高いのです)、刈り取り中に機体が左右に傾いたり、旋回中に機体が上下左右に揺れたり。座席の位置が高い分、スリル倍増です。そして勿論、学生達が大豆コンバインを使うのは初めてなわけで・・・
そのような状況下、学生達はしっかりと大豆コンバインを操作し、大豆を刈りました。作業に慣れてくるとグンと速度を上げ、効率的に旋回しながら、教官の予想よりも早く刈り終えました。やるじゃん!
刈り取った大豆は、県JAの大豆センターに持ち込み、乾燥調製してもらっています。収量、品質の結果に基づき、次年度の栽培の改善点を検討していく予定です。




タマネギ定植の準備 R5.11.15
土地利用学科では、11月13日(月)、タマネギの定植準備を行いました。
まずは、定植するための畝を作らなければなりません。キャベツやブロッコリーの時にも使用した施肥畝立成型機(せひうねたてせいけいき:肥料を施しながら畝を作る作業機)を使い、施肥と畝立てを同時に行いました。ん-、事前の設定が甘かったのか、ちょっと肥料が余ったようですね。次回は必要量をきっちり施肥できるよう、事前調整の改善が必要です。
このように畝立て班が畝立てを行っている間、残りのメンバーはタマネギの苗を苗床から抜き取り、大きさ別に仕分ける作業を行いました。いくら土地利用学科の人数が多いとはいえ、運搬車一杯の苗を仕分けるのは簡単ではありません。日が当たる場所で皆が輪になって、ひたすら苗の仕分け・・・ 仕分けできなかった苗は、明日へ持ち越しです。さあ、苗の仕分けが終われば、畝にマルチを張って、いよいよ定植です!


2日続けてトヨタの生産方式の講義 R5.11.15
土地利用学科では、トヨタ自動車株式会社から講師を招き、トヨタ生産方式について学んでいます。「農業大学校がなぜトヨタ生産方式を?」と思うかもしれませんが、トヨタの「モノづくりは人づくり」という考え方は、農業でも当てはまります。土地利用学科では、この講義を通じて、現場の問題に対して自ら考え行動する人材の育成に取り組んでいます。
このトヨタ生産方式の3回目、4回目の講義を、11月9日(木)、10日(金)に行いました。9日は、防府市内の農業法人「株式会社ファーム大道」と連携し、実際の現場改善活動(整理整頓)や、農業機械の操作の教え方について学びました。整理整頓については6月に学びましたが、よい復習になったと思います。そして、講義が早く終わって迎えのバスを待つ間、学生達はファーム大道の大型トラクタ(98馬力!)に乗って記念撮影!これも農大では絶対にできない体験ですね。
10日は、トヨタの問題解決手法についての座学。現場の問題を解決するための8ステップ(問題の明確化→現状把握→目標の設定→・・・)について、ボリュームたっぷりの2時間の講義でした。講師からの宿題は、次回の講義(1月10日)までに、この手法を使って学科の問題解決に取り組むこと。これから定期的に時間を設けて、実践していく予定です。



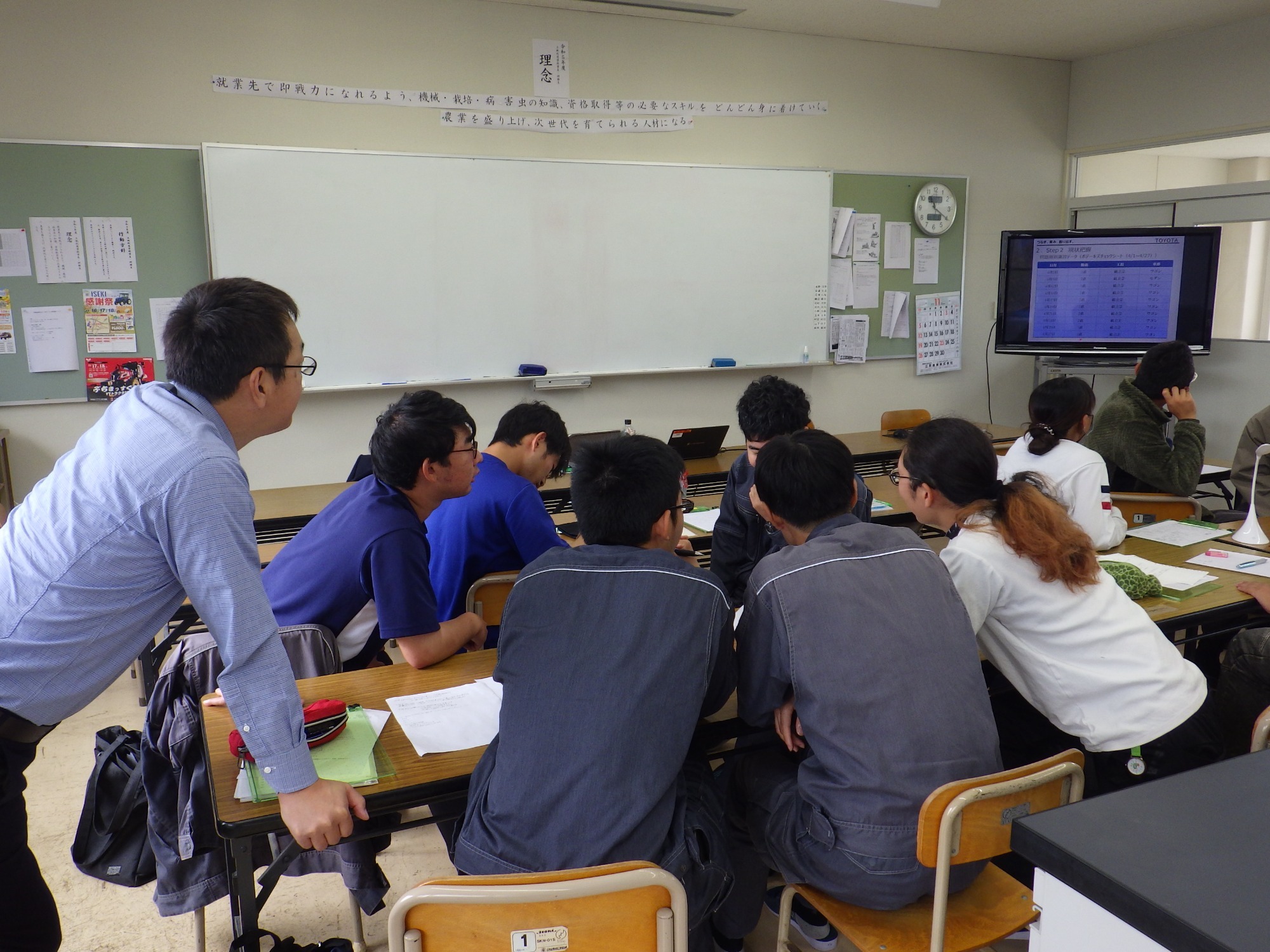
メロンの収穫! R5.11.14
園芸学科の野菜経営コースでは、ガラス温室でメロンの栽培に取り組んでいます。
メロンを栽培するガラス温室2棟のうち、1棟は10月末に収穫し、11月3日開催された「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」で販売し、わずか50分で売り切れるほどの大盛況となりました。
残り1棟については、11月14日(火)に収穫を行いました。
事前の果実品質調査では、15度を超える糖度が確認され、おいしいメロンに仕上がっているようです。
このメロンは、11月15日の「道の駅 ソレーネ周南」で開催する販売実習に出品するほか、近隣の直売所へ出荷します。
ぜひお買い求めください。




メロンの果実品質調査! R5.11.9
園芸学科の野菜経営コースでは、ガラス温室で、秋作メロン栽培に取り組んでいます。
今年は8月15日と8月22日の2回に分けて定植を行い、8月15日に定植したメロンは、11月3日に開催した「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」で、出品した200玉が完売しました。
8月22日に定植したメロンは、これから収穫期を迎えるため、11月9日(木)に、果実品質調査を行いました。
糖度調査を行った結果、高いものでは、糖度が13度を超えるものもありました。
また、試食でも十分な甘みや芳香が感じられ、収穫間近であると判断されました。
果実品質調査の結果から、翌週の木曜日頃、出荷を行う予定です。
防府市内の直売所や周南市の道の駅などに出荷しますので、ぜひお買い求めください。

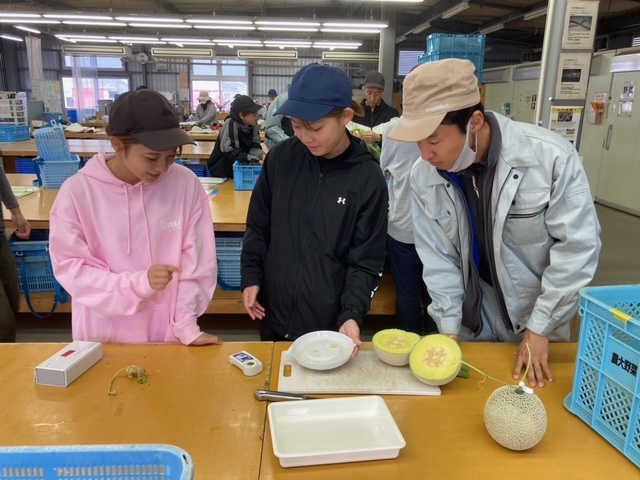


経営プロジェクト中間発表会を開催しました! R5.11.14
園芸学科の経営プロジェクトの中間発表会を、11月14日(火)に開催しました。
今回、花き経営コースの二年生が『葉面散布がやまぐちオリジナルユリの葉焼け症の発生に及ぼす影響』というテーマで発表しました。
発表資料に基づいて、調査内容や結果、現時点での考察を詳しく説明するとともに、未掲載の情報も加えていました。
参加学生からの葉面散布に使用した資材の成分やオリジナルユリの生育適温などといった質問にも、丁寧に回答していました。
発表後には、参加者たちがハウス内を見学し、ユリに発生している葉焼け症を実際に確認し、課題に対する理解を深めました。
今回の中間発表会をもって、本年度は終了となります。今後、学生たちは経営プロジェクトの発表会に向けて、概要書や発表用スライドの作成に取り組んでいく予定です。
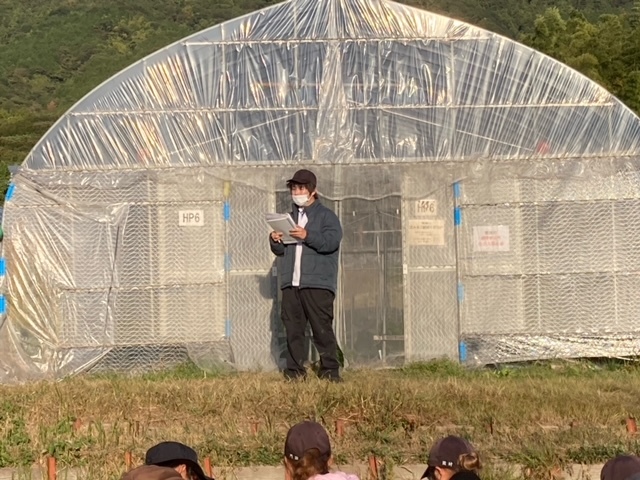



「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備! R5.11.10
「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備が進んでいます。
販売実習は、11月15日(水)の午後2時からの開始を予定しており、当日のスムーズな運営を確保するため、11月10日(金)に、当日対応する学生たちが打合せを行いました。
参加者は、土地利用学科の一年生と園芸学科の二年生で、経験豊富な二年生が多かったことから、打合せは円滑に進みました。
今回は、温室等で栽培されたメロンやトウモロコシ、露地圃場で栽培されたブロッコリーやキャベツ、サツマイモなど野菜の品揃えが多い見込みで、参加者は積極的に情報交換を行い、情報を整理していました。
当日は新鮮な商品と学生の笑顔で素晴らしいおもてなしを提供できることと思いますので、ぜひ、11月15日に「道の駅 ソレーネ周南」へ足をお運びください。

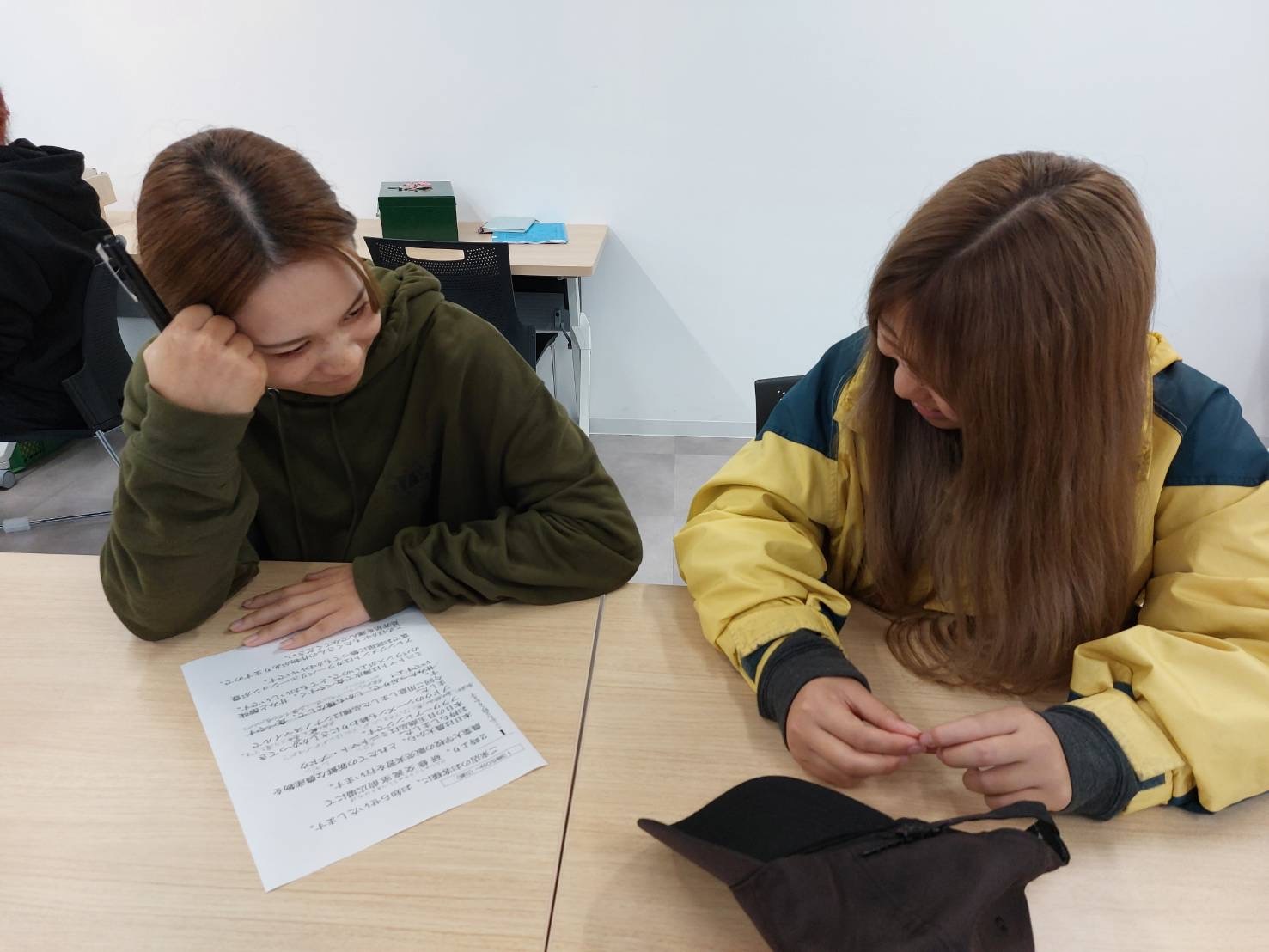


トウモロコシの試し採りpartⅡ! R5.11.9
園芸学科の野菜経営コースでは、トウモロコシの抑制栽培に挑戦しており、黄粒種の「おひさまコーン88」と白粒種の「ホイップコーン」の2品種を栽培しています。
先週行った雌穂の試し採りでは、果粒の色や膨らみは十分でなかったため、本格的な収穫は見合わせました。
このため、一週間後の11月9日(木)に、改めて試し採りを行いました。
今回は、果粒の色や膨らみも十分であり、試食してみると強烈な甘さを感じ、糖度も15度を記録したため、収穫適期であると判断しました。
したがって、翌週から本格的な収穫と出荷を行う予定です。


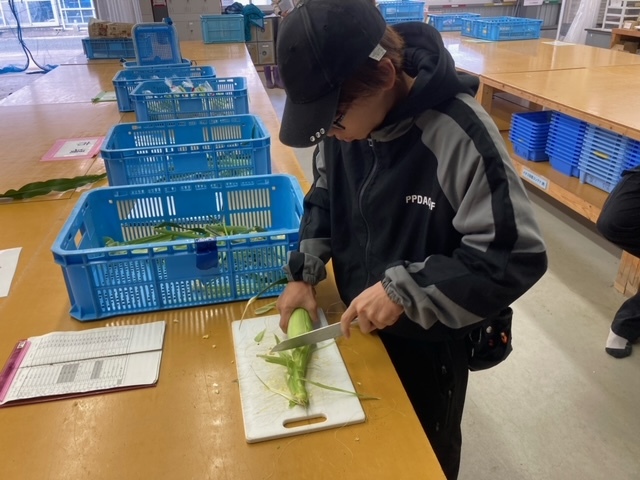

「花回廊」用のマリーゴールド苗の鉢上げ! R5.11.8
毎年4月中旬から5月上旬に、防府天満宮では、「花回廊」として大石段を花鉢で飾る行事が行われており、農業大学校も花鉢の準備に協力しています。
この一環として、園芸学科の花き経営コースでは、11月8日(水)に、この花鉢用のマリーゴールドの苗の鉢上げを行いました。
まず、培土の準備から始まり、次にポットに培土を詰め、その後、セルトレイからマリーゴールドの苗を取り出し、ポットに植え替えていきました。
今回、花色が黄色の「ホットパック イエロー」を含む3品種、計1200本を鉢上げしました。
これらの苗は、今後、ガラス温室内で管理を行い、来年2月には、仕上げ鉢(ボールプランター)に植え替える予定です。
また、11月下旬頃には、ベゴニアやビオラも鉢上げを行う予定です。




トマトの鉢上げ! R5.11.8
園芸学科の野菜経営コースでは、高糖度トマト生産を目指し、塩分ストレス栽培に関する経営プロジェクトに取り組むこととしています。
このプロジェクトの一環として、10月25日に接ぎ木を行いましたが、無事に活着し、現在まで苗は順調に生育しています。
11月8日(水)には、セルトレイで栽培していた接ぎ木苗を、培土を充填したポットに植え替える「鉢上げ」を行いました。
プロジェクトを担当する一年生は、今回、400本のトマト苗を鉢上げしました。
これらの苗は、11月20日頃には、栽培圃場へ定植する予定です。




ナシ園の土壌改良! R5.11.8
園芸学科果樹経営コースのナシ班では、現在、ナシ園の土壌改良に取組んでいます。
11月8日(水)には、二年生と一年生が土壌改良場所の穴掘り作業を行いました。
バックホーを使った二年生は、ナシの樹1本につき、長さ100cm、幅50cm、深さ50cmの穴を掘っていきました。
今後、この穴には、ナシの落ち葉を入れ、掘り上げた土には、バーク堆肥や苦土石灰、パーライトを混ぜて埋め戻す予定です。
ナシ園の土壌改良は、12月中旬までに終え、その後、剪定作業に移行する予定です




白オクラ種子の催芽処理のコツを学びました! R5.11.8
園芸学科の野菜経営コースでは、白オクラ種子の発芽率向上を目指した経営プロジェクトに取り組んでいます。
担当学生は、これまで、白オクラの発芽率を向上させるためには、充実した種子の確保や種子への催芽処理が不可欠であることを学んできました。
11月8日(水)には、長門農林水産事務所を訪れ、職員の方から催芽処理の方法について学びました。
担当学生は、職員の方から指導を受けながら、白オクラ種子への傷のつけ方と程度を学び、実際に鉄ヤスリを使用して催芽処理を行い、そのコツをつかみました。
また、より多くの種子に対して、効率的かつ効果的な催芽処理方法の検討も必要と考えています。
本プロジェクトは12月いっぱいで終了しますが、課題解決に向けて今後も引き続き取り組んでいく予定です。
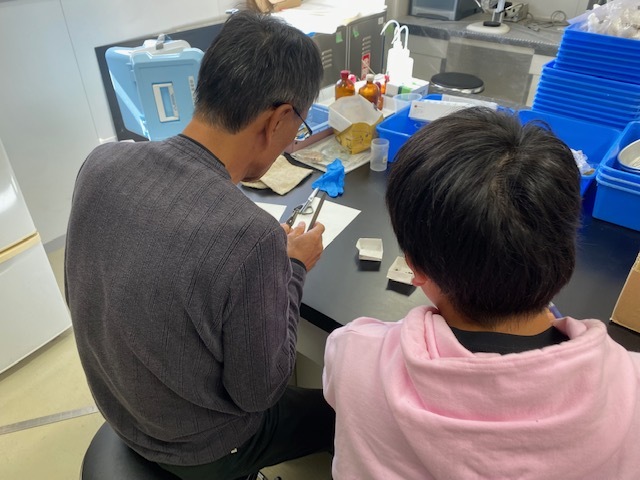
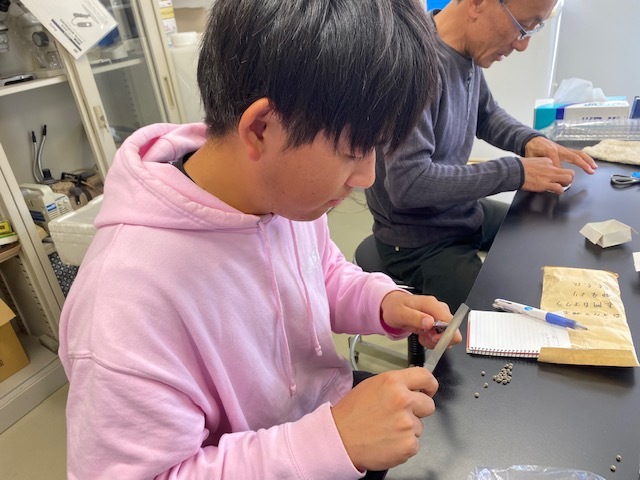

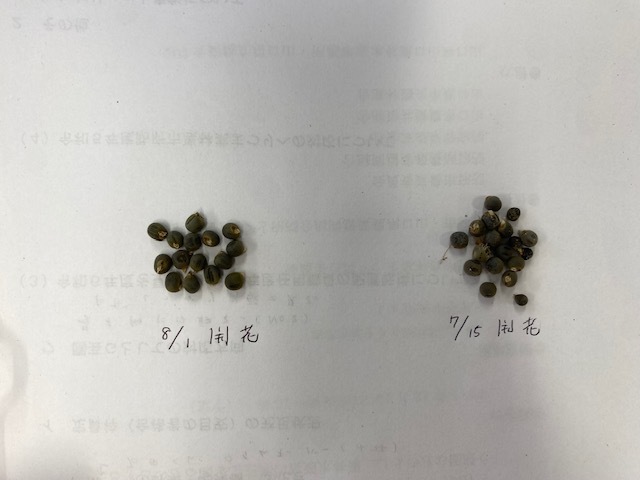
白オクラの採種用果実の収穫! R5.11.6
園芸学科の野菜経営コースでは、白オクラ種子の発芽率向上を目指した経営プロジェクトに取り組んでいます。
本プロジェクトでは、「長門白オクラ部会」の部会長さんからのアドバイスを受けて、7月の梅雨時期、8月上旬、9月中旬に開花し、結実した果実から種子を採取し、発芽率を比較することにしています。
11月6日(月)、担当の二年生が、採種用として残しておいた果実の収穫を行いました。
ただし、今回9月開花の果実は未熟であったため、11月下旬頃まで待って収穫することとしました。
今後は、収穫した果実から種子を取り出し、発芽率の調査を行う予定です。




極早生ミカンの果実品質調査! R5.11.7
園芸学科の果樹経営コースでは、植物成長調節剤による極早生ミカン「日南1号」の果実品質向上に関する生産プロジェクトに取り組んでいます。
11月7日(火)、このプロジェクトを担当する一年生が、収穫した果実の品質調査を行いました。
今回、植物成長調節剤を散布した区と散布しない区の果実各10個について、果実の横径や着色程度、重さ、糖度、酸度を調べました。
一年生は、教官の指導を受けながら、慎重に調査を行っていました。


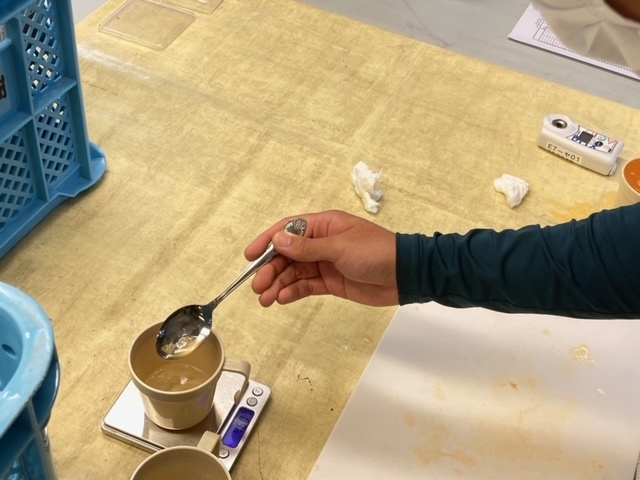

高収量イチゴ生産者への視察! R5.11.1
園芸学科の野菜経営コースでは、移動式高設栽培システムや統合環境制御システムを備えたスマート生育環境制御ハウスを活用したイチゴの経営プロジェクトに取り組んでいます。
11月1日(水)、本プロジェクトを担当する一年生が、山口農林水産事務所が行ういちごの定点調査に同行し、山口市内の高収量いちご生産者のハウスを訪問しました。
担当学生は、生産者の方や同行した農業革新支援専門員より、管理方法や生育状況について、説明や指導を受け、自らのいちごの状況との違いなどを感じとっていました。
また、担当学生はいちごの生育判断方法や冬季の温湿度管理などの質問を積極的に質問していました。
この視察から学んだ情報は、学生にとって貴重なものであり、今後のイチゴの栽培管理に活かされることでしょう。
本視察は、今後も定期的に実施し、次回は12月に予定しています。




メロンの果実品質調査! R5.10.31
11月3日に開催される「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」に向け、園芸学科の野菜経営コースでは、販売物の準備を進めています。
10月31日(火)には、拠点祭で販売するメロンの果実品質を調査しました。
拠点祭では、緑肉系の「ミラノ夏I」と赤肉系の「妃(きさき)」をいう2つの品種を販売する予定ですが、今回は「妃」の果実重や糖度の測定ならびに試食を行いました。
果実は1㎏弱の重さで、目標のLサイズでしたが、糖度は前日収穫したこともあり、目標糖度には達しませんでした。しかし、その後の試食では、充分な甘みや食味が感じられ、上々の仕上がりであることが確認できました。
また、先だって昨日調査を行った「ミラノ夏Ⅰ」については糖度13.5度を記録しており品質はばっちりです。
11月3日の拠点祭にぜひお越しいただき、メロンをお買い求めください。


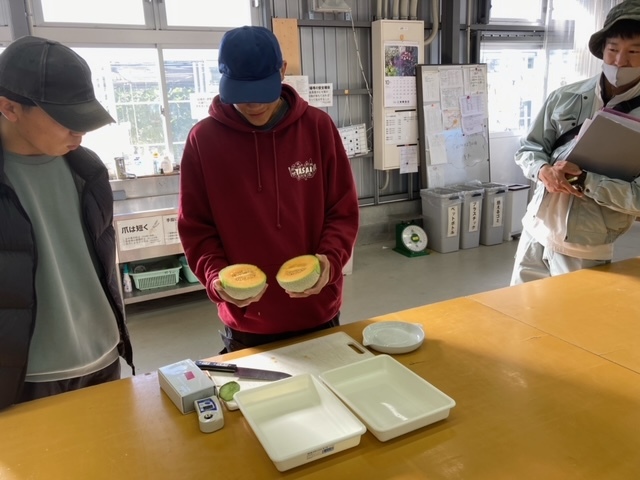
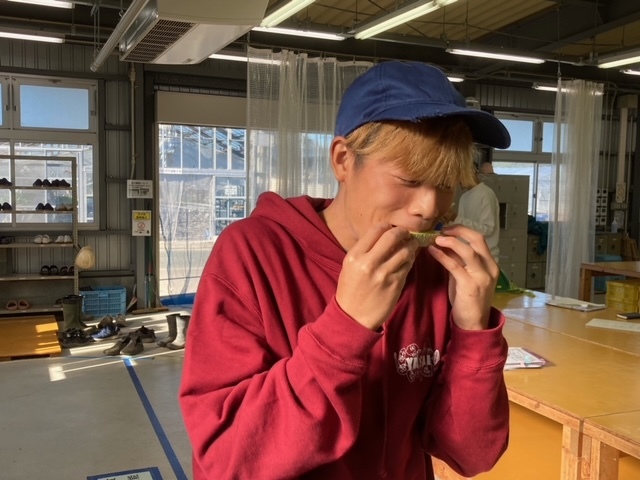
ブドウ園の土壌改良【土壌改良資材の混和・埋め戻し】!
R5.10.31
現在、園芸学科果樹経営コースのブドウ班では、ブドウ園の土壌改良に取り組んでいます。
先日、ガラス温室内のブドウの樹の周辺に溝を掘ったところですが、10月31日(火)には、掘り上げた土に、バーク堆肥、炭酸苦土石灰などを施しました。
その後、レーキを使って、土とバーク堆肥などをしっかり混ぜながら、溝穴に埋め戻していきました。
土壌改良は手間のかかる作業ですが、根の成長と働きやすい環境を整えることは、おいしいブドウの収穫につながることから、学生や研修生たちは、この大切な作業を丁寧に行っていました。




トウモロコシの試し採り! R5.10.31
園芸学科の野菜経営コースでは、本年度、パイプハウス等で、トウモロコシの抑制栽培に挑戦しています。
育てている品種は、黄粒種の「おひさまコーン88」と白粒種の「ホイップコーン」の2品種です。
8月中下旬に播種したトウモロコシは順調に生育しており、雌穂の絹糸も褐変しかけていることから、収穫時期を確認するため、10月31日(火)に、試し採りを行いました。
収穫後、雌穂の状態を確認したところ、先端まで実が詰まり、病害虫の被害も見当たらず、上々の状態でしたが、果粒の色や膨らみは十分でなく、収穫にはもう一週間程度かかると判断しました。
翌週に、再度試し採りを行い、改めて収穫時期を確認する予定です。




拠点祭用のパンジー・ビオラの花がら摘み! R5.10.30
11月3日に開催される「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」への出荷に向け、園芸学科の花き経営コースでは、最後の仕上げに入りました。
10月30日(月)には、拠点祭で販売するパンジー・ビオラの、出荷前の仕上げの作業として、花がら摘みを行いました。
花がら摘みは、咲き終わってしおれた花を取り除く作業で、咲き終わった花をそのままにしておくと、結実により養分を消費して株が弱ったり、病気の原因になったりするので、こまめに花がらを取り除く必要があります。
学生たちは、一鉢一鉢、花がらを確認しながら、丁寧に取り除いていました。



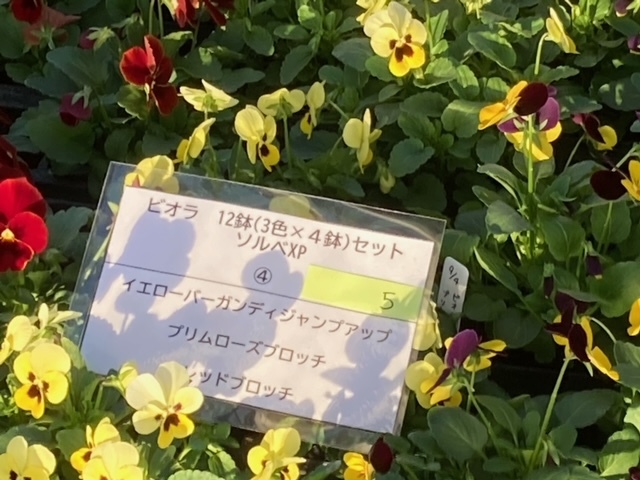
やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました!R5.10.29
10月29日(日)、農業大学校において、受講生5名を対象に作目基礎研修の「農業機械コース」を行いました。
当日は、スマート農業の概要説明とともに、その一例として県内で研究開発を進めている「タマネギ直播栽培」の実証状況を見学しました。
受講生たちは、先進的なスマート農業の現状について、興味深げに熱心に聴講していました。


ブドウ園の土づくり【土壌改良場所の溝掘り】! R5.10.27
落葉果樹のブドウは、収穫も終わり、これから、気温の低下とともに落葉が始まる頃です。
こうした中、園芸学科果樹経営コースのブドウ班では、ブドウ園の土づくりを始めました。
10月27日(金)には、ガラス温室内の土壌改良場所の溝掘りを行いました。
施設内の棚下での作業のため、重機が使えないことから、学生たちと研修生は、スコップを使って溝を掘り上げました。
昨年土壌改良した場所とは違う場所で、根が伸びている場所を選んで、幅30cm、深さ30cmの溝を、3列掘りました。
今後、全ての園地で土壌改良用の溝を掘った後、掘り上げた土に、バーク堆肥や石灰資材等を混ぜて、埋め戻す予定です。


ジャガイモの生育調査! R5.10.26
園芸学科野菜経営コースは、ジャガイモのマルチ栽培に関する経営評価を行なう経営プロジェクトに取り組んでいます。
10月26日(木)には、担当の二年生が、毎週行っている生育調査を行いました。
生育調査では、調査区毎に選定した代表的な株、10株の草丈を測定しました。
学生は、一株一株、丁寧に測定を行っていました。
本調査は、収穫が行われる12月上旬まで続ける予定です。




せとみ・不知火の徒長枝(とちょうし)除去! R5.10.25
園芸学科の果樹経営コースでは、パイプハウス内で中晩生柑橘の「せとみ」と「不知火(しらぬい)」を栽培しています。
このパイプハウスでは、11月中旬ごろにビニルを被覆する予定ですが、被覆するビニルを傷めないよう、ハウス天井部付近まで伸びている徒長枝は除去する必要があります(徒長枝とは、樹勢が良好あるいは強い樹に発生する、長く太い枝のこと)。
そこで、10月25日(水)、かんきつ班の二年生が、徒長枝を除去しました。
学生は、高所作業のため、脚立を使用しましたが、慎重に、徒長枝を切除していました。
この「せとみ」と「不知火」は、来年の1月下旬頃に収穫する予定です。


来年に向けて土づくり 堆肥をまいて耕耘 R5.10.25
水稲の収穫も無事終わりました。土地利用学科では、10月12日(木)以降、来年に向けた土づくりに取り組んでいます。堆肥を圃場にまいて、軽く耕耘しておくわけですが、大量の堆肥を一度に運ぶことができませんので、1圃場ずつ行っています。
使う堆肥は、もちろん畜産学科がつくった農大の堆肥。学生が機械を操作して運搬車に上手に積み込み、運搬役の学生が圃場までひたすらピストン輸送。圃場で待機している学生がどんどん圃場にまいていきます。
堆肥をまき終われば、トラクタでさっと耕耘。トラクタで耕耘する機会も多いようで少ないもの。貴重な実習機会なので、耕耘する学生も圃場毎に代わり、皆が少しずつ経験を積むようにしています。
10月25日(水)、ようやく5圃場目が終わりました。今後もしばらく、堆肥散布と耕耘が続きます。




トマトの接ぎ木! R5.10.25
園芸学科の野菜経営コースでは、高糖度トマト生産に向けた塩分ストレス栽培に関する経営プロジェクトに取り組むこととしています。
このプロジェクトの一環として、10月25日(水)、プロジェクトを担当する一年生が、トマトの接ぎ木を行いました。
今回、栽培適応性が高い「アンカーT」という品種を台木とし、低温伸長性にすぐれ、黄化葉巻病に耐性のある「桃太郎ホープ」という早生品種を穂木としました。
一年生は、合わせ接ぎを行うため、カミソリの刃を使って、切り口の角度がそろうよう台木と穂木を切り取った後に接いで、接ぎ木チューブで固定しました。
この日、担当の一年生は、他の一年生の協力も得て、600本の接ぎ木苗を作成しました。これらの苗は、2週間後に鉢上げを行い、11月下旬に定植する予定です。




ガラス温室内の暖房機の掃除! R5.10.25
10月に入り、朝晩の寒さを感じるようになり、施設内で育てている作目によっては、11月に入ると暖房が必要となる時期です。
このため、園芸学科の花き経営コースでは、10月25日(水)に、ガラス温室内の暖房機の掃除を行いました。
学生たちは、暖房機内のススを除去し、着火部位の掃除を行った後、試運転を行い、着火や燃焼、温風の排出が正常に行われるか確認しました。
花き経営コースで管理する施設内の暖房機の掃除は、翌日までに完了する予定です。




葉ネギの収穫物調査! R5.10.25
園芸学科の野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、高温期の積極的な潅水が葉ネギの葉先枯れの発生や外観品質に及ぼす影響について調査しています。
「やまひこ」と「ブラックキング」という2品種を供試し、8月下旬に、ガラス温室内の隔離ベンチに種を撒きました。
播種から2カ月経過した10月25日(水)、担当の二年生は、葉ネギを収穫するとともに、その後、収穫物に関する調査を行いました。
調査内容は、収穫時や調整後のネギの重量、本数、葉先枯れの程度、葉色、葉の強度の測定です。
今回の調査では、どの調査区でも、葉先枯れは観察されませんでしたが、全体的にネギが細いという結果が得られたようです。今後、この原因について検討する予定です。




サツマイモの収穫! R5.10.25
園芸学科の野菜経営コースでは、10月25日(水)、サツマイモの収穫を行いました。
前日、一部の畝に振動掘取機を使ってイモを収穫しやすくしましたが、この日は、残りの畝に振動堀取機を使用しました。
その後、学生と研修生が協力し、サツマイモを掘り上げていきました。
学生たちは、良型のイモを次々と掘り上げ、コンテナに入れていました。
今回収穫したのは、「紅はるか」と「ふくむらさき」という品種です。
収穫量は、「紅はるか」が20コンテナ、「ふくむらさき」が18コンテナに達し、充分な収穫を得ることができました。
収穫したイモは、キュアリング処理を行った後、直売所や11月3日に開催される「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」で販売する予定です。お楽しみに。




サツマイモの収穫準備! R5.10.24
園芸学科の野菜経営コースでは、10月24日(火)、サツマイモの収穫準備を行いました。
まず、学生や研修生たちは、鎌を使ってサツマイモのつるを取り除き、その後、畝を覆っていたマルチを取り除きました。
次に、トラクターに装着した振動掘取機を使って、土の中を掘るとともに、振動を加えることで、地中に埋まったイモを周囲の土壌から離れやすくしました。
このほ場のサツマイモは、翌日に収穫する予定です。




「花回廊」用のベゴニア・マリーゴールドの播種! R5.10.20
毎年4月中旬から5月上旬に、防府天満宮では、「花回廊」として大石段を花鉢で飾る行事が行われており、農業大学校も花鉢の準備に協力しています。
10月20日(金)には、園芸学科花き経営コースにおいて、この花鉢用のベゴニアやマリーゴールドの種を撒きました。
学生たちは、200穴のセルトレイに培土を充填した後、ベゴニアは真空播種機を使用し、マリーゴールドはピンセットを使って、一粒ずつ種を撒きました。
今回播種した品種は、ベゴニアでは赤色の「スプリントプラス レッド」など3品種、マリーゴールドでは黄色の 「ホットパック イエロー」など3品種です。
播種したセルトレイは、育苗ハウスに移し、発芽後、約4週間育苗した後、鉢上げを行う予定です。




デジタルコンテンツ授業を実施! R5.10.24
学生が動画制作等のデジタルコンテンツ作成の技術習得に向けた授業を10月17日に受講しました。
講義は、TVCMやイベント等の映像制作会社に委託して行い、動画制作にむけストーリーの作り方や映像の取り方等を学んでいました。
今後は、土地利用学科を中心に農業機械メンテナンス等の動画を演習で作成していき、将来的に講義・実習等を効率的に実施するための動画を学生自ら製作する予定です。


4年ぶりに農大生のつどいを山口県で開催! R5.10.24
第38回中国ブロック農業大学校研修生等のつどいが、10月18日~19日に山口県で開催されました。中国地方の大学校生が交流を深め、農業就業に向けた認識を高めることを目的として4年ぶりの開催となり、参加したのは、担当の山口県立農業大学校と鳥取県立農業大学校、島根県立農林大学校、岡山県農林水産総合センター農業大学校、広島県立農業技術大学校です。
初日はソフトボールと卓球の部に分かれてスポーツ大会を行いました。ソフトボールでは、秋空の下、打って走って守り、勝っても負けても楽しんでおり、終わる頃にはみんな打ち解けていたようです。夜は交歓会を実施し、志を同じにする同世代との交流を充実させていました。
2日目に、他県の大学校の参加者は、農林総合技術センターの知と技の拠点施設等を見学して帰られました。
来年度は広島県で開催される予定です。本校学生は「この繋がりを大切にしたい」と挨拶し、また来年を楽しみにしているようでした。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました R5.10.23
10月22日(日)、農業大学校において、受講生5名を対象に作目基礎研修の「農業機械コース」を行いました。
当日は、トラクタの構造の説明とともに、耕耘爪の交換やオイル交換などの基本メンテナンスの実際を体験しました。受講生たちは初めて経験する者が多く、非常に興味深げに熱心に取り組んでいました。
特に、作業に使用する工具類の種類や効率的な使い方は非常に参考になったものと思われます。



JGAP維持審査を受けました! R5.10.23
本校では、GAP(農業生産工程管理)をカリキュラムに取り入れ、平成31年1月にはJGAP認証を取得し、現在の認証品目はトマト、ミニトマト、ブドウです。
JGAP認証は2年間有効ですが、その期間中にも、継続して認証基準を満たす運営ができているかを評価する維持審査を受ける必要があります。
10月23日(月)には、その維持審査を受けました。
書類審査では、園芸学科の二年生が対応しました。二年生は、4月から審査に向けた準備を継続的に行ったとともに、8月には模擬審査を受けたこともあり、当日は、審査員の質問に的確に答えていました。
また、現地審査では、ミニトマトの収穫・調整工程の確認が行われました。野菜経営コース一年のミニトマト担当の学生が実演し、落ち着いて、普段通り行っていました。
今回、山口農業高等学校の生徒さんも参加され、審査の様子を見ていただきました。
審査の最後には、審査員から審査結果の説明があり、数点の是正を求められました。
今後、是正を行い、審査機関に報告した後、問題がなければ認証が継続されます。

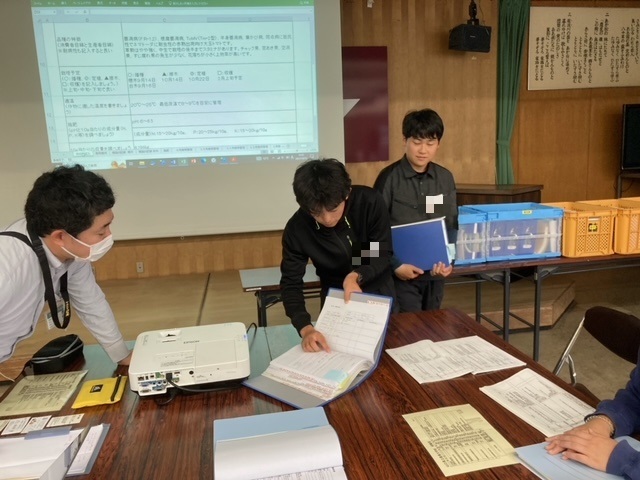
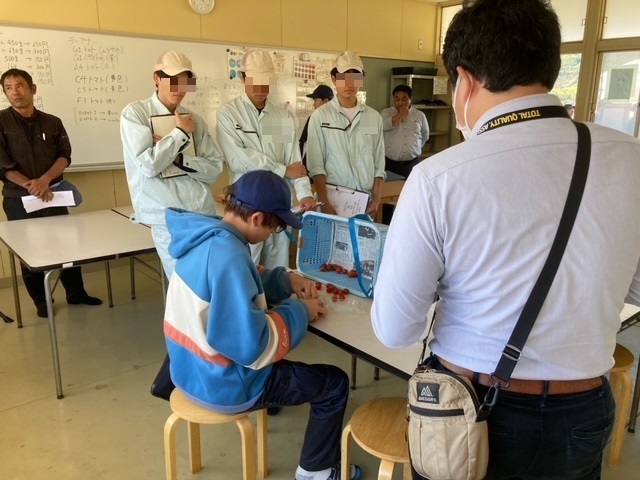
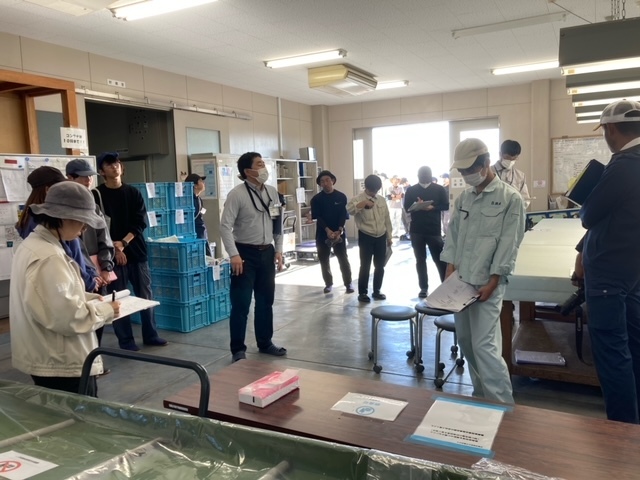
野菜専攻 大掃除! R5.10.20
園芸学科野菜経営コースでは、10月20日(金)に大掃除を行いました。
園芸資材庫の野菜専攻のスペースでは、秋冬野菜の植付けが一段落したこともあり、マルチシートをサイズ別に整理したり、再利用するビニールも適切な場所に戻しました。
肥料庫では、床を徹底的に掃除するとともに、棚上をきれいに拭いていました。
掃除を行った学生たちは、10月23日にJGAPの維持審査が控えているため、通常より一層力を入れて掃除に取り組んだようです。




経営プロジェクト中間発表会を開催しました! R5.10.19
園芸学科では、10月19日(木)、経営プロジェクトの中間発表会を行いました。
今回の課題は、当学科が力を入れているGAP(農業生産工程管理)に焦点を当てた『農薬散布機の洗浄方法の検討とルール化』です。
この課題を担当する果樹経営コースの二年生は、調査内容、結果、現時点での考察を詳しく説明し、果樹で使用される農薬散布機「スピードスプレイヤー」を展示し、洗浄手順をホワイトボードに示すなど、参加者が理解しやすいよう工夫をしていました。
また、参加した学生からの質問に対しても、丁寧に回答していました。
次回の発表会は未定ですが、10月26日には、これまでの課題のうち、発表会で答えきれなかった質問に対応する場を設ける予定です。




JGAP維持審査に向けた収穫・調整工程の確認【ミニトマト】! R5.10.19
本校では、GAP(農業生産工程管理)をカリキュラムに取り入れ、平成31年1月には、トマトとミニトマトでJGAP認証を取得しています。
JGAP認証は2年間有効ですが、途中で維持審査を受ける必要があります。
今年は、維持審査を受ける年で、審査日は10月23日です。
こうした中、園芸学科野菜経営コースでは、10月19日(木)に、審査で実演予定である、ミニトマトの収穫・調整工程の確認を行いました。
ミニトマトを担当する1年生は、教官とともに、本校で定めた収穫・調整工程と実際の作業が整合しているかを、工程ごとに確認しました。
審査当日は、緊張せず、普段通りのパフォーマンスを期待しています。



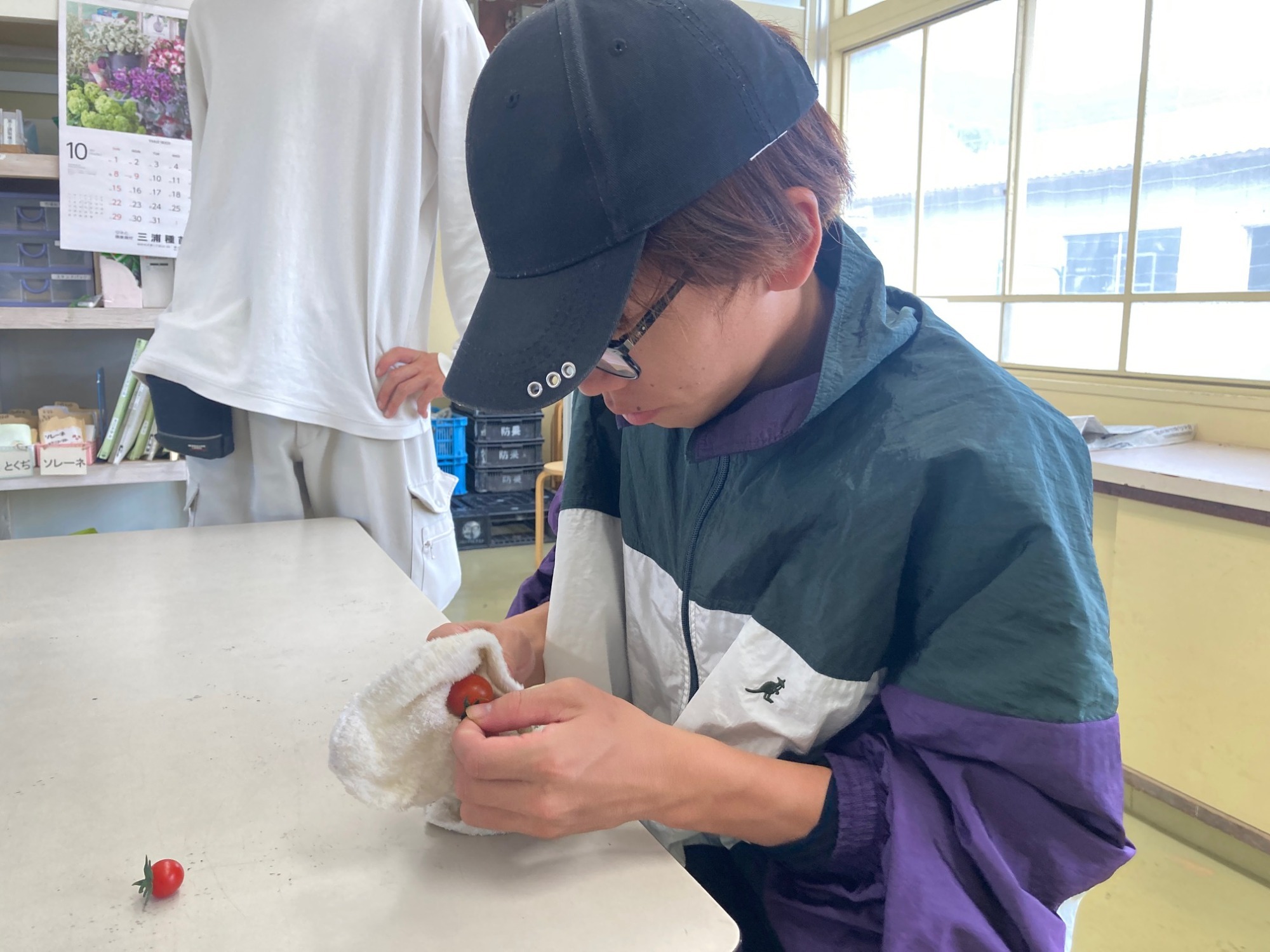
ブロッコリーの生育調査! R5.10.18
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
10月18日(水)には、担当の2年生が、毎週行っている生育調査を行いました。
生育調査では、最大の葉の長さと幅を測定し、ブロッコリーの順調な生育を確認しました。
10月20日には初めての出荷が予定されていますが、春作では収穫が遅れたため、目標とした大きさの花蕾が収穫できなかった経験から、担当の学生は、今作こそは適切なタイミングで収穫すると意気込んでいました。




極早生ミカンの収穫! R5.10.18
園芸学科果樹経営コースでは、10月18日(水)、極早生ミカンの収穫を開始しました。
今回収穫した品種は、「日南1号」で、さわやかな香りと味わいが特徴です。
収穫作業は、かんきつ班の1年生とナシ、ブドウ班の1、2年生が行いました。
学生は、果実の着色状況を丁寧に確認するとともに、果実を傷つけないように注意しながら、ハサミを使って収穫を行いました。
収穫したミカンは、10月20日から、防府市や周南市の直売所に出荷するとともに、11月3日に開催する「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」にも出荷する予定です。
今年は、夏以降の降水量が少なかったため、果実品質は上々ですので、ぜひお買い求めください。




サツマイモの試し掘り! R5.10.17
園芸学科野菜経営コースでは、サツマイモ栽培に取り組んでおり、今年は「紅はるか」と「ふくむらさき」という品種を育てています。
「紅はるか」は、ねっとりとした食感と甘みが特徴で、「ふくむらさき」は、紫色の果肉としっとりとした肉質が特徴です。
5月の定植からおおよそ130日程度経過したことから、10月13日(金)に試し掘りを行いました。
担当の1年生は、スコップなどを使って、一部の株を掘り起こし、さまざまな大きさのサツマイモを収穫しました。
このサツマイモは、3~4日間、高温多湿環境でキュアリング処理を行った後、試食する予定です。
残ったサツマイモは、10月25日に収穫を予定しています。




メロンの袋かけ! R5.10.17
園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室でメロンの栽培に取り組んでいます。
9月中旬の交配後、果実は日々大きくなるとともに、ネットの形成も進んでいます。
10月4日(水)には、担当の1年生が、メロンの果実に袋かけを行いました。
袋かけは、果実を日焼けから守るために行うもので、新聞紙とホッチキスを使って果実を覆っていきました。
メロンの収穫予定は、11月上旬頃です。




イチゴの生育調査! R5.10.17
園芸学科野菜経営コースでは、移動式高設栽培システムや統合環境制御システムを備えたスマート生育環境制御ハウスを活用したイチゴの経営プロジェクトに取り組んでいます。
本プロジェクトでは、定植した株の生育調査として、葉数や葉長、草高などを調査することとしており、10月4日(水)には、1回目の調査を行いました。
担当の1年生は、2年生に手伝ってもらいながら、慎重に調査を行っていました。
本調査は、2週間に1度行うこととしており、次回は10月18日に行う予定です。




充電式ロボット草刈機 稼働準備! R5.10.16
10月13日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、ブドウ園で充電式ロボット草刈機を稼働させるための準備を行いました。
ロボット草刈り機の稼働範囲を決めるエリアロープは8月に設置済みのため、この日は、ロボット草刈機本体と充電ステーションを移設しました。
教官の指導のもと、学生や研修生らは、充電ステーションの配線やロボット草刈機と充電ステーションのペアリングを行いました。
すべての準備が整った後、ロボット草刈機の電源を入れたところ、充電ステーションから出発して、わずか30cm先で停止しました。
この原因は、教官のスマートフォンに「エリアワイヤ未接続」の表示がされたため、すでに設置していたエリアロープが断線している可能性が高いと判断されました。
その後、学生らは、エリアロープ断線の確認を行いましたが、この日は、断線箇所を特定できなかったため、ロボット草刈機の稼働は翌日以降に延期となりました。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました R5.10.15
10月15日(日)、農業大学校において、受講生33名を対象に作目基礎研修の
「野菜Ⅰコース(施設野菜)」と「野菜Ⅱコース(露地野菜)」と「果樹コース」を併行して実施しました。
当日は、コース別に、イチゴのマルチ張りホウレンソウの間引き、レタスの定植、果樹の土壌改良対策などについて、説明及び実習を行いました。
爽やかな秋晴れの下、受講生たちは熱心に聴講するとともに、実習に汗を流していました。



ジャガイモの土寄せ! R5.10.13
園芸学科野菜経営コースでは、ジャガイモのマルチ栽培に関する経営評価を行なう経営プロジェクトに取り組んでいます。
ジャガイモの定植から1ヵ月が経った10月13日(木)、マルチを覆っていない調査区のジャガイモに「土寄せ」を行いました。
この「土寄せ」は、根圏の拡大に伴う収量の増加や雑草の発生抑制、茎葉の倒伏防止を図るために行うものです。
担当の学生は、事前に肥料を施すとともに、畝間の土を柔らかくするため、管理機を使用して耕うんしました。
その後、管理機を使用して、ジャガイモの株元へ土を飛ばし、土寄せを行いました。
2週間後には、2回目の土寄せを行う予定です。




イチゴの株へのマルチ張り! R5.10.13
園芸学科野菜経営コースでは、10月4日(水)、ブドウ園で充電式ロボット草刈機を稼働させるための準備を行いました。
ロボット草刈り機の稼働範囲を決めるエリアロープは8月に設置済みのため、この日は、ロボット草刈機本体と充電ステーションを移設しました。
教官の指導のもと、学生や研修生らは、充電ステーションの配線やロボット草刈機と充電ステーションのペアリングを行いました。
すべての準備が整った後、ロボット草刈機の電源を入れたところ、充電ステーションから出発して、わずか30cm先で停止しました。
この原因は、教官のスマートフォンに「エリアワイヤ未接続」の表示がされたため、すでに設置していたエリアロープが断線している可能性が高いと判断されました。
その後、学生らは、エリアロープ断線の確認を行いましたが、この日は、断線箇所を特定できなかったため、ロボット草刈機の稼働は翌日以降に延期となりました。




果樹専攻 大掃除! R5.10.13
園芸学科果樹経営コースでは、10月13日(木)に大掃除を行いました。
果樹出荷調整棟では、ブドウなどの出荷が一段落し、これからカンキツの本格的な出荷が始まるため、施設内の掃除や出荷資材の確認を行いました。
学生らは、蛍光灯も一本一本外して汚れをふき取るとともに、普段目の行き届かない棚の上もきれいに掃除していました。
また、ブドウなどの出荷資材や道具は2階の資材保管庫に移すとともに、柑橘で使用する資材等は、1階へ移していました。
機械格納庫では、機械をいったん外に出し、床を掃いたり、不要なものを処分していました。
施設の掃除が終わった後は、施設やほ場周辺の水路を点検するとともに、水路に設置されている溜枡に溜まった泥や砂などを上げていました。
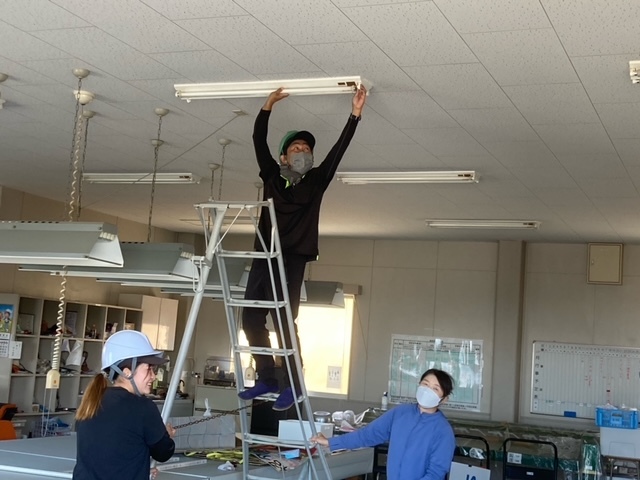
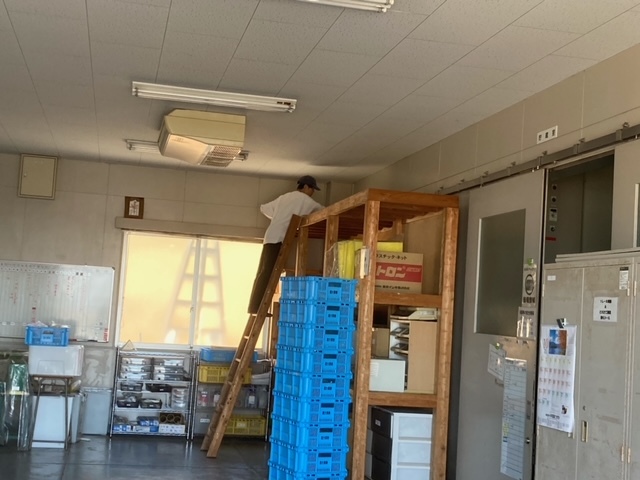


チドリソウの播種! R5.10.13
園芸学科花き経営コースでは、10月13日(木)、チドリソウの播種を行いました。
チドリソウは、キンポウゲ科の一年草で、スッと伸びた枝に穂のように花を咲かせることから、ブライダルブーケなど、幅広く利用される人気の高い花です。
今回、200穴のセルトレイ2枚に種をまいていきました。
担当の学生は、種を一粒ずつピンセットで挟んでは、セルトレイに充填した培土に種を撒いていました。
今回播種した品種は「ブルークラウド」で、花色が青紫色で、小さい一重の花がスプレー状に花を咲かせるのが特徴です。
播種したセルトレイは、約一カ月育苗ハウスで育苗した後、パイプハウスに移植する予定です。


経営プロジェクト中間発表会を開催しました! R5.10.12
園芸学科では、10月12日(木)、経営プロジェクトの中間発表会を行いました。
今回、果樹経営コースの2年生2名が、それぞれが担当した課題を発表しました。
一つは『ナシのIPM防除体系の検討』、もう一つはブドウの課題で『摘粒ゼロに向けた果房管理法の検討』です。
発表した学生らは、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を詳しく説明するとともに、専門用語をわかりやすく説明したり、ホワイトボードに試行した技術を描くなど、参加者が課題に対する理解を深めるよう工夫をしていました。
さらに、参加した学生や研修生からの質問に対しても、担当学生たちは丁寧に答えていました。
次回の発表会は、10月17日に行い、ネギとカンキツに関する課題が発表される予定です。




うんとこしょ どっこいしょ 出てくるお芋は でっかいぞ R5.10.12
土地利用学科では、11月3日(金・祝)に開催される「やまぐち農林業の知と技の拠点祭」で焼き芋を販売することにしています。10月10日(火)、その焼き芋用に栽培してきたサツマイモの掘り取り作業を行いました。
ます、振動掘取機を使って、サツマイモが埋まっている畝の土をほぐしていきます。あとは、サツマイモを手で引き抜くだけ。少し力は要りますが、全て手作業で掘り取っていくよりは格段に楽です。
さて、畝の中から引き抜かれるサツマイモ、まぁ、その大きいこと、大きいこと。これが芋掘り体験会であったなら、子供たちが大喜びしそうなサツマイモ達がゴロゴロ出てきました。ただ、今回の栽培の目的は「焼き芋用のサツマイモ」を作ること。焼き芋に相応しいサイズは半分くらいでしょうか? あとで弩級サツマイモ達の使い道も考えなければいけませんね。




経営プロジェクト中間発表会を開催しました! R5.10.10
園芸学科では、10月10日(火)、経営プロジェクトの中間発表会を行いました。
今回、果樹経営コースの2年生2名が、それぞれが担当した課題を発表しました。
一つは『ブドウの副梢管理の省力化技術の検証』、もう一つは『充電式草刈ロボットを利用したカンキツ園の雑草管理の省力化』です。
発表した学生らは、ホワイトボードに調査区を描いたり、調査に使用した道具や機材を紹介するなど、参加者が課題に対する理解を深めるよう工夫をしていました。
さらに、参加した学生や研修生からの質問に対しても、担当学生たちは丁寧に答えていました。
次回の発表会は、10月12日に行い、ナシとブドウに関する課題が発表される予定です。
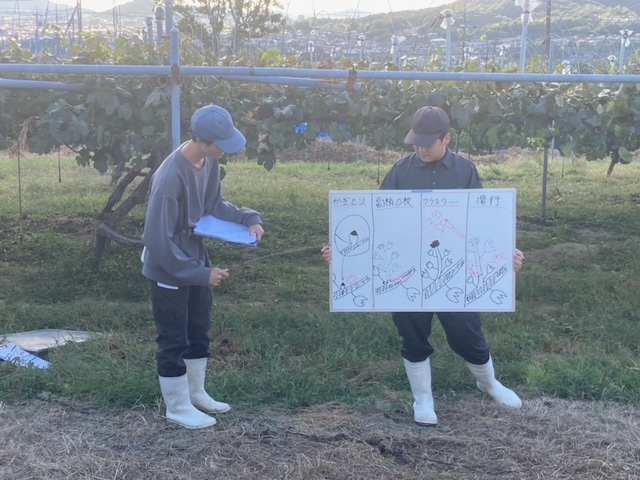

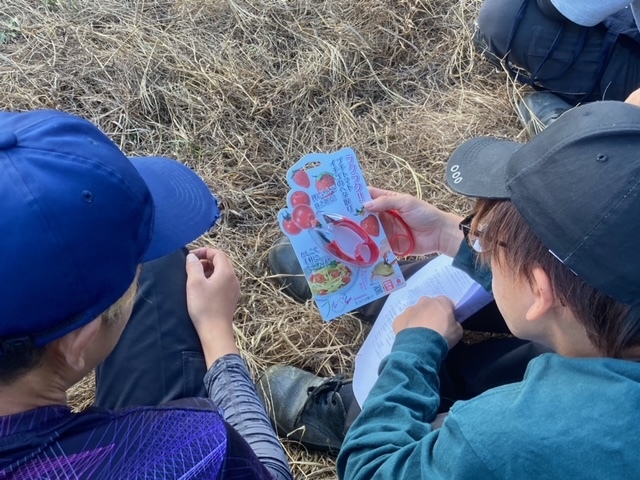

ライスセンターを見学、袋詰めの実習! R5.10.5
土地利用学科は、大規模な乾燥調製について学ぶため、10月5日(木)、JA山口県大道ライスセンターで実習を行いました。
最初にJA山口県の職員から、ライスセンターの作業の流れ(荷受け→乾燥→調製→袋詰め)について説明を受けました。いずれの機械も農大の機械とは比べ物にならない程大きいものですが、その構造や仕組みは同じでしたね。
説明のあとは、いよいよ玄米の袋詰めの実習です。作業としては、米袋に玄米を詰めてパレットの上に積み上げていくだけですが、玄米を米袋へ入れる方法、米袋の縛り方、米袋をベルトコンベアに楽に乗せる方法や受け取る姿勢、パレットの上に米袋を乗せる順番や崩れにくい乗せ方等など、全ての動作にポイントがあります。学生達は、それらポイントについて、JA職員から一つ一つ丁寧に教えてもらっていました。玄米をこぼしたり、ベルトコンベアへの乗せ方が悪くて袋に傷をつけてしまったり、と失敗もありましたが、その時の対処方法についても丁寧に教えてもらうことができ、今後の作業にも活かせる実習になったと思います。




経営プロジェクト中間発表会を開催しました! R5.10.5
園芸学科では、10月5日(木)、経営プロジェクトの中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『ジャガイモのマルチ栽培が労働性や収量性に及ぼす影響』で、野菜経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を詳しく説明しました。
参加した学生や研修生からは、マルチの有無が除草時間に及ぼす影響や生分解性マルチの導入が収益性に及ぼす影響に関する質問などが出され、担当学生は丁寧に答えていました。
また、発表会終了後には、参加者らは、ほ場に植えられているジャガイモを見て、マルチの被覆状況やジャガイモの生育状況を実際に確認し、本課題について理解を深めました。
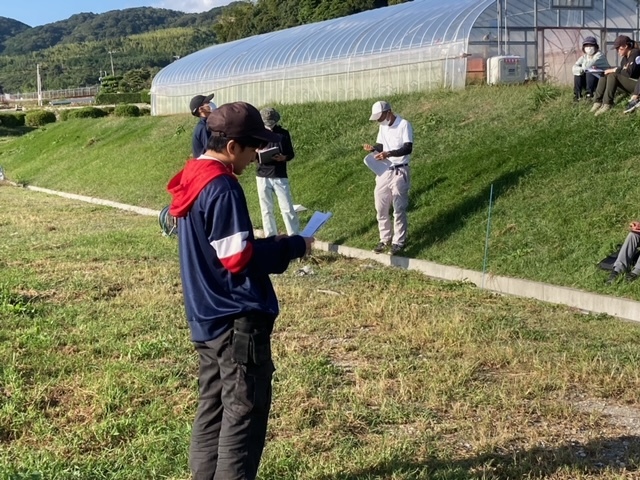



収穫・調製機械の清掃! R5.10.5
土地利用学科では、先週、主食用米「きぬむすめ」の収穫・乾燥調製を行いました。今週は、酒造好適品種「西都の雫」を収穫するため、10月2日(月)、コンバイン、乾燥機、籾摺機の清掃作業を行いました。
学生達は、機械の蓋やカバーを全て外し、コンプレッサー(圧縮した空気を噴射する機械)やブロワー(送風機)を使って、機械の中に残っている籾やゴミを取り除いていきます。時には乾燥機の中に入り(楽しそうでした)、また時には大量の粉塵(ふんじん)と闘いながら(マスクは必須ですね)、黙々と作業に取り組んでいました。
さあ、綺麗に清掃された機械たちを使って、いよいよ最後の稲刈りに臨みます。



「道の駅 ソレーネ周南」で8名の学生が販売実習を実施! R5.10.4
10月4日(水)、「道の駅 ソレーネ周南」において、土地利用学科の一年生1名、園芸学科の二年生4名と一年生2名、畜産学科の一年生1名の合計8名の学生が、販売実習に臨みました。
準備段階では、いくつかの課題に直面しましたが、実際に販売が始まると、学生たちは素晴らしい気配りを見せ、商品の整理や片付けを含む細部にまで気を配り、最後まで一生懸命に実習に取り組みました。
また、天候にも恵まれ、ほとんどの商品が売れ、学生たちは実習の成功に大いに満足しました。
次回の販売実習は、11月15日(水)に、同じ「道の駅 ソレーネ周南」で行う予定です。




経営プロジェクト中間発表会を開催しました! R5.10.3
園芸学科では、10月3日(火)、経営プロジェクトの中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『ブロッコリーの2花蕾どり栽培が収量に及ぼす影響』で、野菜経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を詳しく説明しました。
参加した学生や研修生からは、ブロッコリーの出荷規格と価格の関係、2花蕾どり栽培に係る施肥方法や労働時間、デメリットに関する質問が出され、担当学生は丁寧に答えていました。
また、発表会収量後には、参加者らは、ほ場に植えられているブロッコリーを見て、2花蕾どり栽培の仕立て方を実際に確認し、本課題について理解を深めました。
次回は、10月5日にジャガイモに関する課題の発表が行われる予定です。




「道の駅 ソレーネ周南」での販売実習に向けた準備! R5.10.2
10月4日(水)の午後2時より、「道の駅 ソレーネ周南」で販売実習を行います。
その準備のため、10月2日(月)に、当日対応する学生たちが打合せを行いました。
今回の打合せには、二年生と一年生が参加しました。
一年生はいずれも販売実習を経験済みのため、当日の役割分担や販売品目の紹介などを、二年生と協力してスムーズに決めていきました。
二年生は、一年生に任せるところは任せ、不安なところは手助けするなど、うまくリーダーシップを発揮していました。
販売実習当日も、一年生と二年生が協力して、素晴らしいおもてなしを提供できることを期待します。
ぜひ、10月4日(水)午後2時から「道の駅 ソレーネ周南」へ足をお運びいただき、新鮮な商品と学生の笑顔に出会いに来てください。
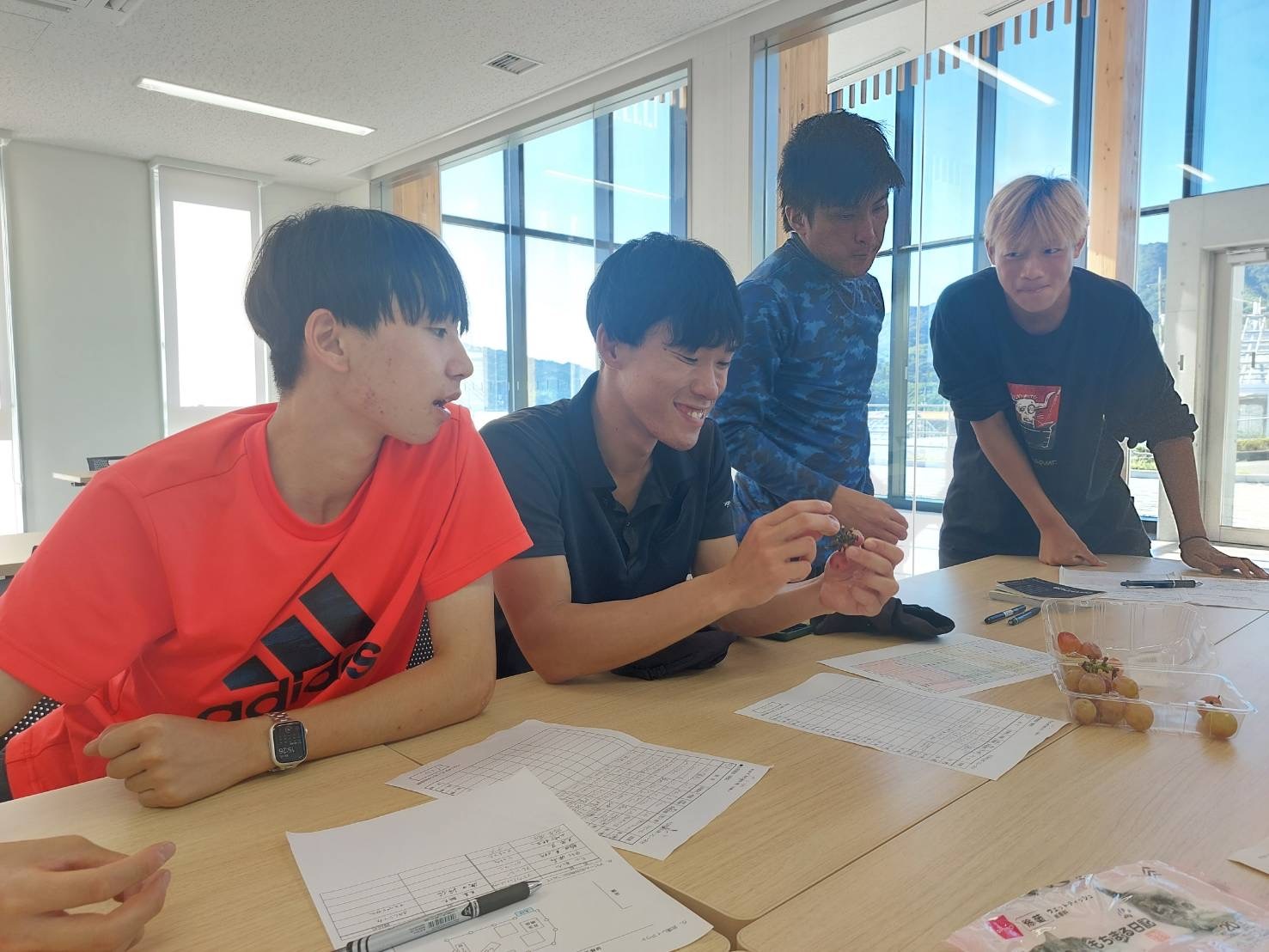
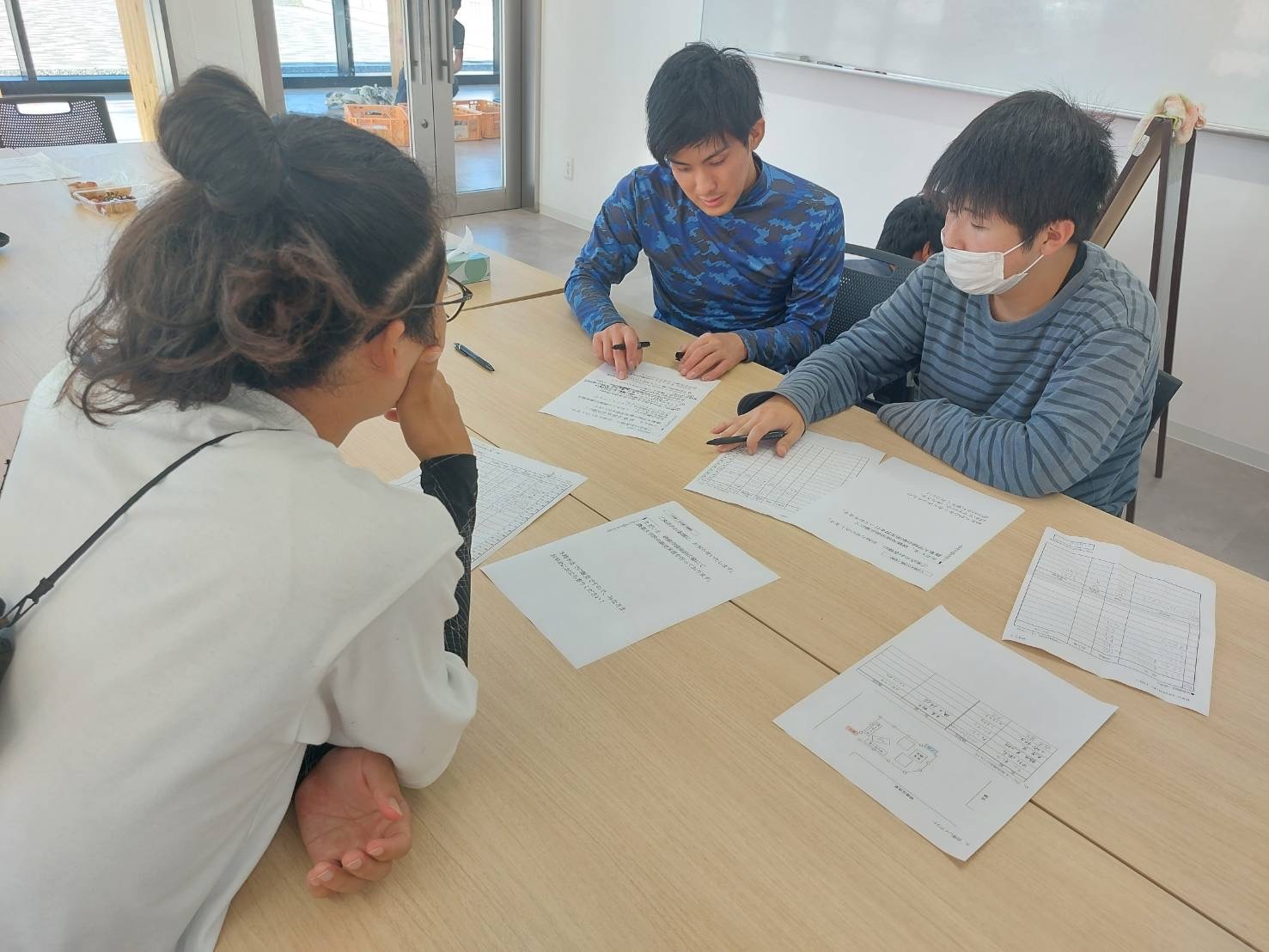


どんどん刈り取るぞ! あっ、しまった・・・ R5.9.27
9月27日(水)、土地利用学科は午前10時頃から2回目の稲刈りを行う予定でしたが、朝、予想もしなかった突然の土砂降り。急遽予定を変更し、昨日使った籾摺機(もみすりき)等の清掃作業を行いました。
そして午後、予定どおり2回目の稲刈りの開始です。品種は、主食用品種の「きぬむすめ」。4圃場のうち2圃場を収穫する計画であり、また午前中作業ができなかったこともあって、どんどんコンバインで刈っていきました。
今回の稲刈りも、作業はすこぶる順調、順調。コンバインには、何のトラブルもありません。が、最後の最後にトラブルが。気がついたときには乾燥機が既に満杯、圃場ではコンバインがまだ収穫作業中・・・ あー、これ絶対乾燥機に入りきらんわ・・・
結局、乾燥機に入れられない籾は、ゴザの上に広げて扇風機で乾かすことにしました。
農大の機械装備では、コンバイン8車分=乾燥機が満杯、忘れないようにしましょう。




「やまぐちオリジナルユリ」の定植! R5.9.25
園芸学科花き経営コースでは、二年生が、「やまぐちオリジナルユリ」をテーマとした経営プロジェクトに取り組みます。
そして、9月25日(月)には、研修中の二年生に代わって、一年生が、畝に潅水チューブの配置やフラワーネットを設置した後、やまぐちオリジナルユリの球根を植付けました。
球根を植え付けた後、土壌の乾燥と雑草を防ぐために、もみ殻で被覆しました。
今回定植した品種は、花色が鮮やかなオレンジ色の「プチソレイユ」です。10月上旬には淡いオレンジの「プチシュミネ」、ピンクの「プチロゼ」を定植します。
今後は試験区の設定を行うとともに、12月上旬の出荷を目指して管理を続けます。


タマネギの播種! R5.9.25
園芸学科野菜経営コースでは、9月25日(月)に、タマネギの播種を行いました。
この作業には、一年生と社会人研修生が参加し、まず、タマネギを育苗する畝に、畝の短辺方向に、間隔10㎝、深さ1cm程度の溝を掘り、次に、溝の中に、1~2cm間隔で種をまいていきました。
種をまいた後、軽く土をかぶせて籾殻(もみがら)をまき、最後に、不織布で覆いました。
今回播種した品種は、極早生の「貴錦」、中生の「ターザン」と晩生の「もみじ3号」で、11月中旬以降に掘り上げた苗を本ぽに定植するとともに、直売所での販売も予定しています。




やさあさ 刈り取れ 実りの秋だ 垂れる稲穂は 黄金色 R5.9.25
土地利用学科が初めて植えた「マンゲツモチ」がいよいよ収穫時期を迎え、9月25日(月)、初めての稲刈りを行いました。
初めての稲刈りでしたが、作業は何のトラブルもなく順調に進み、3時間弱で刈り終えることができました。機械のトラブルがなければ、教官も出番はありません。学生達が稲刈りする姿を、温かい目で見守るだけです。学生達がこの日のためにコンバインをピカピカに清掃し、きちんと整備してきた成果ですね!
明日は、籾摺り(もみすり:籾殻を取り除いて玄米にすること)、選別(玄米をふるいにかけて充実不良のものを取り除くこと)、袋詰めを行う予定です。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.9.25
9月24日(日)、農業大学校において、受講生25名を対象に作目基礎研修の
「野菜Ⅰコース(施設野菜)」と「野菜Ⅱコース(露地野菜)」を実施しました。
当日は、イチゴの植付けやホウレンソウ・レタス・タマネギの種まきなど、秋冬野菜の初期管理について学習しました。
秋晴れの下、受講生たちは爽やかな汗を流しながら実習に取り組んでいました。




秋の種まき「ダイコン」! R5.9.21
園芸学科野菜経営コースでは、9月21日(木)、ダイコンの播種を行いました。
学生や研修生は、畝を白黒マルチで覆った後、3~4条の千鳥状に植え穴を開け、そこに種をまきました。
当初は、ダイコンに加えて、カブも播種する予定でしたが、悪天候のため、ダイコンのみの播種としました。
今回植えた品種はミニダイコンの「ころっ娘(こ)」と青首総太り型の「YRくらま」です。
収穫は、「ころっ娘」が11月上旬、「YRくらま」が11月下旬から始める予定です。
なお、本日中止したカブの播種は、後日、天候やほ場条件が整ってから行う予定です。




「やまぐちオリジナルユリ」の定植準備【畝立て】! R5.9.21
園芸学科花き経営コースでは、2年生が、「やまぐちオリジナルユリ」をテーマとした経営プロジェクトを行うこととしています。
そして、9月21日(木)には、やまぐちオリジナルユリの定植準備として畝立て作業を行いました。
今回は、畝立成形機を使用して畝立てを行い、研修中の2年生に代わって、1年生が操作を行いました。
1年生は、教官に指導を受けながら、慎重に操作を行い、その結果、まっすぐで、均平な畝が完成しました。
今後、9月25日に球根を植え付ける予定で、12月上旬の出荷を目指して管理していきます。




メロンの玉吊りを開始! R5.9.21
園芸学科野菜経営コースでは、9月21日(木)に、ガラス温室で栽培しているメロンの玉吊りを始めました。
一か月前に定植し、約10日前に人工授粉を行いましたが、現在、果実は野球ボールくらいの大きさに成長しています。
玉吊りは、上からひもを垂らし、ひもの先につけたフックをメロンのへたの部分に引っ掛け、ひもで果実を支えます。
この作業の目的は、へた(アンテナ)をまっすぐ伸ばすことや、成長する果実の重みに対応すること、また、葉によって果実の表面に傷がつかないようにすることです。
担当の学生は、メロンを丁寧に扱いながら、玉吊りを実施しました。




実践ハウスへのイチゴの定植! R5.9.20
園芸学科野菜経営コースでは、地元企業と県が共同開発した移動式高設栽培システムや統合環境制御システムを備え、生産量の増加が見込めるスマート生育環境制御ハウス(「実践ハウス」)を活用したイチゴの経営プロジェクトを開始します。
9月20日(水)には、プロジェクトを担当する1年生が、イチゴ苗の定植を行いました。
定植作業の手順は、隔離ベッドの培土上にメジャーを張り、それを目印に、苗を20㎝間隔に2列配置した後、培土に植え込んでいきました。
この日、一部の苗に病気が見られたため、予定していた面積の約8割しか定植できませんでした。
今後、改めて苗を確保し、残りの隔離ベッドに苗を定植する予定です。




防府市まちの駅「うめてらす」での販売実習を実施! R5.9.20
本校では、9月20日(水)、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行いました。
今回参加したのは、土地利用学科の1年生3名、園芸学科の1年生4名、畜産学科の1年生2名です。
1年生のみでの対応となったため、準備に多少手間取ったり、レジも混雑したりもしましたが、観光バスで防府天満宮を訪れたお客様がたくさんお店に来てくださり、学生たちが積極的に売り込んだおかげで、ほとんどの商品が売り切れました。
販売実習後の反省会では、学生たちは、販売目標を達成したことに加え、お客さんへの声掛けや丁寧な接客ができたことなどから、手ごたえ感じました。しかし、スムーズな準備やレジ対応にもっと注意が必要であるとの反省も共有しました。
次回の販売実習は、10月4日(水)に、道の駅「ソレーネ周南」で行う予定です。




野菜経営コース、経営プロジェクト設計検討会を開催! R5.9.14
園芸学科野菜経営コースでは、9月14日(木)、一年生が秋からスタートする経営プロジェクトの設計検討会を行いました。
経営プロジェクトは、本校のカリキュラムの一環であり、最終的に卒業論文として取りまとめるもので、学生らは実践的な経験を積みながら、専門知識を深めていきます。
通常、経営プロジェクトは、2年生時に行われますが、イチゴやトマトなど秋から春にかけて栽培する品目については、1年生の段階から進めていきます。
この設計検討会では、イチゴに関する2つ課題とトマトに関する1課題について、各課題を担当する1年生から詳細な説明を行った後、農林総合技術センターの企画戦略部技術革新普及グループの職員や農業技術部農業技術研究室の職員からアドバイスを受けました。
学生らは、助言を元に調査区の設定や調査方法などを改良し、設計書を修正した上で、経営プロジェクトがいよいよスタートすることとなります。
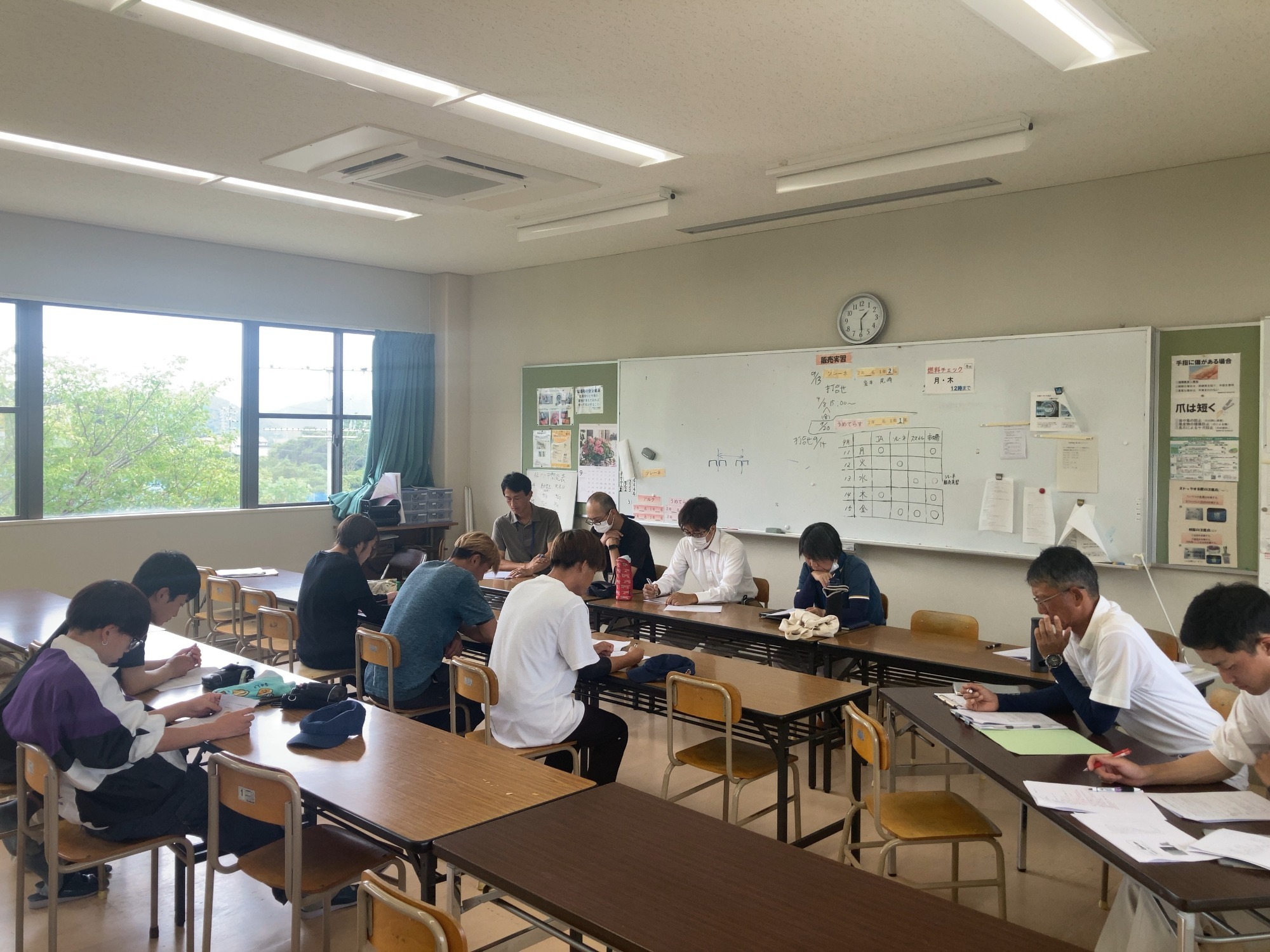

フラワーアレンジメントのラッピング! R5.9.20
本校では、9月20日(水)の午後2時から、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行います。
そのため、同日の午前中に、園芸学科花き経営コースの一年生が、販売実習に出品するフラワーアレンジメントのラッピングを行いました。
一年生らは、フラワーアレンジメントを透明なラップで包み、アレンジに合う色のリボンで飾り付けを施しました。
ラッピングにも手馴れてきたようで、手際よく作業を進めていました。
販売実習では、フラワーアレンジメントの他に、リンドウやバラ、カーネーションの花束、ミニトマト、ブドウ等を販売します。




ハクサイの定植! R5.9.20
園芸学科野菜経営コースでは、9月20日(水)に、ハクサイの定植を行いました。
この作業では、半自動移植機を使用して行いました。
一年生と社会人研修生は、職員の指導のもとで、機械操作を慎重に行いながら、手際よく苗を移植機にセットしていました。
畝とマルチに隙間のある箇所では、移植機がマルチに穴を開けられず、苗が植えれないというトラブルも発生しましたが、全体的には作業は順調に進みました。
今回の定植では、ミニハクサイの「愛姫(めごひめ)」と黄芯系のハクサイである「黄ごころ65」、「黄ごころ85」が植えられました。
ミニハクサイは、11月上旬のイベントに出品する予定であり、黄芯系ハクサイは、11月下旬以降、段階的に収穫する予定です。




果樹専攻と山口農高が連携授業を行いました! R5.9.19
本校と県立山口農業高校は、9月19日(火)、果樹に関する連携授業を実施しました。
本校からは園芸学科果樹経営コースの1年生3名が各自の生産プロジェクトの現段階までの調査結果を発表し、山口農業高校からは生物生産科の2年生で、カンキツ班の生徒5名がプロジェクト学習の内容を紹介しました。
その後、意見交換の場を設け、学生と生徒が質疑応答を行いました。
山口農業高校の生徒からは「オーキシン濃度とは何ですか?」「スマートマルドリとは何ですか?」などの質問が寄せられ、本校の学生からは、「プロジェクトで使ったカンキツのピール(皮)以外の部分はどうなったのですか?」などの質問が出されました。
今後も連携授業の機会を増やし、学習内容を充実させながら、連携を一層強化していく予定です。



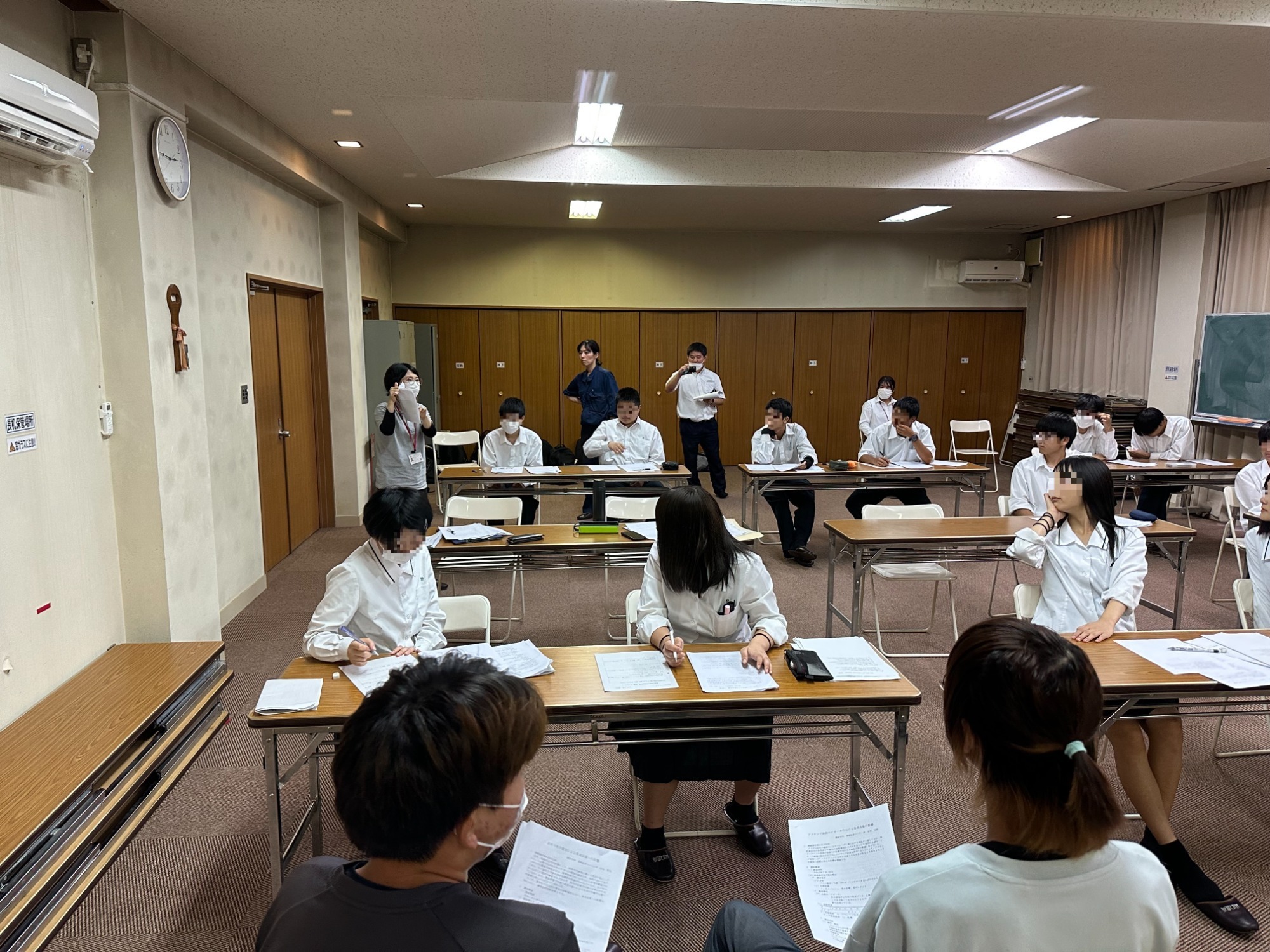
イチゴの苗質調査を実施! R5.9.19
園芸学科野菜経営コースでは、9月19日(火)、イチゴの苗質調査が実施されました。
この調査は、経営プロジェクト「複合環境制御装置を用いた匠の技の実践とイチゴの生育・収量に及ぼす影響への評価」に取り組む1年生によって行われました。
調査項目は、クラウン径や葉数、小葉長といった苗質の指標を調査し、供試する苗の品質を確認することを目的としています。
担当学生は、一株一株、丁寧に調査しました。
今後、9月20日からは、イチゴの苗を定植が行われる予定です。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました R5.9.19
9月17日(日)、農業大学校において、受講生15名を対象に作目基礎研修の
「野菜Ⅱコース(露地野菜)」を実施しました。
当日は秋野菜の管理として、ダイコンの種まきやハクサイの植付けを行うとともに、8月に植え付けたブロッコリーに寄生している今夏発生の多いヨトウムシの被害状況を観察しました。
今年は、異例の暑さが続いた夏特有の症状や病害虫が発生しており、受講生たちは非常に興味深い様子で受講していました。


ニンジン、ダイコン、カブの圃場準備【施肥・畝立て】! R5.9.11
園芸学科野菜経営コースでは、9月11日(月)に、秋播きのニンジンやダイコン、カブの栽培に向けたほ場準備を実施しました。
最初に、畝を立てる位置にメジャーを張り、これを基準にして石灰や肥料を手で散布しました。
その後、畝を立てるための作業機を取り付けたトラクタを使い、畝を立てました。
この作業に携わった一年生や社会人研修生らが、トラクタを慎重に操作した結果、まっすぐで均平な畝が立ちました。
今後、このほ場では、9月13日にニンジン、9月21日にダイコンとカブの播種を予定しています。




タマネギの播種だよ、土地利用全員集合! R5.9.15
土地利用学科が取り組む露地野菜の第4弾は、タマネギ! 9月15日(金)の午後から、タマネギの播種を行いました。
タマネギの種子は1㎜前後の小さいものです。これを等間隔に掘った細い溝に、1~2㎝間隔でパラパラと播いて覆土していくのですが、畝の大きさは幅1m、長さが25mもあります。果たして日が暮れるまで播き終わるのか・・・ いや、今日は金曜日(そして明日から3連休)、必ず終わらせなければなりません!
最初は5人で始めた播種作業、他の作業を終わらせた学生が次々と集まって最後は12名全員が参加。教官の檄が飛ぶ中、作業のスピードもグングン上がり、無事播き終えることができました。
最後に、播種した畝の上に籾殻(もみがら)を薄くまき、不織布を敷いて完成。これから2ヶ月間の育苗期間を経て、11月に定植する予定です。




防府市まちの駅「うめてらす」での販売実習に向けた準備! R5.9.14
9月20日(水)の午後2時より、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行います。
その準備のため、9月14日(木)に、当日対応する学生らが、打合せを行いました。
打合せでは、当日の役割分担を決めるとともに、販売品目の紹介内容や持参物のチェック、レジ操作の確認、ブドウの試食などを行いました。
今回の目玉商品は、「ミニトマト」、「ブドウ(ピオーネ)」、「フラワーアレンジメント」で、その他、アスパラガスやピーマン、花束なども販売する予定です。
ぜひ、9月20日(水)午後2時から「うめてらす」へ足をお運びいただき、新鮮な商品と学生の笑顔に出会いに来てください。


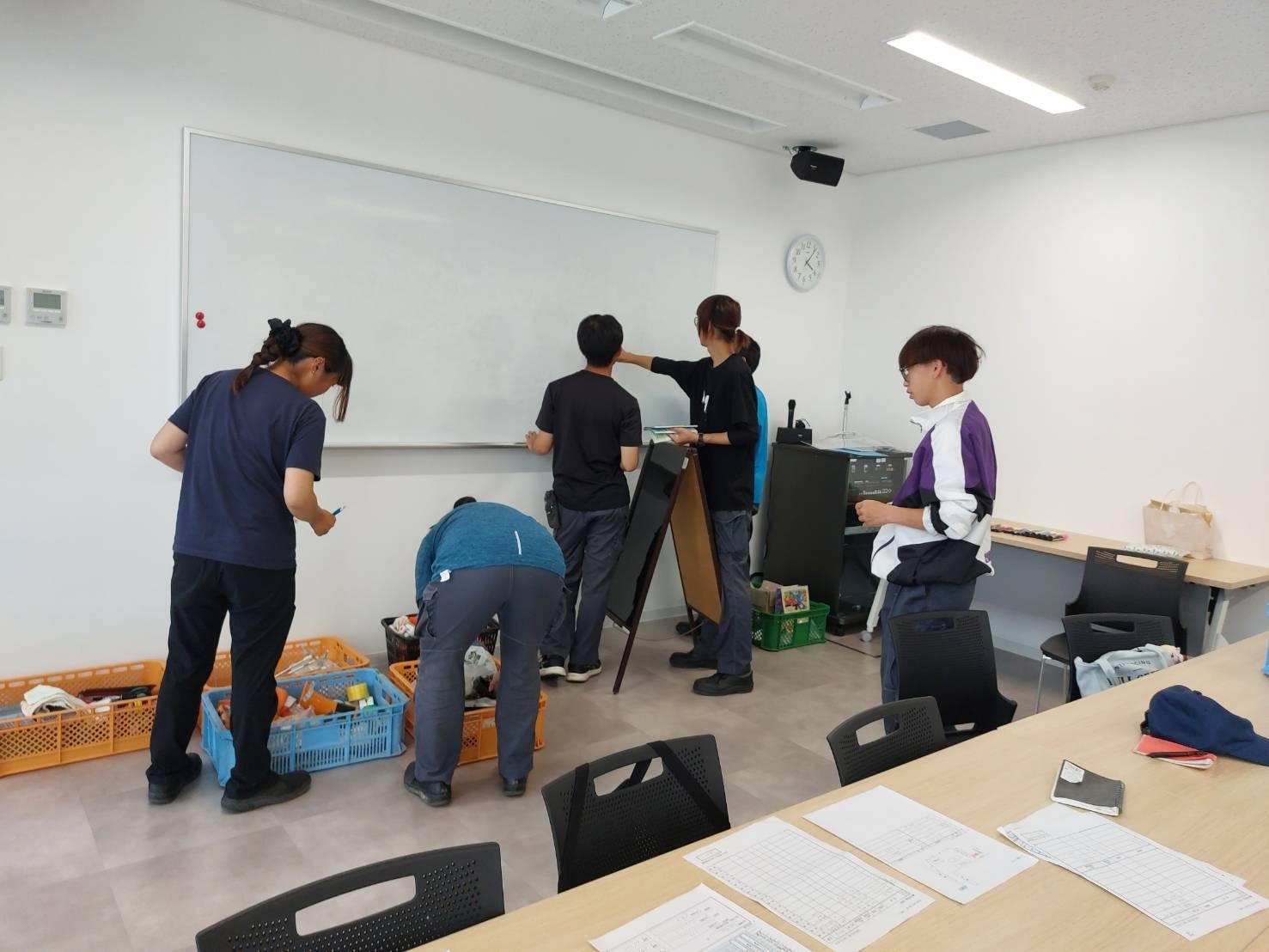

園芸学科野菜経営コース、ジャガイモを定植! R5.9.13
9月13日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、ジャガイモの定植を行いました。
定植には、トラクタに装着した「ポテトプランタ」という作業機を使用しました。
本校のポテトプランタは、人が乗車するタイプで、乗車した人は、種芋を一つ一つ搬送ベルトについている搬送版に置いていき、送られた種芋は地面に落ち、畝立てと同時に畝中に埋められていくもので、畝立てと定植に係る作業時間の短縮が図られます。
一方、ほ場の一部では、ポテトプランタによる畝の整形後、手で種芋を植付けました。
これは、2年生が行う経営プロジェクトの一環で、萌芽率や萌芽ぞろいに影響する種芋の向きを揃えたり、30㎝の株間を確実に確保するために、手で植付けたものです。
暑い中での作業でしたが、作業を行った1年生と社会人研修生は、種芋を丁寧に植付けていました。




白オクラの採種果選定と追肥! R5.9.13
園芸学科野菜経営コースでは、白オクラ種子の発芽率向上を目指した経営プロジェクトが進行中です。
8月下旬、2年生の担当者は、「長門白オクラ部会」の部会長さんに協力を仰ぎ、播種前処理方法や採種方法などについての貴重なアドバイスを受けました。
部会長さんからのアドバイスによれば、発芽率を向上させるためには、充実した種子の確保が必要であり、梅雨明けから8月中下旬あたりまでに開花した果実から採種することが効果的だとのことでした。
そのため、本経営プロジェクトでは7月の梅雨時期開花、8月上旬開花、9月中旬開花の果実から採種し、発芽率を比較することとしており、今回は9月11日(月)の朝に開花した花に1年生が、研修中の2年生に代わり、テープで印をつけました。
さらに、秋以降の白オクラの健全な成長を確保するため、株元に追肥を施しました。
今回印を付けた果実は11月頃に収穫し、発芽率の調査をする予定です。




実践ハウスでのイチゴの定植準備【潅水チューブ設置】 R5.9.13
園芸学科野菜経営コースでは、地元企業と山口県が共同開発した移動式高設栽培システムや統合環境制御システムを備え飛躍的な生産量の増加が見込めるスマート生育環境制御ハウス(「実践ハウス」)を、1年生のイチゴの経営プロジェクトに活用します。
現在、このプロジェクトを担当する1年生は、9月末に予定されているイチゴの定植に向けて準備を進めています。
9月13日(水)には、隔離ベッドの培土上に潅水チューブを設置しました。
これにより、イチゴの生育に適した肥料成分を含む養液を供給することが可能となります。
今後は培土への水の充填作業や苗への農薬の灌注など定植へ向けた準備を進めていきます。

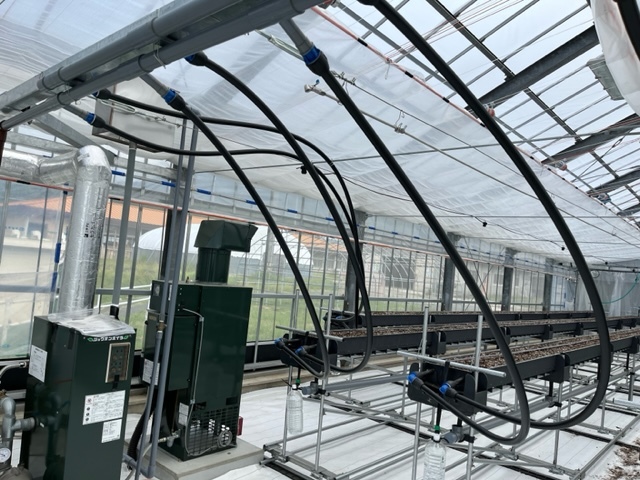


7名の学生が「道の駅ソレーネ周南」で販売実習を実施! R5.9.13
9月13日(水)、「道の駅 ソレーネ周南」で、土地利用学科の1年生3名、園芸学科の2年生2名と1年生1名、畜産学科の1年生1名の計7名が、販売実習に挑みました。
初めての販売実習に臨んだ1年生5名は、2年生のサポートを受けながら、準備から販売、片付けまで、スムーズにこなしていました。
特に、大きな声での呼び込みや積極的なお客様への商品紹介を行う姿が印象的でした。
次回の販売実習は、9月20日(水)に、防府市まちの駅「うめてらす」で行う予定です。




スプレーギクの定植! R5.9.13
9月13日(水)、園芸学科花き経営コースでは、ガラス温室内に、スプレーギクを植付けました。
これは、9月11日に定植した輪ギクに続いて定植したもので、担当の1年生は、教官らの力を借りながら、残り5ベンチにスプレーギクの苗2000本を植付けました。
今回定植したのは、花色が白で中心が緑色のポンポン咲きの「フェリー」やピンク色の「オーサカ」など10品種です。
今後、年末の収穫に向けて、摘芯や整枝、電照といった管理を行っていきます。




ジャガイモ、定植機械の不調により手植えをする・・・ R5.9.12
9月11日、土地利用学科は、ジャガイモの定植を行いました。使用する機械は、かまぼこ状の畝を作りながら種イモを植えていく「ポテトプランタ」。土地利用学科としては初めて使用する機械ですが、これまでも園芸学科が毎作使用している、実績のある機械です。
種イモの準備もOK、さあ作業開始! ・・・ん? イモが植えられない?! 機械の上で種イモを運ぶベルトがうまく回らないのです。原因究明をいろいろ試みましたが、時間が掛かりそうだったので、機械定植は諦め、ポテトプランタで畝を作り、種イモは手で植えることにしました。
午後は予定を変更し、土地利用学科の学生総動員で一斉にジャガイモの手植えです。メジャーで株間(かぶま:種イモを植える間隔)を測って種イモを置き、移植ゴテで深さを確認しながら、どんどん植えていきました。
今回の反省点は、機械の試運転をしておらず事前に機械の不調を把握できなかったことです。この失敗から得た教訓を、次に活かしていきましょう。



土地利用学科、ジャガイモ定植の準備 R5.9.12
土地利用学科では、露地野菜の栽培学修としてキャベツ、ブロッコリーの栽培を開始しています。第三弾として、ジャガイモの準備を始めました。
栽培計画は、夏休みの間にジャガイモ班の3人が検討し、作成済みです。これから、その計画に従って栽培に取り組んでいくことになります。
とはいえ、土地利用学科としては、水稲と同じく学生全員がジャガイモのことを知っておかなければなりません。9月7日(木)、ジャガイモをテーマに教官から講義を受け、生理生態をしっかり学びました。
学んだあとは、種イモの準備開始です。小さい種イモはそのまま使いますが、大きい種イモは半分に切って1日乾燥させました。そして、9月8日(金)、種イモを農薬に漬け、再び乾燥させました。
来週はいよいよジャガイモの定植です。
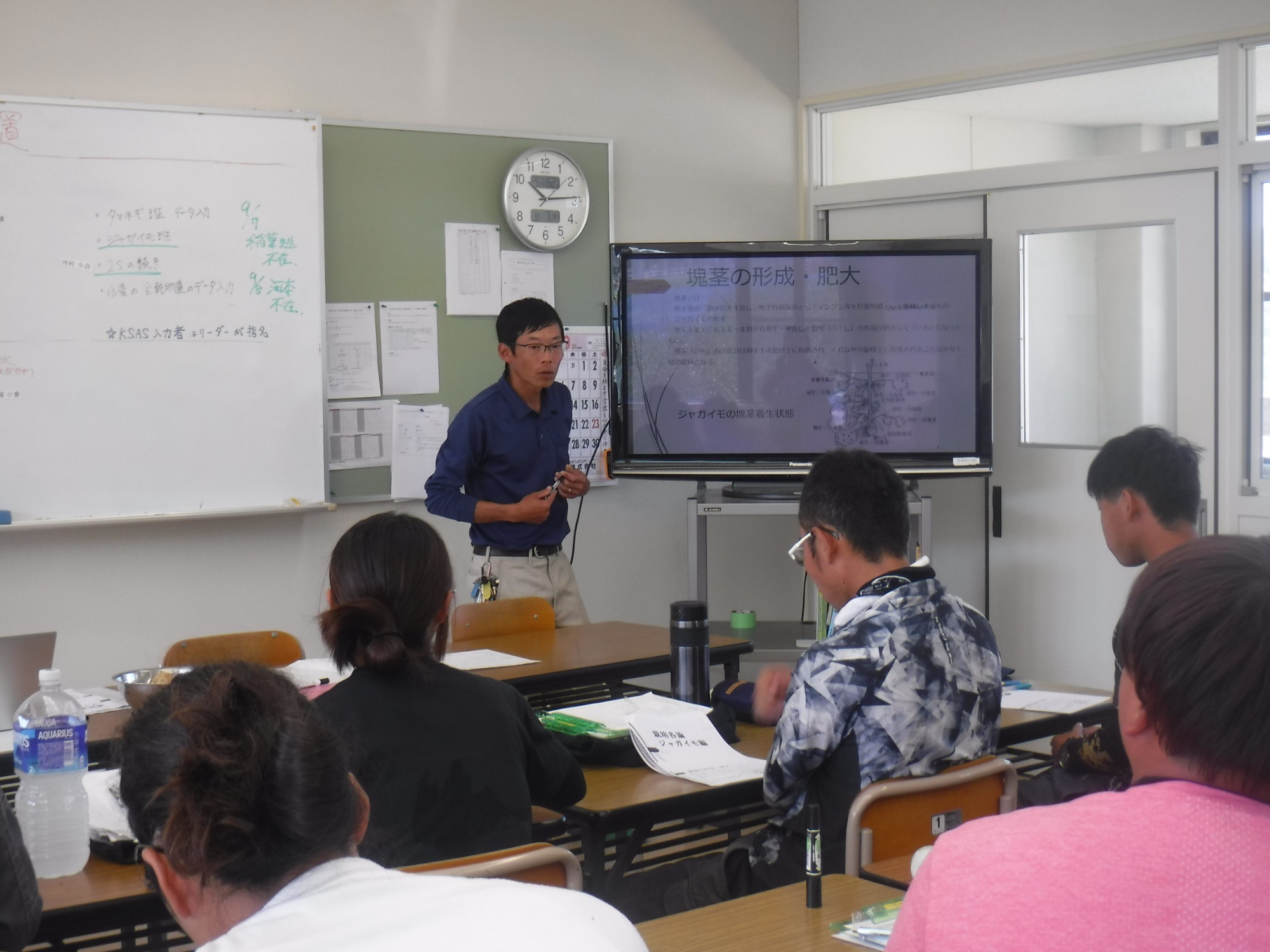



フラワーアレジメントの作成! R5.9.12
本校では、9月13日(水)午後2時より、道の駅「ソレーネ周南」で販売実習を行います。
このため、9月12日(火)には、園芸学科花き経営コースの学生が、販売実習に出品するフラワーアレンジメントの作成を行いました。
作成に携わった1年生は、バラやカーネーション、ナデシコ等を使い、教官のアドバイスを受けつつ、試行錯誤しながら、フラワーアレンジメントを作成していました。
販売実習では、フラワーアレンジメントの他に、リンドウやバラ、カーネーションの花束、ミニトマト、ブドウ等を販売します。




輪ギクの定植! R5.9.11
園芸学科花き経営コースでは、例年、年末出荷に向けたキクの生産に取り組んでいます。
9月11日(月)には、6つあるベンチのうちの1つに、輪ギクの「神馬(じんば)」という品種を植付けました。
この品種は、大輪で、花色は純白で、艶があり、花持ちが非常に良いという特徴を持っており、輪ギクの主要品種の一つです。
今後、残りのベンチには、スプレーギクを植付ける予定です。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.9.11
9月10日(日)、農業大学校において、受講生5名を対象に作目基礎研修の「農業機械コース」を実施しました。
当日は、小型耕運機の構造や安全な使い方の説明を受けた後、実際の耕運作業を体験実習しました。また、小型耕運機の運搬方法として、軽トラへの積み込み及びロープでの固定方法を学びました。
初めて取り扱う受講者が多く、みなさん非常に興味深げに受講していました。



ダリアの定植! R5.9.7
園芸学科花き経営コースでは、昨年からダリアの栽培に取り組んでいます。
県内でのダリアの生産は少ないですが、昨年、市場から高い評価をいただいたため、今年も引き続き、栽培に取り組むものです。
今年は6品種を定植することとしており、これまで5品種の定植を終えています。
9月7日(木)には、最後の品種である「ムーンストーン」(花色は紫)の苗の定植を担当の1年生が行いました。
これらのダリアは、11月中旬から市場や防府市内の直売所への出荷を予定しています。




キンギョソウの定植準備【畝立て】! R5.9.6
園芸学科花き経営コースでは、秋・春開花の作型のキンギョソウ栽培に取り組みます。
9月7日(水)には、定植の準備として、畝立てを行いました。
今回は、畝立成形機を使用して畝立てを行うこととし、操作経験のない1年生3人が操作を行いました。
作業を行った1年生らは、畝立成形機を初めて使用しましたが、教官の指導どおりに操作を行い、きれいな畝が仕上がりました。




ブロッコリーの経営プロジェクトの調査区設定および生育調査! R5.9.6
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
本調査は春作でも行っていますが、今回は、秋作での影響を調べるものです。
9月6日(水)には、ほ場内に調査区を設けるとともに、生育調査を行いました。
調査区は、側花蕾の活用の有無や側花蕾の取り方の違いで、4つの区を設けました。
また、生育調査は、最大葉の長さと幅を調べました。
今回、担当の2年生が研修で不在のため、管理や調査を引継いだ1年生が、調査区の設置や生育調査を行いました。
今後、週一回、生育調査を行っていきます。




イチゴの定植準備【施肥】! R5.9.6
本校では、農林総合技術センター農林業技術部農業技術研究室野菜研究グループが地元企業と共同開発した隔離床栽培システムや統合環境制御システムなどを装備し、イチゴやトマトの生産量の飛躍的な増大につなげるスマート生育環境制御ハウスである「実践ハウス」2棟を整備しており、本年度より運用することとしています。
現在、そのうちの1棟では、園芸学科野菜経営コースの1年生が、イチゴをテーマとした経営プロジェクトに取り組むこととしています。
9月6日(水)には、担当の1年生らが、移動式栽培ベンチ内の培土に、肥料をまきました。
9月下旬には、イチゴの苗を定植する予定です。




スプレーギクの定植準備【施肥・耕うん】! R5.9.6
園芸学科花き経営コースでは、需要の多い年末に向けたスプレーギクの生産を行うこととしています。
9月6日(水)には、担当の1年生が、肥料をまくとともに、ベンチ内の培土を耕うん機で耕しました。
今後、潅水装置や支柱、フラワーネットを設置した後、定植を行う予定です。




葉ネギの生育調査を行いました! R5.9.6
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、高温期の積極的な潅水が葉ネギの葉先枯れの発生や外観品質に及ぼす影響について調べることとしています。
6月から8月に行った1作目の調査に続き、8月30日に播種を行い、現在、2作目の調査を開始しています。
播種から1週間後の9月6日(水)には、生育調査として草丈や葉数を調べました。
担当の2年生が研修で不在のため、管理や調査を引継いだ1年生が、教官の指導のもとに、生育調査を行いました。
この生育調査は、毎週行う予定です。




ホウレンソウの発芽調査を行いました! R5.9.6
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、夏秋ホウレンソウのハウス栽培における屋根散水によるハウス内昇温抑制効果の検証に取り組んでいます。
8月14日に3作目の種を播きましたが、9月6日(水)には、発芽の状況を調査しました。
担当の2年生が研修で不在のため、管理や調査を引継いだ1年生が、発芽調査を行いました。
調査を行った1年生は、発芽した苗の数を真剣に数えていました。



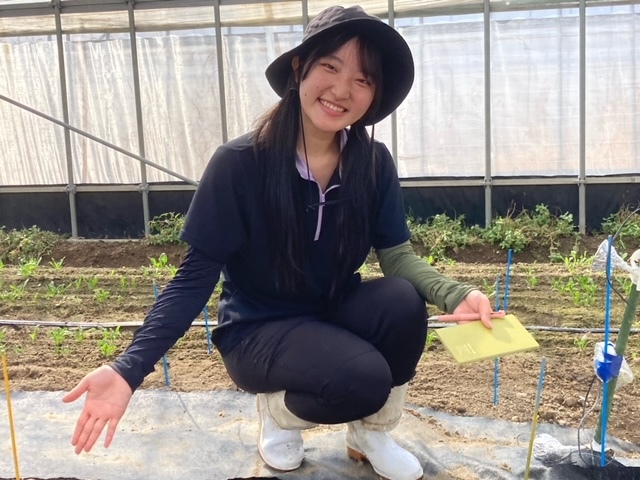
第2回短期入門研修を開催しました! R5.8.28
8月28日から8月31日にかけて、やまぐち就農支援塾第2回短期入門研修を開催しました。この研修は、農業未経験の方などを対象に、将来の就農を目指すきっかけとしていただくために、毎年4回程度実施しているものです。
今回は11名の受講生が参加され、農業大学校の職員や学生らから農業機械・小農具の取り扱いや、普通作物、野菜、果樹の管理指導を受けながら作業体験を行いました。
受講生からは「実際に作物に触れながらの作業体験ができ参考になった」「学生たちともいろんな情報交換ができ良かった」「今後の就農に向けた検討の材料にしていきたい」等の感想が聞かれました。




週間天気と作業計画に悩む(畜産学科) R5.8.31
8月31日(木)、畜産学科の2年生が畜産技術部(美祢市)で、飼料作物の作業機械の研修を行いました。
当初の予定では、29日に刈取りした飼料作物の収穫(ロールベール、ラッピング)の実習をする予定でしたが、残念なことに前夜から雨… 。刈取りの時点の予報で雨が落ちる事も懸念していましたが、なかなか取れない実習の機会… お願いして刈取りしましたが降られてしまいました。 これが「自給飼料」の難しいところ。
この日は、圃場作業は取り止め、飼料作物の作業機の着脱や牽引作業機の連結の実習に取り組みました。
畜産は専用の作業機が多く、もう少し時間がほしいところです。引き続き機会を作って取り組みたいと思います。
畜産技術部の皆さんありがとうございました。



花壇苗の鉢上げ! R5.9.5
園芸課花き経営コースでは、11月3日(金)に開催するイベントへ出品する花壇苗の生産に取り組んでいます。
現在、セルトレイに播種後、生育した苗をポットに植え替える「鉢上げ」という作業を行っています。
葉ボタン、パンジーに続き、9月5日(火)には、ビオラの鉢上げを行いました。
7月31日に播種したビオラの苗は、本葉が3~4枚程度展葉した状態で、担当した1年生は、慎重にポットに植え替えていました。




ジャガイモの施肥・耕うん! R5.9.5
園芸課野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ジャガイモのマルチ栽培導入に係る経営評価に取り組んでいます。
9月5日(火)の午前には、秋作のジャガイモを対象とした調査を行うため、定植の準備を行いました。
担当の2年生が長期研修中のため、引き継いだ1年生が、経営プロジェクトの設計書や教官の指導に基づき、肥料をまいたり、トラクタによるほ場の耕うんを行いました。
なお、午後から雨が降ったため、翌日に予定していた畝立てや定植、白黒マルチの被覆などは、来週に延期することとなりました。




メロンの人工受粉! R5.9.5
園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室2棟で、メロン栽培に取り組んでいます。
現在、8月15日に定植したメロンでは、目標とする着果節位である11~15節に、雌花が咲きだしました。
このため、9月5日(火)には、1年生や研修生が、筆を使って、雄花から花粉をとり、雌花のめしべにつける人工受粉を行いました。
メロンの人工受粉は、花粉の状態がよい朝10時までに行う必要があることから、1年生らは、手際よく行っていました。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました R5.9.3
9月3日(日)、農業大学校において、受講生18名を対象に作目基礎研修の「果樹」、「水稲」の2コースを並行して実施しました。
当日はコース別に、ビワの整枝剪定及びブドウやナシの果実品質調査、水稲の品種別管理について講義及び実習を行いました。
当日は、まだまだ残暑が厳しい天候でしたが、受講生たちは興味深げに聴講・実習を行っていました。


やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました R5.8.27
8月27日(日)、農業大学校において、受講生28名を対象に作目基礎研修の「野菜Ⅰ」、「野菜Ⅱ」、「畜産」の各コースを並行して実施しました。
当日はコース別に、夏野菜の管理や秋野菜の種まき、牛の栄養・病気の管理について講義及び実習を行いました。
当日は朝から気温が上がる猛暑ぎみの天候のもと、熱中症に気をつけながらの実習でしたが、受講生たちは熱心に聴講・実習を行っていました。


大豆の病害虫防除(1回目) R5.9.1
大豆は、開花期から30日後と45日後に、病害虫の防除(農薬散布)を行います。土地利用学科が栽培している大豆は、9月初旬が1回目の防除時期になります。
防除作業に先立ち、まずは防除に使う乗用管理機の準備を行いました。乗用管理機は7月の中耕培土に使用した機械ですが、車体うしろのアタッチメントを中耕培土機から防除機に付け替えれば、あっという間に乗用の防除機に早変わり。また、付け替えの様子をしっかり動画で記録。今後の付け替え作業の参考にしていきます。
そして8月30日(水)、少し早いですが、翌週の天気予報に雨マークが多かったので、大豆の防除作業を行うことにしました。少し雨がパラつく天気とはいえ、暑い中、学生は防護服とマスクを装着し、大豆に農薬が確実にかかるように、乗用管理機の速度や散布機の高さを調節しながら作業を行いました。
次は、9月の中旬に2回目の防除を行う予定です。早く涼しくなればいいな。




牛葉ネギの播種を行いました! R5.8.30
葉ネギの播種を行いました!
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、高温期の積極的な潅水が葉ネギの葉先枯れの発生や外観品質に及ぼす影響について調べることとしています。
8月30日(水)には、担当の2年生らが、ガラス温室内のベンチへ、二作目の播種を行いました。
今回播種したのは「やまひこ」と「ブラックキング」の2品種です。
担当の2年生は、9月1日から一か月間、「先進農家等派遣研修」により不在となるため、その間の栽培管理を担当する1年生に、潅水管理や生育調査の方法について、引継ぎを行っていました。




牛を飼うために汗をかく! R5.8.29
本校では、農林総合技術センター農林業技術部農業技術研究室野菜研究グループが地元企業と共同開発した隔離床栽培システムや統合環境制御システムなどを装備し、イチゴやトマトの生産量の飛躍的な増大につなげるスマート生育環境制御ハウスである「実践ハウス」2棟を整備しており、本年度より運用することとしています。
現在、そのうちの1棟では、野菜研究グループによってトマトが定植されており、塩を添加してEC(電気伝導度)を高めた養液を潅水に用いる「塩分ストレス栽培」が行われています。
8月29日(火)には、園芸学科野菜経営コースのトマト担当の1年生が、同グループの原田専門研究員から、本栽培法の概要や具体的な潅水の仕方などについて教えていただきました。
この1年生は、経営プロジェクトの課題として本栽培法を取り上げることから、原田専門研究員に、収量を確保するための栽植密度や生育調査の方法など、積極的に質問を行っていました。




牛を飼うために汗をかく! R5.8.29
8月29日(火)畜産学科の2年生が、畜産技術部(美祢市)で飼料作物の実習を行いました。
今日も日差しの強い日でしたが、飼料作物の刈り取りには良い日です。
約80aの圃場に植え付けてある飼料ヒエを、大型のトラクタを操作して「刈取り」、「反転」の作業を行いました。
「刈取り」は「モアコンディショナー(牽引)」、「反転」は「テッダ―」を使いましたが、作業幅の大きな機械なので操作に戸惑って… いたのは最初だけだったようで、畜産技術部の先生のアドバイスを受けながら真剣に操作していました。
8月31日には収穫の予定ですが、乾草になるかサイレージにするかは天候次第です。




ブロッコリーの定植を行いました! R5.8.29
8月29日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、ブロッコリーの定植を行いました。
定植は、定植機を使用して行いましたが、学生や研修生らは、定植機の操作やに苗のセットを手際よく行っていました。
定植後は、潅水チューブを設置し、潅水をしっかり行いました。
今回定植した品種は、「夢ひびき」と「ピクセル」の2品種で、前者は2年生の経営プロジェクトに供試します。


経営プロジェクト中間発表会を開催しました! R5.8.29
8月29日(火)、園芸学科で、経営プロジェクトの中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『SP菊のわい化剤の処理回数と濃度の違いが品質に及ぼす影響』で、花き経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を説明しました。
参加した学生からは、電照時期の影響や今回の課題を踏まえた草丈制御の方法に関する質問があり、担当学生は丁寧に答えていました。
次回は、10月3日にブロッコリーやブドウに関する課題の発表が行われる予定です。




JGAP模擬審査を行いました! R5.8.28
本校は、平成31年1月に、JGAP認証を取得しており、現在の認証品目はトマト、ミニトマト、ブドウの3品目です。
本年10月には、維持審査を予定しており、現在、自己点検の実施など、審査に向けた準備を進めている所です。
こうした中、8月28日(月)には、合同会社つちかい代表社員の大神健治様を講師に招いて模擬審査を行い、園芸学科の2年生が受審しました。
審査は、JGAP基準書に沿って進められ、各管理点を担当する学生は、審査員役の大神様からの質問に答えるとともに、大神様からの受審時の対応に係るアドバイスに耳を傾けていました。
書類審査、現地審査併せて5時間に及ぶ審査となりましたが、学生らは、10月の維持審査に向けて、いい練習となりました。
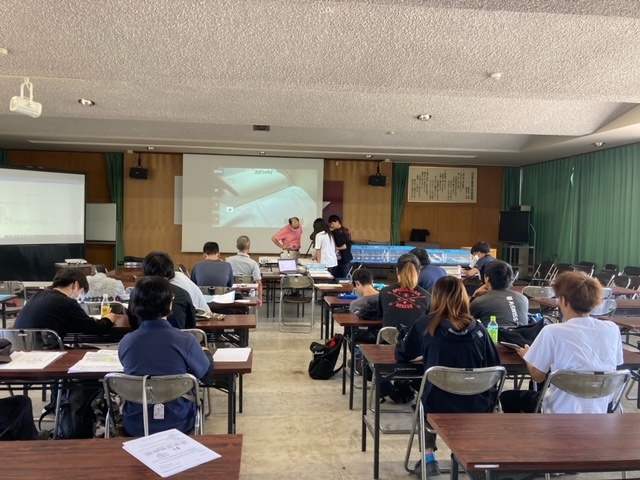
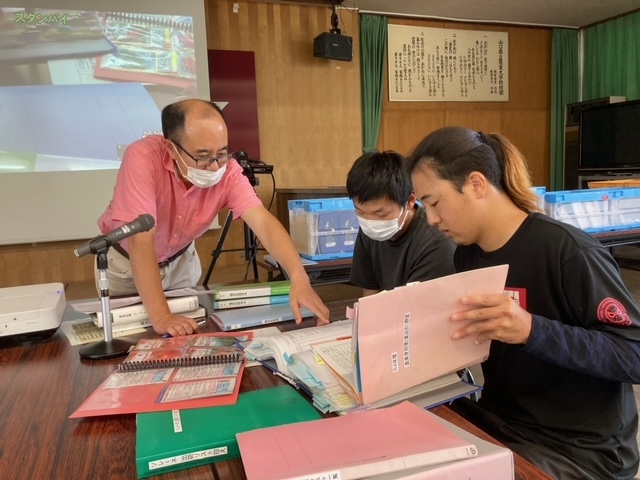
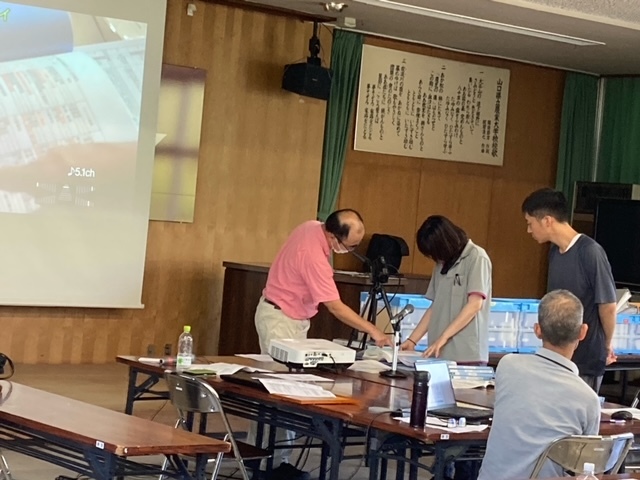
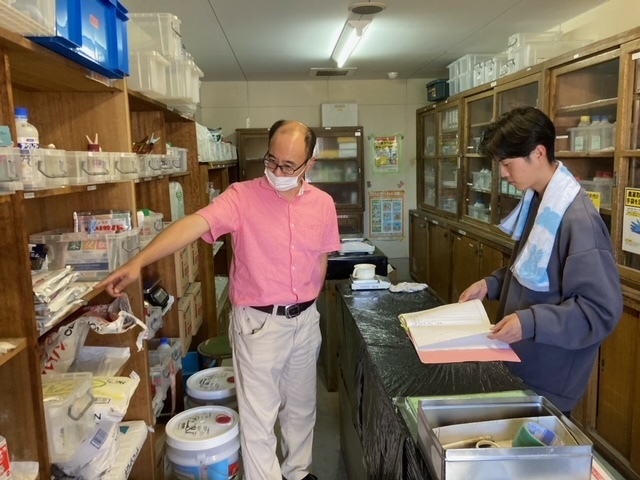
キャベツの定植を行いました! R5.8.28
8月28日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、キャベツの定植を行いました。
定植は、定植機を使用し、職員の指導のもと、移動する定植機に、学生が手際よく苗をセットしていきました。
定植後は、潅水チューブを設置し、潅水をしっかり行いました。
今回定植した品種は、「おきなSP」と「夢いぶき」の2品種で、11月以降、順次収穫する予定です。




経営プロジェクト中間発表会を開催しました! R5.8.24
8月24日(木)、園芸学科で、経営プロジェクトの中間発表会を開催しました。
今回は、『イチゴか「かおり野」の子苗直接定植における鉢受け・定植時期が生育・収量に及ぼす影響』と『屋根散水によるハウス内昇温抑制技術がホウレンソウの生育、収量に及ぼす影響』の2課題で、野菜経営コースの2年生2名が、それぞれ発表しました。
発表者らは、参加した学生や研修生からの質問に丁寧に答えるとともに、発表後もイチゴの育苗方法や屋根散水のシステムについて詳しく説明していました。
次回は8月29日に開催し、キクに関する課題の発表が行われます。




高性能コンバインについて学ぶ! R5.8.25
8月25日(金)、土地利用学科の講義「スマート農業機械論」の一環として、高性能コンバイン(収穫しながら、圃場ごとの収量や食味(タンパク値)を把握する機能がついているコンバイン)の実演会に参加してきました。メーカーの方から収量や食味を測定する仕組みや機能等について説明を受け、いざ試乗! さっと手を挙げた一番手の彼、なかなか操作が上手です。いいオペレーターになれそうですね。さて、次は誰が乗る? ・・・なかなか手が挙がりません。まぁ、全くコンバインに乗った経験も無いのにいきなり戦車みたいなコンバインに乗るのは勇気が要りますよね。勇気を出して乗った二番手の彼女、丁寧な操作、よかったです。
ところで今日の講義、高性能コンバインの仕組みを学び試乗するだけが目的ではありません。重要なのは、高性能コンバインが取ったデータの活かし方。実演会後、農大に帰ってからデータの活用について学びましたが、少しは理解が深まったでしょうか?
農大には高性能コンバインはありませんが、圃場ごとに収量や食味のデータを取り、課題を見つけ、改善につなげていく予定です。




大豆の豊作を願って畝間灌水(うねまかんすい)に励む! R5.8.25
暑い日が続きます。農大近辺では、梅雨明け以降ほとんど降雨がありません。干ばつは大豆の生育や収量に悪影響を及ぼしますので、土地利用学科では8月20日(日)から大豆に2回目の畝間灌水(うねまかんすい:水やりの方法の一つ。水路から畝と畝の間に水を流し込み、圃場全体に水を浸み込ませる)を行いました。
ところが、降雨が少ないので圃場もよく乾いています。また、圃場に高低があったり、水量が少なかったりすると、うまく圃場全体に水が行き渡りません。学生達は水の状況を確認しながら、圃場全体に水が行き渡るように、また水が溜まらないように、鍬で水路を作って水の流れを作り、5日間かけて畝間灌水を完了させました。
水をもらった大豆は、本当に生き生きと、青々と繁っています。ますます豊作が期待できますね!




土地利用学科、初めて露地野菜を圃場に植える! R5.8.25
土地利用学科の露地野菜栽培が本格的に始まりました。第一弾は、キャベツ!
残暑厳しい8月21日(月)から24日(木)にかけて、土地利用学科はキャベツの定植(ていしょく:苗を植えること)を行いました。
畝立て同時施肥機を付けたトラクタを使い、耕うん、施肥(せひ:肥料をやること)、畝立てを行います。今回は仮畝(かりうね)を立てていたので、まっすぐ畝を立てるのが難しかったようです。
畝の準備ができたら、次は苗の移植です。使用する野菜移植機は前日に調整済みですが、まずは圃場で試運転して設定を確認し、微調整を行ってから作業に入ります。移植機の操作は2人での組作業。1人は機械の操作、1人はひたすら苗の補給。苗の補給を手際よく行うこと、2人で声を掛け合って作業することがポイントのようですね。
定植した後は、除草剤を散布。雑草が生えないよう、丁寧な散布が行われました。また、晴天続きで圃場がよく乾いているので、苗が枯れないよう灌水(かんすい:水やりのこと)も行っていきます。
9月に入ってからも、引き続きキャベツ、ブロッコリー、ジャガイモの定植が控えています。良い苗を作って適期に定植できるよう、段取り良く作業を進めていきましょう。




ブドウのリスク評価を行いました! R5.8.23
本校では、JGAPの「農場管理点と適合基準」に基づき、食品安全や環境保全、労働安全の確保、人権・福祉に配慮した労務管理が行えるよう、日々の実習の中で、法令の遵守や農場管理の継続的な改善を行っています。
こうした中、JGAP認証を受けているトマト・ミニトマトおよびブドウでは、栽培行程や収穫行程、農産物取扱い行程におけるリスク評価を毎年行っています。
8月23日(水)には、ブドウに関するリスク評価を行いました。
学生らは、リスク評価を通じて、現在の行程に潜む危害要因を改めて認識するとともに、リスク低減に向けた改善方策を考えるいい機会となりました。
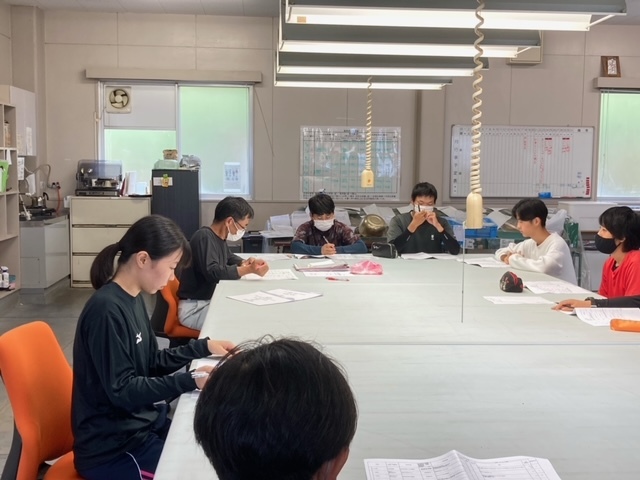

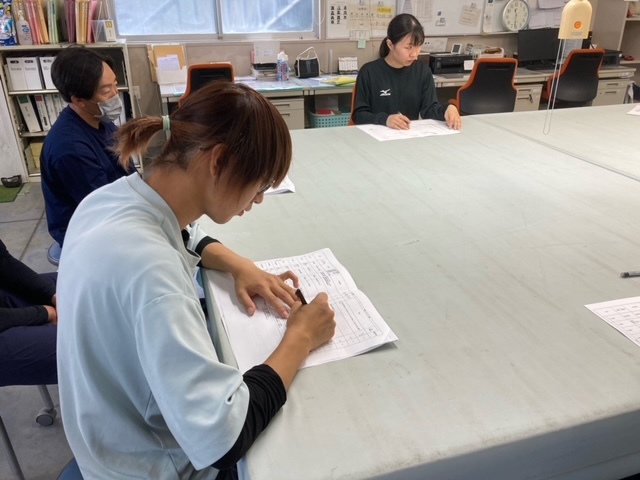
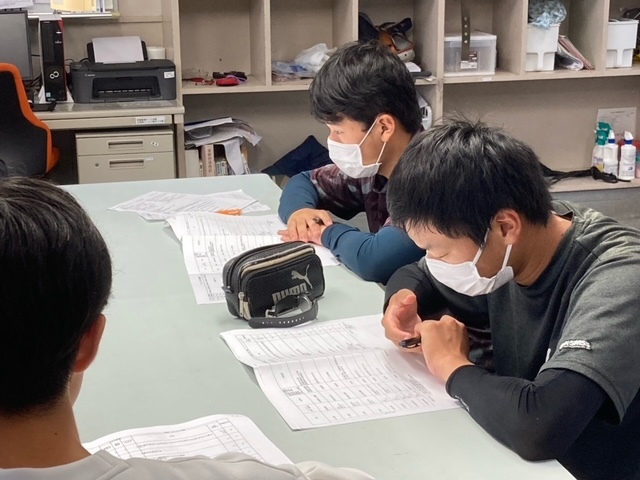
葉ネギの出荷調整! R5.8.23
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、高温期の積極的な潅水が葉ネギの葉先枯れの発生や外観品質に及ぼす影響について調べることとしています。
8月23日(水)には、担当の2年生が、ガラス温室内で栽培している葉ネギを収穫するとともに、その後、同級生や1年生とともに出荷調製を行いました。
調製したネギは、同日午後2時より、防府市まちの駅「うめてらす」で行われる販売実習に出品するほか、市場や直売所へも出荷する予定です。




販売実習を行いました!【防府市まちの駅「うめてらす」】 R5.8.23
8月23日(水)に、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行いました。
今回は、園芸学科の2年生4名に加え、土地利用学科の1年生1名と園芸学科野菜経営コースの1年生1名、畜産学科肉用牛経営コースの1年生1名が参加しました。
初めて参加した1年生は、2年生の動きを見習うかのように、後を追っていました。
次回は、今回の経験を活かして、自主的に動けるようになることを期待したいと思います。
また、お客さんの呼び込みに際しては、1年生が恥ずかしがって声が出せなかったのに対して、2年生は堂々と大きな声で呼び込みを行っており、2年生の成長が垣間見れました。
来月は、9月13日(水)に、道の駅「ソレーネ周南」で販売実習を行う予定です。




フラワーアレンジメントのラッピング! R5.8.23
8月23日(水)の午後2時より防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習が行われます。
このため、同日の午前中に、園芸学科花き経営コースの学生が、販売実習に出品するフラワーアレンジメントのラッピングを行いました。
2年生は、手慣れた様子で、フラワーアレンジメントを透明なフィルムで覆い、リボンを装飾していきました。
販売実習では、フラワーアレンジメントの他に、バラ等の花束も販売します。




GPS車速連動畝内施肥機を用いた畝立て同時施肥! R5.8.23
8月23日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、秋冬野菜のほ場準備を行いました。
今回は、GPS車速連動畝内施肥機をトラクターの後方に取り付けるとともに、ロータリーには畝立て機を取り付けました。
これにより、施肥と畝立てを同時に行うことで作業の効率化が図れるとともに、車速に応じて施肥量が変わるため、均一に施肥することができます。
学生らは、肥料の吐出量を事前に確認・調整した後に、畝立て同時施肥を行いました。
ここには、ブロッコリーやキャベツ、ハクサイを植える予定です。




メロンの定植! R5.8.22
8月22日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、先週に引き続いて、ガラス温室で栽培するメロンの定植を行いました。
今回も、赤肉系と緑肉系の2品種を植付けました。
暑い中での定植でしたが、作業を行った1年生と2年生は、丁寧に苗を植付けていました。
これまで2年間、メロン栽培に携わってきた2年生は、最後の定植となりましたが、10月下旬には美味しいメロンを収穫するために、今後の管理にも積極的に係わっていこうと意気込んでいました。




知事に農大生の会社を紹介。学生一人一人と握手! R5.8.21
8月21日(火)の午後、農業者団体と知事との意見交換会後に、知事と農大生で交流を行いました。その時に、今年度7月に設立された農大生の会社(「(一社)やまぐち農大」)について、学生役員2名から説明し、知事との名刺交換が行われました。その後、集まった学生たちと記念撮影を行い、知事から学生に向け、「若い力に期待している。」と励ましの言葉があり、集まった学生一人一人と握手をして帰られました。学生も知事の対応に胸を熱くしたようです。




畦畔(けいはん)の草刈り、圃場のヒエ取り R5.8.17
8月17日(木)は、全員で畦畔の草刈りを行いました。学生達は、入学してからしばらくはナイロンコード(ナイロン製の紐。高速回転させて草を刈る)を使っていましたが、4ヶ月経った今ではチップソー(金属刃)も使っています。この日も、畦畔の状況に応じてチップソーかナイロンコードを選択し、どんどん草を刈っていました。もちろん、刈った草が水路に落ちたら取り除きます。併せて水路に生えている雑草も取ります。これらも、水管理をスムーズに行うための大事な作業ですね。
さて、除草剤の効きが悪かった場所は、ヒエ(イネ科の雑草で、穂が出る前の姿はイネそっくり)が目立つようになりました。ヒエが多いとコンバイン収穫の支障になりますが、さすがに刈払機で刈るわけにはいきません。ここは、最終兵器テトール(手取り除草です)の出番! 鎌を片手に田んぼに入り、少しずつヒエを取っていきます。イネでないことを確認しながら。




販売実習の打合せを行いました! R5.8.16
8月23日(水)の午後2時より、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行います。
その準備のため、8月16日(水)に、打合せを行いました。
当日の役割分担を決めるとともに、販売する品目の紹介内容や持っていく物品のチェック、レジ操作の確認、イチジクやナシなどの試食などを行いました。
今回の目玉は、「かぼちゃ(くりゆたか)」、「ブドウ(ブラックビート)」、「フラワーアレンジメント」です。
その他、トマトやナス、葉ネギ、ナシ、イチジク、花束なども販売する予定です。ぜひ、お立ち寄りください。




メロンの定植! R5.8.15
8月15日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室で栽培するメロンの定植を行いました。
今回、赤肉系の「妃(きさき)」と緑肉系品種の「ミラノ夏Ⅰ」を植付けました。
担当の1年生加えて、2年生や社会人研修生も作業に携わり、丁寧に定植を行っていました。
このメロンの収穫は、10月下旬頃を予定しています。




野菜苗の育苗状況! R5.8.15
園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室内で野菜苗を育てています。
8月15日時点では、2年生が経営プロジェクトで供試するブロッコリーや作目基礎研修等で使用するキャベツ、1年生が担当するメロンなどが育苗されています。
メロンは、本日も定植していますが、残りは8月22日に定植する予定です。


葉ネギの収穫物調査! R5.8.15
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、高温期の積極的な潅水が葉ネギの葉先枯れの発生や外観品質に及ぼす影響について調べることとしています。
8月15日(火)には、担当の2年生が、ガラス温室内で栽培している葉ネギを収穫するとともに、その後、収穫物に関する調査を行いました。
調査では、収穫時や調整後のネギの重量や本数、葉先枯れの程度、葉色、葉の強度を調べました。
このうち、葉の強度は、ネギを横にした時の葉先のしなり具合で評価を行いました。




花の出荷調整の様子! R5.8.14
園芸学科花き経営コースでは、盆需要に向けて生産した花の出荷調製に追われています。
8月14日(月)には、当番の学生に加えて、専攻教官らも総出で、出荷調製を行いました。
この出荷調製の忙しさのピークも、今週末には収まりそうです。




ホウレンソウの播種(はしゅ)! R5.8.14
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、夏秋ホウレンソウのハウス栽培における屋根散水によるハウス内昇温抑制効果の検証に取り組みます。
8月14日(月)には、2棟のハウスへホウレンソウの種を播きました。
今回が3作目の播種となりますが、担当の2年生が9月の1ヶ月間、農家体験研修で不在となるため、その間の管理や調査を行う1年生が播種作業に参加しました。
1年生は、発芽率の調査を行う箇所へ、種子100粒を手で正確に播いていました。



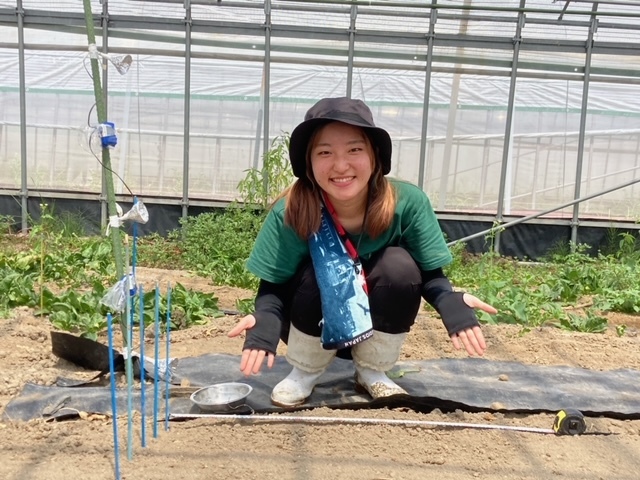
露地野菜を植える圃場の準備 R5.8.14
土地利用学科では、水稲や大豆のほかに露地野菜の栽培を学修することとしています。露地野菜はキャベツ、ブロッコリー、ジャガイモ、タマネギを予定していますが、まず8月下旬にキャベツの定植が控えています。
8月14日(月)、キャベツを定植する圃場の耕耘(こううん)を行いました。トラクタでの耕耘も、最初は基本的な操作を覚えるために指導を受けながら作業を行いますが、いつまでも教官が傍で指導するわけにはいきません。基本操作を覚えたら、次は耕耘ルートを自分で考えるなど、少しずつレベルアップしていきます。作業の目的に応じてトラクタや作業機を設定し、速やかに作業を行えるよう、少しずつ知識・技術を身につけていってほしいものです。
ちなみに、耕耘作業が終われば「お疲れさまでした! 解散!」ではありません。トラクタを洗車、給油、格納してようやく実習が終了します。洗車しておけばオイル漏れ等のトラブルをすぐに発見して対応することができますし、給油しておけば次に使う人が安心してスムーズに作業に取り掛かることができます。洗車も給油も実習のうち、これらも手際よく行えるよう実習を重ねていきましょう。




メロン定植に向けた蒸気消毒! R5.8.14
園芸学科野菜経営コースでは、毎年、11月3日に開催されるイベントへの出品に向けて、メロンの作付けを行っており、今年は2棟のガラス温室で栽培します。
8月14日(月)には、2棟のうちの1棟で、ベンチ内の培土を蒸気消毒しました。
蒸気消毒は、蒸気の熱を土壌に浸透させ、病害虫や雑草の駆除を行う土壌消毒方法で、土壌の温度を80度とし、30分間保ったら完成です。
蒸気消毒機の移動、設置、操作を行った2年生は、今回が4回目の蒸気消毒でしたが、これが最後の蒸気消毒ということで、感慨深げでした。




水稲に穂肥(ほごえ)や農薬をまいています R5.8.9
土地利用学科の学生は、7月下旬から水稲の幼穂(ようすい:茎の中にできる穂のもと)を観察しており、早いものは8月中旬から出穂(しゅっすい:穂が出ること)すると予想しています。このため、水稲の生育に合わせて、7月末から順次、穂肥(ほごえ:穂を充実させ収量を確保するために施す肥料)や病害虫防除の農薬をまいています。
穂肥や農薬の散布には背負式の動力散布機を使いますが、当然のことながら圃場一面に均等にまくのはなかなか難しい・・・ 穂肥の散布で明らかに散布ムラができたことがわかる場合は、頑張ってムラ直し(散布量が少ない箇所に手で追加でまくこと)を行います。しかし、このムラ直しがまた難しい・・・。 それもそのはず、ほとんどの学生は肥料を手まきした経験など無いのですから。
最初はぎこちなく穂肥を手まきしていた学生も、教官の指導によって最後は上手にまけるようになりました。暑い中お疲れさまでしたね! そして教官の頭の中では、「学生に習得させる農作業リスト」に「肥料の手まき」が追加されたのでした。




インドネシア共和国研修生との意見交換 R5.8.9
8月9日(水)山口大学から牛の繁殖技術を勉強中のインドネシア人研修生2名が来校されました。
来校の目的は、「農業の担い手の育成機関の視察」の他、「インドネシアの紹介」、「本校学生との意見交換」です。
インドネシアの紹介では、同国の食文化や観光スポットの他、畜産を中心とした農業の概要を、スライドを使って説明していただきました。
しかし、言葉はインドネシア語です。「インドネシア語
⇔ 英語 ⇔ 日本語」と2重に通訳するため、少々時間はかかりましたが、畜産の話だけでなく「インドネシアの伝統的な柄のシャツ」の話も聞くことができました。
日本滞在中は休む間もなく勉強され、帰国後は現地農家の指導にあたられるとのことです。
ちなみに、インドネシアの平均気温は30℃程度とのことですが、35℃を超えることは無いそうで、日本の夏はインドネシアの方にとっても暑いようです。




!やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.8.6
8月6日(日)、農業大学校において、受講生45名を対象に作目基礎研修の6コース共通の研修を行いました。
当日は、作物の病害虫対策の基礎知識について、室内講義と屋外実習を組み合わせた内容で実施し、屋外実習では、薬剤の調合方法や4種類の防除器を使って散布方法について学びました。
防除器を使うのが初めての受講者もおられ、興味深げに実習に取り組んでいました。


メロン定植に向けた蒸気消毒の準備! R5.8.2
園芸学科野菜経営コースでは、毎年、11月3日に開催されるイベントへの出品に向けて、メロンの作付けを行っています。
今年は、緑肉系のメロン「ミラノ夏Ⅰ」と赤肉系の「妃(きさき)」を、2棟のガラス温室で栽培します。
メロンの定植にあたっては、毎回、栽培ベンチ内の土の蒸気消毒を行っています。
8月2日(水)には、蒸気消毒の準備として、蒸気放出用のホースをベンチの中央に敷き、その上にシートを敷きました。
担当の1年生は、職員らとともに、手際よくシートの敷設や固定等を行っていました。
今週末には、蒸気消毒を行う予定です。




大斜面の草刈り! R5.8.2
8月2日(水)の午前、園芸学科野菜経営コースの学生と研修生4名が、大斜面の草刈りを行いました。
気温が30度を超える中での草刈りでしたが、学生らは適宜休憩や水分をとりながら、昼前までにはきれいに刈り終えていました。




イチゴの株管理! R5.8.2
園芸学科野菜経営コースでは、6月上旬より、イチゴの採苗を行っており、親株から伸びるランナーを鉢受用のポットで受け、本圃へ定植する子株を増やしているところです。
子株の切り離しが間近となった8月2日(水)には、担当の2年生が、子株の管理を行いました。
古葉を中心に葉を除いた子株は、すっきりとした見た目になりました。
8月15日頃には、子株の切り離しを行う予定です。




メロンの果実品質調査! R5.7.31
7月31日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの収穫時期を把握するための果実品質調査を行いました。
今回調査したのは、「ミラノ夏Ⅰ」という緑肉系のメロンです。
果実を切るとメロンの香りが広がり、収穫適期かと期待しましたが、糖度は目標に達していなかったため、収穫はもう少し待つこととしました。


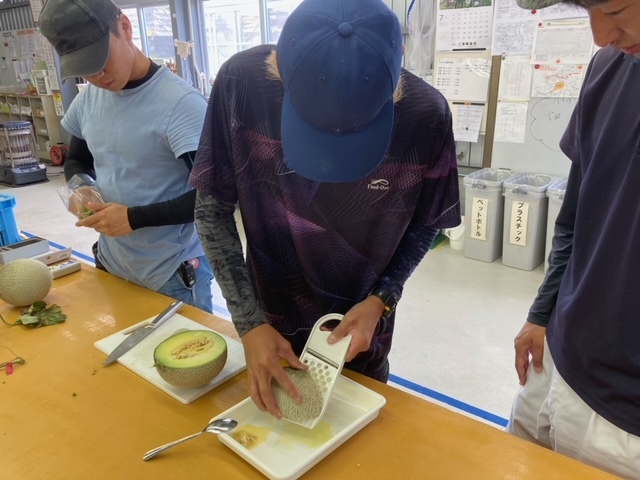
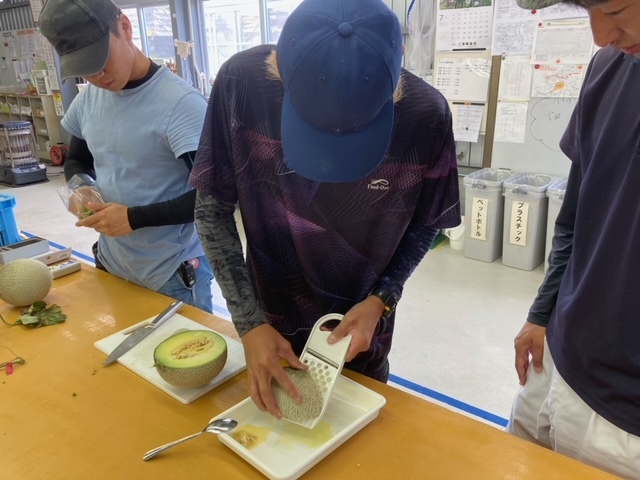
パンジーやビオラの播種を行いました! R5.7.28
7月28日(金)、園芸学科花き経営コースでは、パンジーやビオラの播種を行いました。
今回の作型は、11月3日(金)に開催するイベントへの出品に合わせたもので、パンジーが「よく咲くスミレ スィートポテト」他5品種、ビオラが「ソルベXP プリムローズブロッチ」他4品種の種を播きました。
担当の1年生は、真空播種機を用いて、セルトレイへ播種するとともに、播種していない所がないか確認を行っていました。

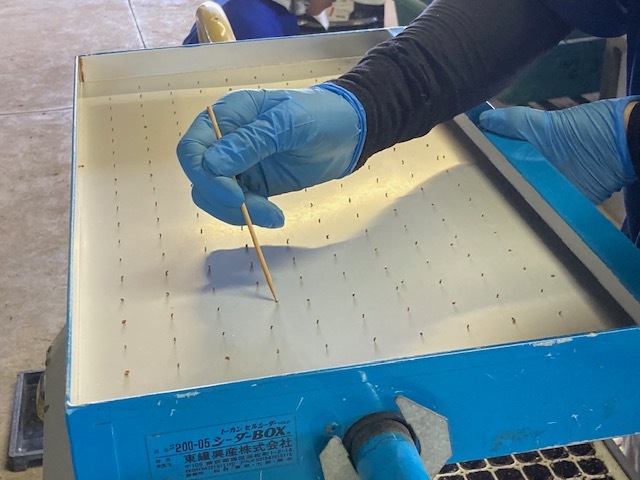
キャベツの播種を行いました! R5.7.31
7月31日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、キャベツの播種を行いました。
今回、「おきなSP」と「夢いぶき」の2品種の種をまきました。このうち、早生品種の「おきなSP」は、11月3日(金)に開催するイベントへの出品をねらっています。
担当の1年生は、教官から、セルトレイへの培土を充填、播種、覆土の仕方を教わりながら、両品種とも9枚のセルトレイに播種を行いました。
今後、種子の発芽を確認すれば、育苗用ガラス温室へ移動する予定です。




ブドウ園のイノシシ対策! R5.7.31
本校では、今年4月中旬頃、1頭のイノシシが校内で確認されました。
現在、そのイノシシは果樹園を中心に活動しており、ほ場の掘り起こしといった被害が散見されています。
こうした中、園芸学科果樹経営コースでは、これから収穫期を迎えるブドウに被害が及ばないようにするため、露地のブドウ園にワイヤーメッシュを設置することとしました。
7月28日(金)には、ブドウ班の学生や研修生に加え、ナシ班の学生も参加して、ワイヤーメッシュを設置しました。翌日には、露地ブドウ園地全体を囲む予定です。




ナシ「新水」の果実品質調査! R5.7.31
7月31日(月)、園芸学科果樹経営コースでは、ナシの収穫時期を把握するための果実品質調査を行いました。
今回調査したのは、早生の赤ナシである「新水」です。
糖度は12度あり、食味も申し分なかったことから、来週には直売所へ出荷する予定です。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.7.30
7月30日(日)、農業大学校において、受講生11名を対象に作目基礎研修の「果樹コース」を行いました。
当日は、夏空が広がる暑い一日となりましたが、比較的涼しい午前中に温州みかんの摘果作業を行いました。受講生たちは、習った摘果基準を頭に思い浮かべながら作業に奮闘していました。
午後は室内で、各種果樹の夏場の管理について講義を受けました。
受講生たちは、積極的に質問をしながら、熱心に聴講していました。




ブロッコリーの播種を行いました! R5.7.28
7月28日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、ブロッコリーの播種を行いました。
今回の作型は、11月3日(金)に開催するイベントへの出品をねらうものです。
品種は、「ピクセル」で、花蕾の粒が細かく、歯触りがよいのが特徴です。
担当の1年生は、教官の指導の下、セルトレイへの培土を充填、播種、覆土を行いました。その後、セルトレイの上を新聞紙で覆い、新聞紙に水をかけました。
これは、乾燥を防いで、発芽を促すために行うもので、新聞紙は、発芽すれば取り除く予定です。




メロンの播種を行いました! R5.7.28
7月28日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの播種を行いました。
今回の作型は、11月3日(金)に開催するイベントへの出品に合わせたもので、品種は赤肉系の「妃(きさき)」と緑肉系の「ミラノ夏Ⅰ」です。
野菜経営コースの1年生は、教官や2年生の指導のもと、育苗箱に培土を充填したり、培土にスジをつけたり、種子の向きをそろえながら種を播いていました。
このメロンは、翌週には鉢上げを行う予定です。




ガラス温室内のベンチの耕うん! R5.7.28
7月28日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室内のベンチの耕うんを行いました。
このガラス温室では、今年の2月からキュウリを栽培していましたが、6月上旬にの収穫を終え、その後は病害虫対策として、施設を密閉してハウス内を高温に保つ「蒸し込み」処理を行っていました。
今週まで、残渣やマルチなどの片付けが終わったため、仕上げとして、ベンチ内の培土の耕うんを行ったものです。
作業を行った1年生は、ベンチ耕うん機を要領よく操作していました。
本ガラス温室では、今後、メロン栽培に使用する予定です。




栽培管理票の取りまとめ! R5.7.28
野菜経営コースでは、学生や研修生が、自身が担当した作目や品種ごとに、栽培管理票を作成しています。
栽培前には、目標とする収量や売上、使用する資材等を取りまとめておくとともに、栽培や販売終了後には、生産実績に加え、販売実績を取りまとめて、経営収支を算出します。
学生らは、7月27日より夏休みに入ったため、気温の高い午後1時から午後3時の間は、冷房の効いた教室で、この栽培管理票の取りまとめを行っています。
7月28日(金)には、2年生2名と1年生3名が取りまとめ作業を行っていました。
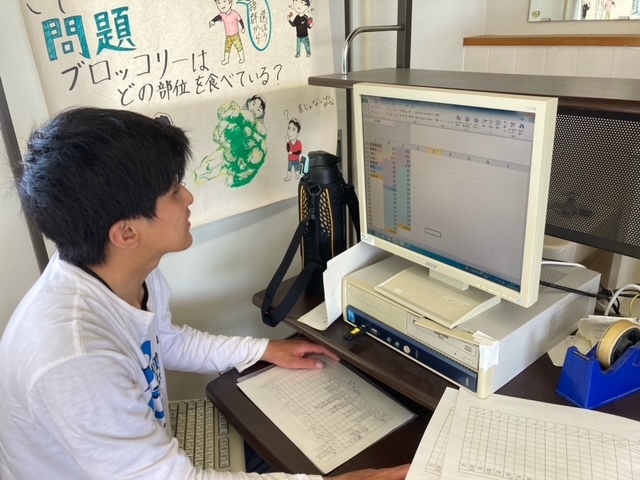

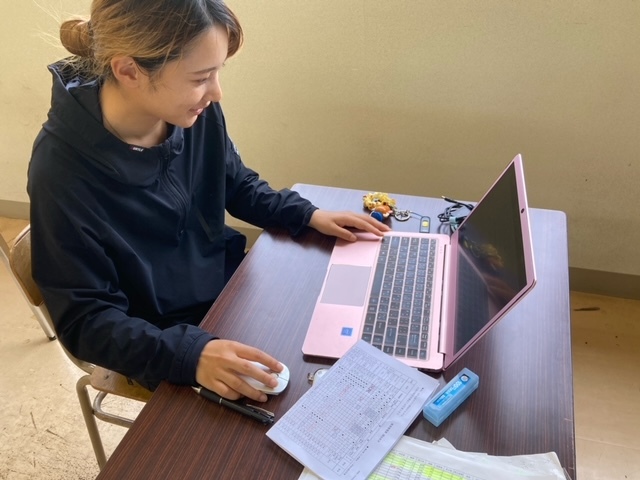

リモコン式草刈機、その名は「アラフォー傾子」! R5.7.26
土地利用学科では、入学直後の4月にリモコン式草刈機の学修を行いました(詳細は4月17日の農大ニュースを参照)。このリモコン式草刈機ですが、メーカー各社がそれぞれ特徴ある機種を開発、販売しています。7月26日(水)は、中四国クボタさんの御協力のもと、筑水キャニコムさんが開発したリモコン式草刈機について学びました。その名前も「アラフォー傾子(けいこ)」! 傾斜40度前後の斜面でも草刈作業ができるということから、この名が付いたとか。
平坦なところと違って斜面を走らせるのは、機械を転倒させるかもしれないという恐怖感もあって非常にドキドキするものですが、学生達は積極的に手を挙げて操作に挑戦していました。傾斜約30度で凸凹も少なく比較的操作しやすかったかもしれませんが、初めての斜面での操作は、貴重な経験になったことでしょう。
学生達は、将来リモコン式草刈機を所有している農業生産法人に就業するかもしれません。農業大学校にもリモコン式草刈機はありますので、時にはそれも使いながら、多くの機械の操作を習得していきましょう。




経営プロジェクト中間発表会【LAユリ】! R5.7.25
7月25日(火)、園芸学科で、経営プロジェクト中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『LAユリの球根解凍後の貯蔵期間が品質に及ぼす影響』で、花き経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を説明しました。
参加した学生や研修生からは、草丈が等級に及ぼす影響や目指す時期に出荷する方法に関する質問があり、担当学生は丁寧に答えていました。
また、発表会の後は、調査を行っているガラス温室内の見学を行いました。
次回は8月24日に開催し、ホウレンソウやイチゴ、キクに関する課題の発表が行われます。


土地利用学科、ドローンの操作演習を始める! R5.7.24
土地利用学科では、トラクタやコンバイン同様、ドローンも重要な農業機械の一つと位置づけ、基本的な操作方法や農業現場での活用について学修してくこととしています。
7月21日(金)、第1回の講義・操作演習を行いました。講師は「やまぐちドローン操友会」、腕利きのドローンパイロットの集団です。まずは、ドローンを使用する際に必ず覚えておかなければならないことについて教わりました。昼食後、冷房の効いた部屋、眠たくなる条件は揃っているにもかかわらず、皆しっかり起きて(一部アブナイ学生もいましたが)聴いていました。講義が終われば、いよいよグラウンドで操作演習です!
それにしても、グラウンドの暑いこと暑いこと・・・気温はかるく30℃を超えています。とはいえ、カラッとした風が吹いていましたので、テントの陰で水分補給しながら約1時間、組み立てから基本操作まで教えてもらうことができました。
さあ、9月から本格的な操作演習が始まります。この2年間でどこまで上達するか、楽しみですね。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.7.23
7月23日(日)、農業大学校において、受講生35名を対象に作目基礎研修の「野菜Ⅰ・Ⅱコース」、「水稲コース」を並行して実施しました。
当日はコース別に、夏野菜の管理や秋野菜の種まき、水稲の中間管理について講義及び実習を行いました。
朝から強い陽光が照りつける夏らしい天気になり、熱中症に気をつけながらの実習でしたが、受講生たちは熱心に聴講していました。



ナシ園への防蛾灯の設置! R5.7.20
7月20日(木)、園芸学科果樹経営コースのナシ班では、ナシ園へ防蛾灯を設置し始めました。
これからナシの成熟が進むにつれ、園外から夜行性の蛾が飛来します。蛾が果実を吸汁すると、変色腐敗して、落果するなど大きな被害となります。
そこで、光によって蛾の飛来を防ぐため、防蛾灯を設置するものです。
防蛾灯は20台程度設置する予定で、ナシ園全体をカバーできるよう均等に配置していきます。
今後、ナシ園では、これから10月にかけて、夜間は黄色の光に包まれます。




露地カボチャの収穫! R5.7.20
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、カボチャの施肥体系の検証に取り組んでいます。
7月20日(木)には、露地ほ場で栽培しているカボチャの収穫を行いました。
収穫しようとした果実には、高温による日焼けや収穫前の大雨による腐りなどがみられるものもありましたが、担当の2年生は、1果ずつ状態を確認しながら、丁寧に収穫を行っていました。
今後、収穫物調査を行うとともに、株を回収して親づるの主茎長や重さを計測する予定です。




経営プロジェクト中間発表会【トルコギキョウ】! R5.7.20
7月20日(木)、園芸学科で、経営プロジェクト中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『トルコギキョウの直播、稚苗定植が省力化、収益に及ぼす影響』で、花き経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を説明しました。
参加した学生や研修生からは、調査区の設置の仕方や発芽率を高める温度管理などに関する質問があり、担当学生は丁寧に答えていました。
また、発表会の後は、調査を行っているハウス内の見学を行いました。
次回は7月25日に開催し、イチゴやLAユリ、キクに関する課題の発表が行われます。


販売実習を行いました!【防府市まちの駅「うめてらす」】! R5.7.19
7月19日(水)に、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行いました。
今回は、園芸学科の2年生4名に加え、土地利用学科の1年生2名と園芸学科野菜経営コースの1年生1名、畜産学科酪農経営コースの1年生1名が初めて参加しました。
お客様が少ない中、学生らは、お客様一人一人に、自分たちが作った農産物について、丁寧に説明を行っていました。
販売実習後には、積み忘れた商品があったなどの反省点を話し合うとともに、次の販売実習に活かせるよう対策を考えていました。
来月は、8月23日(水)に、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行う予定です。


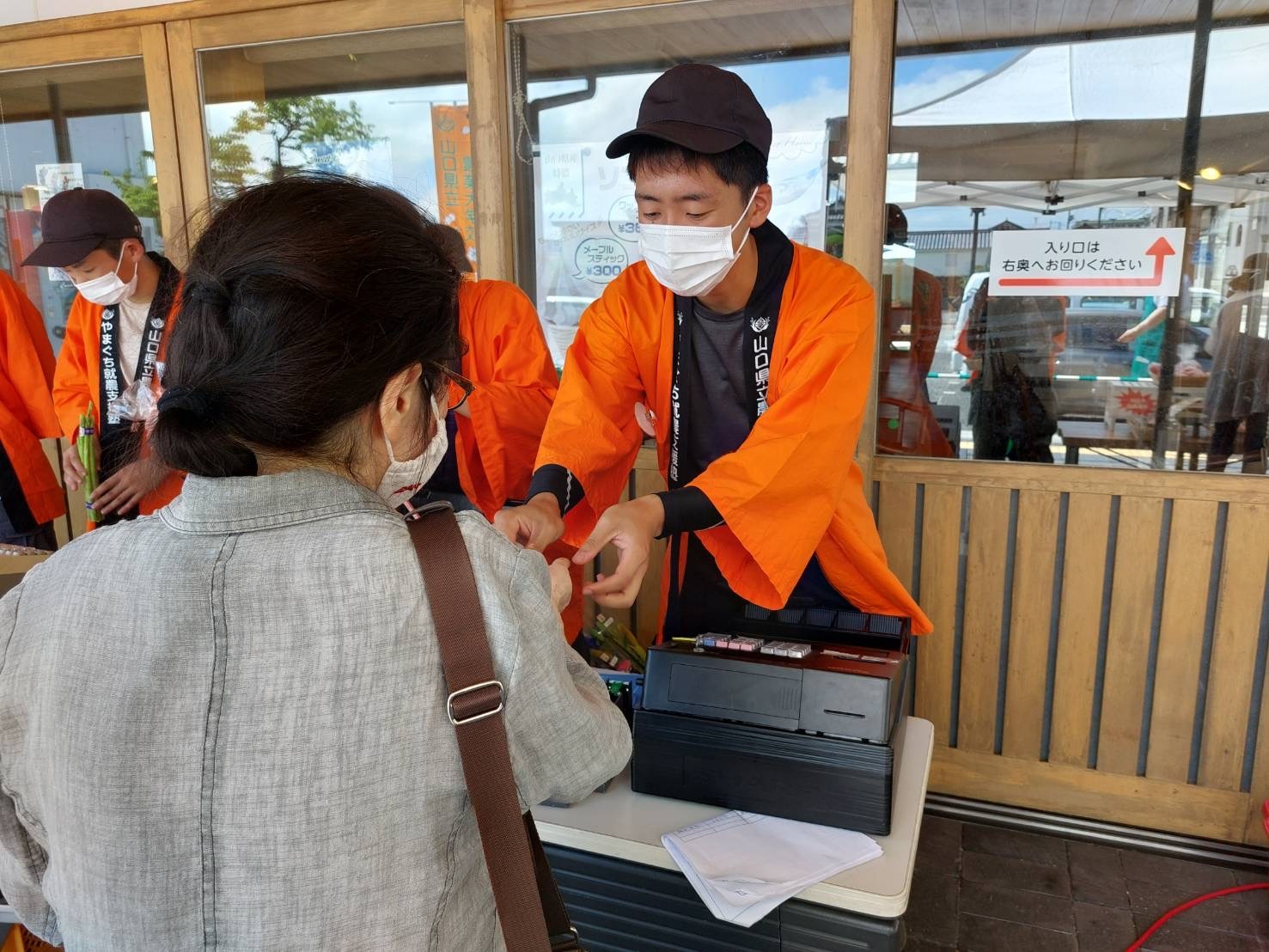

JA山口県の広報誌の取材を受けました! R5.7.19
A山口県の広報誌「JAやまぐちけん」では、2023年7月号より、農業大学校の紹介記事を掲載されています。
2023年8月号の園芸学科花き経営コースに続き、2023年9月号では、果樹経営コースが紹介されます。
このため、7月19日(水)には、果樹経営コースの学生や職員が取材を受けました。
学生らは、自身が担当しているハウスで撮影されるとともに、果樹出荷調整棟でインタビューを受けました。
取材の結果は、来月末に発刊される広報誌をご覧いただくか、JA山口県のホームページでご覧いただけます。




明日は雨。なら今日中に2回目の中耕だ! R5.7.19
土地利用学科が7月7日に中耕培土した大豆は、その後の生育も順調に進み、7葉期になりました。ちょうど2回目の中耕培土の時期。圃場を見ると、4日間降雨がなかったため程よく乾いています。しかも明日は雨予報・・・ 2回目の中耕培土をするならまさに今でしょ! ということで、土地利用学科は7月18日(火)、大豆の2回目の中耕培土を行いました(10日前にも似た文章を書いたような・・・)。
さて、乗用管理機は1人乗りです。学生は交代で乗りますが、乗らない学生は待っている時間に何をしているのでしょうか。実は、雨水を圃場外に排水するための大事な溝が乗用管理機の走行でつぶれるので、その溝を作り直すという大事な作業を行っています。皆鍬を手に、溝に落ちた土をさらい、溝と溝をきっちりつないで、ようやく作業終了です。
このように学生達が協力して作業したお陰で、中耕培土のお手本のような見事な出来栄えとなりました。2回の中耕培土がまさに適期に実施できたので、これから大豆がグンっと生育していくことでしょう。




フラワーアレンジメントのラッピング! R5.7.19
7月19日(水)の午後2時より防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習が行われます。
このため、同日の午前中に、園芸学科花き経営コースの学1年生が、販売実習に出品するフラワーアレンジメントのラッピングを行いました。
フラワーアレンジメントを透明なフィルムで覆い、リボンを装飾していきました。
学生らは、リボンの色や組み合わせに悩みながら装飾していましたが、最後は見事な仕上がりとなりました。




経営プロジェクト中間発表会【トマトの天敵による防除】! R5.7.13
7月13日(木)、園芸学科で、経営プロジェクト中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『トマト栽培におけるコナジラミの天敵を導入した防除体系の確立』で、野菜経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を説明しました。
参加した学生や研修生からは、要防除水準に基づく防除や天敵温存植物に関する質問があり、担当学生は丁寧に答えていました。
また、発表会の後は、調査を行っているハウス内の見学を行いました。
次回は7月20日に開催し、課題はトルコギキョウに関するプロジェクトです。

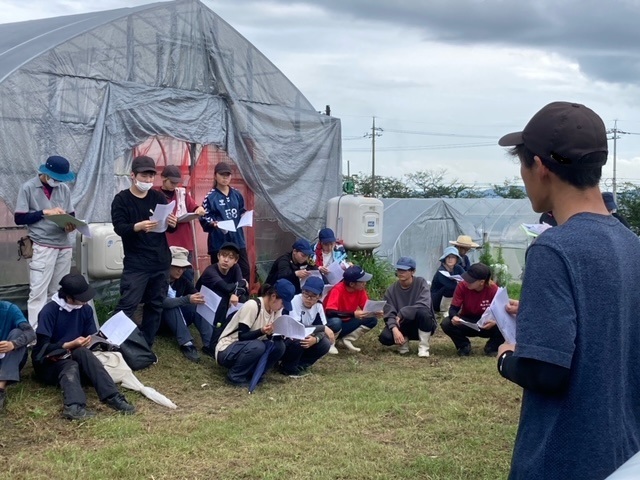
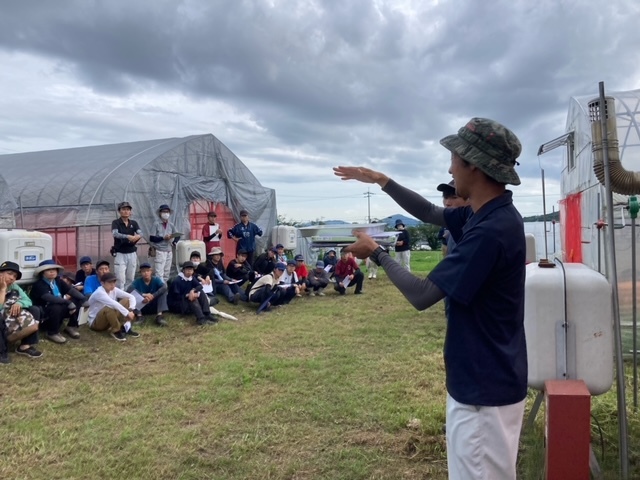

水稲の生育は順調かな? R5.7.13
土地利用学科では、水稲については全員を5班に分け、班毎に課題を決めて試験区を設置しています。毎週水曜日を水稲の生育調査日と決めており、7月12日(水)に3回目の調査を行いました。
調査項目は、水稲の生育調査の基本である、草丈(くさたけ:稲株の高さ)、茎数(けいすう:茎の数)、葉齢(ようれい:何枚目の葉が出ているか)、葉色(ようしょく:葉の色の濃淡の度合い)の4つです。
3回目ともなると慣れてきたのでしょう、各自さっさと調査を進めていました。ただ、葉齢の数え方やカラーチャートを使った葉色の判定など、まだまだ難しいようです。あとで教官が確認すると「・・・」と絶句するおかしなデータもありますが、そこは随時確認、復習しながら、全員がしっかり調査ができるようになるまで励みましょう。
生育調査は夏休みの間も続きます。土地利用学科では、今後も調査や日々の観察を通じて、作物を見る目を養っていきます。



ブドウのトンネルメッシュのビニル除去! R5.7.12
ブドウでは、雨を介して広がる病気を防ぐため、雨よけ栽培が行われます。
本校では、ガラス温室やパイプハウスでの栽培に加え、果樹棚の上にトンネル状の簡易雨よけ資材(トンネルメッシュ)を設置し、これにビニルを被覆する簡易雨よけ栽培を行っています。
本年は、3月中下旬にトンネルメッシュにビニルを被覆しましたが、6月末に果房への袋掛けを終えるとともに、近々、梅雨明けが見込まれることから、トンネルメッシュのビニルを外すこととしました。
7月12日(水)には、園芸学科果樹経営コースのブドウ班が、ナシ班やカンキツ班の学生に手伝ってもらいながら、次々とビニルを外していきました。
ビニルを除去することで、日中の棚上の温度が下がることから、果粒の着色がさらに進むものと期待しています。



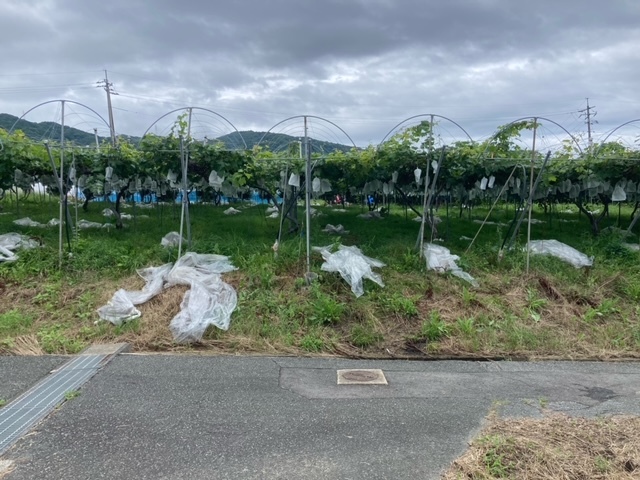
ミニトマト定植準備【施肥・耕うん・畝立て】! R5.7.11
園芸学科野菜経営コースでは、1年生がミニトマトの栽培に取り組みます。
7月11日(木)には、パイプハウス内にたい肥や石灰質肥料をまいた後、トラクタで耕うんしました。1年生は、トラクタによる耕うんは初めてでしたが、職員の指導に従いながら、慎重に作業を行っていました。
耕うん後は、畝立て成形機を使用して、畝立てを行いました。畝の位置や幅の決定にあたっては、2年生や職員らが丁寧に教えていました。
今後、潅水装置の設置やマルチを被覆し、今週末にはミニトマトを定植する予定です。




カボチャの収穫物調査! R5.7.12
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、カボチャの施肥体系の検証に取り組んでいます。
7月12日(水)には、15日前に収穫したカボチャの収穫物調査を行いました。
担当の2年生は、試験区ごとに、果実の重量や果実径、糖度などを調べました。
カボチャの出荷は、翌日から行う予定です。




販売実習の打合せを行いました! R5.7.12
7月19日(水)の午後2時より、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行います。
その準備のため、7月12日(水)に、打合せを行いました。
当日の役割分担を決めるとともに、販売する品目の紹介内容や持っていく物品のチェック、レジ操作の確認などを行いました。
今回の目玉は、「スイートコーン」、「レモン」、「フラワーアレンジメント」です。
その他、シシトウやピーマン、アスパラガス、キュウリ、トマト、花束も販売する予定です。
ぜひ、お立ち寄りください。
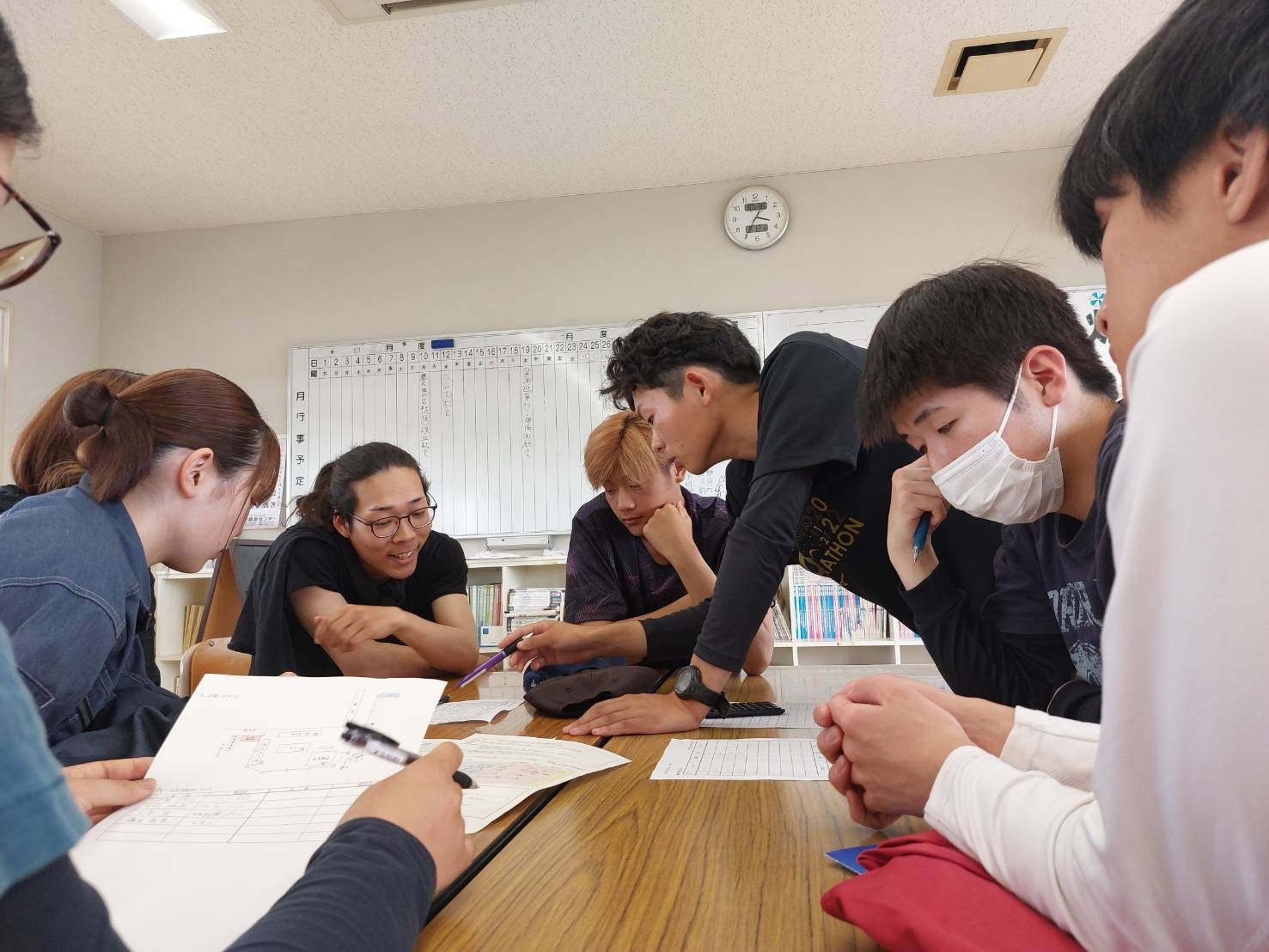
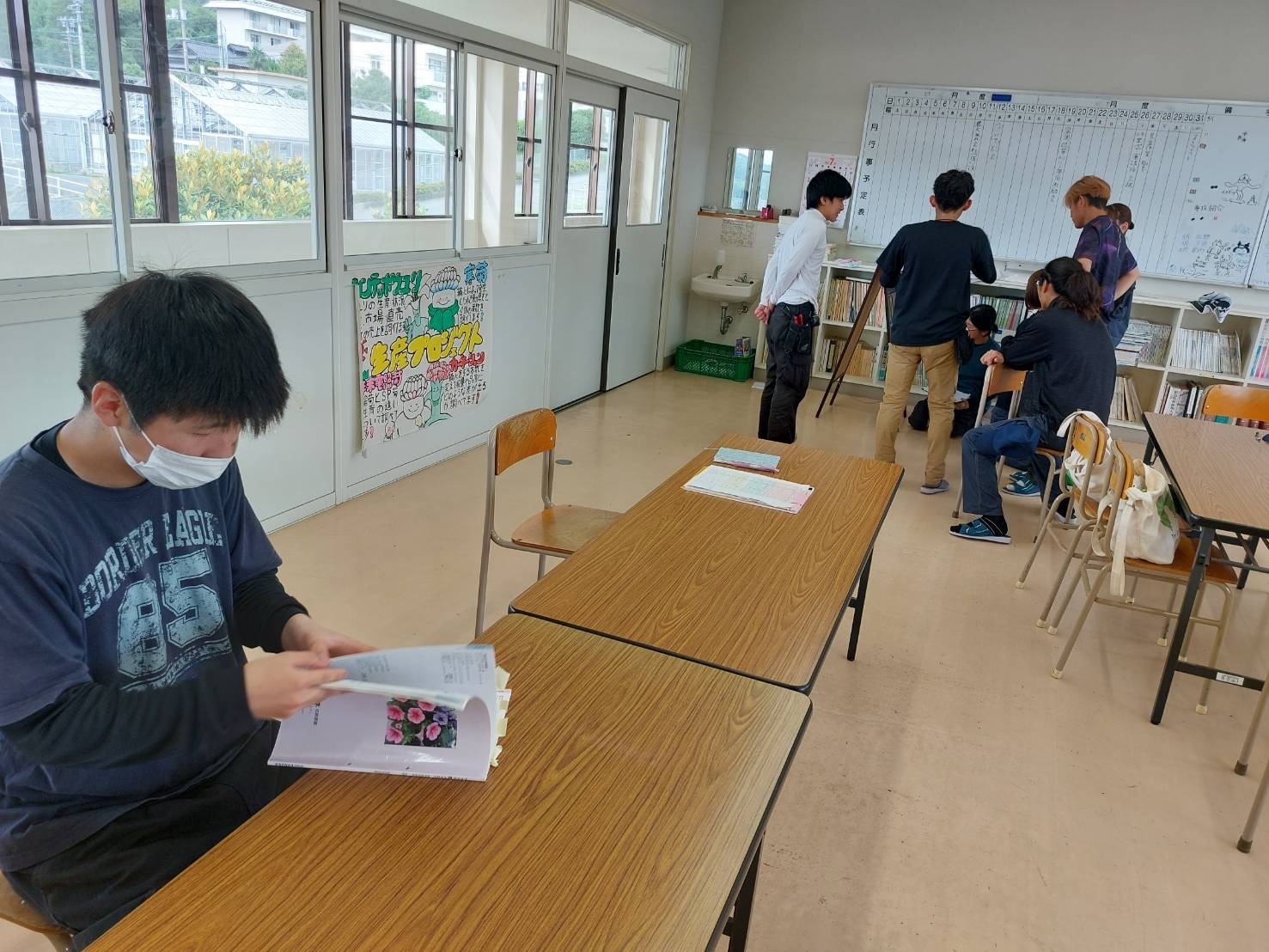
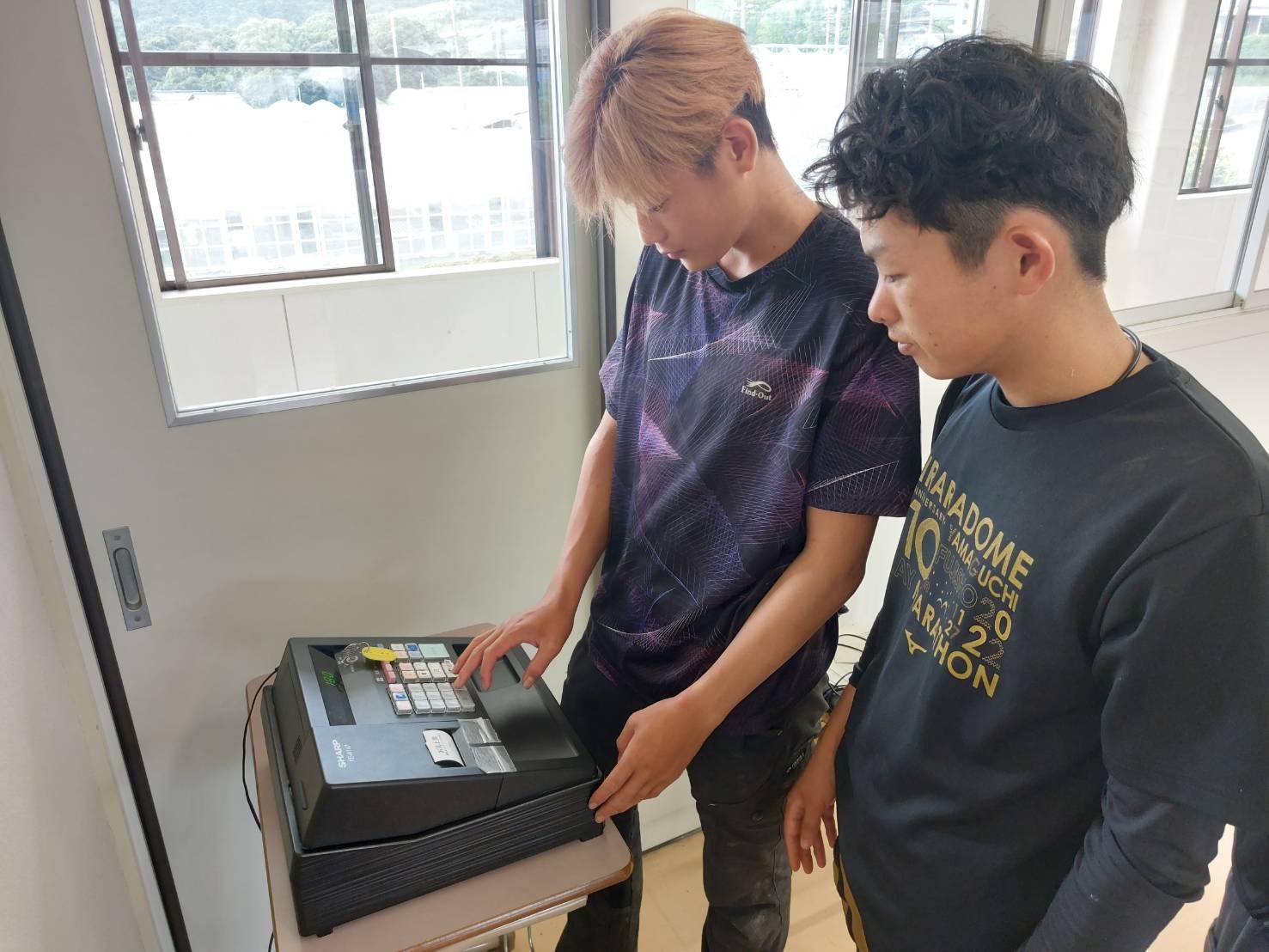
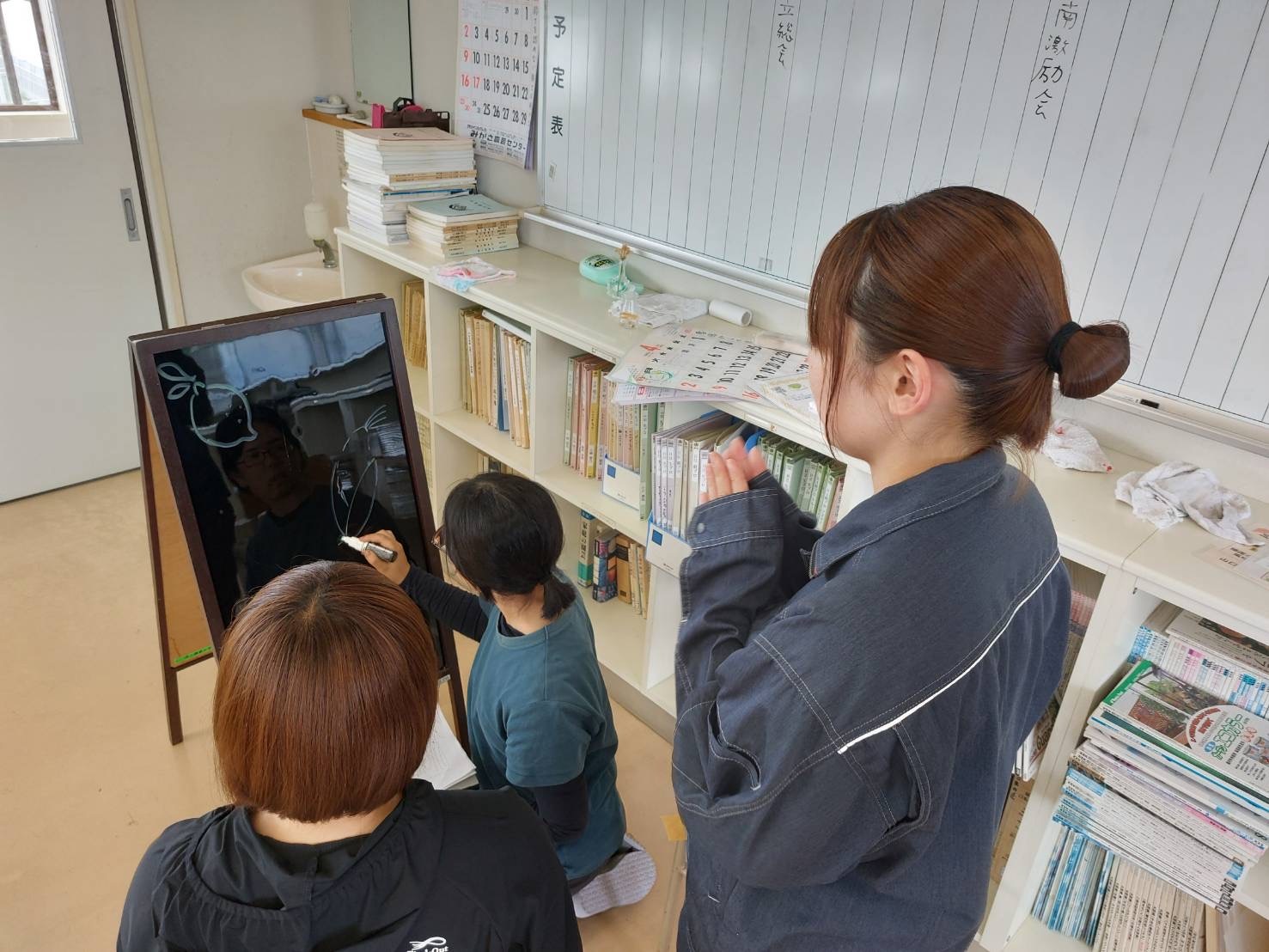
花きの出荷数量のチェック方法の再周知! R5.7.11
本校が出荷している花市場では、7月より切花市のWeb販売を開始されました。
これを受けて、園芸学科花き経営コースでは、出荷伝票の内容と実際の出荷数量に間違いがないよう、これまで以上に、出荷前チェックの徹底を図ることとしました。
7月7日(金)の夕方の専攻タイムで、学生らがチェック方法について話し合いを行い、対策を整理しました。
7月11日(火)には、朝の専攻タイム後に、出荷前チェックの方法について、改めて説明、確認を行い、周知を図りました。
その後、出荷伝票を入れるボックスを、学生らが主体となって作成しました。
今後も、正確に出荷できるよう、適宜改善を行っていきます。


1haの田んぼで田植えに挑戦だ! R5.7.10
土地利用学科が通常管理している圃場は、大きくても20aに満たない圃場ばかりです。この度、市内の農業法人の協力を得て、1ha規模の圃場での田植えを行わせてもらえることになりました。1haって、広いですね・・・ こちらの畔(あぜ)から反対側の畔まで、直線距離で約170m! 全部で7圃場・合計6.7haを3日で植えるというのが、今回土地利用学科に与えられた課題です。
学生達も圃場を目の前にして、これを真っすぐ植えるなんてとても無理・・・ と思ったことでしょう。しかし、植えなければ作業は終わりません。とにかく植えるぞ!
かくして、土地利用学科は7月4日(火)から6日(木)の3日間、終日田植えを行いました。
反対側の畔に目印(ポール)を立て、それを目掛けてひたすら植えていきます。畔に着いたら、みんなで苗、肥料、除草剤等を補給し、旋回し、また真っすぐ植えていきます。朝から晩まで、それの繰り返しです。学生達の操作スピードがどんどん上がっていきます(でなければ、終わりません・・・)。そして、当初計画どおり、3日間でなんとか6.7haを植え切りました。1年生、よく頑張りました!
さて、田植えの作業は終わりましたが、これで終わりではありません。これから全員で作業の振り返りを行い、来年度に向けて取組の改善等を検討していく予定です。




午後から雨が降る!午前中に大豆の中耕だ! R5.7.10
土地利用学科が6月16日、18日に播種した大豆は、出芽も良好で、既に3葉期になりました。1回目の中耕培土(ちゅうこうばいど)の時期ですが、梅雨の長雨でなかなか作業ができませんでした。ところが、今週は比較的好天だったため、圃場が程よく乾きました。中耕培土をするならまさに今! でも午後からは雨予報! ・・・ならば、午前中に中耕培土をやろうじゃないか!
ということで、土地利用学科は7月7日(金)、急遽、大豆の中耕培土を行いました。使用するのは乗用管理機(しかも新車!)です。いつものことながら、学生達は初めての機械で緊張したと思いますが、事前に教わった操作を確実に行い、トラブルもなく作業は終了しました。作業終了直前に雨が降り出してヒヤヒヤしましたが、圃場の状態や機械の調子も良好で、学生達が頑張って作業したお陰で、中耕培土のお手本のような見事な出来栄えでした。
約10日後には、2回目の中耕培土を行う予定です。今後も天気予報を注視しながら、適期を逃さず、作業に取り組んでいきましょう。




全国初となる農大生の会社が設立! R5.7.10
本校の学生による「一般社団法人やまぐち農大」(代表理事:稲垣晃太朗、社員数:57名)の設立総会を7月10日(月)に開催しました。
総会では設立経緯の説明の後、会社の定款、役員選出、本年度事業計画の議案が満場一致で承認されました。
本年度は青果物販売実習や拠点祭(仮称)等の農産物販売事業が主となり、今後は新商品開発事業も並行して進める計画です。
学生は、この「一般社団法人やまぐち農大」で、事業計画の決定プロセス、会計、決算、経営責任などを実体験し、将来、法人経営などの中核を担うために必要な経営能力やビジネス感覚を学修することとなります。
なお、農業大学校の学生が構成員として会社登記するのは、全国初となります。


実物鑑定競技大会を開催! R5.7.3
農大では普段の講義や実習で学んだ知識の他、農業全般に関する幅広い知識を習得することを目的として、毎年、実物鑑定競技を実施しています。今年は7月3日に開催し、学生55人と社会人研修生9人が競技に参加しました。
学生や研修生は、日頃の成果を発揮しようと計45問の問題に真剣に向き合っていました。成績優秀者は、後日、表彰を行うことにしています。



トルコギキョウ定植準備【トラクタによる耕うん】! R5.7.6
園芸学科花き経営コースでは、トルコギキョウの定植準備を行っています。
7月6日(木)には、パイプハウス内をトラクタで耕しました。
前日、耕うん機で耕したところ、思いのほか土が固くしまっており、深くまで耕うんできなかったため、今回、トラクタで耕うんするものです。
今回、トラクタの操作は、1年生が行いました。
1年生らは、職員から操作の指導を受けながら、慎重にトラクタ操作を行っていました。




販売実習を行いました【道の駅ソレーネ周南】! R5.7.5
7月5日(水)に、「道の駅ソレーネ周南」で販売実習を行いました。
今回は、園芸学科の2年生5名に加え、土地利用学科の1年生1名と園芸学科果樹経営コースの1年生1名、畜産学科肉用牛経営コースの1年生1名が初めて参加しました。
あいにくの雨模様で、お客様が少ない中、参加した学生は、それぞれが工夫してお客様を呼び込んでいました。
次回は、7月19日(水)に、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行う予定です。




トルコギキョウ定植準備【耕うん】! R5.7.5
園芸学科花き経営コースでは、年末出荷用のトルコギキョウの栽培を行います。
7月5日(金)には、定植準備のため、パイプハウス内を、耕うん機で耕しました。
耕うん作業を行ったのは1年生で、今回初めて操作するため、専攻教官に操作方法を指導してもらいながら、ハウス内を耕していました。
今後、土壌消毒を行った後、9月上旬にトルコギキョウの苗を定植する予定です。




販売実習に向けたフラワーアレンジメントの作成! R5.7.5
7月5日(水)の午後2時より、「道の駅ソレーネ周南」で、販売実習が行われます。
このため、同日の午前中に、園芸学科花き経営コースの学1年生が、販売実習に出品するフラワーアレンジメントを作りました。
今回は、「トルコギキョウ」、「リンドウ」、「バラ」、「カスミソウ」などを使って作成しましたが、1年生も数をこなすことで、少しずつ上手になってきています。


トマト苗の鉢上げを行いました! R5.7.5
7月5日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、トマト苗の鉢上げを行いました。
1年生2名が、セルトレイに播種した台木の「Bバリア」に、穂木の「桃太郎ホープ」を接いだ苗を、ポットに移植するもので、今回約140鉢を鉢上げしました。
鉢上げ後は、約2週間、ガラス温室内で管理した後、7月下旬にハウスに定植を行い、10月下旬頃まで栽培する予定です。




キクの親株定植準備【土壌分析】! R5.7.4
園芸学科花き経営コースでは、ガラス温室にキクの親株の定植を予定しています。
7月4日(火)には、定植を予定しているベンチ内の培土の土壌分析を行いました。
今回、1年生が初めて土壌のpHとECを測定することから、専攻教官が分析手順を指導しました。
その後、1年生は、手順どおりにpHとECを測定しました。
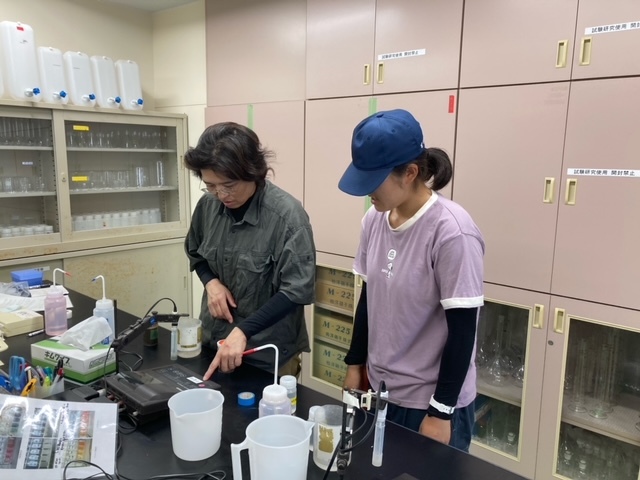

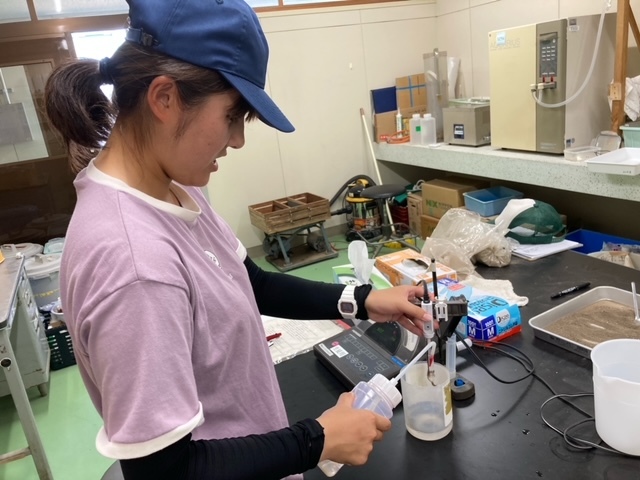
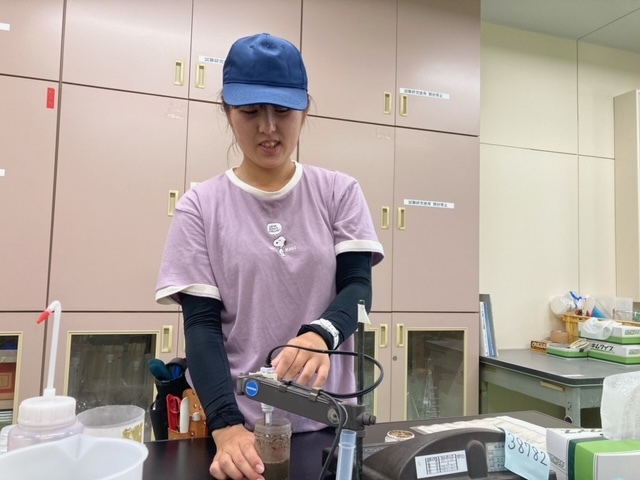
メロンの袋かけを行いました! R5.7.4
園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室でメロン栽培に取り組んでいます。
6月上旬の交配後、果実は日々大きくなるとともに、ネットの形成も進んでいます。
7月4日(火)には、1年生と研修生が、メロンの果実に袋かけを行いました。
袋かけは、果実を日焼けから守るために行うもので、新聞紙とホッチキスを使って果実を覆っていきました。
メロンの収穫は、今月末頃を予定しています。




白ネギの移植! R5.7.4
7月4日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生が白ネギを移植しました。
今回、チェーンポットで育苗したネギの苗を、簡易移植器「ひっぱりくん」で移植しました。
圃場の耕うん、溝切は6月23日に行いましたが、その後天候に恵まれず、当日も土が湿った状態でしたが、貴重な晴れ間を逃さないよう移植を行ったものです。
このため、本来なら移植器が行う覆土を、人力で行いました。
今後は、大きくになるにつれ、根元に土をかけて白い部分を作り、鍋が恋しくなる時期に収穫を予定しています。




水稲の追肥 ! R5.6.30
土地利用学科では6月上旬から田植えが始まり、田植が早い圃場ではもう3週間が経ちました。おやおや、一部の圃場で、葉色が淡い箇所が見えますね・・・。田植機には施肥機が付いているので、田植えと同時に肥料を施用したはずですが、どうやら施肥機が詰まってうまく施肥できなかったところがあったようです。
そこで、少しだけ追肥を行うことにしました。動力散布機を使うのは除草剤散布に続いて2回目です。とはいえ、蒸し暑いなか、重さ15kg以上の動力散布機を背負って、幅の狭い畦畔の上を歩いて肥料を散布するのは大変な作業です。それでも、学生達は散布ムラができないように考えながら、頑張って散布していました。作業後は、もう汗びっしょり・・・よく頑張りました!
しかし、動力散布機を使っての追肥はこれで終わりではありません。一番暑い時期には穂肥の散布があります(しかも2回も!)。穂肥の時に上手く散布できるよう、今日は良い練習になったことでしょう。



休耕田で牛が食べ歩き! R5.6.29
6月29日(木)肉用牛専攻の1年生が、学校近くの休耕田で放牧の実習をするため繁殖牛を連れて行きました。
こうした圃場は、作付けを休んでいるため野草が伸び放題です… が、野草は牛のエサになります。
野草は、この時期になるとすっかり伸びて牛の背中が隠れるくらいになっていますが、牛が1~2カ月間、野草をしっかり食べ歩くことできれいになります。
学生は、定期的に放牧地の状況を確認し、その効果を確認に行く予定です。



販売実習の打合せを行いしました! R5.6.29
7月5日(水)の午後2時から、道の駅「ソレーネ周南」で販売実習を行います。
その準備のため、6月29日(木)に、打合せを行いました。
当日の役割分担を決めるとともに、販売する品目の紹介内容や持っていく物品のチェック、レジ操作の確認、商品候補の試食などを行いました。
今回の目玉は、「トマト」、「レモン」、「フラワーアレンジメント」です。
その他、シシトウやニンニク、アスパラガス、花束も販売する予定です。
ぜひ、お立ち寄りください。
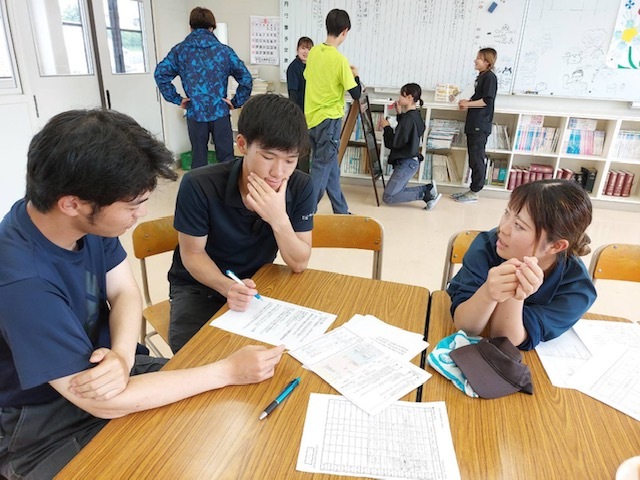

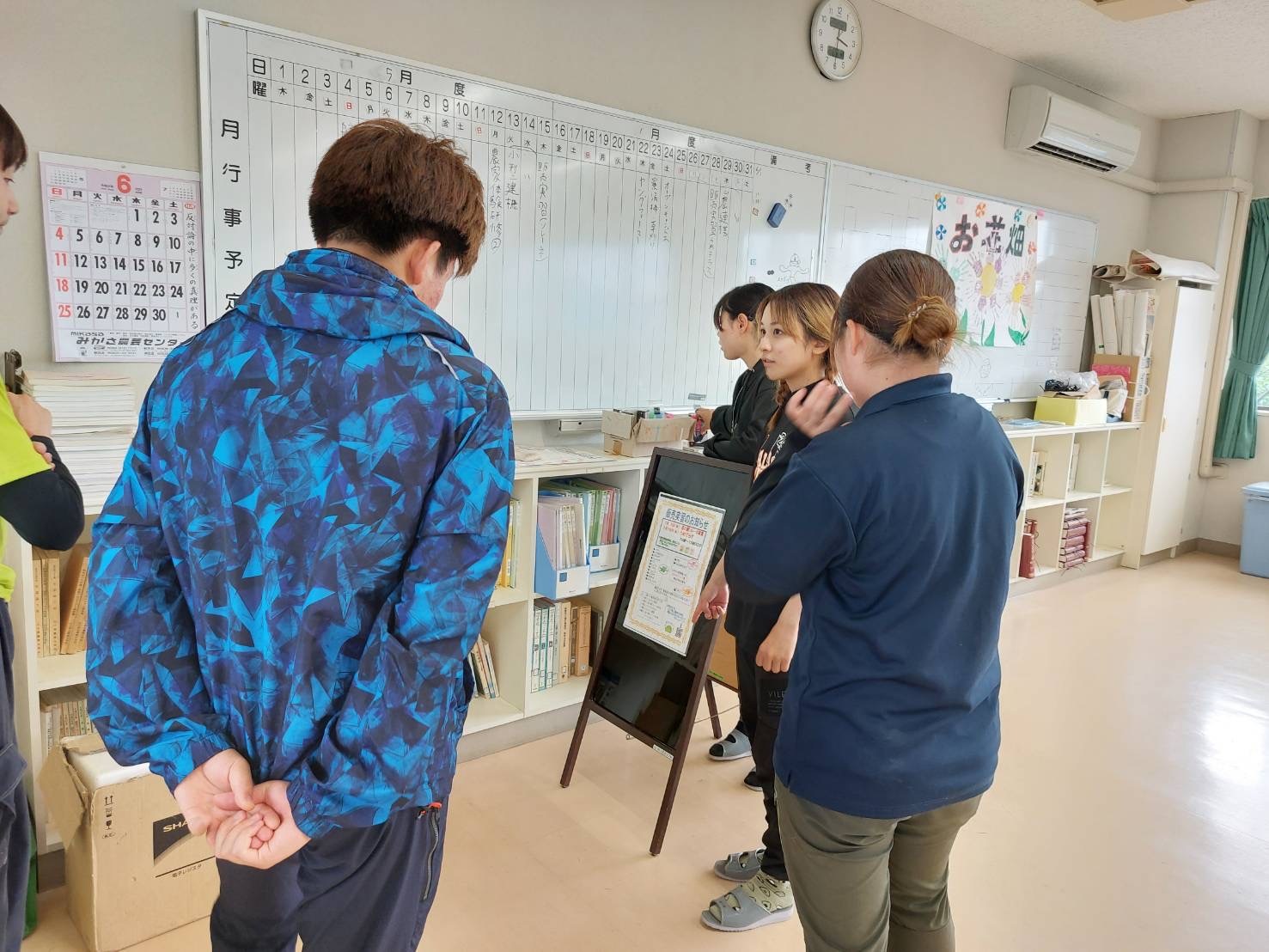

故障する原因を知る(酪農専攻) R5.6.28
6月29日(水)平素から搾乳機器のメンテナンスをお願いしている事業者様に、搾乳機器の取扱いのポイントを説明していただきました。
1年生は入学して2カ月が経ち、搾乳機器の取扱いも覚え、日々の搾乳当番も問題なく取り組んでいます。
ですが、搾乳は専用の機器が正常に作動しないとできません。
突然起こる故障や不調、異音も機器の仕組みを理解し、適切な「操作」と「メンテナンス」を行うことで予防することができ、原因の特定にもつながります。
本校の機器は使い込んだものが多いですが、今後も丁寧に使っていきましょう!



ホウレンソウの耕うん・播種! R5.6.29
園芸学科野菜経営コースでは、1年生3名が、ガラス温室でホウレンソウ栽培に取り組みます。
6月28日(水)には、1年生が、施肥したベンチ内の培土を、ベンチ耕うん機で耕しました。
その後、手押式播種機を用いて、ホウレンソウの種を播いていきました。
1年生らは、初めて行う作業でしたが、2年生がしっかり教えてくれたため、無事に作業を終えることができました。




ハウスカボチャの収穫! R5.6.28
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、カボチャの施肥体系の検証に取り組んでいます。
6月28日(水)には、鉄骨ハウスで栽培しているカボチャの収穫を行いました。
担当の2年生は、手塩にかけて育てたカボチャが収穫に至ったことから、喜びもひとしおであったようです。
今後、10日程度風乾させた後、糖度測定等の収穫物調査を行うとともに、県内かぼちゃ産地の出荷規格に基づいて出荷を行う予定です。




販売実習を行いました!【防府市まちの駅「うめてらす」】! R5.6.28
6月28日(水)に、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行いました。
今回は、園芸学科の2年生5名に加え、土地利用学科の1年生1名と園芸学科花き経営コースの1年生1名、畜産学科肉用牛経営コースの1年生1名が初めて参加しました。
雨が降ったり、やんだりする天候で、お客様は少なかったですが、学生らは一生懸命声を出して頑張りました。
また、2年生は、1年生へ、商品の展示やお客様への誘導、声掛けなどを丁寧に教えていました。
来月は、7月5日(水)に、道の駅「ソレーネ周南」で販売実習を行う予定です。




JA山口県の広報誌の取材を受けました! R5.6.28
JA山口県の広報誌「JAやまぐちけん」では、2023年7月号より、農業大学校の紹介記事を掲載されています。
2023年7月号の園芸学科野菜経営コースに続き、2023年8月号では、花き経営コースが紹介されます。
このため、6月28日(水)には、花き経営コースの学生や職員が取材を受けました。
学生らは、自身が担当しているハウスで撮影されるとともに、教室でインタビューを受けました。
取材の結果は、来月末に発刊される広報誌をご覧いただくか、JA山口県のホームページでご覧いただけます。
来月は、果樹経営コースが取材を受ける予定です。




販売実習に向けたフラワーアレンジメントの作成! R5.6.28
6月28日(水)の午後2時より、「防府市まちのえき うめてらす」で、販売実習が行われます。
このため、同日の午前中に、園芸学科花き経営コースの学1年生が、販売実習に出品するフラワーアレンジメントを作りました。
初めてフラワーアレンジメントを作成する学生もいましたが、教官の指導を受けながら、最後は見事な作品を作っていました。




ニンジンの収穫を行いました! R5.6.28
6月28日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、ニンジンの収穫を行いました。
今回、ニンジンの掘取りには、トラクタに取り付けた振動掘取機を使用しました。
この機械は、土中にあるニンジンの下に入れて、振動で土を柔らかくし、ニンジンを引き上げやすくするものです。
雨が降ったり、やんだりする不順な天候の中でしたが、掘り取りを機械で行ったため、収穫作業は予想以上に早く終了しました。
その後、収穫したニンジンは、洗浄機にかけて洗浄しました。
このニンジンは、翌日に出荷する予定です。




経営プロジェクト説明会の開催! R5.6.27
6月27日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生を対象に、経営プロジェクトの説明会を開催しました。
1年生は、今後、2年生時に経営プロジェクトとして取り組む課題設定を行うとともに、設計書を作成する必要があります。
そこで、農林総合技術センターの企画戦略部の野菜担当の職員から、県内野菜産地の課題について説明を受けるとともに、農業技術研究室の野菜研究グループの専門研究員より研究や取組課題について紹介していただきました。
今後、1年生らは、いただいた情報を参考にして、課題設定を行っていきます。



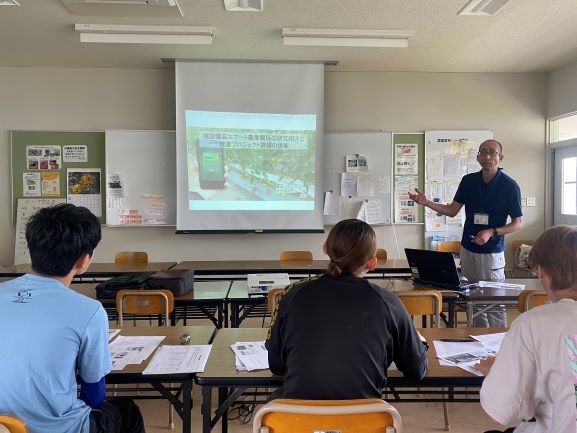
カーネーションの摘芯! R5.6.27
園芸学科花き経営コースでは、ガラス温室でカーネーションを栽培しています。
カーネーションでは、10月ごろから5月中旬までの長期間の収穫を行うため、側枝の摘芯時期を変えて、開花を調整します。
6月27日(火)には、園芸学科花き経営コースの1年生が、まず側枝を発生させるための1回目の摘芯を行いました。
学生は、初めてのカーネーションの摘芯ということもあり、慎重に作業を行っていました。

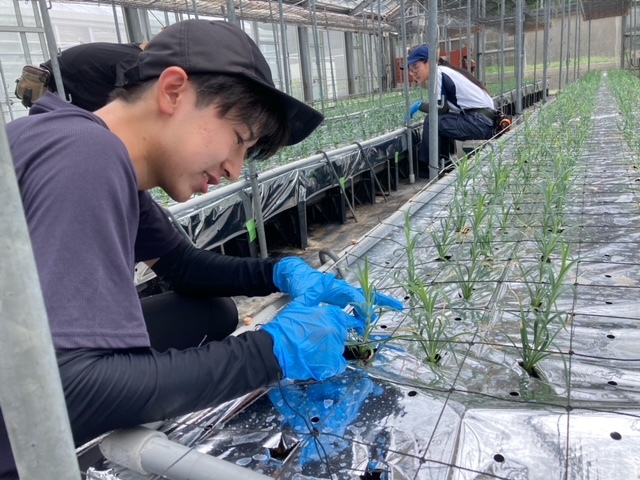
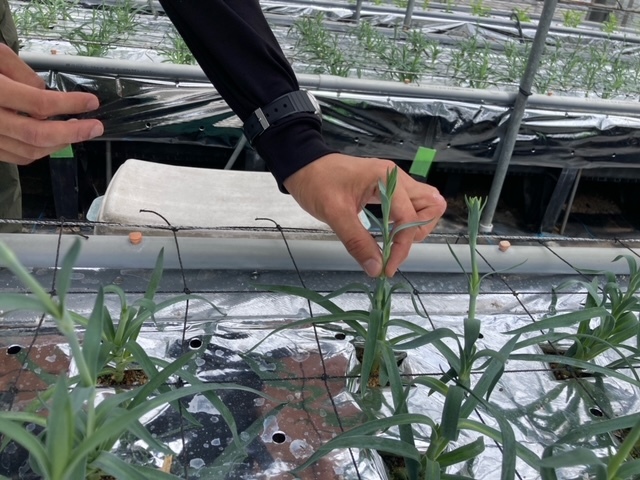

シクラメンの鉢替え! R5.6.26
園芸学科花き経営コースでは、現在、シクラメンの鉢替えを行っています。
6月26日(月)の午前中は、2年生が鉢替えを行いました。
シクラメン担当の学生は、今週中に鉢替えを終わらせると、意気込んでいました。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.6.26
6月25日(日)、農業大学校において、受講生49名を対象に作目基礎研修を行いました。
当日は、防府市消防本部から「農作業事故時の応急手当について」、山口県農林総合技術センター企画戦略部から「土づくりの基礎と肥料について」と題して講義・実習をいただき、熱中症対策のノウハウや土づくりの基礎等について学びました。
これから販売農家を目指す受講生たちにとっては、農業実践時の基本となる必要知識であり、興味深い分野でもあることから、非常に熱心に聴講しており、今後の活動に向け大いに参考になったものと思われます。


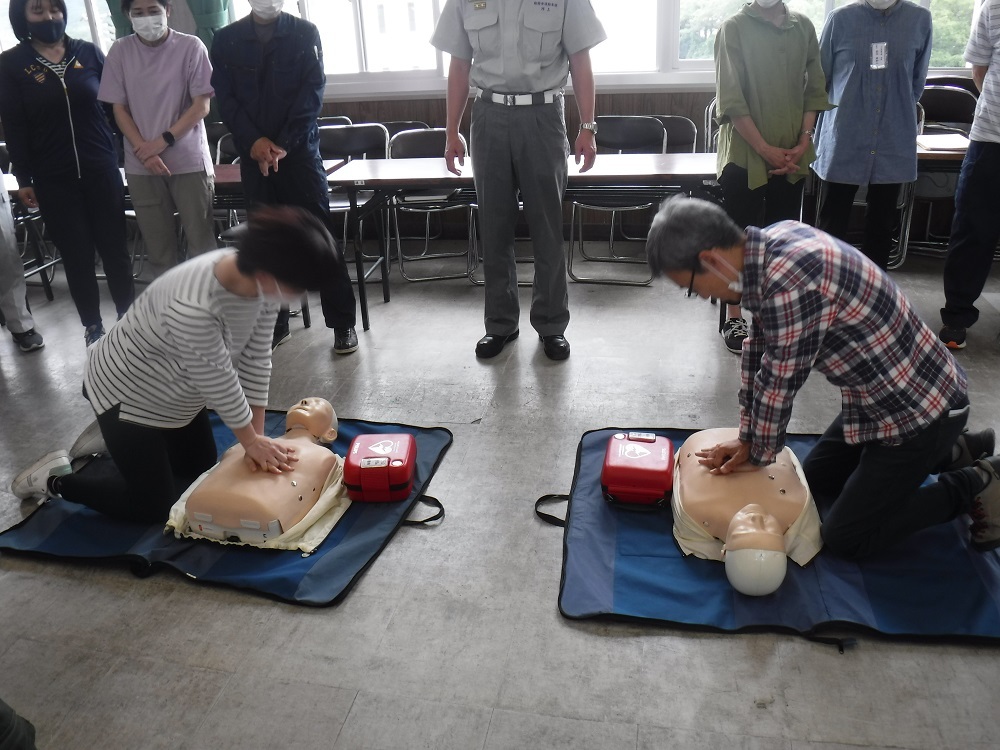
ナシ幼木の誘引! R5.6.26
6月26日(月)、園芸学科果樹経営コースのナシ班は、ナシの幼木の誘引を行いました。
4月に発芽した枝も順調に伸びてきたことから、将来に主枝となりそうな枝を主体に誘引を行っていきました。
主枝候補枝は、まっすぐ、しっかりと伸びるよう、誘引ひもで固定しました。




ブドウの袋掛けを行っています! R5.6.26
園芸学科果樹経営コースのブドウ班では、ブドウの袋掛けの真っ最中です。
袋掛けは、6月22日にハウスで栽培しているブドウからスタートしました。
6月26日(月)には、露地ほ場で栽培しているブドウの袋掛けに取り掛かりました。
ブドウを加害する病気や害虫が入らないよう、袋の口はしっかり止めています。
早生品種は、7月下旬頃から出荷する予定です。




ニンジンの試し掘りを行いました! R5.6.26
6月26日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ニンジンの試し掘りを行いました。
畝の一部(作付面積の5%程度)を掘り、2コンテナ分のニンジンを収穫しました。
収穫後は、洗浄機にかけて、ニンジンについている泥を落としました。
今回確認した収量や品質を元に、販売先や出荷量などを決める予定です。




シクラメンの溶脱水調査! R5.6.26
6月26日(月)、園芸学科花き経営コースでは、シクラメンの溶脱水調査を行いました。
本調査は、培養土の溶脱水に含まれる肥料成分を計測し、今後の施肥管理に役立てるもので、5月以降、毎週行っています。
担当の2年生は、マニュアルを確認しながら、慎重に調査を行っていました。




花の出荷調製の風景! R5.6.26
園芸学科花き経営コースでは、毎朝、花の出荷調製を行っています。
6月26日(月)には、リンドウやトルコギキョウなどを花市場中心に出荷準備を行いました。
1年生も調製作業に慣れた様子で、入学当初に比べると手早く行えるようになっています。




白ネギの移植準備! R5.6.23
園芸学科野菜経営コースでは、本年度も、白ネギの栽培に取り組みます。
6月23日(金)には、ほ場へ肥料をまいた後、トラクタを使って、除草、耕うんを行いました。
耕うん後は、歩行型トラクタを使って、溝切を行いました。
白ネギの移植は、再来週の天気の良い日に行う予定です。


シクラメンの鉢替え開始! R5.6.23




ミニトマトの接ぎ木を行いました! R5.6.22
6月22日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、1年生がミニトマトの接ぎ木を行いました。
斜めにカットした台木「キングバリア」と穂木「TY千果」の切り口を合わせてチューブ型の接ぎ木クリップに差し込み固定しました。
今回接ぎ木した苗の本数は、350本で、約3週間後に鉢上げを行う予定です。




経営プロジェクト中間発表会【カボチャ】! R5.6.22
6月22日(木)、園芸学科で、経営プロジェクト中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『寝太郎かぼちゃにおける商品化率の向上に向けた最適な施肥体系の検討』で、野菜経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を説明しました。
参加した学生や研修生からは、施肥の量や割合が果実の糖度に及ぼす影響や調査区間の葉色の違いに関する質問があり、担当学生は丁寧に答えていました。
次回は7月13日に開催し、課題はトマトに関するプロジェクトです。


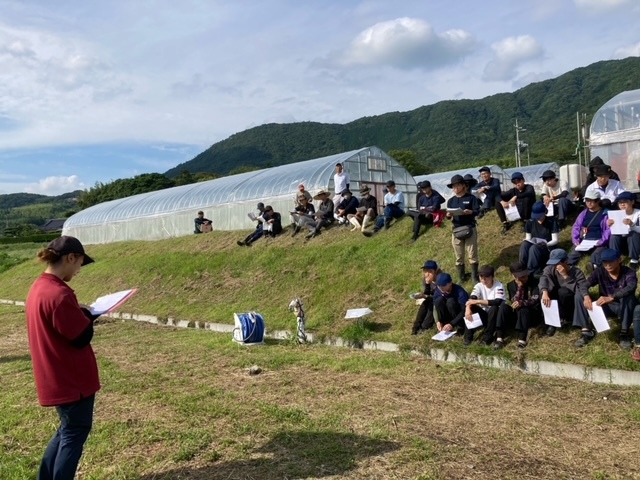

タマネギの選果を行いました! R5.6.22
6月22日(木)、園芸学科野菜経営コースではタマネギの選果を行いました。
6月15日にはほ場から拾い上げたタマネギは約300コンテナ分あり、一週間、ハウス内で乾かしていました。
今回、乾燥後のタマネギの選果機にかけ、サイズ別に分けていきました。
担当の2年生をはじめ、学生や研修生には、効率よく選果できるよう声を掛け合いながら作業を行っていました。
このタマネギは、来週から、直売所等で販売する予定です。




カボチャの生育調査! R5.6.22
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、カボチャの施肥体系の検証に取り組んでいます。
担当の2年生は、3月末に定植して以降、週に一度、生育調査を行っています。
6月22日(木)には、最大葉の長さと幅や果実がついた節の太さを調べました。
収穫間近となったため、このほ場での調査は、来週で終了する予定です。




LAユリの定植を行いました! R5.6.21
園芸学科花き経営コースでは、LAユリの盆出し出荷に向けた球根処理に係る経営プロジェクトを行っています。
具体的には、届いた球根の解凍後の低温貯蔵期間を変えて、定植時期を変えた場合の収穫時期や品質について調べることとしています。
6月21日(水)には、上記プロジェクトに関わる最後の定植を行いました。
今回の定植で調査区の設定が終了したため、担当の2年生は一安心したようです。




葉ネギの調査を行いました! R5.6.21
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、高温期の積極的な潅水が葉ネギの葉先枯れの発生や外観品質に及ぼす影響について調べることとしています。
6月14日にまいた種は、見事に発芽しています。
播種から1週間後の6月21日(水)には、生育調査として草丈や葉数を調べました。
この生育調査は、毎週行う予定です。




梅雨の合間に大豆を播く R5.6.19
土地利用学科では、6月16日(金)、19日(月)の2日に渡って大豆の播種作業を行いました。5月29日に梅雨入りしてから6月上旬は曇雨天が続き、いつ大豆の播種が行えるのかと心配していましたが、6月中旬になってから天候が安定したため、よい土壌条件で播種することができました。
大豆の栽培管理は乗用機械で行うため、播種作業は等間隔で真っすぐ行うことが重要になります。まだまだトラクタ初心者の学生達ですが、できる限りトラクタを真っすぐ走らせられるよう頑張っていました。たとえ曲がっても、時々社会人研修生が交代して真っすぐ走らせてくれるので(土地利用学科には頼もしいアニキがいるのです)、学生もそれに倣って真っすぐ走らせることができたようです。
今後は、乗用機械を使った中耕・培土、農薬散布があります。今回真っすぐ播種した成果が試されます。今から楽しみですね!




飼料用イネの播種(続き) R5.6.14
6月14日(水)、土地利用学科は13日に引き続き、飼料用イネの残りの播種を行いました。
今回の播種は、6月上旬に農業生産法人で研修を受けてきた1年生が、研修先で実習した手法を取り入れて行ってみました。
具体的には、13日の播種は、従来どおり播種した苗箱を地面に並べて保温シートを掛け、芽出しする方法でしたが、今回は播種した苗箱をパレットの上に積み重ねて保温シートを掛けてラッピングし、芽出しする方法です。少人数で作業ができ、保温シートの使用量を減らすことができる、というメリットがあります。芽出し後に苗箱を地面に並べる作業が必要となりますが、作業を分散させることが可能です。13日の半分の人数での播種作業でしたが、計画どおりに作業を終えることができました。
そして、6月18日(日)、無事出芽していることを確認し、苗箱を並べる作業を行いました。日曜日に作業? そうです、今回の最大の失敗は、播種を水曜日に行ってしまったこと。この時期、水曜日に播種すると、苗箱を並べる日が日曜日になってしまうことを完全に失念していました! 来年は、木曜日と金曜日に播種するよう計画したいと思います。




ナス苗の定植! R5.6.19
6月19日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、ナス苗の定植を行いました。
今回、「筑陽」という品種の苗550本を、1年生と研修生が露地ほ場に植え付けました。
定植後は、風で折れないように支柱で固定し、たっぷり水やりをしました。
今後は区画を割り当てて各自で管理していきます。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.6.18
6月18日(日)、農業大学校において、受講生15名を対象に作目基礎研修「果樹コース」を行いました。
当日は、梅雨の中休みで、果樹の管理作業を行う上では絶好の日となりました。
午前中の室内講義に引き続き、午後は、ナシの生育状況の観察・調査、ウメの枝管理、カキの摘果を行いました。
受講生たちは、積極的に質問をしながら、熱心に実習に取り組んでいました。




山口市の肥育経営を見学しました! R5.6.15
本校では、学修意欲の向上を図るため定期的に先進農家を見学しています。
肉用牛専攻の6名(2年生2名、1年生4名)が、6月15日(木)山口市阿知須の福嶋牧場をしました。
福嶋牧場は肥育経営をされており、その枝肉は県畜産共進会だけでなく、全国和牛能力共進会での受賞歴も多く、数々の実績があります。
牧場では、福嶋会長から牧場の始まりや枝肉成績等の概要、社長、奥様及び山本職員様から、牛を見ながら、飼養環境を整え牛に合わせた飼料管理の実践について、説明していただきました。
出荷間近の肥育牛の肩や背の張り、尻の大きさに圧倒され、帰りの道中もしばらく牛の話が続きました。
このような機会を通じ、日々の飼養管理の重要性を学修していきます。
なお、見学の調整及び防疫措置は、山口農林水産事務所畜産部に御尽力いただきました。




タマネギを拾い上げました! R5.6.15
6月16日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、タマネギの拾い上げを行いました。
6月12日に掘り上げたタマネギを、貯蔵性を高めるため3日間天日干しした後、「ピッカー」という機械で拾いあげていきました。
拾い上げたタマネギは、2週間程度ハウス内で乾かした後、根と茎を取り除き、サイズや品質別に選別する予定です。




経営プロジェクト中間発表会【白オクラ】! R5.6.15
6月15日(木)、園芸学科で、経営プロジェクト中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『白オクラ種子の発芽率の改善に向けた発芽処理方法の検討』で、野菜経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を説明しました。
参加した学生や研修生からは、供試した種子や発芽処理方法に関する質問があり、担当学生は丁寧に答えていました。
また、発表後には、白オクラの産地である長門市の生産者よりわけていただいた種子を披露し、担当教官からは、農大で採種したものとの違いについて説明がありました。
次回は6月22日に開催し、課題はカボチャに関するプロジェクトです。




メロンの摘果・玉吊りを行いました! R5.6.15
園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室でメロン栽培に取り組んでいます。
6月上旬の交配後、現在メロンの果実は、鶏卵大の大きさになりました。
そこで、形の良い果実を1つだけ残す作業(摘果)と同時に、果実をひもで吊り下げる「玉吊り」を行いました。
玉吊りは、メロンの果皮がとても傷つきやすいため、果皮が葉や茎に当たらないようにするとともに、果実の重みでヘタが曲がったり、千切れたりしないようにするために行うものです。
現在、この温室には、ライブカメラを設置しており、県内の量販店に設置されている「ぶちうま!情報ステーションDX」(デジタルサイネージ)より、ライブ映像を発信しています。ぜひ、ご覧ください。




牛を審査!(学校農業クラブ開催を支援) R5.6.14
6月14日(水)、時折雨が降る中、本校を会場に「第74回山口県学校農業クラブ連盟大会(家畜審査競技会」が開催されました。
参加は、「田布施農工高等学校」、「山口農業高等学校」及び「大津緑洋高等学校
日置校舎」の3校から計63名が参加し、乳用牛の部及び肉用牛の部のそれぞれの競技に臨みました。
各部で最優秀賞となった2名は、10月に熊本県で開催される全国大会に出場するとのこと。さらなる研鑽を積んで上位入賞を目指していただければと思います。


やまぐちオリジナルリンドウ「西京の夏空」の収穫! R5.6.15
園芸学科花き経営コースでは、やまぐちオリジナルリンドウの「西京シリーズ」5品種の栽培に取り組んでいます。
6月15日(木)には、担当の1年生が、「西京の夏空」を収穫しました。
本来は、7月上旬から8月上旬に開花する品種ですが、本校では、半月程度早い収穫初めを迎えました。
収穫のピークは、1週間後を見込んでいます。
蒸し暑い梅雨に涼しげなリンドウをぜひお買い求めください。




ネギの播種を行いました! R5.6.14
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、高温期の積極的な潅水が葉ネギの葉先枯れの発生や外観品質に及ぼす影響について調べることとしています。
6月14日(水)には、ガラス温室内のベンチへ葉ネギの種を播きました。
今回播種した2品種のうちの1品種は、県農林総合技術センターと福岡県の種苗会社とで共同育成した「やまひこ」という品種です。
担当の2年生は、1年生とともに、温室内の6ベンチに、1ベンチ当たり4条、5cm間隔で、種をまきました。
収穫は8月上旬頃で、その間、1週間おきに生育調査を行う予定です。




販売実習を行いました!【道の駅「ソレーネ周南」】 R5.6.14
6月14日(水)に、周南市道の駅「ソレーネ周南」で販売実習を行いました。
今回は、園芸学科の2年生5名に加え、土地利用学科の1年生1名と園芸学科野菜経営コースの1年生1名が参加しました。
初めて販売実習を体験する1年生2名は、2年生や職員が感心するほど、大きな声で呼び込みを行ったり、お客さんへ丁寧に商品説明を行っていました。
今月は、6月28日(水)にも、防府市まちの駅「うめてらす」で販売実習を行う予定です。




LAユリの定植を行いました! R5.6.14
園芸学科花き経営コースでは、LAユリの盆出し出荷に向けた球根処理に係る経営プロジェクトを行っています。
具体的には、届いた球根を低温貯蔵して定植時期を変えた場合の収穫時期や品質について調べることとしています。
6月14日(水)には、5月25日、6月5日に続く3回目の定植を行いました。
定植したLAユリは、展葉後から週に1度、草丈や葉数などを調べる予定です。




カーネーションの定植を行いました! R5.6.14
6月14日(水)、園芸学科花き経営コースでは、カーネーションの定植を行いました。
この日は、ガラス温室内のベンチの半分に、花色が黄色でスプレー(枝分かれ)タイプの「レスカ」など5品種を植えました。
残りのベンチには、苗が届き次第、定植する予定です。
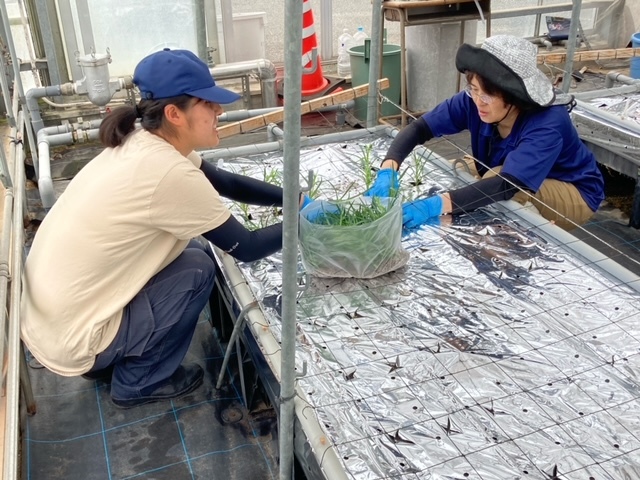


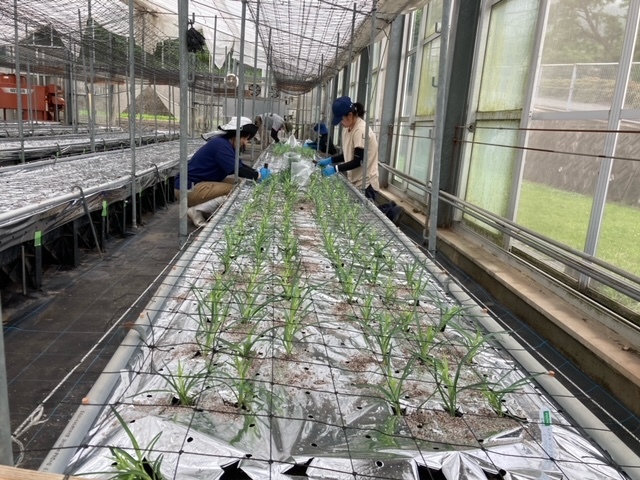
キクへのわい化剤散布! R5.6.13
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用スプレーギクの草丈の調節に向けたわい化剤の処理方法に係る経営プロジェクトに取り組むこととしています。
6月14日(水)には、担当の2年生が、1回目のわい化剤処理を行いました。
各処理区をビニールで隔てるとともに、セット動噴やハンドスプレーを使い、処理区ごとに異なる濃度のわい化剤を散布していました。
2回目のわい化剤処理は、蕾が確認された頃に行う予定です。




飼料用イネの播種! R5.6.13
土地利用学科では、7月上旬に飼料用イネ約6.8haの田植えを行うこととしています。6月13日(火)に、畜産学科と協力し、飼料用イネ660枚の播種作業を行いました。
今回は大人数での作業となることから、学生のリーダーを決めて、作業前の打合せ、役割分担の決定、時間配分や作業まで全て、リーダーが指示する形で行いました。
学生達は、説明書を読んで播種機を設定し、役割に応じて培土や種籾、苗箱の運搬を行い、時には歌を歌い談笑しながら(結構にぎやかでしたね)、テンポよく作業を行っていきます。リーダーが作業の進捗状況を見ながら的確に指示を行い、学生もみな協力して作業を確実に進めていくので、同席した教官が「自分の出番がない!」と感動していました。
今日は機械トラブルもなく、計画どおりに作業が終わりました。明日も残りの660枚播種する予定です。




6/14の販売実習でフラワーアレンジメントを販売します! R5.6.13
6月13日(火)、園芸学科花き経営コースでは、販売実習で販売するフラワーアレンジメントを作りました。
今回、2年生とともに、1年生がフラワーアレンジメントを作成しました。
販売実習は、6月14日(水)の午後2時より、道の駅「ソレーネ周南」で行います。
フラワーアレンジメントの他に、花束やニンニク、シシトウ、レモンなどを出品しますので、ぜひお立ち寄りください。




販売実習の打合せを行いました! R5.6.12
6月14日(水)の午後2時より、道の駅「ソレーネ周南」で販売実習を行います。
その準備のため、6月12日(月)に、販売実習に係る打合せを行いました。
当日の役割分担を決めるとともに、販売する品目の紹介内容や持っていく物品のチェック、レジ操作の確認などを行いました。
今回の目玉は、「ニンニク」、「シシトウ」、「フラワーアレンジメント」です。
ぜひ、お立ち寄りいただき、お買い求めください。



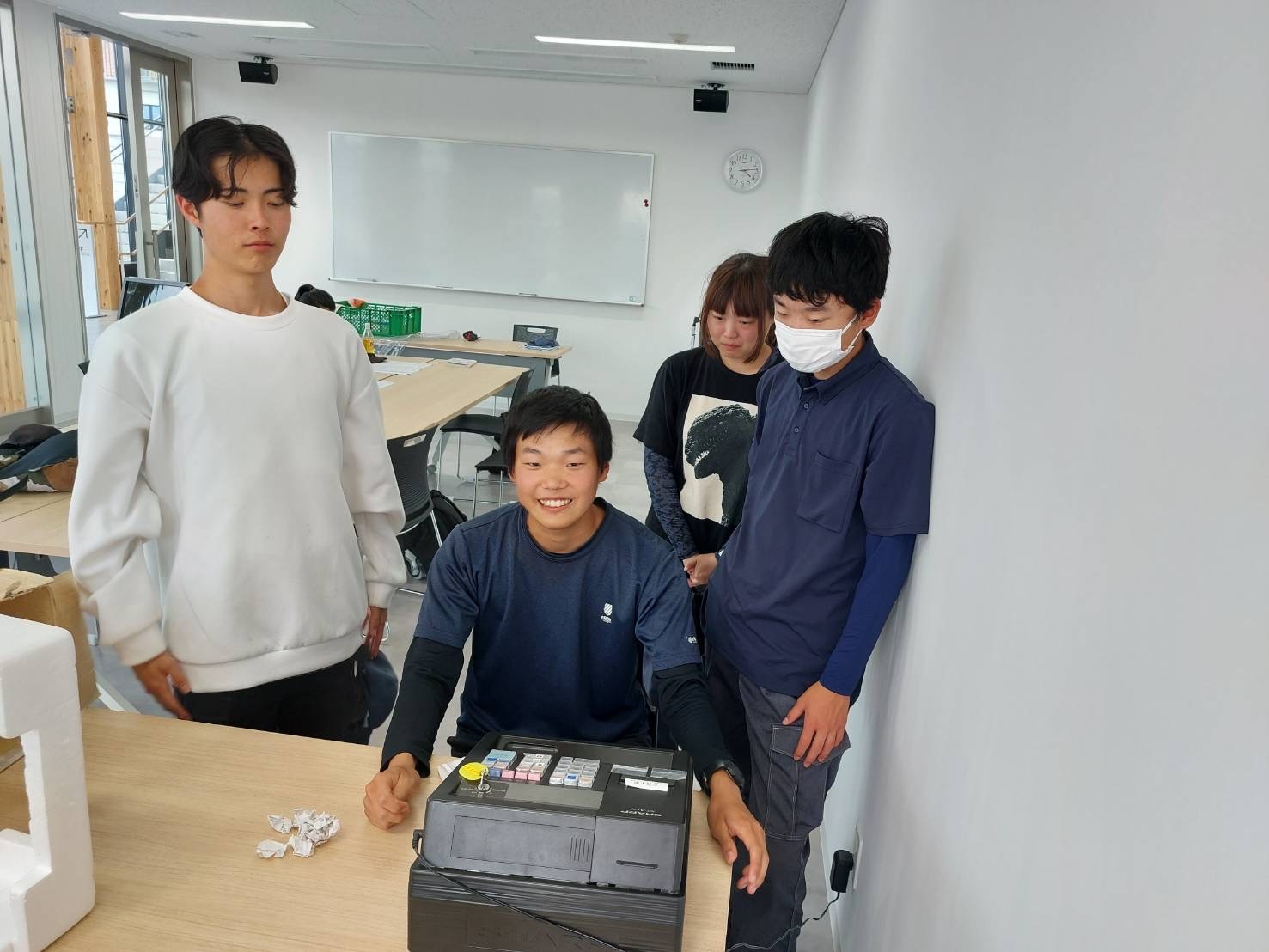
タマネギの掘り取り! R5.6.12
6月12日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、タマネギの掘り取りを行いました。
今回掘り取ったのは、中生品種の「ターザン」で、1年生2名が、堀取機を使って掘り取りました。
作業を行った1年生は、すぐに掘取機の操作のコツをつかんだようで、タマネギを傷つけることなく掘り取っていました。
このタマネギは、貯蔵性を高めるため、3日間天日干しした後に拾い上げる予定です。




ホウレンソウの播種(はしゅ) R5.6.12
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、夏秋ホウレンソウのハウス栽培における屋根散水によるハウス内昇温抑制効果の検証に取り組みます。
6月12日(月)には、担当の2年生が2棟のハウスへホウレンソウの種を播きました。
今回、手押式播種機を用いて、ハウスの半分に10条播種しました。
また、発芽率の調査を行う箇所では、種子100粒を手で播きました。
ハウスの残り半分は、2週間後に播種を行う予定です。




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました R5.6.11
6月11日(日)、農業大学校において、受講生34名を対象に作目基礎研修の「野菜コース」、「水稲コース」、「畜産コース」を並行して実施しました。
当日はコース別に、夏野菜の管理、水稲の植付け、子牛の飼養管理について講義及び実習を行いました。
当日は朝から梅雨らしい曇り空でしたが、幸いにも実習中は時折晴れ間も覗き、受講生たちは熱心に実習に取り組んでいました。




温風ダクトの洗浄【野菜専攻】! R5.6.9
園芸学科野菜経営コースでは、イチゴの栽培が5月末で終わったため、栽培資材等の片付けを行っています。
6月9日(金)には、イチゴ担当の学生が、暖房に使用した温風ダクトの洗浄を行いました。
学生らは、デッキブラシを使って、汚れをしっかり落としていました。



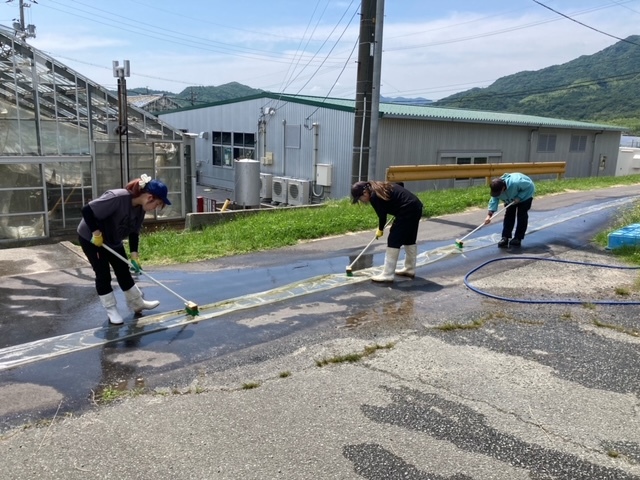
大斜面の草刈り【野菜専攻】! R5.6.9
6月9日(金)、園芸学科野菜経営コースの学生と研修生4名が、大斜面の草刈りを行いました。
安全確保のため、それぞれが十分な距離をとって作業にあたりました。




ナシの降雹被害調査! R5.6.9
今年の4月16日、農業大学校では雹(ひょう)がふり、ナシの幼果が被害に遭いました。
このため、園芸学科果樹経営コースのナシ班の1年生が、生産プロジェクトとして、
降雹被害に遭った果実の追跡調査を行っています。
6月9日(金)には、降雹により果実にできた傷の大きさをノギスで測ったり、果実の画像を撮影しました。
この調査は、5月下旬から開始しており、10日おきに行うこととしています。




ナシの大袋かけ【最終日】! R5.6.9
園芸学科果樹経営コースのナシ班では、5月18日より始めたナシの大袋かけが、6月9日(金)に終了しました。
学生らは、鶏卵ほどの大きさになった果実に、丁寧に袋をかけていました。


白オクラの補植! R5.6.7
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、白オクラの発芽率の改善に向けた播種前処理方法を調べることとしています。
このプロジェクトの一環で、経営収支を求めるため、5月29日に露地ほ場へ白オクラを定植しました。
その際、苗が足りなかったことから、6月7日(水)に、定植できなかった植穴に白オクラを定植しました。
今後、畝の周辺にソルゴーを播種する予定です。




今日のよい日のお田植えはじめ♪ R5.6.8
6月8日(木)、土地利用学科の田植えが始まりました。ポツポツと小雨の降る肌寒い中での作業となりましたが、みんなで協力しあい、雨足が強くなる直前に植え終わることができました(終わった途端に土砂降り)。
もちろん、植付け部を下ろしたまま後進したり(ストップ!ストップ! 肥料の吐出部が詰まるっ!)、植付け爪を作動させずにしばらく走行したり(後を見て!苗を植えてないよっ!)、といったトラブルはありましたが、初めてにしては上手にできたほうではないでしょうか。
しばらくは代掻きと田植えを同時進行で行うことになりますが、みんなで分担しながら乗り切りましょう。



カボチャの生育調査! R5.6.8
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、カボチャの施肥体系の検証に取り組んでいます。
担当の2年生は、3月末に定植して以降、週に一度、生育調査を行っています。
6月8日(水)には、果実がついた節の太さや最大葉の長さと幅を調べました。
今月下旬には、収穫を行う予定です。




ナスの定植準備【支柱立て】! R5.6.7
園芸学科野菜経営コースでは、1年生と社会人研修生が、露地ナスの栽培に取り組みます。
6月7日(水)には、定植に向けて、枝を誘引するための支柱の設置を行いました。
学生と研修生は、お互いに協力しながら、作業を行っていました。
ナスの定植は、来週に行う予定です。




溝掃除【花き経営コース】! R5.6.7
今年は例年より早い5月29日に梅雨入りしており、今後まとまった雨が降る可能性があります。
そこで、6月7日(水)、園芸学科花き経営コースでは、ハウス周辺の溝掃除を行いました。
学生らは、溝に溜まった泥や石、溝に生えている草等をきれいに取り除いていました。




ジャガイモの収量・階級調査! R5.6.7
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ジャガイモのマルチ栽培に係る経営評価に取り組んでいます。
6月5日(月)に掘り上げたジャガイモの重量は、約600㎏で、上々の収量でした。
6月7日(水)には、調査区ごとの収量や階級、品質等の調査を行いました。
担当の2年生は、マルチの有無や管理、マルチの種類によって、階級や品質に違いがありそうだと言っていました。




ホウレンソウ定植準備【施肥・耕うん】! R5.6.7
園芸学科野菜経営コースでは、夏秋ホウレンソウのハウス栽培における屋根散水によるハウス内昇温抑制効果の検証を行うこととしています。
6月7日(水)には、担当の2年生が肥料をまいた後、トラクターで耕うんしました。
今週金曜日には、ホウレンソウの種を播く予定です。




イチゴの親株移動・定植! R5.6.7
6月7日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、イチゴ「かおり野」の親株の移動や定植を行いました。
これまで、ハウス内で管理・増殖していたイチゴの親株を、子株の鉢受ができるスペースが確保できる屋外で管理するため、移動させたものです。
移動させた親株は、ラック内に定植し、子株を切り離す8月末頃まで管理を行います。




第1回短期入門研修を開催しました! R5.6.6
5月29日から6月1日にかけて、やまぐち就農支援塾第1回短期入門研修を開催しました。10名の受講生が、職員や学生から農業機械・小農具の取り扱いや、水稲、野菜、果樹の管理指導を受けながら作業体験を行いました。
受講生からは「実際に作物に触れながらの作業体験ができ参考になった」、「学生たちともいろんな情報交換ができ良かった」、「今後の就農に向けた検討の材料にしていきたい」等の感想が聞かれました。




整理整頓の素晴らしさを実感! R5.6.5
土地利用学科では、トヨタ生産方式を取り入れた学修を行うこととしています。6月1日(木)、トヨタ自動車株式会社から講師を招き、基本となる2S(整理整頓)について学びました。
まずは、「整理整頓」についての講義。
そして、講義が終わったら即実践です。今回は、機械格納庫で実践してみました。まずは格納庫に所狭しと詰め込まれている機械の長さや幅を計って、現状をホワイトボードに書き込みます。次に、必要なものと不要なものを分け、必要なものは使用品目や使用時期を確認し、使い易くなるような配置をみんなで考えます。ある程度考え方がまとまったら、全ての機械を格納庫から出し、新たな配置図に沿って、さあ格納です!
・・・すると、どうでしょう! 脈絡もなく機械が詰め込まれ、歩くのにも困るようだった格納庫に、通路ができたではありませんか! 整理整頓の凄さの一面を実感した次第です。もっと早く知りたかったですね・・・
とはいえ、講師の評価は「まぁ、20点ってとこでしょうか」。まだまだ整理整頓するところは山ほどあります。整理整頓が身につくよう、引き続き実践あるのみ!




初めての代掻き(しろかき) R5.6.5
ようやく圃場の耕耘が終わったと思ったら、次はいよいよ代掻きです。5月31日(水)、今年初めての、そして土地利用学科初めての代掻きを行いました。今年は雨が多かったので川の水も多く、圃場への入水が比較的容易だったため、計画通り作業に取り組めました。
代掻きは2回行いますが、今回は1回目の荒代(あらじろ)です。水位を浅くしての作業なので、作業した場所が一目瞭然だったことから、迷うことなく作業できたのではないでしょうか。
最初は手間取っていた学生も、作業後半になると少しずつトラクタの扱い方に慣れてきたようで、旋回も少し「さま」になっていました。いい感じです!
これから毎日のように代掻きがありますが、どれだけ上達するか楽しみです。


露地ナス定植準備【畝立て・マルチ被覆】! R5.6.5
園芸学科野菜経営コースでは、1年生と社会人研修生が、露地ナスの栽培に取り組みます。
6月5日(月)には、定植に向けて、畝立てとマルチ被覆を行いました。
畝立てでは、長さ20mで13畝立てるとともに、その周囲に、防風効果や天敵となる益虫を呼び込むためのイネ科植物である「ソルゴー」を植えるための畝を立てました。
その後、立てた畝に、黒マルチを被覆していきました。
この日は、全ての畝にマルチ被覆が行えなかったため、翌日も被覆を行います。




カーネーション定植準備【潅水チューブ設置・マルチ被覆】! R5.6.5
園芸学科花き経営コースでは、ガラス温室で栽培するカーネーションの定植準備を行っています。
担当の1年生らは、翌週が「農家体験研修」で作業ができないため、今週中に定植準備を終わらせるよう、急ピッチで作業を行っています。
6月5日(月)には、栽培ベンチへの潅水チューブの設置やマルチの被覆を行いました。
今後、フラワーネットの設置や調整、補修を行う予定です。




ジャガイモの収穫! R5.6.5
園芸課野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ジャガイモのマルチ栽培に係る経営評価に取り組んでいます。
6月5日(月)には、トラクタに取り付けたポテトディガーを使い、ジャガイモの収穫を行いました。
担当の2年生は、教官と収穫ルートや操作方法を確認した後、ジャガイモを掘り上げていきました。
掘り上げたジャガイモは、収量調査を行った後、直売所を主体に出荷を行う予定です。




メロンの人工受粉! R5.6.5
現在、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの人工受粉を行っています。
6月5日(月)には、1年生や2年生が、筆を使って、雄花から花粉をとり、雌花のめしべにつけていました。また、人工受粉を行った日が分かるようにテープで印を付けていました。
このメロンの収穫は、7月中旬頃を予定しています。




「航空祭」で販売実習を行いました! R5.6.4
6月4日(日)、園芸学科では、防府北基地で開催された「防府航空祭~幸せます防府北~」で、販売実習を行いました。
今年も、防府市及び防府観光コンベンション協会の方々と同じテントで出店させていただきました。
今回、2年生3名が参加し、タマネギや柑橘の「せとみ」を販売しましたが、学生による積極的な声掛けもあって、昼前には販売物の大半を販売することができました。
また、学生らは、ブルーインパルスによる曲技飛行も間近でみることができ、たいへん有意義な一日となったようです。


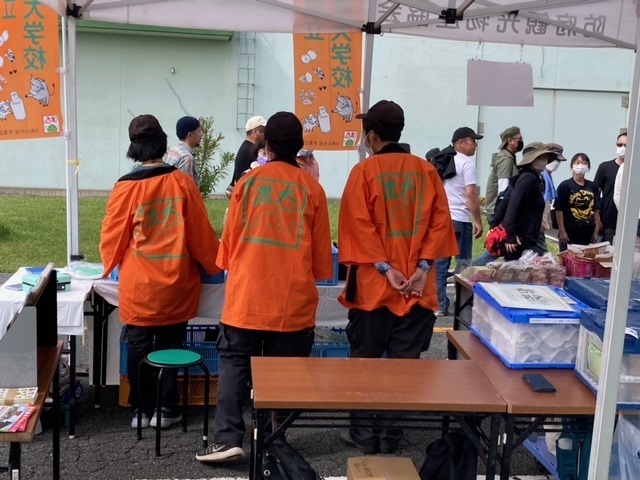

カーネーション定植準備【耕うん】! R5.5.31
5月31日(水)、園芸学科花き経営コースでは、ガラス温室で栽培するカーネーションの定植に向けて、ベンチ内の土の耕うんを行いました。
担当の1年生は、教官から管理機の操作方法や耕うんの留意点を教わった後、耕うんを行いました。
今後、潅水装置の設置やマルチ被覆を行い、6月中旬には、カーネーションの定植を行う予定です。




LAユリの定植! R5.5.26
5月26日(金)、園芸学科花き経営コースでは、ガラス温室へLAユリを定植しました。
今回定植したのは、花色がオレンジ色の「コルトーナ」という品種です。
担当の2年生らは、教官から定植方法の指導を受けた後、300球の球根を定植しました。
本品種は、8月上旬に収穫する予定です。




麦わらの回収! R5.5.26
5月26日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、土地利用学科が栽培した小麦の麦わらを回収しました。
小麦の刈り取りは前日に行われましたが、天気予報では翌週から雨が降るということで、天気のよいこの日に、学生、職員が総出で対応しました。
学生らは、麦わらを結束した後、ほ場外に運び出し、ハウス内へ保管したり、スイカやカボチャの敷きわらとして利用しました。




白オクラ定植準備【施肥・畝立て】! R5.5.25
園芸学科野菜経営コースでは、白オクラの発芽率の改善に向けた播種前処理方法についての経営プロジェクトを行うこととしています。
本プロジェクトでは、播種前処理を行った種子の生育や収量も確認します。
5月25日(木)には、担当の2年生が、定植の準備として、石灰の施用や畝立て成形機による畝立てを行いました。




家畜審査競技 合同練習会が開催されました! R5.5.24
5月24日、山口県学校農業クラブ連盟主催「家畜審査競技」の合同練習会が本校で開催され、田布施農工高等学校、山口農業高等学校及び大津緑洋高等学校から68名の生徒が参加されました。
大会は6月14日に開催されるとのこと。
練習会の成果を本番で発揮し、好成績を残していただければと思います。


今日も天気だ、耕耘(こううん)しよう! R5.5.24
土地利用学科では6月から始まる田植えに向けて、急ピッチで圃場の耕耘を行っています。先週末からの好天で、今週はまさに耕耘日和。1年生もこの機を逃すことなく、交代で耕耘に参加しています。
5月24日(水)は、4名が耕耘を行いました。第一関門は真っすぐに耕耘することです。ただそれだけなのに、圃場の凸凹にタイヤをとられるのでなんとも難しい。早くコツをつかんでくださいね。第二関門は旋回(Uターン)することです。自分が耕耘した場所の隣に行くために、的確なハンドル操作が求められます。トラクタ独特の動きに早く慣れましょう。
そもそも1年生は、つい最近自動車運転免許を取得した新免マーク集団。初めてのトラクタともなれば、後進が苦手、旋回が上手くできない、それは当たり前です(中には教官が驚くほど上手に耕耘する学生もいましたが)。これから、お互い切磋琢磨して、1年後には、全員が新1年生に教えられるようになってください!




食品衛生の講習を実施しました! R5.5.26
5月26日(金)、山口健康福祉センター防府保健所から講師をお招きし、手洗いの方法や服装のチェックなど食品衛生に関する基礎知識について、学びました。
農畜産物の生産から利活用までの流れを学ぶ一環で企画した講習で、参加した1・2年生、社会人研修生たちは、メモを取るなど熱心に聞き入っていました。

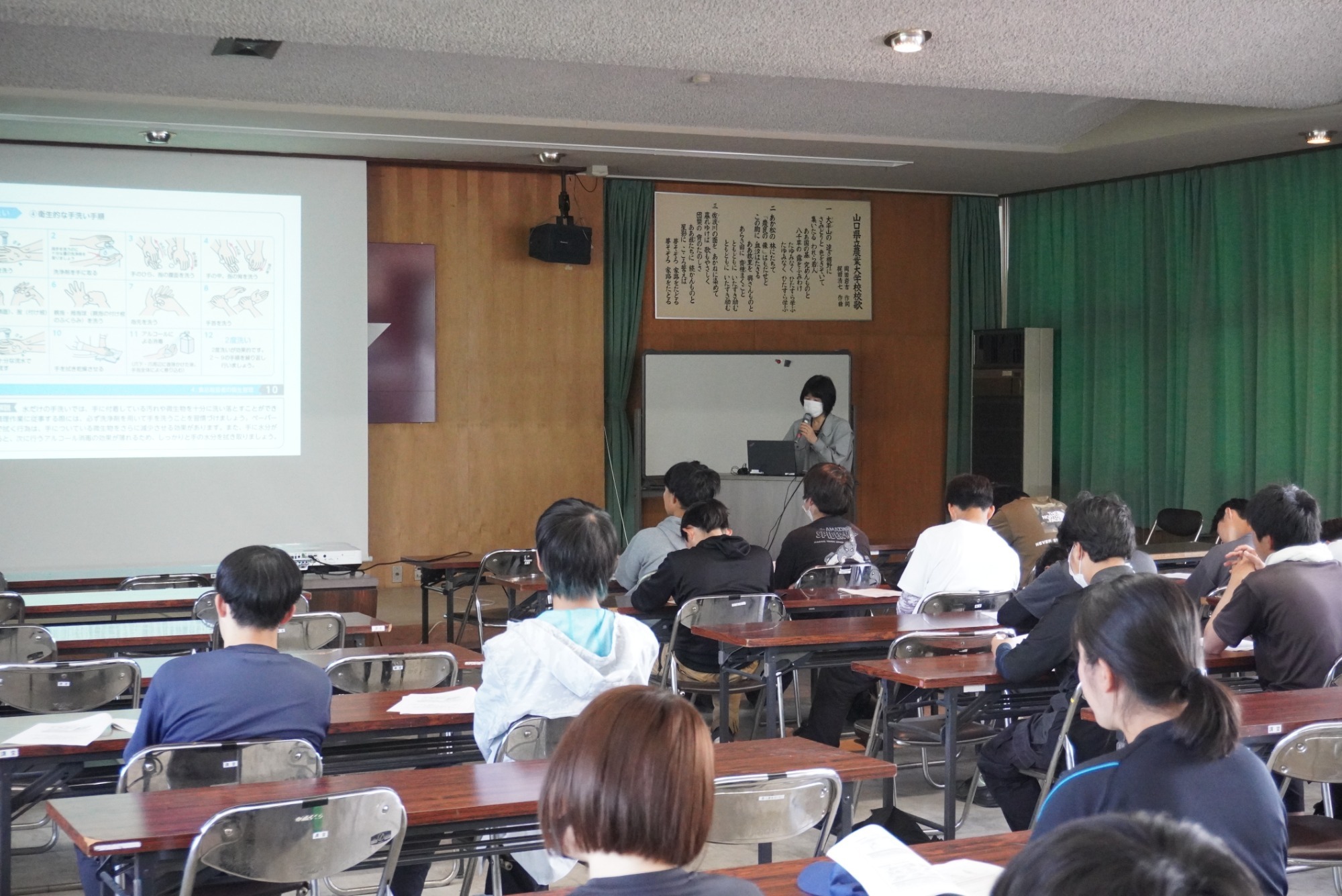
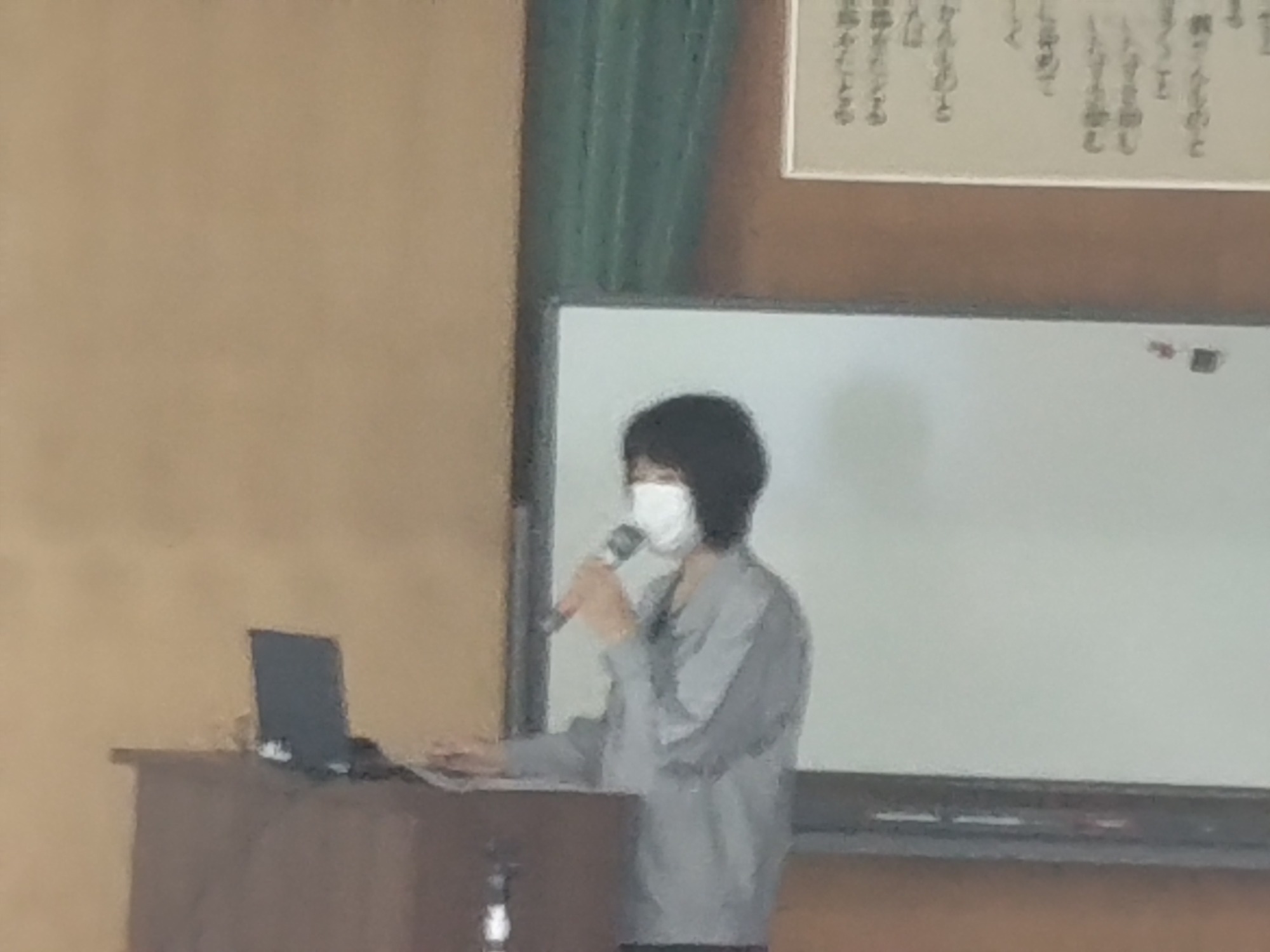

LAユリのプレルーティング処理! R5.5.25
園芸学科花き経営コースでは、LAユリの盆出し出荷に向けた球根処理に係る経営プロジェクトを行うこととしています。
昨年、葉焼け症対策として「プレルーティング処理(球根を湿ったピートモスで包んだ後、12℃前後で約10日間保管し、上根(球根から出る茎の周辺から発生する根)を発生させる処理のこと)」を定植前の球根に行ったところ、葉焼け症は軽減しましたが、6月の気温が高かったため、出荷時期が早まり、盆に出荷できませんでした。
そこで、今回は、「プレルーティング処理」を行う前の球根を低温貯蔵して、定植時期を遅らせることで、盆前に収穫できるかを調べることとしています。




トルコギキョウの生育調査に係る株の選定! R5.5.24
園芸学科花き経営コースでは、盆前出荷のトルコギキョウ栽培における定植作業の省力化の検証に係る経営プロジェクトを行っています。
5月24日(水)には、担当の2年生が、生育調査を行う株の選定を行いました。
今後、一週間おきに、草丈や葉数を調査する予定です。




ケイトウの定植! R5.5.24
5月24日(水)、園芸学科花き経営コースでは、ガラス温室へ盆出荷するケイトウを定植しました。
今回定植するのは、「スプリンググリーン」、「ボンベイチェリー」、「ボンベイピンク」、「センチュリーイエロー」、「黄玉」、「ファイアリーレッド」の6品種です。
1年生と2年生が、しっかり役割分担しながら、定植作業に取り組んでいました。




今日も天気だ 耕耘(こううん)しよう R5.5.24
土地利用学科では6月から始まる田植えに向けて、急ピッチで圃場の耕耘を行っています。先週末からの好天で、今週はまさに耕耘日和。1年生もこの機を逃すことなく、交代で耕耘に参加しています。
5月24日(水)は、4名が耕耘を行いました。第一関門は真っすぐに耕耘することです。ただそれだけなのに、圃場の凸凹にタイヤをとられるのでなんとも難しい。早くコツをつかんでくださいね。第二関門は旋回(Uターン)することです。自分が耕耘した場所の隣に行くために、的確なハンドル操作が求められます。トラクタ独特の動きに早く慣れましょう。
そもそも1年生は、つい最近自動車運転免許を取得した新免マーク集団。初めてのトラクタともなれば、後進が苦手、旋回が上手くできない、それは当たり前です(中には教官が驚くほど上手に耕耘する学生もいましたが)。これから、お互い切磋琢磨して、1年後には、全員が新1年生に教えられるようになってください!




家畜審査競技 合同練習会が開催されました R5.5.24
5月24日、山口県学校農業クラブ連盟主催「家畜審査競技」の合同練習会が本校で開催され、田布施農工高等学校、山口農業高等学校及び大津緑洋高等学校から68名の生徒が参加されました。
大会は6月14日に開催されるとのこと。
練習会の成果を本番で発揮し、好成績を残していただければと思います。


やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました R5.5.21
5月21日(日)、農業大学校において、受講生9名を対象に作目基礎研修の「農業機械コース」の第2回目を行いました。
当日は、各種農業機械の特徴や農作業安全のための留意点の説明を受け、実習として、刈払機による草刈作業を体験しました。
刈払機をはじめ農業機械の扱いが初めての受講生が多く、当日は、熱心に聴講・実習に取り組んでいました。


カーネーションの植え替え準備! R5.5.18
園芸学科花き経営コースでは、母の日を過ぎたため、カーネーションの植え替えの準備を始めました。
5月18日(木)、新たにカーネーション担当となった1年生が、現在、植栽されているカーネーションの抜き取りを行いました。
フラワーネットにカーネーションが絡んでいるため、1本抜くのにも非常に手間がかかりますが、担当の1年生は、辛抱強く抜き取り作業を行っていました。




ナシの大袋かけ! R5.5.18
園芸学科果樹経営コースのナシ班では、5月18日(木)より、ナシの果実への大袋かけを開始しました。
袋掛けは、病気や害虫の被害から果実を守るとともに、果実の果面を保護するために行うものです。
この日は、青ナシの「二十世紀」や「なつしづく」に大袋をかけました。
ナシ班の学生らは、袋が外れないようしっかり取り付けるとともに、袋かけの際に果実を落果させないよう慎重に作業を行っていました。
青ナシの大袋かけが終われば、「新水」や「幸水」といった赤ナシの大袋かけを行います。




「売れる売り場づくり研修会」を開催! R5.5.19
5月19日(金)、園芸学科では、園芸学科2年生、研修生、大平山麓会会員を対象に、売り場づくりに係る研修会を開催しました。
講師に、山口県よろず支援拠点の東コーディネーターをお招きし、商品販売の考え方を解説いただくとともに、商品陳列や接客等のポイントなどを紹介していただきました。
また、農産物や本校で使用しているコンテナやかごを用いて、実際の陳列の仕方について実演していただきました。
学生らはたいへん参考になったようで、今後、直売所への出荷や販売実習において、本日学んだことを実践してくれることでしょう。




牛の体を測る(酪農専攻) R5.5.18
先日は肉用牛専攻の体型測尺をアップしましたが、酪農専攻も測尺をしています。
乳用牛は、生乳をたくさん搾れるように品種改良された牛ですので、肉用牛とは体つきが違います。
乳用牛の経産牛の体格は、肉用牛より一回りくらい大きくなりますが、今日は、1年生の練習のために育成中の若い牛を選んでいます。
今日は天気が良く急に気温が高くなりました。乳用牛もこんな気温の変化にはストレスを感じます。全員で確認しながら測尺したので、実習後はゆっくり休ませました。



牛の体を測る(肉用牛専攻) R5.5.18
牛の体を測ることは、その牛が月齢に合った発育をしているのかを知るうえで重要な手段です。
ただし、牛は「じっと」してくれません。
正しい姿勢をしていないと正確に測ることはできませんが、特に子牛は正しい姿勢を維持するのが難しく、素早い測尺が必要です。
今日は、先生が説明しながら測尺した後、1年生を中心に測る部位と方法の確認をしました。
専用の測尺器具は取扱いに慣れが必要ですが、経験を重ねて素早く正しい測尺をしていきます。




水稲「きぬむすめ」の播種! R5.5.17
5月17日(水)、土地利用学科では、1年生全員で水稲「きぬむすめ」の播種を行いました。播種する箱数は100箱。育苗箱に土を詰めて灌水し、播種機の調節が済んだら速やかに播種していきます。しかし、午前中は資材の準備や播種機の調整でドタバタして、2時間で40箱しか播種できませんでした。播種の後も、育苗用プールを作り、育苗箱を並べ、太陽シートを設置するといった作業が待っています。これ、17時までに終わるのか・・・教官の頭に。ところが、作業の流れをつかんだ1年生、午後の作業の早いこと! 1時間で残り60箱の播種をさっさと終えてしまいました。おおーっ、やるねー!
その後、全員で協力して育苗用プールを作り、育苗箱を運んできれいに並べ、太陽シートを掛けました。ぴったり時間内での終了、お見事です。
来週も播種がありますが、この調子で頑張りましょう!
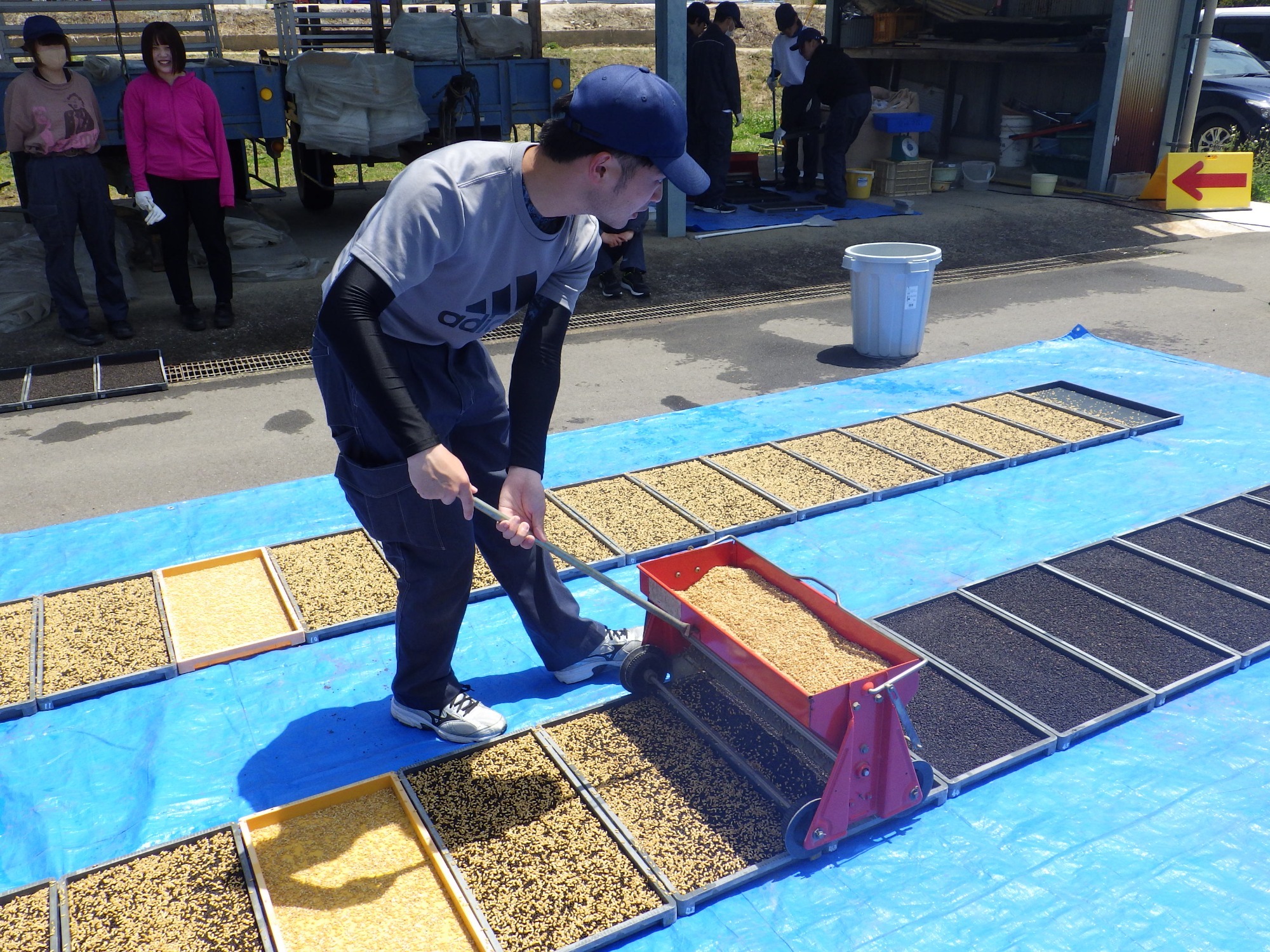



メロンのツルの誘引! R5.5.17
園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室でメロン栽培に取り組んでいます。
4月28日に定植したメロンは、ツルが順調に伸びており、誘引可能な長さになってきました。
そこで、5月17日(木)、ツルを誘引ヒモに結束する作業を行いました。
担当の学生らは、暑い中での作業でしたが、黙々と誘引作業を行っていました。
今後、5月末頃から、メロンの実をつけるための交配作業を行う予定です。




イチゴの生育調査! R5.5.17
園芸学科野菜経営コースでは、イチゴ「かおり野」の栽植密度と芽整理による株管理の違いが収量に及ぼす影響に関する経営プロジェクトに取り組んでいます。
本課題では、草高、葉長、展開葉数といったイチゴの株の生育に係る調査を、2週間おきに行っています。
5月末には、イチゴの栽培が終了するため、5月17日(水)に行った生育調査が、最後の調査となりました。
今後、担当の2年生は、生育や収量等に係る調査データの取りまとめを行うとともに、労働時間や経営収支の解析も行う予定です。




ブロッコリー初収穫! R5.5.17
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾(からい)取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
5月17日(水)、ブロッコリーの株の先端にできた花蕾(「頂花蕾」)を活用する調査区から、頂花蕾を収穫しました。
今回、思いのほか多く収穫でき、担当の2年生は、1年生の手を借りながら、忙しく出荷調整を行っていました。




ミニトマトの播種! R5.5.17
5月17日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、ミニトマトの播種を行いました。
今回播種したのは、「TY千果(ティーワイちか)」という品種で、裂果しにくく、トマト黄化葉巻病にかかりにくいのが特徴です。
播種作業では、2年生が1年生に、培養土の水分調製やセルトレイへの充填方法、鎮圧ローラーを用いた播種穴づくり、竹串を使った播種など、実演を交えて丁寧に教えていました。
今後、今週金曜日には台木用品種の播種を行うとともに、一か月後には接木を行う予定です。




ニンニクの収穫! R5.5.17
5月17日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、ニンニクの収穫を行いました。
今回、2品種を収穫し、このうちの一つは「大島赤丸」という萩市沖合の大島で生産されてきた品種であり、一般的な品種に比べて、りん片が多く、外皮が赤いのが特徴です。
収穫したニンニクは、ハウス内で1週間程度乾燥させた後、直売所等へ出荷する予定です。




ブドウの花穂整形! R5.5.17
園芸学科果樹経営コースブドウ班では、現在、枝の整理や誘引、花穂整形、植物成長調整剤処理に日々追われています。
5月17日(水)の午後からは、ブドウの花穂整形を行いました。
花穂整形は、花の数を制限して実どまりを高めるとともに、ブドウの房の形を整えるために行うものです。
学生や研修生らは、花穂の状態を確認しながら、手早くハサミを動かしていました。




スプレーギクの生育調査! R5.5.17
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用スプレーギクのわい化剤の処理濃度・回数に係る経営プロジェクトに取り組むこととしています。
4月13日に定植したキクは、日に日に成長しており、5月12日には生育の揃った枝を3本に整理する整枝を行ったところです。
5月17日(水)には、担当の2年生が、調査区ごとに株を選び、草丈や葉数といった生育に係る調査を行いました。
本調査は、今後、1週間おきに行います。




イチゴの苗づくり準備【ポットづくり】! R5.5.17
園芸学科野菜経営コースでは、5月15日(月)より、イチゴの苗を育てるための、ポットづくりを行っています。
イチゴでは、親株から伸びる「ランナー」と呼ばれる細い茎を、培養土を入れたポットに受けて、根付かせた後に切り離し、苗として活用します。
ランナーは6月頃から盛んに伸び始めるため、その前にポットを準備するものです。
今回、5,000ポット以上作成する計画であり、5月17日(水)は、残る2,000ポットを作成しました。
暑い中での作業でしたが、学生や研修生は、黙々と培養土を混ぜ、ポットに詰めていました。




環境にやさしい技術「糖蜜還元土壌消毒」の試行! R5.5.17
園芸学科野菜経営コースでは、5月17日から5月18日にかけて、ミニトマトの定植を予定しているハウス内で、「糖蜜還元土壌消毒」を試行することとしました。
当該ハウスでは、青枯(あおがれ)病という土壌伝染性の病気が発生するため、作付け前には土壌消毒が不可欠ですが、従来の農薬を使った消毒法では効果が不十分なため、今回、効果があると言われる「糖蜜還元土壌消毒」を行うこととしました。
この方法は、希釈した糖蜜を土壌に潅注し、土壌表面をビニルで覆うことによって、地温を高めるとともに、土壌微生物の活動により、土壌中が酸欠状態となり、青枯病菌を死滅させることができます。自然由来の糖蜜を利用するため、環境にもやさしい土壌消毒法の一つです。




シクラメンへの液肥施用! R5.5.17
4月下旬に鉢上げを行ったシクラメンは、現在、順調に生育しています。
5月17日(水)には、鉢上げ後、初めて液肥を施用しました。
園芸学科花き経営コースのシクラメン担当の2年生は、前日に行ったポット内の土の分析結果を元に液肥の濃度を決め、液肥混入器を使って所定の濃度に薄め、一鉢一鉢に液肥を施用しました。
シクラメンでは、今後、11月頃まで、土の分析に基づく液肥施用を行っていきます。




ブドウの枝管理! R5.5.12
現在、園芸学科果樹経営コースブドウ班では、枝の整理や誘引、花穂整形、植物成長調整剤処理に日々追われています。
5月12日(金)の午後からは、ブドウの枝管理を行いました。
日当たりを良くするため、混み合った枝を抜くとともに、枝を棚面に固定するため、テープナーという器具を用いて枝と棚線を結束していきます。
学生や研修生らは、ブドウの花穂の開花が進んでいる様子を見て焦る気持ちもありますが、まずは枝管理を最優先とし、収集して作業を行っていました。




トラクタのロータリーの詰めを交換、これで耕耘(こううん)もバッチリ! R5.5.16
土地利用学科では、全員が農業機械の安全な操作技術・保守管理技術を習得することを目標にしています。ちょうどトラクタのロータリーの爪が摩耗して交換時期になっていたので、5月16日(火)、1年生全員で爪の交換を行いました。
まず、教官から、爪の交換に関する説明を受けました。爪の交換が必要な理由(摩耗すると耕耘性能が下がること)、爪の交換に必要な工具や作業手順、作業時の安全確保や注意事項等、爪の交換作業一つだけでも学ぶことは山ほどありますね。
説明を受けた後は、即実践です。が・・・
さて、ボルトを緩めるにはどっちに回す? わかっていてもついつい逆に回そうとする人、多いですね。危ない、危ない。
あれ?その爪、向きが逆ですよ。爪交換あるあるです。
明日の午前中には全ての爪が新品に替わります。これで春の耕耘作業も順調に進むことでしょう!




育友会総会及び学校説明会を開催! R5.5.15
5月12日(金)に在校生の保護者が集まり、年に1回の定例の育友会総会を開催しました。その後、学校説明会と称して、学生の卒業後の進路状況や新しい施設の見学、食堂での試食会を実施しました。
総会においては、全議案が承認され、新しい役員が決定されました。また、学校説明会では、この春に「知と技の拠点」工事で竣工した本館並びに連携交流館で説明を聞いた後に、改装された食堂で昼食をとりました。進路や6次産業化に向けた学修の取り組み内容、365日朝・昼・晩と栄養士がバランスを考えて食事を提供していることなど、日頃の学生生活に係る話を保護者の皆さんは興味津々の様子で聞いていました。




スプレーギクの整枝! R5.5.12
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用スプレーギクのわい化剤の処理濃度・回数に係る経営プロジェクトに取り組むこととしています。
5月12日(金)には、プロジェクトに供試するスプレーギクの整枝を行いました。
担当の2年生は、1株あたり3本程度の揃った枝を残して弱い枝を摘み取ったり、下葉をかぐ作業を手早く行っていました。
今後、6月中旬には、わい化剤処理を行う予定です。




LAユリ定植準備【耕うん】! R5.5.12
園芸学科花き経営コースでは、LAユリの盆出し出荷に向けた球根処理に係る経営プロジェクトを行うこととしています。
5月12日(金)には、LAユリを定植するベンチ内の土へ肥料をまいた後、耕うん機で耕うんを行いました。
今後、6月上旬から中旬にかけて、定植を行う予定です。




シシトウ定植準備【マルチ被覆】! R5.5.12
5月12日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、シシトウの定植準備のため、パイプハウス内の畝へ、黒マルチを被覆しました。
2年生は、1年生に、マルチの被覆の仕方やコツを、実演しながら教えていました。
1年生は、すぐに要領を得て、マルチをピンと張らせて被覆していきました。




セット動噴の洗浄に係る研修! R5.5.11
5月11日(木)、園芸学科の学生や研修生を対象に、セット動噴の洗浄に係る研修会を開催しました。
今回、野菜専攻が作成しているマニュアルを、園芸課共通のマニュアルとして採用することに決めたので、学生、研修生、職員それぞれが理解し、実践できるよう研修を行ったものです。
講師は、野菜専攻の2年生で、実演を交えながら、バケツやセット動噴の洗浄、洗浄液の取扱など、順を追って丁寧に説明していました。
防除後のセット動噴の洗浄を誤ると、大きな事故につながることから、参加者らは、真剣に聞き入っていました。




促成スイカ初出荷! R5.5.12
5月12日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、促成スイカ初出荷をしました。
今回、大玉スイカの「祭りばやし777」と小玉スイカの「ひとりじめ7」を、それぞれ1個ずつ収穫し、道の駅「ソレーネ周南」に出荷しました。
「祭りばやし777」は、約13㎏の立派なスイカであり、担当の2年生は、価格設定に頭を悩ませていました。
この促成スイカは、5月末まで継続的に出荷する予定です。




経営プロジェクト中間発表会【イチゴ】! R5.5.11
5月11日(木)、園芸学科で、経営プロジェクト中間発表会を開催しました。
今回の課題は、『イチゴ「かおり野」の栽植密度と芽整理による株管理の違いが収量に及ぼす影響』で、野菜経営コースの2年生が、課題の背景や目的、調査の内容や結果、現時点での考察を説明しました。
参加した学生や研修生から多くの質問があり、担当学生は丁寧に答えていました。
発表後は、試験を行っているハウス内を見学しました。
次回は、5月25日に開催し、イチゴに関する他のプロジェクト課題について中間発表が行われます。

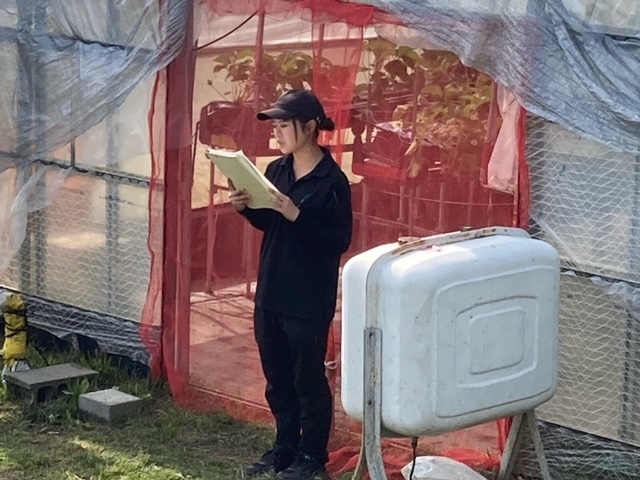

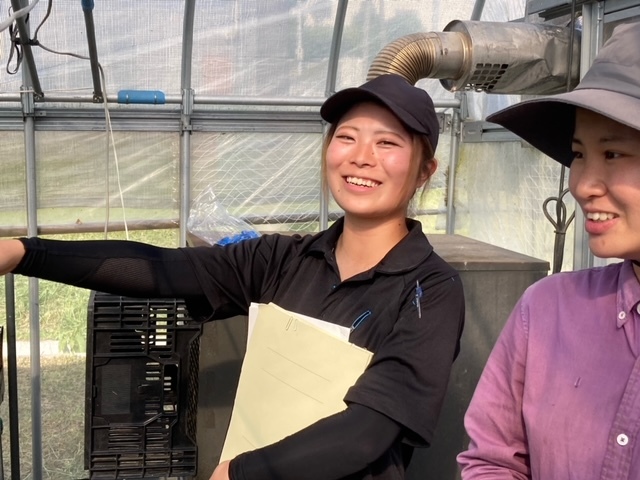
ハウスカボチャの生育状況! R5.5.11
園芸学科野菜経営コースでは、カボチャ「くりゆたか」を供試し、施肥体系に係る経営プロジェクトに取り組んでいます。
鉄骨ハウス内に、3月31日に定植したカボチャは、5月2日より人工受粉を行っています。
担当の2年生は、人工受粉を行った雌花の位置にポールを立て、受粉日毎に色を変えたテープを貼って、果実の状況を確認するための目印としています。
5月11日(木)には、5月2日に受粉した果実が、ソフトボール大の大きさになっており、順調に生育していることがうかがえました。




ナスの接ぎ木! R5.5.11
5月11日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、栽培各論の授業の中で、ナスの接ぎ木を行いました。
今回、台木に接ぐ穂木(ほぎ)品種は「筑陽」で、秀品率が高い首太の太長ナスです。
1年生と研修生は、教官から説明を受けた後、カミソリの刃を使って、台木を切り割り、穂木を調製した後、接木を行い、接木クリップで止めていきました。
今回は、800本の接ぎ木苗を作成し、約1か月育苗した後、露地ほ場に定植する予定です。




イチジクの挿し木! R5.5.11
5月11日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、栽培各論の授業の中で、イチジクの挿し木を行いました。
今回使用した品種は、県内で一般的に栽培されている「蓬莱柿(ほうらいし)」など2品種で、冬に剪定して冷蔵庫で保管していた枝を使用しました。
1年生と研修生は、教官の指導の下、培土づくり、ポット詰め、穂木の調製、挿し木といった工程を丁寧に行っていました。




ほ場・施設周辺の草刈り【花き専攻】! R5.5.11
気温の上昇や適度な雨により、ほ場周辺等の草が旺盛に伸びています。
こうした中、園芸学科花き経営コースでは、5月11日(木)に、ほ場や施設周辺の草刈りを行いました。
今回、1年生は、4月の刈払機研修以降、初めて刈払機や自走式斜面草刈機を使用しました。
2年生や教官が、操作方法や草刈り作業の仕方を丁寧に説明した後、1年生が実際に草刈りを行いました。
1年生は、恐る恐る草刈りを行っていましたが、時間が経つにつれスムーズに作業が行えるようになっていました。




ナシの樹への交信かく乱剤の設置! R5.5.10
5月10日(水)、園芸学科果樹経営コースのナシ班では、ナシの害虫であるナシヒメシンクイなどの発生を減らすため、「コンフューザーN」という交信かく乱剤をナシの樹に設置しました。
この剤は、昆虫の交尾行動を誘起する性フェロモンと呼ばれる化学物質を利用したもので、直接昆虫を殺す活性はありませんが、空気中に性フェロモン物質がただようことによって、雄成虫が同じ種の雌成虫を発見にくくなり、雌成虫の交尾の機会が減り、子孫の数を減らす効果があります。
担当の2年生らは、高さ150㎝程度の位置に、若木のナシ1本あたり3本の交信かく乱剤を設置していきました。




母の日前の収穫・出荷調整の様子! R5.5.8
現在、園芸学科花き経営コースでは、母の日前の出荷をねらったバラやカーネーションの収穫や出荷調製が最盛期を迎えています。
5月8日(月)には、2年生が授業で抜けた後も、1年生が収穫、出荷調製を忙しく行っていました。
母の日出荷に向けたピークは、今週水曜日まで続く予定です。

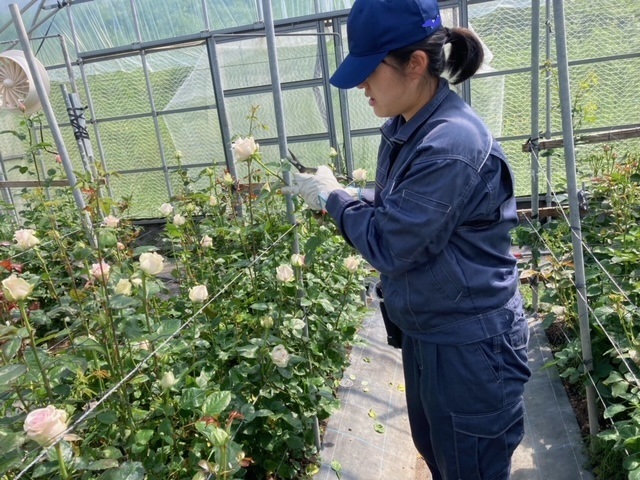


校内河川の清掃を行いました! R5.5.8
5月10日(水)、本校敷地内を流れている柳川の清掃を行いました。
土地利用学科や園芸学科の学生、担い手養成研修生、農林総合技術センター各部の職員ら約50名が参加し、川底に生えている草や堆積した泥などを取り除いていきました。
約1時間の作業の後、川底は、見違えるほどきれいになりました。




促成スイカ収穫に向けた果実品質調査! R5.5.8
5月8日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、促成スイカの収穫時期を把握するための果実品質調査を行いました。
今回調査したのは、大玉スイカの「祭りばやし777」と小玉スイカの「ひとりじめ7」です。
初めて調査した「祭りばやし777」は、果実の重さが11.8㎏で、果肉の色も濃く、糖度は目標の10度を超える10.5度あり、食味も上々でした。
今回の結果を受け、今週金曜日には、直売所へ初出荷を行います。

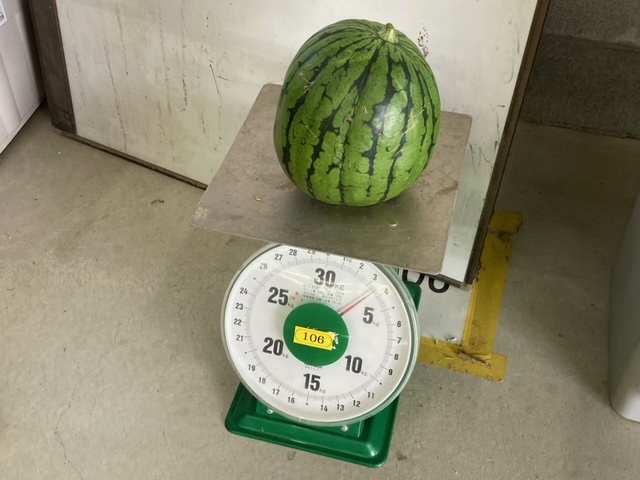


LAユリ定植準備【土壌分析】! R5.5.8
5月8日(月)、園芸学科花き経営コースでは、LAユリの定植に向け、施肥量を決めるため、栽培ベンチ内の土壌のpHやECを測定しました。
担当の2年生は、6つの栽培ベンチから採取した土壌について、それぞれ分析を行いました。
今週中には、施肥を行い、再度、耕うんを行う予定です。
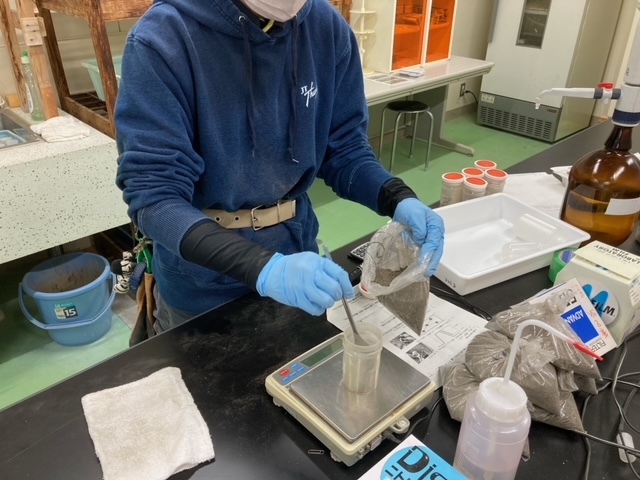

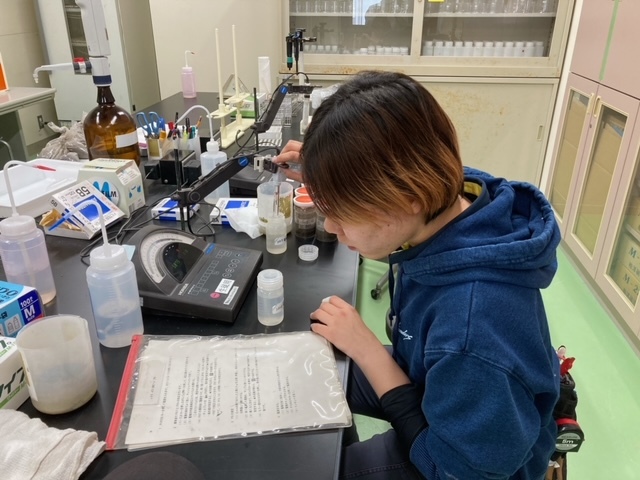
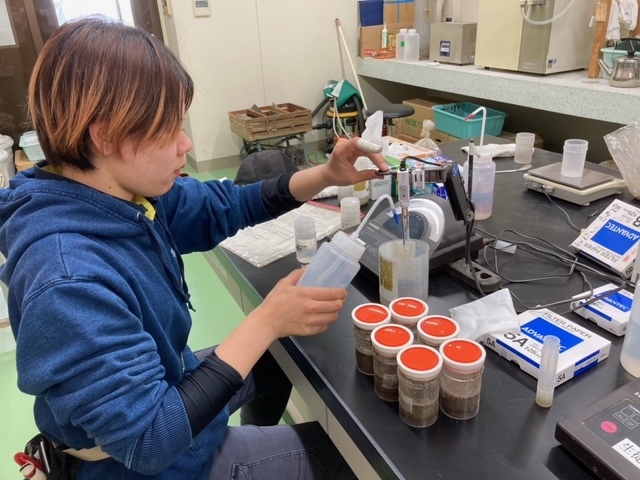
元気な子牛が産れました!(肉用牛専攻) R5.5.8
今年度、最初の分娩は黒毛和種でした。
5月2日(夕方)、この日お母さんになったのは、昨年10月に鹿児島県で開催された第12回全国和牛能力共進会に出場した「えこ」です。
初めての分娩にみんなで介助し、体重35kgの元気なオスが産れました。
本校は人工哺乳をしていますので、しっかり観察をしながら育てていきます!
(耳標は撮影後の実習で装着しています。)



斜面の草刈りを機械で! R5.5.8
いよいよ、雑草がぐんぐん茂る時期に突入しました。草刈りが待っています。土地利用学科1年生は、5月8日(月)、自走式斜面草刈機(通称:スパイダーモア)の操作方法を学びました。
教官から機械の構造や基本的な操作方法について説明を受けたら、草刈り練習をする斜面に移動。でも、すぐに草刈り作業に入るわけではありません。安全に作業するために、まずは作業場所を点検し、大きな石が露出している箇所や杭が打ち込んである箇所に目印を立てたうえで、草刈り練習を行いました。
初めて操作する機械、しかも作業場所は斜面とあって、なかなか思うように操作できない学生もいました。とはいえ、斜面の草刈りでは非常に役立つ機械です。これから少しずつ経験を積んで、使いこなせるようになりましょう!




やまぐち就農支援塾で「作目基礎研修」を行いました! R5.5.7
5月7日(日)、農業大学校において、受講生42名を対象に作目基礎研修の「野菜コース」、「果樹コース」、「水稲コース」、「畜産コース」を行いました。
当日はコース別に、夏野菜やカンキツ等果樹類の管理、水稲の播種、牛の飼養管理について講義及び実習を行いました。
あいにくの雨模様の中での研修でしたが、受講生たちは熱心に聴講したり、作業に汗を流していました。




LAユリの定植に向けた蒸気消毒! R5.5.1
園芸学科花き経営コースでは、LAユリの盆出し出荷に向けた球根処理に係る経営プロジェクトを行うこととしています。
5月1日(月)には、LAユリの定植に向け、栽培ベンチ内の土の蒸気消毒を行いました。
担当者は2年生ですが、授業と重なったため、蒸気消毒機の操作は、1年生が行いました。
1年生4名は初めての操作でしたが、教官の指導や確認のもと、無事に蒸気消毒を行うことができました。

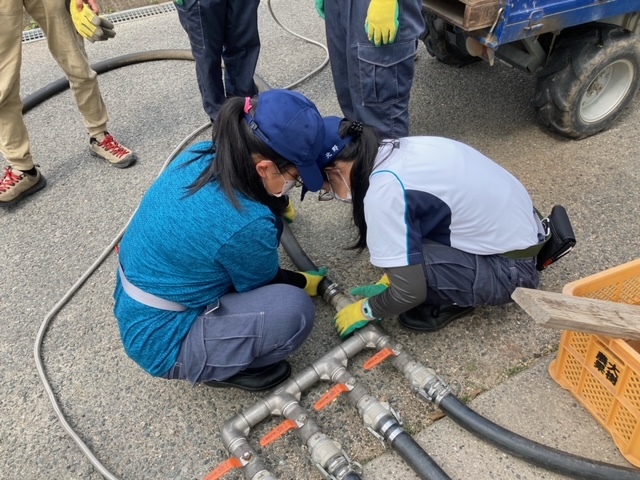


ナシ園での晩霜対策燃焼試験 R5.5.1
ナシでは、開花期から幼果期頃まで、低温による被害を受けやすく、5月上旬頃までは晩霜害に注意が必要となります。
そこで、5月1日(木)、園芸課果樹経営コースでは、ナシ園において、晩霜対策に向けた燃焼試験を行いました。
具体的には、缶の中に灯油をしみこませたチップを燃焼させ、燃焼時間や温度の推移を調査しました。
今後、調査結果を取りまとめ、次年度以降の晩霜対策に活用する予定です。




ナシのIPM防除に係る害虫調査 R5.4.24
園芸学科果樹経営コースでは、土着天敵を保護し、利用するナシの防除体系の検証を行うこととしています。
4月中旬からは、ナシの害虫であるアブラムシ類の発生状況調査を10日に一度行っています。
4月24日(月)には、担当の2年生が、各区の供試樹5本について、ランダムに選んだ20葉に係るアブラムシ類の成虫数を調査しました。
アブラムシ類以外にも、葉に異常がみられる場合は、手を止めて確認していました。




これから栽培する圃場の状態を知る R5.5.1
土地利用学科では、圃場の状態を知るための土壌分析に取り組んでいます。5月1日(月)は、土壌担当教官の指導のもと、pHの測定を行いました。使用する土壌サンプルは、1週間前に各自が圃場から採取し、乾燥させ、細かく砕いたのち、篩(ふるい)にかけて準備しておいたものです。
教官から、「この分析機器は高価なんだよ」と説明されたからでしょうか・・・、全員慎重に、慎重に、分析を行っていました。ほとんどの圃場は問題ない数値でしたが、一部改善が必要な圃場を見つけることができました。今後、学生と教官とで、施肥設計等を検討していくこととしています。


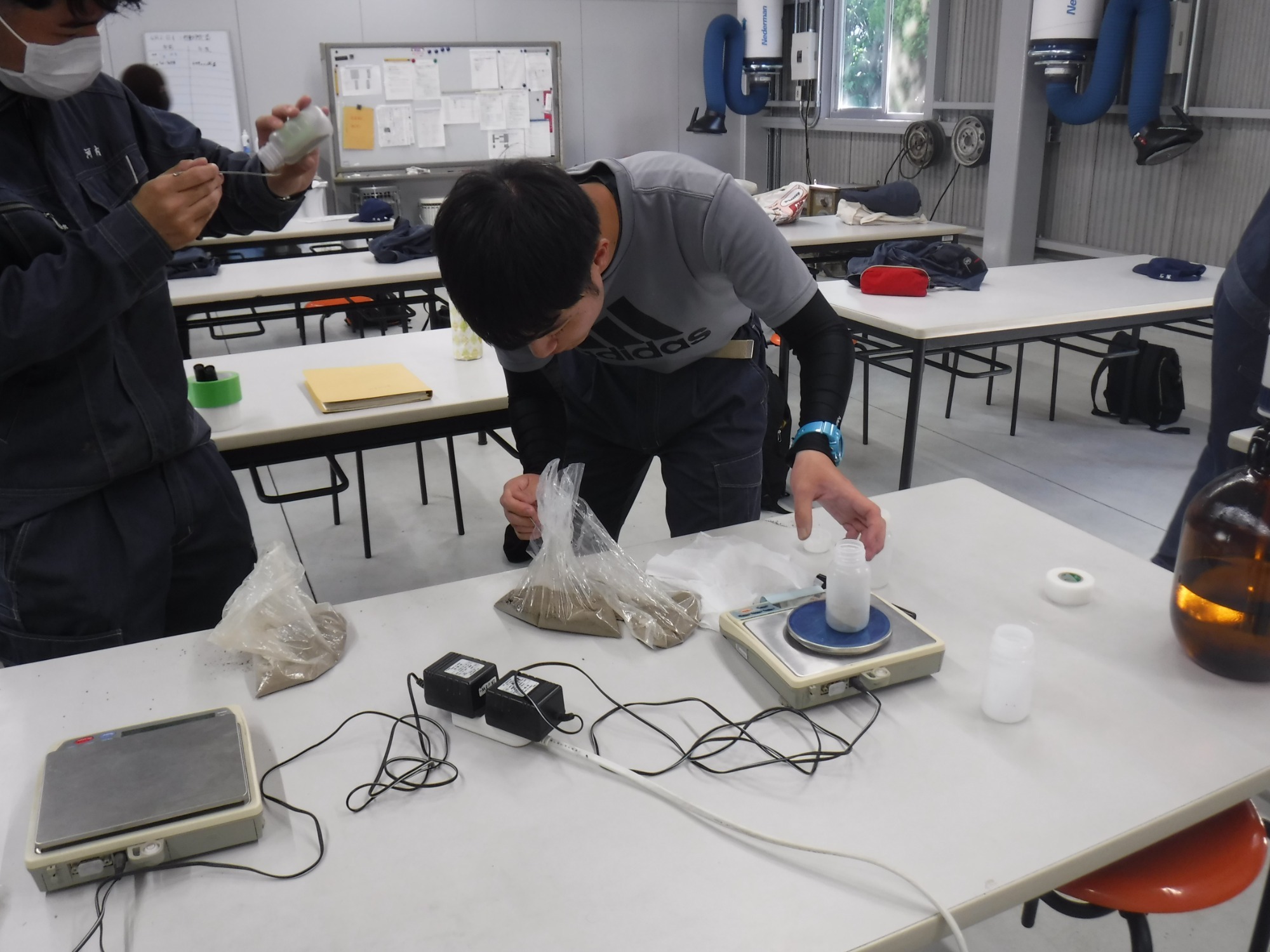
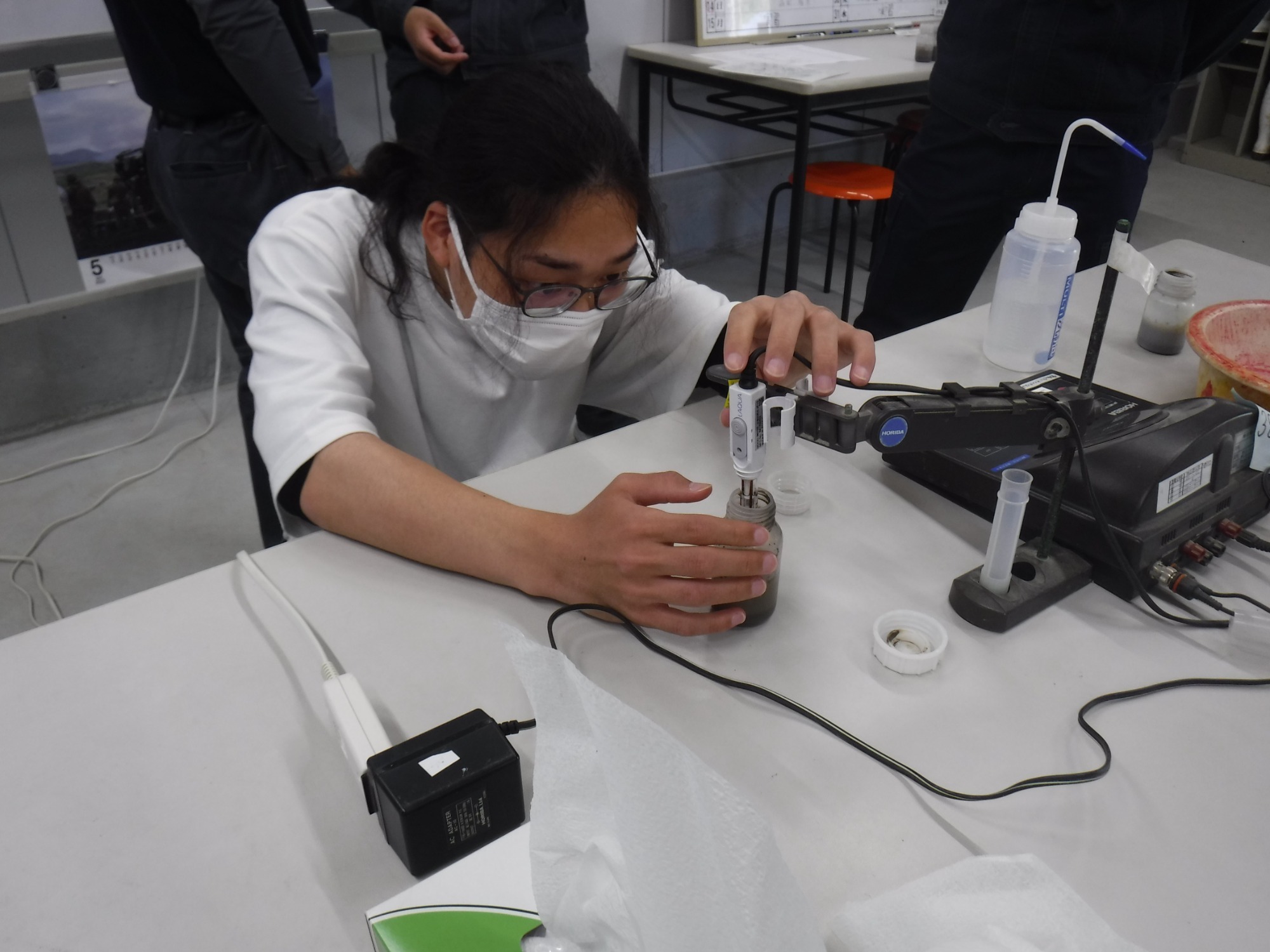
メロンの定植! R5.4.28
4月28日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、ガラス温室で栽培するメロンの定植を行いました。
今回、緑肉系品種の「ミラノ夏Ⅰ」を420株植付けました。
1年生や社会人研修生も作業に携わり、教官や担当の2年生の指示通り、丁寧に定植を行っていました。
このメロンの収穫は、7月中下旬頃を予定しています。




白いもの生育状況! R5.4.28
園芸学科野菜経営コースでは、本年度も白いもの育苗に取り組んでおり、3月13日には種芋を5つのプランターへ植え付け、その後、各プランターで発芽を確認するとともに、徐々にツルが伸びている状況です。
このプランターは、今後、山口銀行防府支店へお渡しし、採取されたツルを防府市野島の管理ほ場へ定植される予定です。
しかし、4月28日(金)現在、20cmを超えるツルも確認されていますが、総じてツルの伸びがやや穏やかであり、プランターの引き渡しは、もう少し先となりそうです。


促成スイカの果実品質調査! R5.4.28
4月28日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、促成スイカの収穫時期を把握するための果実品質調査を行いました。
今回調査したのは、小玉スイカ「ひとりじめ7」の3月24日に受粉した果実です。
果実の重さは2.8㎏で、果肉の色はやや淡かったものの糖度は11.3度あり、食味も悪くはありませんでした。
今回の果実は、若干青臭さが残り、果皮と果肉の境界もはっきりしていなかったため、本格的な収穫はゴールデンウイーク明けを予定しています。




青ナシの小袋かけ! R5.4.27
4月27日(木)、園芸学科果樹経営コースでは、青ナシの「二十世紀」や「なつしずく」へ小袋かけを開始しました。
青ナシへの小袋かけは、果皮のクチクラ層を保護し、果面をきれいに仕上げたり、病害虫の被害等を防ぐために行うものです。
ナシ班の2年生と1年生は、果実一つ一つに、丁寧に小袋をかけていました。




大型特殊自動車免許取得に向けて! R5.5.1
農業大学校では、就農、就業時に求められるトラクタなどの安全な運転操作技術を身につけるため、入学後に大型特殊自動車免許(農耕車限定)を取得することとしています。
ただ、免許を取得するためには、総合交通センター試験官による厳しい実技試験に合格しなければなりません。今年の1年生で最初に試験に挑むのは、土地利用学科及び畜産学科の 15名。実習や講義の合間を利用し、日々練習に励んでいます。今日も、土地利用学科の学生が教官の指導を受けながら、練習に取り組んでいました。
試験日は、連休明けの5月11日(木)。全員合格に向けて、気合を入れて練習していきましょう!



毎日の当番(畜産学科) R5.4.29
飼養管理は毎日です。
この日(4/29(土))も、両専攻の当番が朝の管理に取組んでいます。
酪農専攻は、搾乳も終盤となり、消毒液や器具の等の片付けをしています。
肉用牛専攻は飼料の給与を終え、次の準備をしているようです。
.両専攻とも、2年生と1年生が手順を確認しながら取組んでいます。
1年生は、実習の手順は覚えていても、まだ「えぇっと …」はたくさんありますね。
今日も、頑張りましょう!


経営プロジェクト中間発表会【イチゴ】! R5.4.27
園芸学科では、2年生が行う経営プロジェクトについて、その内容や途中経過を紹介する中間発表会を行っており、今後の調査や結果の取りまとめに活かしています。
4月27日(木)には、本年度初めての中間発表会を開催しました。
今回は、『イチゴにおける複数の天敵を活用した防除体系の検証』について、野菜経営コース2年の担当学生が、調査の概要や結果を説明しました。
担当学生が丁寧に説明したこともあり、参加した学生や研修生から多くの質問がされ、有意義な発表会となりました。
次回は、5月11日に開催し、イチゴに関するプロジェクトについて発表が行われます。
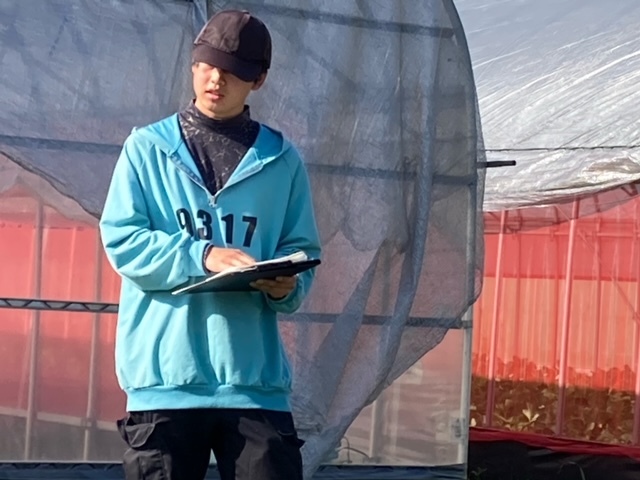

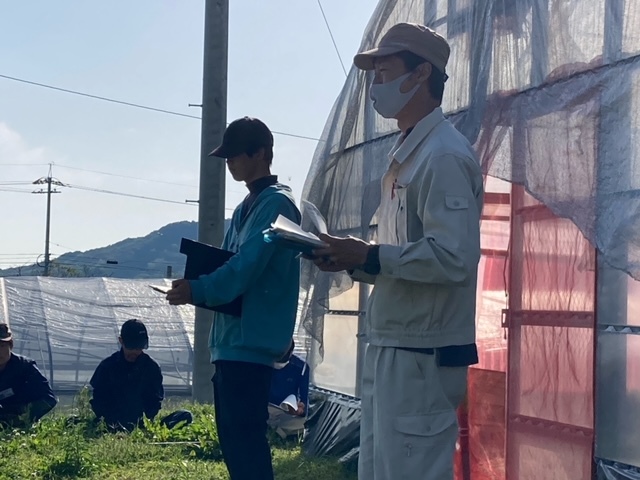

LAユリ定植準備【ベンチ耕うん】! R5.4.27
4月27日(木)、園芸学科花き経営コースでは、LAユリの定植に向け、栽培ベンチの土を耕うんしました。
担当の2年生は、耕うん機を使って、丁寧に行いました。
翌週には蒸気消毒を行うとともに、6月から時期をずらしながら定植を行う予定です。




LAユリ定植準備【天地返し・たい肥施用】! R5.4.26
園芸学科花き経営コースでは、LAユリの盆出し出荷に向けた球根処理に係る経営プロジェクトを行うこととしています。
4月26日(水)には、LAユリを定植するベンチ内の土の天地返しを引き続き行うとともに、バークたい肥や牛ふんたい肥をまきました。
翌日には、耕うんを行う予定です。




白ネギの播種! R5.4.26
園芸学科野菜経営コースでは、毎年、白ネギの栽培を行っており、本年も栽培を行うこととしています。
4月26日(水)には、白ネギの播種を行いました。品種は、「夏扇4号」です。
2年生が、1年生に指導しながら、ペーパーポットへの培土の充填、潅水、播種を行いました。
この白ネギは、約1ヶ月半ほど育苗した後、ほ場へ植え付け、来年1月頃に収穫する予定です。




イチゴ栽培ベンチ下のスカート除去! R5.4.26
4月26日(水)、園芸学科野菜経営コースのイチゴ担当の2年生と1年生が、イチゴ栽培用高設ベンチの下部を覆っていたビニル(スカート)を除去しました。
寒い時期には、ベンチの下に通したダクトから温風を送りますが、その保温効果を高めるため、ベンチの下部をスカートで覆っていました。
4月にはいってから、気温が高くなり、暖房が不要になったことから、覆っていたビニルを取り除いたものです。
その後、ベンチ下の雑草を抜き取ったり、通路部を掃いたりするなど、ハウス内の清掃にも取り組みました。




ブドウ棚のトンネルメッシュのビニル被覆! R5.4.26
4月26日(水)、園芸学科果樹経営コースのブドウ班の学生と研修生は、強風で剥がれたブドウ棚のトンネルメッシュのビニルを被覆し直しました。
学生らは、ビニルを傷つけないよう、丁寧かつ手早く被覆していきました。




刈払機操作指導! R5.4.26
4月26日(水)、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班では、職員立会いのもと2年生が1年生に刈払機の操作を指導しました。
2年生は、1年生に、刈払機の始業点検やナイロンコードのセット、給油の仕方等について説明した後、ほ場で、草の刈り方の実演を交えて指導しました。
1年生は、わからない所や疑問に思うところを積極的に質問するとともに、2年生は丁寧に回答していました。




カーネーション収穫最盛期間近! R5.4.24
4月24日(月)、園芸学科花き経営コースでは、カーネーションの収穫量が増えてきています。
母の日需要に合わせて仕立ててきましたが、現在のところ、ねらいどおり連休明け前後に収穫ピークを迎えそうです。
収穫を手伝う1年生は、2年生に確認しながら、花の咲き具合に応じて収穫を行っていました。




指先の感覚を磨く(畜産学科) R5.4.26
畜産学科の学生にとって、習熟しておきたい重要な技術の一つに「直腸検査」があります。
この技術は、人工授精をする前に、その適期や受胎を確認するためには不可欠なのですが、写真のとおり「手探り」です。
2年生は、1年生で家畜人工授精師の資格を取得した後、先生の指導を受けながら繰り返しトライしています。

苗箱、どんどん洗います! R5.4.26
土地利用学科では、今年、約8haの田植えを行う予定です。GW明けから始まる播種(種まき)に備えて、ただいま急ピッチで苗箱の準備を進めています。
この苗箱、全部で1,500枚くらいありますので、大人数で一斉に洗うのが精神的に楽な作業です。4月26日(水)は、一年生全員で約2時間、集中して洗いました。機械でざっと洗った苗箱を、学生が手際よく仕上げ洗いしていきます。天気もよく、雑談しながらの作業は、はかどりますね。綺麗になった苗箱がどんどん積み上っていきました。
今後は、水稲の栽培について学びながら、同時に圃場の準備を行っていく予定です。




イチゴの生育調査! R5.4.19
園芸学科野菜経営コースでは、イチゴ「かおり野」の栽植密度と芽整理による株管理の違いが収量に及ぼす影響に関する経営プロジェクトに取り組んでいます。
本課題に係る生育調査は、2週間おきに行っています。
4月19日(水)には、草高、葉長、展開葉数などを調べました。
担当の2年生によると、弱っていた株も、少しずつ回復しているとのことです。




畦畔の草刈り、いざ実践! R5.4.24
土地利用学科の1年生は、先週、刈払機の安全な操作方法を学んだばかりですが、実践こそ上達への早道です。4月24日(月)、さっそく1年生全員が、畦畔の草刈りを行いました。
土地利用学科の実習圃場は、近隣の生産者の圃場を借用しているため、畦畔の形状や傾斜はバラエティに富んでおり、また段差もあれば石垣もあるため、極めて実践的な実習が可能となっています。
今日は初めての実践なので、金属刃ではなく、ナイロンコードを使っての草刈りでした。少しずつ、少しずつ、試しながら刈るような感じでしたが、今後慣れてくれば、刈るスピードも速くなり、刈り跡もきれいに仕上げられるようになることでしょう。どれだけ上達するか、今から楽しみです!



スプレー菊の摘芯! R5.4.24
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用スプレーギクのわい化剤の処理濃度・回数に係る経営プロジェクトに取り組むこととしています。
4月24日(月)には、プロジェクトに供試するスプレーギクの摘芯を行いました。
これは、頂芽を摘み取ることで、脇芽の発生を促し、出荷花数の確保を行うものです。
担当の2年生は、手慣れた様子で、摘芯を行っていました。
6月中旬には、わい化剤処理を行う予定です。


令和5年度作目基礎研修がスタート!第1回講座が行われました。 R5.4.16
やまぐち就農支援塾では、新たに農業を始めようとされている方、農業法人等への就業(就職)を検討中の方などを対象に、日曜日を利用して農業・畜産の基礎的な知識・技術を学ぶ「作目基礎研修」を開講しました。
日曜日に開催することで、とても参加しやすく、さらにベテラン講師陣による充実した講義・実習で、毎年多くの方に受講いただいています。
今年度は6コース(野菜Ⅰ(施設)、野菜Ⅱ(露地)、果樹、水稲、畜産、農業機械)で63名の方が受講します。
開講式のあと、各コースに分かれて、最初の講義・実習を行いました。


ブドウの枝管理! R5.4.24
園芸学科果樹経営コースのブドウ班では、現在、ブドウの枝管理を行っています。
ブドウ栽培では、旺盛に伸びる新梢の伸びを弱めて新梢間の生育をそろえたり、新梢と新梢を適度な間隔に配置するため、新梢を棚に水平に誘引します。
誘引にあたっては、新梢の可動域を確保するため、新梢基部を捻じり折る「捻枝(ねんし)」という作業を行います。
この作業は、一歩間違えれば新梢を折ってしまうため、学生や研修生らは、集中して作業を行っていました。


ナシ幼木へのバークたい肥施用! R5.4.24
4月24日(月)、園芸学科果樹経営コースのナシ班が、ナシの幼木へバークたい肥を施用しました。
今回は、ナシ幼木の株元への散布で、根域の乾燥防止や雑草防止をねらうものです、
ナシ班の1年生は、2年生の指示のもと、1樹当たりバークたい肥約20リットルを株元に施用していきました。


促成スイカの生育状況! R5.4.24
園芸学科野菜経営コースでは、5月に収穫するスイカの栽培に取り組んでいます。
受精からの積算温度も、先週の時点で650時間を超えており、来週には小玉スイカの成熟の目安となる800℃に達する見込みです。
今週には、小玉スイカ「ひとりじめ7(セブン)」の試食を行う予定です。


サツマイモのマルチ張り! R5.4.21
4月21日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、サツマイモの定植に向け、1年生が畝へのマルチ張りを行いました。
慣れないクワ使いに、四苦八苦していましたが、教官の指導のもと、徐々に要領をつかんできて、きれいにマルチが張れました。
来月には、「紅はるか」と紫芋の「パープルスイート」のつるを定植する予定です。


メロン定植に向けた蒸気消毒! R5.4.21
4月21日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、メロンを定植するガラス温室のベンチ内の培土を、土壌消毒しました。
蒸気消毒は、蒸気の熱を土壌に浸透させ、病害虫や雑草の駆除を行う土壌消毒方法で、土壌の温度を80度とし、30分間保ったら完成です。
今後、潅水チューブの設置やマルチ被覆を行った後、メロンを定植する予定です。

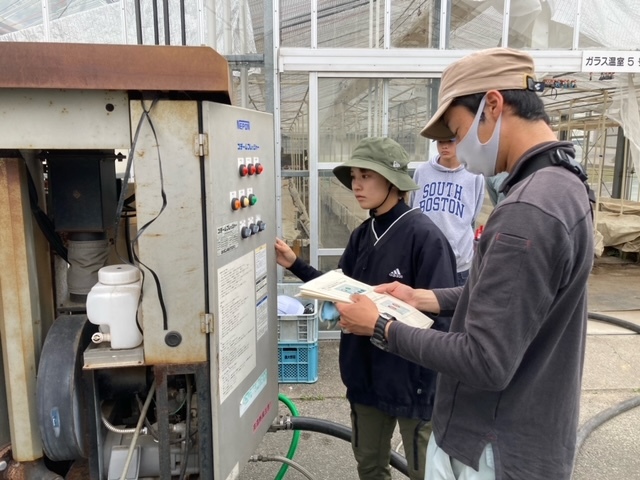
メロン定植に向けた蒸気消毒の準備! R5.4.20
園芸学科野菜経営コースでは、毎年、夏と秋に収穫するメロンを栽培しています。
今年も、7月に収穫する緑肉系のメロン「ミラノ夏Ⅰ」をガラス温室で栽培します。
メロンの苗を定植する前には、毎回、ガラス温室ベンチ内の土壌を蒸気消毒しています。
4月20日(木)には、蒸気消毒の準備として、蒸気放出用のホースをベンチの中央に敷き、その上にシートを敷きました。
担当の2年生に加えて、同級生や1年生、研修生、職員らが携わり、手際よく準備を進めていきました。
翌日には、蒸気消毒を行う予定です。




シクラメン鉢上げ! R5.4.20
園芸学科花き経営コースでは、主力品目であるシクラメンの鉢上げを行っています。
4月20日(木)には、1年生4名が、培土づくりや鉢上げを行いました。
1年生らは、2年生の虎の巻を確認した後、役割分担しながら、作業を行いました。
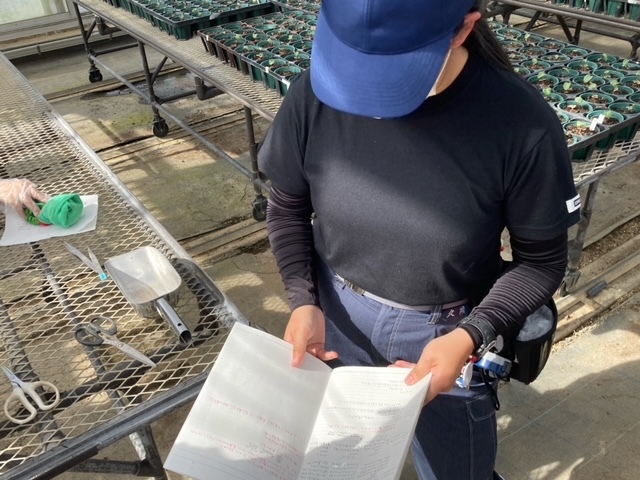

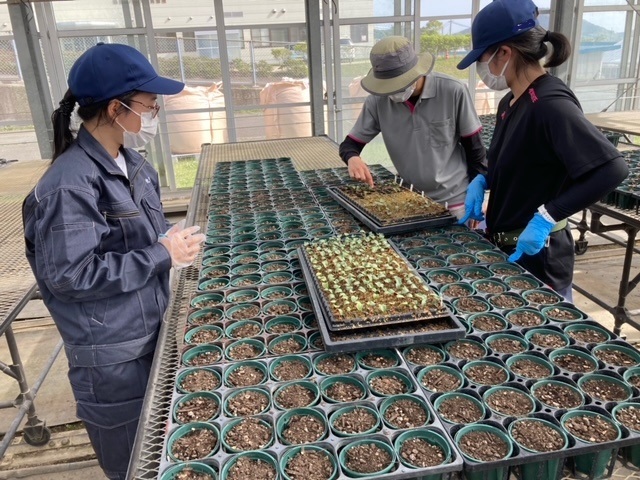

白オクラ種子のジベレリン処理および播種! R5.4.20
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、白オクラの発芽率の改善に向けた播種前処理方法を調べることとしています。
4月20日(水)には、担当の2年生が、白オクラの種子に「ジベレリン処理」を行いました。
今回、ジベレリンの濃度や浸漬時間を変えた9パターンの処理方法を試してみました。
処理した種子のうち、浸漬時間が5分のものは、セルトレイに充填した培土へ、播種を行いました。
今後、発芽状況を確認しながら、発芽率調査を行う予定です。
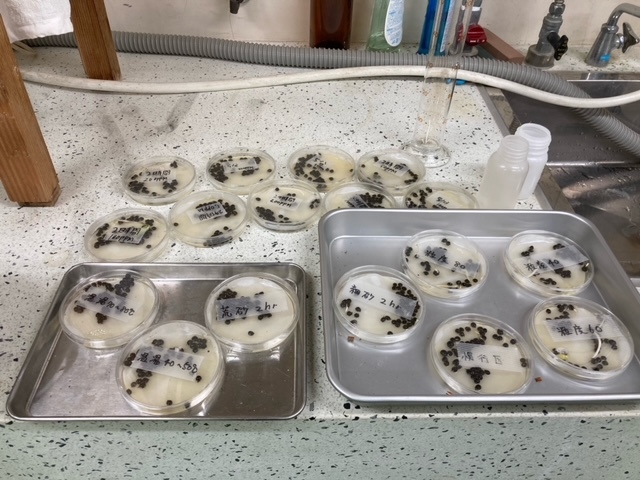


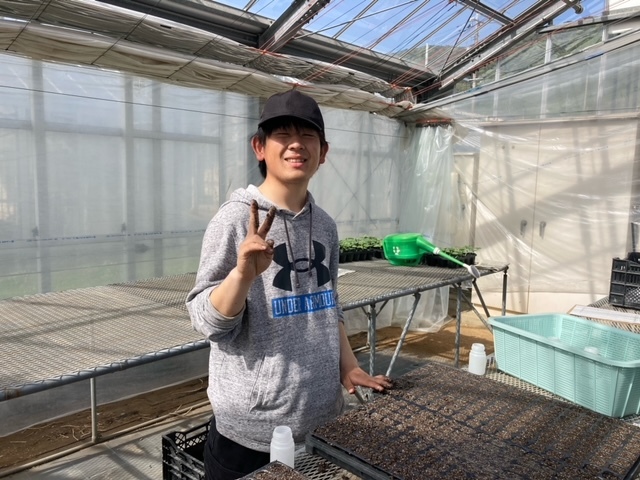
イチゴハウスへの寒冷紗被覆! R5.4.20
園芸学科野菜経営コースでは、気温の上昇に伴う暑熱対策として、今週からイチゴのハウスに寒冷紗をかけています。
4月20日(水)には、パイプハウスYC1及びYC2の2棟へ被覆しました。
担当の2年生や社会人研修生は、手際よく作業を行っていました。




牛舎に響く「声」! R5.4.20
今、酪農舎では搾乳の手順を確認する「声」が響いています。
二年生の指示する「声」に、一年生が応える「声」。
一つ一つの手順を確認するため、遅くなっていた搾乳の修了時間も、ずいぶん短くなってきました。
とはいえ、覚えなきゃいけないことは、まだまだたくさんあります。
頑張りましょう!



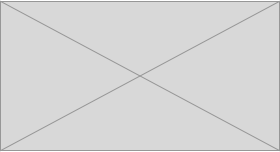
安全な草刈機の使い方! R5.4.20
4月20日(木)、1年生は農業機械の講義で、刈払機(草刈機)の安全な使い方を学びました。土地利用学科の学生は、講義終了後も引き続き、土地利用学科教官の指導のもとで刈払機の操作練習を行いました。
昨日の農薬散布同様、全員刈払機を使うのは生まれて初めてとのことでしたが、指導した教官曰く「全員イイ感じ」だそうです。
来週からは本格的に草刈り作業が始まりますが、これは期待できますね!
さあ、どんどん刈っていきましょう!



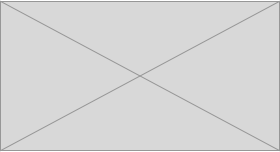
肉用牛専攻の朝! R5.4.20
肉用牛専攻の朝の実習風景です。
一枚目は、1年生が飼料の扱いについて先生から指示を受けています。カゴに入っているのは食べ残したエサです。
二枚目は、放牧場の水飲み場の掃除をしています。マメに掃除しないと汚れます。
三枚目は、1年生が肥育牛の午後エサを、確認しあいながら準備しています。バケツの数だけ牛房があります。
四枚目は、繁殖舎です。ひととおりの管理を終えたところです。牛の「痒い!」に応えています。




小麦の農薬散布! R5.4.19
土地利用学科の小麦栽培圃場に黄色い軍団が登場! 防護衣を着用した1年生11名です。4月19日(水)、学生全員で小麦の赤かび病の防除を行いました。
といっても、全員、農薬散布は初めてです。まずは、防護衣の着用、農薬散布用機械(セット動噴)の使い方、農薬の希釈について、教官から丁寧な説明を受けました。そして、全員新品の防護衣(まっ黄色)を着用して、昨日制作した飛散防止ビニール幕を準備して、準備万端いざ出陣!
農薬散布ではただ散布するのではなく、2種類のノズルを使って薬液の飛散距離の違いを比べたり、散布時の写真を撮って飛散状況を確認したりしました。ほとんど風の無い、農薬散布には最適な天候で、非常にスムーズに作業を終えることができました。
作業はスムーズにできたものの、初めての防護衣、初めての農薬散布、体力を消耗したことと思います。今日はゆっくり休んで、また明日も頑張りましょう!




白オクラの発芽率改善に向けた処理方法の検討! R5.4.19
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、白オクラの発芽率の改善に向けた播種前処理方法を調べることとしています。
3月から4月にかけて、様々な処理方法や条件を試行しながら、発芽率への影響を確認しているところです。
4月19日(水)には、担当の2年生が、「機械的処理」や「紙やすり処理」、「温湯処理」を行いました。
このうち、「温湯処理」は、「40~50℃のお湯に種子を漬け、自然冷却させる」方法と「70~80℃のお湯に数分漬け、すぐに冷水で冷却する」方法を試みました。
各処理を行った種子は、27℃の恒温器に24時間入れた後、発芽率を調査する予定です。




シクラメンの鉢上げ準備! R5.4.19
園芸課花き経営コースでは、今月、主力品目であるシクラメンの鉢上げを行うこととしています。
現在、ガラス温室内で、大輪の「パステルレッド」やミニシクラメンの「ベラノ」など13品種を育苗していますが、これらを3.5号ポットに植え替えることにより、株を大きくするものです。
4月19日(水)には、2年生の指導のもと、1年生4名が、培土づくりや培土のポット詰めを行いました。
1年生らは、最初は慎重に作業を行っていましたが、徐々に手際がよくなっていきました。




キュウリの液肥施用方法の指導! R5.4.19
園芸学科野菜経営コースでは、新たに入学した1年生に対し、2年生がトレーナーとなって、担当する作物を中心に、栽培管理や収穫・出荷調整等について指導を行っています。
4月19日(水)には、ガラス温室でキュウリ栽培を担当する2年生が、1年生へ液肥の施用方法を指導しました。
2年生は、液肥施用に係る装置の操作方法や液肥の希釈の仕方を丁寧にわかりやすく伝え、1年生は十分理解したようでした。




アスパラガスの潅水方法の指導! R5.4.19
4月19日(水)、園芸学科野菜経営コースでアスパラガスを担当する2年生が、1年生へ潅水方法を指導しました。
2年生は、潅水の操作方法やタイミング等を熱心に伝えるとともに、1年生は真剣に聞き入っていました。
今後、本ハウスでは、フラワーネットを設置する予定です。




屋根散水装置の設置! R5.4.19
園芸学課野菜経営コースでは、夏秋ホウレンソウのハウス栽培における屋根散水によるハウス内昇温抑制効果の検証を行うこととしています。
4月19日(水)には、担当の2年生らが、パイプハウスの屋根部分に潅水チューブを設置しました。
今後、晴天時の9~16時に散水し、ハウス内の温度の推移を確認する予定です。




イチゴの害虫発生調査! R5.4.19
園芸学課野菜経営コースでは、イチゴにおける複数の天敵を活用した防除体系の実証に取り組んでいます。
本課題に係る害虫発生調査は、1週間おきに行っており、4月12日(水)には、担当の2年生が、葉裏のハダニや花のアザミウマの発生状況を調べました。
天敵を放飼したハウスでは、今回もハダニは確認できませんでしたが、アザミウマは前回より多く確認されました。
本ハウスでは、天敵がいなくなったものと考えられますが、残りの収穫期間を考慮すると、天敵の再放飼は見送ることとしています。




トルコギキョウの定植! R5.4.19
園芸学科花き経営コースでは、盆前出荷のトルコギキョウ栽培における育苗作業の省力化の検証に係る経営プロジェクトを行っています。
4月19日(水)には、担当の2年生が、供試品種である「ボヤージュ(2型)ブルー」の苗を定植しました。
今回は「慣行区」用として、本葉4枚が十分に生長して3節目の葉が見え始めたステージの苗を定植しました。




ブロッコリーの生育調査! R5.4.19
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
3月末に定植して以降、週に一度、生育調査を行っており、4月19日(水)には、最大葉の長さと幅を調べました。
担当の2年生曰く、順調に生育しているとのことです。




カボチャの生育調査! R5.4.19
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、カボチャの施肥体系の検証に取り組んでいます。
3月末に定植して以降、担当の2年生は、週に一度、生育調査を行っています。
4月19日(水)には、同級生とともに、茎の太さを調べました。
調査結果は、自身のノートにきれいに整理していました。
今後、二本仕立てとするため、株ごとに、生育の揃った2本の子づるを残す作業を行っていきます。




ワサビの収穫・栽培に係る講義! R5.4.19
4月19日(水)、園芸学課野菜経営コースでは、ワサビ篤農家で山口県農業士協会会長でもある梅川仁樹さんに来校いただき、ワサビの収穫作業に係る指導やワサビの生理・生態やワサビを取り巻く近年の情勢などについての講義を受けました。
作業指導や講義を受講した学生や社会人研修生は、梅川さんの話に、目を輝かせながら興味深く聞き入っていました。
本日、収穫したワサビは、明日出荷する予定です。




カンキツ園にロボット草刈機導入! R5.4.19
園芸学科果樹経営コースでは、経営プロジェクトの一環として、カンキツ園の草刈り作業の省力化を行っています。
このたび、必要な準備がほぼ整い、試運転を行いました。
初めに、区画内の草を刈りはらいました。次いで、エリアワイヤと呼ばれる被覆銅線を、ロボット草刈り機に刈ってほしい区画の縁に張りました。さらに、充電ステーションと延長コードを設置し、近くの施設から電源を確保しました。最後に、試運転をして、動作を確認しました。動作確認の際には、区画内に設置しているマルチ被覆用鉄管を除去する、ロボットが切ってしまいそうなチューブの有無を確認するなど、想定される対策を施しました。
しかし、試運転の際に刈りはらって放置していた長い草を巻き込んだり、マルチ抑え用のピンを弾いたりし、より丁寧な事前準備が必要と分かりました。
今後、刈りはらった草を除去する、金属製品の徹底的な除去、潅水チューブなどを地際から浮かないように抑えるか、カバーをかけるなどの工夫をして、今週中に本格運用する予定です。




防除用の資材を作ったり、育苗用の資材を片づけたり R5.4.18
土地利用学科では、今週、小麦に農薬散布を行う予定です。4月18日(火)、農薬散布に向けた準備を行いました。一つ目は、農薬の飛散を防ぐために散布箇所周辺に設置する飛散防止幕です。幅約1.5m×長さ約20mのビニールを使って、学生4人がテキパキと作りました。
二つ目は、農薬散布時に着用する防護衣を干す簡易物干しです。学生3人と研修生が、グラインダーや鋸で資材を切断して、手際よく作っていました。
また、水稲の育苗に使用する、ながーい(40m程度?)ビニールシートを洗って干していましたが、これも学生4人が協力して片づけました。とても風が強い日で、ビニールが煽られて四苦八苦していましたが、最後はチームワークで綺麗にまとめていました。グッジョブ!



パイプハウスへの「妻窓」の設置! R5.4.18
4月18日(火)、園芸課花き経営コースでは、前日に1年生がシンテッポウユリを定植したパイプハウスへ、「妻窓(つまそう)」を設置しました。
これは、これから徐々に気温が高くなるため、ハウス内ができるだけ高温にならないよう、ハウスの妻面上部に、空気の取り込みや排出ができる窓を設置するものです。
妻窓の設置に携わった1年生は、高所での作業のため、ヘルメットを着用するとともに、脚立に上がる際には、他の学生が脚立を支えていました。




ケイトウの播種! R5.4.18
4月18日(火)、園芸課花き経営コースでは、ケイトウの播種を行いました。
今回播いたのは、久留米系の「ファイアリーレッド」や「ボンベイピンク」など4品種です。
担当した2年生は、培土をセルトレイに充填した後、真空播種機を用いて、セルトレイへ1粒ずつ播種しました。
播種後は、1ヶ月程度育苗した後、ガラス温室内に定植します。
収穫は、7月下旬に開始する予定です。




LAユリの定植準備【天地返し】! R5.4.18
園芸課花き経営コースでは、経営プロジェクトとして、LAユリの葉焼け症対策を検証することとしています。
4月18日(火)には、LAユリの定植準備として、ベンチ内の土壌の天地返し(てんちがえし)を行いました。
天地返しとは、文字通り天と地をひっくり返すように畑の表層の土と下層の土とを入れ替える作業のことで、土壌の物理性や排水性の改善などをねらうものです。
今回は、1年生4名がスコップを使って行いました。慣れないスコップ作業でしたが、丁寧に土の入替を行っていました。




ブロッコリーの摘芯! R5.4.18
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾(からい)取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
4月18日(火)には、調査区の一つである「V字仕立区」で、ブロッコリーの摘芯を行いました。
本葉が9枚程度になったのを確認した後、頂芽を摘芯していきました。
この仕立てでは、摘芯後に発生した側枝のうち強勢な2本を残し、それにつく花蕾を収穫する
もので、慣行に比べて、収穫花蕾の本数増加をねらうものです。




促成スイカの生育状況! R5.4.18
2月1日に定植したスイカは、果実が順調に肥大しており、4月18日(火)には、大玉スイカの「祭りばやし777」で、直径が24センチに達する果実を確認しました。
スイカの成熟は、受精からの積算温度が中大果種で1,000~1,100℃、小果種で800~1,000℃必要とされており、目安として中大果種で45日前後、小果種で38~40日といわれています。
5月上旬に、果実品質の確認を行った後、収穫時期の決定を行う予定です。


白いもの生育状況! R5.4.18
園芸課野菜経営コースでは、本年度も白いもの育苗に取り組んでおり、3月13日には種芋をプランターへ植え付け、3月28日には一部のプランターで発芽を確認されるなど、順調に生育しています。
4月18日(火)現在、長いものでは 15cm程度のツルが確認されています。
このプランターは、4月末以降には、山口銀行防府支店へお渡しし、採取されたツルを防府市野島の管理ほ場に定植される予定です。


高速切断機によるパイプの切断! R5.4.18
4月18日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、パイプハウス補強用の直管パイプの切断を行いました。
今回、1年生が高速切断機を使って、直管パイプの切断を行いました。
1年生は、高速切断機を初めて使いましたが、教官の指導のもと、要領を得て、上手に切断していました。




肉用牛専攻 本年度初出荷! R5.4.17
肉用牛専攻の 本年度 初出荷は、無角和種の子牛です。
生まれてから、これまで学生が丁寧に育成してきました。出荷先の「無角和種振興公社」では、繁殖雌牛として活躍してくれるものと思います。

ゆっくり!丁寧に!確認しながら!! R5.4.17
搾乳の手順や飼養管理の一つ一つの手順を2年生が1年生にゆっくり、丁寧に教えています。この日も、いつもより実習終了時間が遅くなりましたが、1年生の「聞きたい」に2年生が応えていました。


シンテッポウユリの定植! R5.4.17
4月17日(月)、園芸課花き経営コースでは、新たに入学した1年生4名が、シンテッポウユリの定植を行いました。
教官から、植え方の指導を受けた後、二人がペアになり、定植作業を行いました。
1年生は、ピンセットでセルトレイから苗を抜き取り、マルチに穴を開けて苗を植付けるといった工程を、丁寧に進めていました。
今回植え付けた品種は、「雷山1号」と「雷山2号」で、7月上旬から下旬にかけて収穫する予定です。




「スマート農業機械論」でリモコン式草刈機の操作実習! R5.4.17
土地利用学科には、他の学科には無い講義が二つあります。そのうちの一つ、「スマート農業機械論」が、4月17日(月)から始まりました。今回のテーマは、「リモコン式草刈機(リモコンによる遠隔操作で草刈りを行う機械)」です。
学生たちは、リモコン式草刈機の概要について講義を受けた後、圃場に出て、リモコン式草刈機の操作実習を行いました。このリモコン式草刈機、その名のとおり、リモコンのボタンやレバーを使って、エンジン始動、前進後進旋回、草刈り等の操作ができる優れモノ。とはいえ、草刈機が走る場所は舗装道路と違って凸凹や草があるので、真っすぐ走らせることが意外と難しいんです。今回は一人一往復のみの操作でしたが、真っすぐ走らせられる人もいれば、ぐにゃぐにゃ曲がる人も。
今後、多くの農業機械を使いこなせるように実習が続きますが、このリモコン式草刈機も上手くなってほしいものです。みんな若いから、すぐ上達するはずです。まずはチャレンジ!




セット動噴の洗浄に係る講習【野菜専攻】! R5.4.17
4月17日(月)、園芸課野菜経営コースでは、新たに入学した1年生や3月に入塾された担い手養成研修生を対象に、セット動噴の洗浄に係る講習会を開催しました。
講師は2年生が務め、マニュアルに基づき、順を追って、丁寧に説明していました。
防除後のセット動噴の洗浄を誤ると、大きな事故につながることから、1年生や研修生は、真剣に聞き入っていました。




新入生がオリエンテーションで自己紹介! R5.4.13
4月13日(木)、新入生が、互いの理解と共同生活に慣れるきっかけづくりとしてオリエンテーション内で一人ずつ前に出て自己紹介を行いました。
人前でしゃべるのは苦手だと話していた学生もいましたが、皆さん堂々と農大に進学にした理由など発表していました。中には、趣味の話で盛り上がる学生もいるなど、個性溢れる発表ばかりで終始和やかなムードで進みました。




肥料、農薬の計算の練習! R5.4.14
土地利用学科では、現在小麦の管理を中心に学修していますが、今後、水稲や大豆等の栽培が本格的に始まります。
4月14日(金)、それらが始まる前に、栽培管理の基礎となる肥料や農薬の量の計算を練習しました。
単純に掛け算すれば済むような問題であれば、みんな難なく計算することができますが、窒素成分が〇%含まれる肥料を施肥する時の必要量は何キロ? など少し複雑な計算になると、ムムム・・・?
今は時間がかかっても、栽培が始まるときにはスラスラ計算できるように、頑張って練習していくこととしています!


ジャガイモの生育調査! R5.4.14
園芸課野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ジャガイモのマルチ栽培に係る経営評価に取り組んでいます。
3月14日の定植後、「生分解性マルチ区」、「黒マルチ区」、「裸地区」の3つの調査区では、萌芽が確認されるとともに、順調に生育しています。
4月14日(金)には、初めて生育調査を行いました。担当の2年生が、慎重に草丈を計測していました。
本調査は、毎週行う予定です。


メロン苗の鉢上げ! R5.4.14
4月14日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、メロンの鉢上げを行いました。
まず、鉢上げするポットの培土を作成し、その後、4月1日に播種した緑肉系メロン「ミラノ夏Ⅰ」の苗をポットに植え替えました。
メロン担当の2年生は、他の2年生や1年生、研修生の補助を受けながら、420本を鉢上げしました。
翌週にガラス温室内のベンチの土壌を蒸気消毒した後、4月末頃に定植する予定です。




トルコギキョウの発芽率調査! R5.4.13
園芸学科花き経営コースでは、盆前出荷のトルコギキョウ栽培における定植作業の省力化の検証に係る経営プロジェクトを行っています。
4月13日(木)、担当の2年生が、直播区、吸水低温処理種子直播区、稚苗区、慣行区の発芽率調査を行いました。
慣行区は、8割を超える発芽率であり、来週には定植を行う予定です。




ロボット草刈機設置準備! R5.4.13
園芸学科果樹経営コースでは、経営プロジェクトとして、充電式ロボット草刈機による柑橘園の草刈り作業の省力化の検証を行うこととしています。
4月13日(木)には、カンキツ班の2年生2名と、当日より専攻実習に参加した1年生1名が、教官の指導のもと、ロボット草刈機に草刈りをさせるエリアを決めました。
エリアロープを地表面に設置することで、そのエリア内をロボット草刈機が草刈りを行うものです。
今週末は雨模様のため、ロボット草刈機の初稼働は、翌週に延期されました。




盆出荷用スプレー菊の定植! R5.4.13
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用のスプレー菊へのわい化剤の処理方法の違いが草丈や切花品質、作業性に及ぼす影響を調査する経営プロジェクトに取り組んでいます。
4月13日(木)には、2年生や教官らにより、ガラス温室内のベンチへキクを定植しました。
今回定植した品種は、「セイオルビア」ら4品種です。
担当の2年生は、真剣な表情で定植作業を行っていました。
今後、週1回のペースで、草丈や葉数といった生育調査を行う予定です。




土地利用学科が始動! R5.4.13
4月13日(木)、いよいよ新設の土地利用学科の実習が始まりました。
最初の課題は、実習する圃場の場所を覚えることです。土地利用学科の実習圃場は農林総合技術センター正門から結構距離があるものも多いため、11名の学生は、教官の説明を受けながら、2時間以上かけて巡回を終えました。
途中の小麦作付圃場では、小麦を観察するだけでなく、麦で問題となる雑草を覚えるため、全員でヤエムグラやカラスノエンドウ等の雑草を探しました。雑草を見つけた学生が「ヤエムグラ見つけた!」と言うと、教官から「10ポイント!」と返事が・・・
ちょっと楽しそうでした。


防府天満宮「大石段花回廊」の展示状況! R5.4.13
4月12日(水)、本校や市内の中学校等が管理したビオラ、ゼラニウム、ガザニアの花鉢が、防府天満宮に搬入され、「大石段花回廊」に展示されました。
今年は、700鉢以上の花鉢を用いて、「幸せます」の文字やハート形となるよう並べられました。
この「大石段花回廊」は、5月14日(日)まで展示されますので、ぜひご覧ください。


ジャガイモの土寄せ! R5.4.13
園芸課野菜経営コースでは、ジャガイモのマルチ栽培導入に係る経営評価を行うこととしており、調査区として、マルチ被覆区とマルチを被覆しない慣行区を設けています。
4月13日(木)には、担当の2年生が、管理機を使用して、慣行区の土寄せを行いました。
土寄せは、新しいイモが肥大するよう根圏を拡大するとともに、イモに直接日光が当たらないようにしたり、雑草を減らすために、行うものです。
本ほ場は、石が多いため、耕うん時に石が挟まって、管理機が動かなくなるというトラブルにも見舞われましたが、担当の2年生は上々の仕上げで土寄せを終えていました。




イチゴの害虫発生調査! R5.4.12
園芸課野菜経営コースでは、イチゴにおける複数の天敵を活用した防除体系の実証に取り組んでいます。
本課題に係る害虫発生調査は、2週間おきに行っています。
4月12日(水)には、担当の2年生が、葉裏のハダニや花のアザミウマの発生状況を調べました。
天敵を放飼したハウスでは、今回もハダニは確認できませんでしたが、アザミウマは確認されました。また、アザミウマの被害を受けた花や果実も散見されました。




カボチャの生育調査! R5.4.12
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、カボチャの施肥体系の検証に取り組んでいます。
担当の2年生は、3月末に定植して以降、週に一度、生育調査を行っています。
4月12日(水)には、茎の長さや太さ、最大葉の長さや幅を調べました。




露地ほ場のほ場準備【たい肥散布・耕うん】! R5.4.12
4月12日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、正門横に位置する露地ほ場のほ場準備を行いました。
2年生が、マニュアスプレッダーを使って、たい肥を散布しました。
その後、2年生や社会人研修生が交代しながら、トラクタで耕うんしました。
本ほ場では、今後、ナスや白オクラを定植する予定です。




防府天満宮「大石段花回廊」展示に向けた花鉢の搬出! R5.4.12
4月12日(水)、「大石段花回廊」の展示に向け、本校のガラス温室等で育てたビオラ、ゼラニウム、ガザニアの寄せ鉢、423鉢を防府天満宮へ搬出しました。
防府天満宮の「大石段花回廊」は、今年で11回目を迎える恒例行事です。
今年は、花鉢を「幸せます」の文字となるよう並べられるとのことです。
この「大石段花回廊」は、4月14日(金)から5月14日(日)まで展示されます。




入学式を挙行しました! R5.4.11
4月11日(火)、令和5年度の入学式を挙行しました。33名の新入生を代表して、畜産学科肉用牛経営コースの濱田さんが誓いの言葉を述べました。新入生は、これからの2年間、全寮制のもと、それぞれの専攻で実践的な学修に取り組みます。




花粉採取用ナシへの施肥! R5.4.11
4月11日(火)、園芸学科果樹経営コースでは、花粉採取用として植栽しているナシ「ヤーリー」や「長十郎」等へ施肥を行いました。
花粉を採取するため、3月下旬に昨年伸びた枝を全て切ったところですが、来年の枝を確保するため、施肥を行うものです。
今回は、窒素成分で10a当たり12㎏程度をまきました。




極早生タマネギの収穫! R5.4.11
4月11日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、極早生タマネギの「貴錦(たかにしき)」の収穫を行いました。
昨年9月14日に播種し、11月7日に定植した後、担当の2年生が、除草や防除等を行い、無事、収穫に至りました。
収穫したタマネギは、ハウス内で、3日間程度乾燥させた後、直売所や市場へ出荷する予定です。


促成スイカの生育状況! R5.4.10
園芸学科野菜経営コースでは、5月に収穫するスイカの栽培に取り組んでいます。
2月1日に定植したスイカは、果実が順調に肥大しており、4月10日(月)には、大玉スイカの「祭りばやし777」で、直径が20センチに達する果実を確認しました。
また、当日は、2月22日に定植したスイカの人工受粉も開始しました。




トルコギキョウの稚苗定植! R5.4.10
園芸学科花き経営コースでは、盆前出荷のトルコギキョウ栽培における育苗作業の省力化の検証に係る経営プロジェクトを行っています。
4月10日(月)、担当の1年生が、トルコギキョウ「ボヤージュ(2型)ブルー」の稚苗を定植しました。
通常は、本葉4枚が十分に生長して3節目の葉が見え始めたステージで定植を行いますが、稚苗定植は、子葉展開期の稚苗を定植することで、育苗期間の短縮による育苗作業の省力化を図るものです。
調査区あたり50株を供試する予定ですが、今回、2株定植でき、先週金曜日の定植分と合わせて15株定植が済みました。今後、苗の生育状況に応じて、順次定植を行っていきます。




入学式前の環境整備(野菜ゾーン)! R5.4.10
4月10日(月)、園芸学科野菜経営コースでは、翌日に挙行される「令和5年度入学式」に向けて、環境整備を行いました。
正門横の正面ほ場や資材庫前の道路沿いは、ナイロンコードを装着した刈払機で丁寧に草を刈るとともに、ガラス温室横は、自走式草刈機を用いて慎重に刈り進めていきました。




卒業式会場への壺花活け込み! R5.4.10
いよいよ、明日4月11日(火)に「令和5年度入学式」が挙行されます。
4月10日(月)には、卒業式の会場である本館講堂や階段横の壺花の活け込みが、学生支援課園芸グループ職員により行われました。




レモンの整枝(せいし)! R5.4.10
4月10日(月)、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班が、レモンの整枝を行いました。
今回行った整枝は、受光態勢や作業性を良くするため、主枝や亜主枝など、骨格となる枝を改めて定めるためのものです。
カンキツ班の2年生は、枝の方向や太さ、空間を確認しながら、枝を誘引していきました。




ナシの摘花(てきか)・摘果(てきか)! R5.4.10
4月10日(金)、園芸学科果樹経営コースのナシ班が、ナシの摘花・摘果を行いました。
今年のナシは、3月24日から4月5日の間に人工受粉を行っており、遅れて開花した花や、本来、葉になるはずの芽が花芽分化した子花(こばな)が結実した果実は、ナシの樹体に貯蔵されている養分を浪費することから、摘み取っていきます。
ナシ班の学生は、枝毎に丁寧に確認しながら摘花を行っていました。




花回廊用花鉢の施肥・花摘み! R5.4.10
毎年4月中旬から5月上旬に、防府天満宮では、大石段を花鉢で飾る「花回廊」が行われており、本校も花鉢の準備で関わっています。
3月17日に、ビオラの花鉢300鉢を防府市内の5つの中学校等に搬出しましたが、残りのバーベナやベゴニア等400鉢は、本校で管理を続けてきました。
これらは、4月12日(水)に防府天満宮へ搬出されることから、4月10日(月)には、各鉢に肥料を施すとともに、しおれた花や咲き終わった花を摘み取りました。




ナシ「豊水」の苗木定植! R5.4.6
4月6日(木)、園芸学科果樹経営コースのナシ班が、ナシ「豊水」の苗木を植付けました。
「豊水」は、農大で最も多く植えられており、9月上旬から収穫できる品種です。
果実は、甘さと酸味が調和し、直売所でも人気があります。
今後、こまめな潅水や施肥を行って、樹を大きくしていく予定です。


トルコギキョウの発芽率調査! R5.4.6
園芸学科花き経営コースでは、盆前出荷のトルコギキョウ栽培における定植作業の省力化の検証に係る経営プロジェクトを行っています。
4月6日(木)、担当の2年生が、3月2日に播種した稚苗区の発芽率調査を行いました。
現時点では、発芽の揃いが思わしくないため、定植は時期をずらしながら行う予定です。




ブドウの苗木定植! R5.4.6
4月6日(木)、園芸学科果樹経営コースのブドウ班が、ブドウの苗木を植付けました。
今回植え付けたのは、「シャインマスカット」3本、「涼香」1本、「ナガノパープル」2本の合計6本です。
一週間前に掘っておいた植穴に、苗木を入れ、根を切らないよう丁寧に土と水を施しました。その後、苗木は支柱と結束しました。
今後は、定期的に潅水や施肥を行い、今年度中に棚付けして、主枝候補枝を育成していきます。


温州ミカンの苗木定植! R5.4.6
4月6日(木)、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班が、温州ミカンの幼木を植付けました。
今回植え付けたのは、「青島温州」5本です。樹齢が過ぎて枯れてしまった成木を伐採・伐根し、新しい幼木(苗木)を植えました。
「青島温州」は山口県のミカンの栽培面積のうち60%を占める品種で、12月ごろに収穫して1月~3月にかけて出荷します。
少しでも早く樹を大きくするため、苗木の周辺にビニルを巻いて温度上昇を図ります。
今後は、定期的に潅水や施肥を行うとともに、6~8枚の葉が開いたところで先端を摘心し、樹が早く大きくなるよう管理します。


キウイフルーツの苗木定植! R5.4.6
4月6日(木)、園芸学科果樹経営コースのブドウ班が、キウイフルーツの苗木を植付けました。
今回植え付けたのは、「トムリ」の3品種です。
キウイフルーツは、雌雄別株のため、果実を収穫する樹(雌株)と花粉採取用の樹(雄株)を別に植える必要があります。
雌株は、「東京ゴールド」と「ヘイワード」で、前者は果肉が黄色い品種、後者は国内で最も多く栽培されている品種です。雄株は、「トムリ」です。
今後は、定期的に潅水や施肥を行うとともに、今年中に棚付けして主枝候補枝を選定していきます。


柑橘「みはや」主枝の摘蕾(てきらい)! R5.4.6
4月6日(木)、園芸学科果樹経営コースのカンキツ班が、「みはや」の摘蕾を行いました。
「みはや」は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が育成した年内に収穫できるカンキツで、果皮が濃いオレンジ色になり、糖度が高く食べやすいため、果樹経営コースの人気品種の一つです。
今回は、主枝の先端の蕾を取る作業を行いました。
主枝は、たくさんの枝に養水分を分配するよう『汲み上げポンプ』の役割をします。『汲み上げポンプ』の役割を徹底するため、主枝先端50cm程度は蕾を除去する必要があります。
難しいのは、蕾と一緒に葉を取らないように作業することです。
また、一度蕾をとっても、再び蕾が着くことがあるため、7~10日おきに見回って摘蕾を徹底します。


バラハウスへの循環扇設置! R5.4.5
4月5日(水)、園芸学科花き経営コースでは、バラを栽培しているパイプハウスに循環扇を設置しました。
循環扇の設置は、空気を対流させることにより、夏場の気温上昇や病害虫の発生を抑制することを目的とするものです。
設置にあたっては、バラ担当の2年生らが行い、慎重に設置場所を決めるとともに、手早く設置を行っていました。
本ハウスには、「サムライ」など9品種を植えており、5月上旬より収穫を開始する予定です。




ブロッコリーの生育調査! R5.4.5
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
3月にに定植して以降、担当の2年生は、週に一度、生育調査を行っています。
4月5日(水)には、最大葉の長さと幅を調べました。
現時点では、ブロッコリーは順調に生育しています。




促成スイカの生育状況! R5.4.4
園芸学科野菜経営コースでは、5月に収穫するスイカの栽培に取り組んでいます。
2月1日に定植したスイカは、3月24日から4月2日にかけて人工受粉を行っており、結実するとともに、果実が肥大しています。
4月4日(火)には、大玉スイカの「祭りばやし777」で、直径が10センチを超える果実を確認しました。
担当する2年生は、スイカの順調な生育に喜んでいました。




メロンの播種を行いました! R5.4.4`
4月4日(火)、園芸学科野菜経営コースの2年生が、メロンを播種しました。
今回播種した品種は、緑肉系の「ミラノ夏Ⅰ」です。育苗箱に培土を充填した後、種子の向きをそろえながら、種を播きました。
今回、約420鉢の苗を作る予定で、育苗後はガラス温室で栽培します。収穫は、7月中下旬頃を予定しています。


カボチャの定植! R5.3.31
園芸学科野菜経営コースでは、カボチャの施肥体系に係る経営プロジェクトに取り組むこととしており、露地ほ場およびハウス内でカボチャの栽培を行います。
3月31日(金)には、担当の1年生らが、カボチャの定植を行いました。
品種は、「くりゆたか」で、ほくほくとした食感で甘みが強いのが特徴で、県内では山陽小野田市で産地化され、「寝太郎かぼちゃ」のブランドで販売されています。
今後は、週1回、茎径や最大葉長等の生育調査を行う予定です。


ナシの人工授粉! R5.3.31
園芸学科果樹経営コースのナシ班では、ナシの人工受粉を行っています。
本年は、先週金曜日より人工受粉を開始しましたが、今週に入って好天に恵まれ、順調に人工受粉が進んでいるところです。
3月31日(金)は、本校の主力品種「豊水」や「ゴールド二十世紀」等の人工受粉を、ブドウ班とともに行いました。
確実に結実させるため、4月5日(火)頃まで人工受粉を行う予定です。




かんきつ「南津海」の収穫・選果! R5.3.31
園芸学科果樹経営コースでは、ガラス温室で「南津海」を栽培しています。
「南津海」は、本県の周防大島町(旧橘町)で、カラマンダリンと吉浦ポンカンを交配して生まれた柑橘の品種で、収穫は4月前後で、樹上で完熟させるため、酸味が落ち着き、高糖度に仕上がるのが特徴です。
3月31日(金)、果樹経営コースのカンキツ班が、「南津海」の収穫、選果を行いました。
午前中に約400㎏を収穫し、午後からは選果を行い、階級や等級別に分けました。
果実の糖度は14度を超えており、十分な甘みを確保できているため、4月上旬から直売所に出荷する予定です。


危険個所啓発掲示物作成に向けた撮影! R5.3.30
園芸学科では、GAP(適正農業規範)による適切な農場管理に関する学習を行っており、この一環で、学生や研修生、職員らが、重大な災害や事故に直結する一歩手前の出来事のことを体験したら、「ヒヤリハット報告」を行うこととしています。
3月27日(月)には、園芸学科野菜経営コースの1年生から、見通しの悪い通路を通って校内の道路に出ようとした際、危うく車にぶつかりそうになったとの報告がありました。
そこで、3月30日(木)に、本危険個所で飛び出ししないよう啓発するための掲示物作成に向けた画像撮影を行いました。
モデルとなった学生は、掲示物の趣旨を踏まえて、より効果的なポーズをとってくれました。




トマトの天敵製剤放飼! R5.3.30
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、天敵製剤(生物農薬)の活用を軸としたトマトのIPM防除体系の検証を行うこととしています。
3月30日(木)には、トマト栽培ハウスへ、天敵製剤を放飼しました。
今回放飼したのは、トマトの難防除害虫であるコナジラミ類やアザミウマ類を捕食する天敵昆虫「タバコカスミカメ」であり、慣行の化学農薬を主体とした栽培に比べ、防除回数の削減等が期待されます。
今後は効果を確認するため、調査を行い、害虫発生の推移を把握していきます!






カボチャ苗の親ヅルの摘芯! R5.3.29
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、カボチャの施肥体系の検証に取り組みます。
3月29日(水)には、カボチャ苗の摘芯を行いました。
本葉が4~5枚展葉した時点で、親づるの先端を摘芯し、今後は、下位節から発生した子づるのうち、生育の揃った2本を残し、残りを摘除する予定です。
このカボチャ苗は、3月31日(金)に定植します。




乳牛共励会に出品しました! R5.3.28
酪農専攻コースでは、3月24日(金)に山口県酪ホルスタイン改良同志会が主催する「第33回山口県酪ホルスタイン改良同志会乳牛共励会」に3頭を出品しました。(第1部から3部まで全13頭出品)
本共励会は、会員のホルスタイン種牛の改良と親睦・交流を目的に開催されています。
本校の出品牛は、調教や毛刈り等を頑張った成果を発揮して、審査ではスムーズに歩き、第1部で優等賞を受賞することができました。
審査後の研修会でも牛の見方を教えていただき、大変有意義な時間になりました。


環境整備(花きゾーン)! R5.3.28
3月28日(火)、園芸学科花き経営コースでは、環境整備として、花きパイプハウス群の前の水路周辺の草刈りを行いました。
草刈りを行った1年生は、ナイロンコードを使って、やや丈の高い草も、バリバリ刈っていきました。




環境整備(野菜ゾーン)! R5.3.28
本校の桜も見ごろとなる一方で、ほ場周辺の雑草も旺盛に伸びています。
こうした中、3月28日(火)には、園芸学科野菜経営コースが、環境整備として、ハウス群や露地ほ場の周辺の草刈りを行いました。
天気もよく、汗ばむ陽気でしたが、刈払機を操る学生3人は、丁寧に草を刈っていました。




白いもが発芽しました! R5.3.28
3月28日(火)、3月13日(月)にプランターへ伏せこんだ白いもの発芽が確認されました。
園芸学科野菜経営コースの担当学生が、地温を確認しながら管理を行った結果、現在まで順調に生育しています。




ナシの人工授粉! R5.3.27
今年は、農大の桜の開花も早く、3月27日(月)現在、本館周辺の桜は8部咲きとなっています。同じく、ナシの開花も早く、園芸学科果樹経営コースでは、ナシの人工受粉に追われている状況です。
この日は、ナシ班だけでなく、カンキツ班やブドウ班の学生も動員し、人工受粉を行いました。
気象条件が花粉の発芽や花粉管の伸長に影響するため、気温の上昇を待って、 時から人工受粉を行いました。
ナシは一つの花芽から複数の花が咲きますが、学生は、このうち果形や果実品質が良好な3~5番花をねらって、丁寧に受粉を行っていました。


トマト誘引用の支柱設置! R5.3.24
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、天敵製剤を活用したトマトの防除体系の検証を行うこととしており、3月23日(木)には定植を行ったところです。
3月24日(金)には、トマトの誘引が行えるよう、ハウス内に支柱を設置しました。
週明けには、アザミウマ類やコナジラミ類を捕食するタバコカスミカメを放飼する予定です。


露地カボチャのトンネル設置! R5.3.24
3月24日(金)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、露地ほ場で栽培するカボチャに、保温のため、トンネルを設置しました。
定植は、3月30日(木)頃を予定しており、先日ほ場準備を行ったハウス栽培と合わせて、施肥体系に係る経営プロジェクトを実施予定です。




ナシの人工授粉開始! R5.3.24
3月24日(金)、園芸学科果樹経営コースのナシ班では、今年初めての人工受粉を行いました。
昨年に比べ、1週間早い人工受粉となります。
担当の1年生は、暖かい日中に、5部咲きとなった「愛宕(あたご)」に、石松子(せきしょうし)という目印の資材を混ぜた花粉を、梵天(ぼんてん)を使って、ナシの花一つ一つに授粉しました。
翌週は、ナシの人工受粉のピークとなりそうです。


セット動噴の修理! R5.3.24
3月24日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、エンジンのかからなくなったセット動噴の修理を行いました。
1年生が、機械担当教官に指導してもらいながら、作業を行いました。
主な原因は、空気とガソリンを混合するキャブレター内のフロートの不具合による燃料のオーバーフローでした。
一度キャブレターを分解して組み直すことで、再びエンジンが始動するようになりました。
今後は、古くなったガスケットの付け替えを行い、機械が正常に動作するようメンテナンスを行う予定です。




促成スイカの人工授粉! R5.3.24
スイカやメロン、カボチャなど、ひとつの株に雌花と雄花が別々に咲く雌雄異花の野菜では、確実に着果させるためには、人工授粉を行う事が一般的です。
3月24日(金)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、促成スイカの人工受粉を行いました。
担当の1年生は、雄花をつるから取り、雄花の花びらをめくり、雄しべの花粉を、雌花の雌しべにこすり付けていきました。
また、受粉した日付を記録していました。
小玉スイカでは、受粉から30~40日後に収穫できる予定です。




ナシの花粉採取(採葯・発芽率調査)! R5.3.23
今年、農大のナシは、例年になく開花が早まっています。
このため、園芸学科果樹経営コースのナシ班では、人工受粉に向け、花粉の採取作業を慌ただしく行っています。
3月22日(水)には、受粉樹より取った花を採葯器にかけて葯を取るとともに、花粉を取り出すため、葯を温度25℃の恒温器内に20時間入れました。
3月23日(木)には、取り出した花粉を、グラニュー糖10%を加えた1%の寒天培地に薄く撒き、25℃の恒温器で2時間加温した後に、顕鏡で観察し、発芽率を確認しました。


カボチャ定植準備(潅水チューブ敷設とマルチ被覆)! R5.3.23
園芸学科野菜経営コースでは、カボチャの施肥体系に係る経営プロジェクトに取り組みます。
3月23日(木)には、担当の1年生らが、ハウス内でのカボチャ定植に向けて、潅水チューブ敷設とマルチ被覆を行いました。
被覆したマルチは、地温が上昇するよう透明マルチを使用しました。
3月末には、定植を行う予定です。




トルコギキョウの発芽! R5.3.23
花き経営コースでは、トルコギキョウにおける育苗の省力化に係る経営プロジェクトに取り組んでいます。
3月2日(木)に播種した直播区では、3月23日(木)に、発芽が確認されました。
また、マルチの穴からは、トルコギキョウ以外に雑草も確認されており、担当する1年生は、丁寧に雑草を除去していました。
直播区内では、今後、発芽率の調査を行う予定です。




ホウレンソウの播種! R5.3.23
3月23日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、ホウレンソウを播種しました。
播種前には、教官から、ベルト繰上げ式播種機の使用方法について指導を受けました。
その後、担当の1年生が、実際に播種機を使って、播種しました。1年生は、足跡がつかないようにするため、「左官下駄」を履いて作業を行いました。
今回播種した品種は、「ジャスティス」で、5月上旬頃収穫する予定です。




イチゴ親株の移動! R5.3.23
3月23日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、イチゴの親株を移動させました。
これまでガラス温室でイチゴの親株を育苗していましたが、今後、親株からランナーが伸び、子株の鉢受けを行うことから、そのスペースを確保するため、一部の苗をパイプハウスに移動しました。
1年生と担い手養成研修の研修生が協力して行いました。




経プロ用トマトの定植! R5.3.23
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、天敵製剤を活用したトマトの防除体系の検証を行うこととしています。
供試ほ場として、パイプハウス2棟を使用し、それぞれ異なる体系で防除を行うこととしています。
3月23日(木)には、各ハウスに、トマトの苗を定植しました。
品種は「麗月」で、各ハウスとも、200本以上の苗を定植しました。
今後、誘引ができるよう支柱の設置を行うとともに、今月末には、天敵製剤を放飼する予定です。




イチゴの経プロ調査! R5.3.22
園芸課野菜経営コースでは、イチゴに係る経営プロジェクトを3課題行っています。
本課題に係る生育調査や害虫発生調査は、2週間おきに行っています。
調査日である3月22日(水)には、担当の1年生らは、草高や展開葉数などの生育状況や葉裏のハダニや花のアザミウマの発生状況を調べました。




ナシの花粉採取準備(受粉授の枝採取)! R5.3.22
3月22日(水)、果樹経営コースのナシ班では、花粉の採取に向け、受粉樹として栽培している「ヤーリー」の枝と花を採取しました。
採取した枝は、ガラス温室内の保温施設に移し、開花を促した後、花粉の採取を行う予定です。


白オクラ種子の機械的傷つけ処理の施行(その2)! R5.3.22
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、白オクラの発芽率の改善に向けた播種前処理方法を調べることとしています。
3月22日(水)、担当の1年生が、2回目の種子の傷つけ処理を試しました。
今回は、紙やすりを用いたり、砂を混ぜて乳鉢に入れて乳棒ですりつぶしたりして、種子を傷つけてみました。
前回よりも、種子表面についたことを、実態顕微鏡で確認しました。
その後、傷つけた種子を、水に24時間浸した後、インキュベーターに入れ、発芽の確認を行います。




ハウス側面への防虫ネットの設置! R5.3.22
3月22日(水)、園芸学科野菜経営コースでは、パイプハウスの側面に、防虫ネットを設置しました。
アザミウマ対策として、防虫ネットの目合いは0.4ミリで、色は赤色です。
学生らは、たるんだり、しわが入らないよう、丁寧に設置し、ピンと張った仕上がりとなりました。




経営プロジェクトの設計検討(果樹経営コース)! R5.3.22
3月22日(水)、園芸学科の果樹経営コースでは、経営プロジェクトの設計検討を行いました。
設計検討では、1年生6名が、カンキツやナシ、ブドウに係るそれぞれの課題について発表するとともに、教官等とともに内容の検討を行いました。
調査区の設定や調査方法等、指摘のあった部分を修正した上で、今後、各学生の経営プロジェクトがスタートします。




ブロッコリー経プロの調査区設置・生育調査! R5.3.22
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
3月22日(水)には、ほ場内に調査区を設け、その後、ブロッコリーの生育調査を行いました。
側花蕾の活用の有無や側花蕾の取り方の違いで、4つの調査区を設けました。
生育調査は、最大葉の長さと幅を調べました。この調査は、毎週行うこととしています。




トマトの定植準備! R5.3.22
3月22日(水)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、トマトに係る経営プロジェクトを行うパイプハウス2棟の定植準備を行いました。
3月23日(木)の定植に向け、マルチに穴を開けるとともに、潅水を行いました。




イチゴの早朝収穫! R5.3.20
4月に近づき、気温の上昇とともに、イチゴの収穫量が増えています。
このため、園芸学科野菜経営コースのイチゴ担当の1年生は、鮮度のよいイチゴを出荷するため、また、午前10時までに出荷調整を終わらせるために、午前4時から収穫作業を行っています。
ハウス内の電照を点灯させて、イチゴの色を確認しながら、丁寧に収穫を行います。
3月20日(月)は、市内2カ所の直売所へ出荷を行いました。
ぜひ、直売所へお立ち寄りいただき、お買い求めください。
白オクラ種子の機械的傷つけ処理の試行! R5.3.17
ニンジンの作付けの播種! R5.3.17
3月17日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、ニンジンの播種を行いました。
畝に巻き尺を伸ばし、それに沿って、ベルト繰上げ式種まき機を押し、「種まき」、「覆土」、「鎮圧」の行程を一度に行っていきました。
品種は、「向陽2号」で、6月下旬頃に収穫する予定です。
防府天満宮「大石段花回廊」展示用の鉢花の搬出! R5.3.17
毎年4月中旬から5月上旬に、防府天満宮では、大石段を花鉢で飾る「花回廊」が行われており、農業大学校も花鉢の準備で関わっています。
3月17日(金)、園芸学科花き経営コースで育ててきたビオラの花鉢300鉢が、防府市内の5つの中学校等に搬出されました。
残ったバーベナやベゴニア等の花鉢は、引き続き校内で管理を続け、4月12日に防府天満宮に搬出する予定です。
促成スイカの孫づる除去! R5.3.17
3月17日(金)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、促成スイカの孫づるを除去しました。
2月1日(水)に定植したスイカは、順調に生育しており、小玉スイカでは15節以上伸びた子づるもあり、3番花の着生も確認できました。
花き経営コースの出荷調整風景! R5.3.16
園芸学科花き経営コースでは、現在、カスミソウやキンギョソウ、ダリア、カーネーションなどの収穫が行われています。
2年生卒業後、1年生が職員の支援を受けながら、収穫調整を行っています。
3月16日(木)に収穫調整を行ったものは、市場と直売所へ出荷する予定です。
促成スイカの生育状況! R5.3.16
野菜経営コースでは、5月に収穫するスイカの促成栽培に取り組んでいます。
2月1日(水)に定植したスイカは、順調に生育しており、3月16日(木)のj調教は画像のとおり、子づるが伸び、茂ってきました。
担当する1年生は、子づるを伸ばしたい方向に整えるとともに、孫づるを摘み取っていきました。
ブドウ園のトンネルメッシュ被覆! R5.3.16
3月16日(木)、果樹経営コースのブドウ班が、露地ブドウ1号園のブドウ棚のトンネルメッシュをビニルで被覆しました。
ブドウ班の1年生2名に加え、カンキツ班や教官の支援を得て、トンネルメッシュの被覆作業を行いました。
当日は、風の無い絶好の被覆日和で、被覆作業も思いのほか進みました。
ニンジン作付けのほ場準備! R5.3.16
3月16日(木)、園芸学科野菜経営コースでは、ニンジンの作付けに向けたほ場準備を行いました。
施肥を行った後、トラクタで耕うんし、歩行式の畝立成形機で畝を立てました。
担当の1年生は、教官と相談しながら、丁寧に作業を進め、真っすぐな畝を立てていきました。
翌日には、播種を行う予定です。
環境整備実施(斜面等の草刈り)! R5.3.16
3月16日(木)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、環境整備として、担当箇所である斜面等の草刈りを行いました。
3月20日(月)には春のオープンキャンパスが、3月22日(月)には、入学事前説明会があることから、環境整備を行ったものです。
これから暖かくになるにつれ、雑草も旺盛に伸びてくるため、各経営コースでは、適宜、草刈りを行っていきます。
キク栽培用の電照設置! R5.3.16
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用のスプレー菊の植え付け準備を行っています。
3月16日(木)には、担当の1年生が、電照を設置しました。
1ベンチあたり、電球4個が配置できるよう、配線を行っていました。
キクの定植は、4月上旬頃で、「セイオリビア」ら4品種を栽培する予定です。
また、経営プロジェクトとして、わい化剤の処理濃度・回数に係る調査を実施する予定です。
ジャガイモの植え付け・マルチ被覆! R5.3.15
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ジャガイモの生分解性マルチ等を用いた場合の収量性や労働性、収益性に係る調査を行うこととしています。
3月15日(水)には、担当の1年生らが、調査区用のジャガイモの種芋を植付けるとともに、マルチを被覆する区では、生分解性マルチ等を被覆しました。
種芋の植え付けは、調査用のため、全て手作業で行いました。
1ヶ月後には萌芽率の調査を行う予定です。
カボチャ用の畝立て! R5.3.15
園芸学科野菜経営コースでは、カボチャ「くりゆたか」を供試し、施肥体系に係る経営プロジェクトに取り組みます。
3月15日(水)には、 担当の1年生が、施肥を行い、トラクタで耕うんした後、畝立て成形機により、畝を立てました。
3月下旬には、定植を行う予定です。
キク栽培ベンチへの支柱・フラワーネット設置! R5.3.15
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用のスプレー菊の植え付け準備を行っています。
3月15日(水)には、担当の1年生が、教官とともに、ベンチへ支柱やフラワーネットを設置しました。
担当学生は、作業の途中で直売所の出荷補助を行うなど、忙しい中での実習でしたが、丁寧に作業を行っていました。
ブロッコリーの苗質調査! R5.3.14
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
3月14日(火)にブロッコリー苗の草丈、葉数、最大葉(葉長、葉幅)を調査しました。
来週からは、週1回、本圃での生育調査を行い、生育の状態を調べていきます。
トマトの潅水チューブ敷説とマルチ被覆! R5.3.15
3月15日(水)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、パイプハウス2棟の潅水チューブ敷設とマルチ被覆を行いました。
マルチ被覆では、クワを用いてマルチがしっかり張るよう土寄せを行いました。
これら2つのハウスでは、天敵製剤を活用したトマトの防除体系の検証を行うこととしています。
今後、トマトの定植、天敵の放飼を行う予定です。
ジャガイモの畝立て・植え付け! R5.3.14
3月14日(火)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、ポテトプランタを用いて、ジャガイモの畝立てと植え付けを同時に行いました。
この作業は二人で行い、一人がトラクタの運転を、もう一人がポテトプランタに種芋の供給を行うものです。
1年生の二人は、教官の指導のもと、丁寧に作業を行っていました。
このジャガイモは、6月上旬頃に収穫する予定です。
キク栽培ベンチの潅水パイプ設置! R5.3.14
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用スプレー菊のわい化剤の処理濃度・回数に係る経営プロジェクトに取り組むこととしています。
3月14日(火)、担当の1年生らが、ガラス温室内のベンチに潅水パイプを設置しました。
設置後は、実際に水を出し、不具合等がないか点検を行っていました。
ナシ防除体系調査の準備! R5.3.14
園芸学科果樹経営コースでは、経営プロジェクトとして、在来天敵や天敵製剤を活用したナシの防除体系の検証を行うこととしています。
3月14日(火)には、ナシ班の1年生らが、ナシ園に、防除の際、慣行区と調査区を仕切るためのブルーシートの設置を行いました。
高所での作業であり、また棚線があるため、手間がかかりましたが、無事に設置できました。
カボチャの施肥・畝立て準備! R5.3.14
園芸学科野菜経営コースでは、カボチャの施肥体系に係る経営プロジェクトに取り組みます。
3月14日(火)には、担当の1年生が、調査ほ場にまく肥料の準備を行いました。
また、翌日の畝立ての準備として、ほ場で、教官とともに測量し、畝を立てる位置に目印を立てました。
トマトの畝立て! R5.3.14
3月14日(火)、園芸学科野菜経営コースの1年生が、トマトに係る経営プロジェクトを行うパイプハウス2棟の畝立てを行いました。
担当学生は、立てる畝の測量を教官とともに正確に行い、管理機を用いて畝立てを行いました。
今後、マルチ被覆と潅水チューブの敷設を行った後、トマトの定植、天敵の放飼を行う予定です。
「農林業の知と技の拠点 新施設竣工式」の装花! R5.3.14
農業試験場・農業大学校・林業指導センターを統合する「農林業の知と技の拠点」の新施設が完成し、3月15日(水)に、竣工式が開催されます。
3月14日(火)には、園芸学科花き経営コースの担当職員が、竣工式会場に飾る鉢花等の活け込みを行いました。
パイプハウスの天井ビニル被覆! R5.3.14
3月14日(火)、園芸学科野菜経営コースでは、パイプハウスの天井ビニルを被覆しました。
昨年10月以来の久しぶりのビニル被覆であり、1年生のみでの作業となりました。
学生は、それぞれが声を掛け合いながら作業を行うとともに、スプリングでビニルを留める際には両端でビニルを引っ張る力を加減しながが行い、ビニルがピンと張るように被覆することができました。
カボチャ苗の鉢上げ! R5.3.13
園芸学科野菜経営コースでは、カボチャの施肥体系に係る経営プロジェクトに取り組みます。
3月6日(月)に、水稲育苗箱へ播種したカボチャは、双葉が展葉しています。
そこで、3月13日(月)に、カボチャの苗の鉢上げを行いました。
培土を作成し、ポリポットへ充填した後、鉢上げを行いました。
今回、鉢上げした数は、300鉢です。
ガラス温室内でしばらく育苗し、3月下旬頃に本ぽに定植する予定です。
経営プロジェクトの設計検討(花き経営コース)! R5.3.13
3月13日(月)、園芸学科の花き経営コースでは、経営プロジェクトの設計検討を行いました。
設計検討では、1年生3名が、トルコギキョウやキク、LAユリに係るそれぞれの課題について発表するとともに、教官等とともに内容の検討を行いました。
調査区の設定や調査方法等、指摘のあった部分を修正した上で、今後、各学生の経営プロジェクトがスタートします。
白いもの消毒・仕込み! R5.3.13
園芸学科野菜経営コースでは、昨年、山口銀行や防府商工高校と連携して、白いも栽培に取り組みました。
今年は、昨年収穫した白いもを種芋として、プランターに植え付け、芽が出れば、山口銀行へお渡しすることとしています。
3月13日(月)には、種芋となる白芋を温湯消毒し、その後プランターに伏せこみました。
ブドウの枝への芽傷処理! R5.3.13
3月13日(月)、園芸学科果樹経営コースのブドウ班では、ブドウの枝への芽傷処理を行いました。
ブドウでは、昨年伸びた枝を長く残すと先端の芽が強く伸び出して、基部の芽の発芽や伸長が抑えられます。
これは、先端の芽から分泌された植物ホルモンが基部の芽に作用するのが原因であり、新梢は頂芽より下の全ての芽に芽傷処理を行って発芽を促します
芽傷処理は、芽の上側に芽傷等で幅 5~10ミリ、深さ 2 ミリ位の傷を入れます。
サツマイモの温湯消毒! R5.3.13
園芸学科野菜経営コースでは、本年度もサツマイモの作付けを行います。
3月13日(月)、「安納芋」と「白いも」の種芋の温湯消毒を行いました。
温湯消毒は、黒斑病などの予防のため、種芋を48度の湯に40分間浸すものです。
学生は、お湯の温度を測りながら、温度が下がったらお湯を足し、温度の維持に努めました。
温湯消毒後、種芋は、パイプハウスYA8号の土の中に伏せこみました。
一か月程度で、移植用のツルが取れる予定です。
盆出荷用スプレー菊への施肥! R5.3.13
園芸学科花き経営コースでは、盆出荷用スプレー菊のわい化剤の処理濃度・回数に係る経営プロジェクトに取り組むこととしています。
3月13日(月)、ガラス温室内のベンチ内の培土に施肥を行いました。
担当する1年生は、ベンチ毎に分量を正確に量り、丁寧に散布していました。
翌日は、耕うん機を用いて、耕うんを行う予定です。
ジャガイモの施肥・畝立て! R5.3.10
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ジャガイモの生分解性マルチ等を用いた場合の収量性や労働性、収益性に係る調査を行うこととしています。
3月13日(月)の午前中には、露地ほ場Bのジャガイモの植え付け予定地へ、肥料をまき、午後には、経営プロジェクト調査区の耕うんと畝立てを行いました。
翌日は、調査区以外をポテトプランタにより畝立て・植え付けを同時に行うとともに、調査区への種芋の植え付けを行う予定です。
トマトの施肥・耕うん! R5.3.10
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、天敵製剤を活用したトマトの防除体系の検証を行うこととしています。
供試ほ場として、パイプハウス2棟を使用し、それぞれ異なる体系で防除を行うこととしています。
3月13日(月)には、各ハウスに肥料をまき、トラクタで耕うんしました。
今後、畝を立て、マルチ被覆して、トマトを定植するとともに、3月下旬には、一方のハウスに天敵を放飼する予定です。
露地ほ場への額縁明渠の設置! R5.3.10
3月10日(金)、園芸学科野菜経営コースでは、露地Eほ場に額縁明渠を設置しました。
これは、ほ場の排水性を高めるため、ほ場周辺部分に溝を設けるものです。
トラクタにリッジャーを取り付けて、深さ40cm程度の溝を掘っていきました。
また、畝の溝と額縁明渠をつなげるために、管理機に培土器をつけて、溝を掘るとともに、クワで整えていきました。
このほ場では、ブロッコリーやカボチャの経営プロジェクトを行うとともに、新入生が白ネギを栽培する予定です。
白オクラの塩水選! R5.3.10
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、白オクラの発芽率の改善に向けた播種前処理方法を調べることとしています。
この調査に供試する白オクラの種は、2月15日(水)に比重1.05の塩水で選別を行ったところですが、産地のマニュアルに基づき、比重1.13で試すこととなりました。
そこで、3月10日(金)に、塩水の比重を変えて、再度塩水選を行いました。
ジャガイモの種芋の切断! R5.3.10
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、ジャガイモの生分解性マルチ等を用いた場合の収量性や労働性、収益性に係る調査を行うこととしています。
3月10日(金)には、種芋となるジャガイモの切断を行いました。
担当の1年生は、120gを超える種芋を、半分に切っていきました。
今後、3月13日頃、露地Bほ場で畝立てを行い、種芋を植付けるを予定です。
ブロッコリーの定植! R5.3.10
園芸学科野菜経営コースでは、経営プロジェクトとして、2花蕾取りのブロッコリーの仕立て方法が収量に及ぼす影響を調べることとしています。
3月10日(金)には、供試するブロッコリーの苗をほ場に定植しました。
調査区のうち、「V字仕立区」では、1ヶ月後に摘芯を行う予定です。
野菜経営コース記念撮影! R5.3.9
3月9日(木)の午後、昼食会を兼ねた専攻送別会が各経営コースで行われました。
園芸学科野菜経営コースでは、送別会閉会後、卒業生、在校生、研修生、職員による記念撮影が行われました。
専攻送別会の風景【花き経営コース】! R5.3.9
3月9日(木)、午前中に挙行された「令和4年度卒業式」の後は、昼食会を兼ねた専攻送別会が行われました。
園芸学科の花き経営コースは、園芸・バイテク棟の教室に、卒業生、在校生、職員が一堂に会して、送別会を行いました。
1年生の司会進行のもと、昼食会や記念品の贈呈が行われるとともに、卒業する2年生から1年生へ激励の言葉が送られました。
専攻送別会の風景【果樹経営コース】! R5.3.9
3月9日(木)、午前中に挙行された「令和4年度卒業式」の後は、昼食会を兼ねた専攻送別会が行われました。
園芸学科の果樹経営コースは、果樹出荷調整棟で、送別会を行いました。
送別会では、1年生が幹事となって、NGワードゲームを行い、2年生との最後のひと時を過ごしました。
送別会の終わりには、2年生、1年生、教官らが、それぞれ挨拶を行い、共に過ごした季節を懐かしみながら、互いのこれからに幸あるよう願い、閉会しました。
2年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
専攻送別会の風景【野菜経営コース】! R5.3.9
3月9日(木)、午前中に挙行された「令和4年度卒業式」の後は、昼食会を兼ねた専攻送別会が行われました。
園芸学科の野菜経営コースは、新生館で、卒業生、在校生、職員が一堂に会して、送別会を行いました。
送別会では、卒業する2年生一人一人から、2年間の思い出や感謝の気持ち、はなむけの言葉が贈られました。
令和4年度卒業式! R5.3.9
3月9日(木)、令和4年度卒業式を挙行しました。
好天にも恵まれ、33名の卒業生の門出を祝う佳き日となりました。
4月から、新たな地での活躍を祈念します。
畜魂祭を行いました! R5.3.8
畜産課では、3月8日(水)に畜魂祭を行いました。
畜産課は、日々、生乳や肥育牛を生産する実践学修をしています。
そうした学修の中で、出荷した牛や治療の甲斐なくへい死した牛への感謝、日々の実習への感謝をするため、毎年畜魂祭を行っています。
畜魂祭では、校長先生にも参列いただき、畜産課の学生、職員が校内の畜魂碑に、1人ずつ献花して感謝と敬意を表し祈りました。
命の尊さを忘れず、日々感謝して生産していきたいと、皆が改めて感じる機会となりました。
トルコギキョウの潅水! R5.3.8
花き経営コースでは、トルコギキョウにおける育苗の省力化に係る経営プロジェクトの実施を計画しています。
調査区の一つである、直播区では、3月2日(木)に本ぽに播種しており、その後担当の一年生は、潅水を毎日行っています。
また、2月2日(木)にセルトレイに播種した慣行区では、発芽が確認されています。
卒業式会場への壺花活け込み! R5.3.8
いよいよ、明日3月9日(木)に「令和4年度卒業式」が挙行されます。
3月8日(水)には、卒業式の会場である本館講堂や階段の装花が、花き経営コースの学生や職員により行われました。
講堂の壺花は、明日の主役である2年生が活け込みを行い、技能五輪全国大会に出場した腕前を、遺憾なく発揮してくれました。
卒業式会場の装花! R5.3.8
いよいよ、
3月8日(水)、翌日の「令和4年度卒業式」に向けて、会場である本館講堂までの階段の装花を、花き経営コースの1年生や職員が行いました。
前日までに作成したアレンジを階段に並べたり、手すりに括り付けたり、色付けしたカスミソウを吊り下げたりし、華やかに飾り付けました。
卒業生への花束作成! R5.3.8
いよいよ、明日3月9日(水)に「令和4年度卒業式」が挙行されます。
3月8日(水)には、花き経営コースの1年生が、卒業する2年生のために、花束を作成しました。
農大産のカーネーションやダリア、トルコギキョウ、カスミソウなどを使用して花束を作るとともに、ラッピング資材は卒業生をイメージしながら色を選んでいました。
イチゴの経プロ調査! R5.3.8
野菜経営コースでは、イチゴに係る経営プロジェクトが3課題行われています。
3月8日(水)は、これら課題に係る生育や害虫発生状況の調査を行いました。
担当の1年生らは、生育調査では草高や展開葉数などを、害虫発生調査では葉裏のハダニや花のアザミウマの発生状況を調べていました。
夕方の専攻タイムの風景【野菜経営コース】! R5.3.8
園芸学科の野菜経営コースは、夕方、園芸・バイテク棟の教室で、専攻タイムを行っています。
夕方の専攻タイムでは、学生、研修生から当日の作業内容や翌日の作業計画などの報告や教官から指示、連絡等が行われます。
夕方の専攻タイムの風景【花き経営コース】! R5.3.8
園芸学科の花き経営コースは、夕方、園芸・バイテク棟の教室で、専攻タイムを行っています。
夕方の専攻タイムでは、翌日の実習内容の確認や連絡事項の伝達等が行われます。
夕方の専攻タイムの風景【果樹経営コース】! R5.3.8
園芸学科の果樹経営コースは、夕方、果樹出荷調整棟内で、専攻タイムを行っています。
翌日の実習内容、ヒヤリハットなど実習中の気づき報告、当日の実習に関する学生からの一言、出荷上の注意事項(値段シールの不足はないかなど)の共有などをしています。
専攻タイムにより、教官と学生の情報共有を測っています。
ナシ園の防風ネット修繕! R5.3.8
3月8日(水)、果樹経営コースのナシ班の1年生が、ナシ園の防風ネットの修理を行いました。
農業大学校は、風当たりが強く、とくにナシ園では、防風対策が必須です。
1年生らは、生育期に入る前に、防風ネットが裂けた部分を、丁寧に縫い合わせていました。
朝の専攻タイムの風景! R5.3.8
園芸学科の野菜経営コースと花き経営コースは、毎朝、野菜・花き出荷調整棟内で、専攻タイムを行っています。
専攻タイムでは、当日の作業内容を確認したり、教官から指導や連絡、学生、研修生から報告を行ったりします。
資材庫の整理整頓! R5.3.7
園芸学科野菜経営コースでは、令和5年度の経営プロジェクトとして、資材の整理整頓に係る課題を行うこととしています。
3月7日(火)、担当の1年生は、資材庫から必要なサイズの内張用ビニルを探すのに要した時間や内張設置に係る時間の計測を行いました。
その後、より効率的に資材が探せるよう、ビニルの長さを測り、記録した上で、片付けていました。
ジャガイモ作付け用の畝立て準備! R5.3.7
園芸学科野菜経営コースでは、露地Bほ場において、ジャガイモを作付けします。
ここでは、経営プロジェクトとして、生分解性マルチ等を用いた場合の収量性や労働性、収益性に係る調査を行うこととしています。
3月7日(火)には、担当の1年生が、畝立てを行うために、距離を測り、目印をつけていきました。
ブロッコリー作付けに向けた畝立て! R5.3.7
園芸学科野菜経営コースでは、3月に入り、露地野菜作付けに向けた準備を行っており、露地Eほ場では、白ネギ、ブロッコリー、かぼちゃの作付けを予定しています。
3月7日(火)、前日に堆肥の施用や耕うんを行ったほ場のうち、ブロッコリーの作付予定地の土壌改良と畝立てを行いました。
担当する1年生は、石灰を施用した後、トラクタを使って畝立てを行いました。
ブロッコリーの定植は、近日を予定しており、2花蕾取り栽培に係る経営プロジェクトに供試されます。
卒業式の装花の準備! R5.3.7
「令和4年度卒業式」挙行まで、あと二日!
3月7日(火)には、前日に続き、花き経営コースでは、会場となる本館の玄関横へ寄せ植えを行うとともに、講堂までの階段を飾るアレンジを作成しました。
ナシの花粉採取準備! R5.3.7
本校では、例年4月上旬にナシが開花期を迎えます。
本校で栽培するナシの品種の多くは、自家不和合性のため、確実に結実させるためには、他の品種の花粉で受粉させる必要があります。
このため、この時期、果樹経営コースナシ班では、人工受粉用の花粉採取の準備を行います。
3月7日(火)には、受粉樹の切り枝の開花を促進するための保温施設を、ガラス温室内に設けました。
3月中旬頃には、切り枝を保温施設に移し、1週間程度で開花させ、花粉の採取を行う予定です。
卒業式の装花の準備! R5.3.6
3月9日(木)に、「令和4年度卒業式」が挙行されます。
3月6日(月)には、花き経営コースの1年生2名が、会場となる本館講堂までの階段を飾るアレンジを作成しました。
農大産のカーネーションやカスミソウを使用し、卒業生のために、一生懸命作っていました。
直売所への出荷風景! R5.3.6
園芸学科では、学生や研修生が作った農産物を市場や直売所へ出荷を行っています。
3月6日(月)は、「JA山口県中部営農センター農産物直売所とれたて満菜」へ出荷を行いました。
果樹経営コースの学生らは、車に出荷物を積んだ後、毎回、車の見送りを行います。
今回、出荷に同行したのは、野菜経営コースの1年生です。出荷者用のオレンジ色の帽子を被り、トマトやナスといった出荷物を手早く棚に並べていました。
蒸気消毒後の片づけ! R5.3.6
花き経営コースでは、3月3日(金)に、盆出荷用スプレー菊の定植に向け、蒸気消毒を行ったところです。
3月6日(月)には、担当の1年生が、蒸気消毒で使用した被覆シート6枚や蒸気放出用ホースの清掃を行いました。
泥汚れをデッキブラシでこすったり、水で洗い流して、きれいにした上で、管理棟に片付けました。
ブドウ園トンネルメッシュの被覆準備! R5.3.6
果樹経営コースのブドウ班では、トンネルメッシュのビニル被覆の準備を行っています。
3月6日(月)には、1年生2名が、ビニルを押さえるためのマイカー線をブドウ棚に取り付けていきました。
3月中旬頃には、ビニルを被覆する予定です。
トラクタで耕うんを行いました! R5.3.6
3月6日(月)、野菜経営コースの1年生が、トラクタで耕うんを行いました。
正面のほ場では、白ネギの収穫が終わったため、残渣のすき込みを兼ねて耕うんを行いました。
もう一つのほ場では、堆肥を散布した後、耕うんを行いました。
このほ場では、経営プロジェクトとしてブロッコリーとカボチャを植え付けるとともに、4月に入学する新入生が白ネギを作る予定となっています。
トラクタに搭乗した1年生は、教官に指導してもらいながら、丁寧に耕うんを行っていました。
トマト苗の鉢上げを行いました! R5.3.6
3月6日(月)、野菜経営コースの1年生が、トマト苗の鉢上げを行いました。
これは、セルトレイに播種した台木に穂木を接いだ苗を、ポットに移植するものです。今回460鉢を鉢上げしました。
このトマト苗は、約2週間、ガラス温室内で管理した後、3月下旬にハウスに定植を行う予定しており、天敵を用いた防除体系に係る経営プロジェクトに供試します。
カボチャの播種を行いました! R5.3.6
3月6日(月)、野菜経営コースの1年生が、かぼちゃの播種を行いました。
品種は「くりゆたか」で、ほくほくとした食感で甘みが強いのが特徴で、県内では山陽小野田市で産地化され、「寝太郎かぼちゃ」のブランドで販売されています。
播種は、水稲育苗箱4枚に行い、約300鉢の苗を作る予定です。
このかぼちゃは、3月下旬頃に本ぽに定植し、かぼちゃの施肥体系に係る経営プロジェクトに供試します。
堆肥の散布を行いました! R5.3.6
3月6日(月)、野菜経営コースの1年生が、パイプハウス内に堆肥を散布しました。
このハウスでは、サツマイモの苗取りを行う予定で、土壌改良のために堆肥を施用するものです。
ハサミ置き場を設けました!(野菜経営コース) R5.3.3
3月3日(金)、野菜経営コースでは、学生が使用するハサミの置き場を設けました。
これは、昨年12月に起きたハサミカバーの破片がコンテナ内に入っていたという事故の再発防止対策で行うものです。
今後、野菜経営コースでは、ハサミは使用時のみ携行し、使用しない時は置き場に戻すこととなります。
定位置管理を通じて、ハサミやカバーの紛失、破損等の確認が行えるようになります。
温州ミカン「石地」の間伐を行いました! R5.3.3
3月3日(金)、果樹経営コースのカンキツ班では、「石地」の間伐を行いました。
「石地」は、定植から10年程度経過し、個々の樹の樹冠が拡大してきたことから、1列12本の間伐を行うものです。
間伐により、一時的に収量は下がりますが、翌年には樹冠拡大が勝り、収量が回復するとともに、樹体に日がよく当たるようになり、果実品質の向上効果も期待できます。
1年生は、慣れないチェーンソー操作に苦戦していましたが、教官の指導により、スムーズに伐採が行えるようになりました。
キンギョソウの芽整理を行いました! R5.3.3
3月3日(金)、花き経営コースの1年生が、キンギョソウの芽整理や脇芽取りを行いました。
今回の芽整理は、3番花採取に向けたもので、太く丈夫な茎を必要数残し、余計な茎を取り除いていきました。
3番花は、5月に収穫する予定です。
盆出荷用スプレー菊の定植のための蒸気消毒を行いました! R5.3.3
3月3日(金)、花き経営コースでは、盆出荷用スプレー菊の定植に向け、蒸気消毒を行いました。
蒸気消毒機を用いて、蒸気の熱を土壌に浸透させ、土壌の温度が80度、30分間保ったら完成です。
担当の1年生は、温度計等を見ながら、蒸気消毒の状況を確認していました。
キクの定植は、4月上旬頃で、「セイオリビア」ら4品種を栽培する予定です。
また、経営プロジェクトとして、わい化剤の処理濃度・回数に係る調査を実施する予定です。
カスミソウの枝整理を行いました! R5.3.3
3月3日(金)、花き経営コースでは、カスミソウの枝整理を行いました。
枝整理は、草勢の維持や調節のために行うものです。
2年生から担当を引き継いだ1年生は、枝の繁茂状況を確認しながら、慎重に枝をせん徐していました。
経営プロジェクトの設計検討及び中間発表を行いました(野菜)! R5.3.3
3月3日(金)、野菜経営コースでは、経営プロジェクトの設計検討及び中間発表を行いました。
設計検討では、1年生7名が、ホウレンソウやトマト、ジャガイモ、白オクラ、ブロッコリー、カボチャ、経営改善に係るそれぞれの課題について発表するとともに、教官等とともに内容の検討を行いました。
また、すでにイチゴの経営プロジェクトを実施している1年生3名は、現在までの状況、データ等について説明を行いました。
キンギョソウへの液肥施用! R5.3.2
3月2日(木)、花き経営コースの1年生が、パイプハウスで栽培しているキンギョソウへ液肥を施用しました。
液肥混入器を用いて、専用液肥1,000倍を施用しました。
このキンギョソウは、5月まで収穫を予定しているため、養分不足に陥らないよう、定期的に(1週間に1回)液肥を施用しています。
トルコギキョウの播種を行いました! R5.3.2
花き経営コースでは、盆前出荷のトルコギキョウ栽培における定植作業の省力化の検証に係る経営プロジェクトを行っています。
3月2日(木)には、担当の1年生が、トルコギキョウの播種を行いました。
直播区では、本圃に直接播種を行い、1穴に種子2粒ずつを播きました。
稚苗定植区では、セルトレイに充填した固化培地に播種を行いました。
今後、稚苗定植区及び慣行定植区では、4月上旬頃に本圃に定植を行う予定です。
ナシの剪定枝回収! R5.3.2
果樹経営コースでは、ナシの剪定が終り、園内の片付けを行っています。
3月2日(木)には、ナシ班の1年生が、園内に残った剪定枝を回収しました。
剪定枝を片付けて、園内はすごくきれいになりました。
スマート農業技術を活用したイチゴ栽培の勉強会を行いました! R5.3.2
本校では、農林総合技術センター農業技術部園芸作物研究室が地元企業と共同開発した複合環境制御システム「Evoマスター」を活用したイチゴの栽培をしており、定期的にセンター研究員を招いて、勉強会を開催しています。
3月2日(木)には、イチゴ栽培を担当している学生・研修生3名が、原田専門研究員から、「生育推移や測定した環境データを踏まえた環境制御設定の方法、制御装置の設定変更の実践」などを学びました。
本年度の勉強会は今回が最終回ですが、次年度も継続して行います。
ハウスビニルの洗浄! R5.3.2
3月2日(木)、野菜経営コースの1年生が、ハウスビニルの洗浄を行いました。
このハウスビニルは土壌消毒で使用したもので、土等の汚れを除くために行うものです。
ホースで粗洗いした後、高圧洗浄機を用いて、徹底的に洗浄していきました。
バラの剪定を行いました! R5.3.2
3月2日(木)、花き経営コースの1年生が、パイプハウスで栽培しているバラの剪定を行いました。
この時期の剪定は、寒さに合わせて休ませていた株から、立派な花を咲かせるために行うものです。
なお、このハウスでは、「エンジェルローラ」など9品種を育てており、5月頃には収穫が始まる予定です。
イチゴ果房へのマーキング! R5.3.2
野菜経営コースでは、『イチゴ「かおり野」の栽植密度と摘果等による着果量の違いが収量に及ぼす影響』と題した経営プロジェクトを行っています。
本プロジェクトでは、第2果房以降、摘果により着果数を変えた区を設けます。
このため、3月2日(木)には、担当学生が調査区の株の第3果房にテープナーをつけて、マーキングを行いました。
これは、学生自身が考えたもので、調査や摘果作業が効率的にできるよう工夫したものです。
販売実習を行いました!【道の駅「ソレーネ周南」】 R5.3.1
3月1日(水)に、周南市道の駅「ソレーネ周南」で販売実習を行いました。
野菜、花き、果樹の1年生8名は、これまで販売実習を数回経験しており、手際よく準備を行い、対面販売に臨みました。
今回の目玉商品は、「ミニトマト」、「フラワーアレンジメント」、「ハッサク」で、学生らは、お客様へ商品の特徴等を丁寧に説明していました。